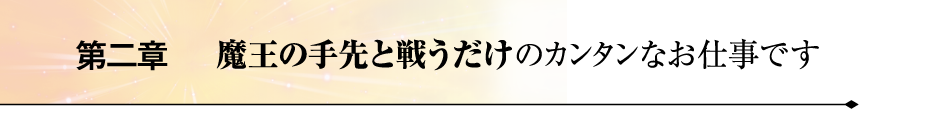「俺バベったわー、小テストマジでバベったわー」
ある日、昼休み前の英語の授業が終わった後、根岸が話しかけてきた。
「長文の予習の量が半端なかったからな。小テストの対策は虚の世界に消えたわけだ」
バベる、とは、根岸と僕との間で使っている造語だ。英語のテストの成績が悪いときに、バベルの塔の古事を捩って使っている。
遥か古代、人間たちは神に近づこうとして、天まで届くバベルの塔を作ろうとした。そのことを怒った神は塔の建設を妨害するために、人間それぞれが話す言葉をばらばらにしてしまった。話す言葉が通じなくなった人間たちは、力を合わせることができなくなり、巨大な塔の建設をやめてしまった。世界に複数の言語ができたのはこのためであるという。
そして現代、神話の通りであるならば、僕と根岸が英語をうまく話すことができないのは、神のバベルの塔対策が原因なのだ。多分。
「千早もバベリッシュホワイトペーパーか」
「まだ単位の死線には触れてない」
根岸と掛け合っている僕の脇を、弁当箱の包みを持った黒土が通り過ぎていく。この人たちは一体何を話しているんだろう、そんな目をしていた。
根岸は日頃から女の子にモテたいと言っているけど、仲のいい友達以外には意味の通じない、内輪ネタや造語を連発しながら話す性格では難しそうだ。例えば根岸は、ゲームでバグが発生して、有り得ない数字が出たことを楽しそうに話すのだが「村人の攻撃力が、素手の一撃で魔王を殴り倒せるくらいになっちまったぞ」と言っても、その値がおかしいのか、常識の範囲内なのか、分かっている人にしか通じないだろう。
僕は根岸と、財布に入ってる金がオーバーフローしねえかなと話しながら購買にパンを買いに行き、教室でお喋りをしながら昼食を済ませた。
「アニメの専門店ってさ、床にキャラクターの絵が描かれてることがあるよな」
「僕はあまり行ったことがないんだけど。そういえば本屋でも見たことがある気がする」
「あれってさ、踏み絵みたいだよな」
「信者の何を試しているんだろうな。もしかすると……」
僕は話を続けていたが、根岸の様子がおかしいことに気づき、そこで口を閉じた。
根岸が欠伸をし、やたらと眠そうにしていた。オンラインゲームのやりすぎか、と思って見ていると、すぐに机に体を預けて、そのまま鼾をかき始めた。
昼休みは居眠りに丁度いいとはいえ、話の途中で唐突に寝るとはどういうことだ。
教室がやけに静かなことに気がついて辺りを見回すと、普段騒がしいグループもみんな机に伏せたり、椅子の背もたれに寄りかかったりして、動かなくなっている。
僕も眠い。明らかにこれはおかしい。朦朧としながら、机の脇に提げている鞄に手を入れた。目的のものを探り当て、取り出した丸薬を急いで口に入れて噛み砕く。
その瞬間に、霧が風で吹き散らされたかのように、意識がクリアになる。
クラス全員が、魔法か何かで睡眠の状態異常にかかっていると確信した。万能薬という、死んでしまった状態以外をたちどころに治す薬がよく効いたからだ。
ミカゼの方を見る。姿勢よく椅子に座っていて、首から上が前後にふらふらと動いていた。流石は勇者だ、完全に睡眠状態になるまでが、クラスの皆よりも遅いようだ。
ミカゼの席の前まで行って、声をかける。
「ミカゼ、何か変だ、起きてくれ」
「羊は、何匹もいる」
「寝ぼけているのか」
「羊の数が多すぎる」
「おーい」
「羊を包囲する、罠に誘い込むんだ」
うとうととしていたミカゼの目が閉じられ、すやすやとした寝息が聞こえてきた。
「起きてくれ」
肩を掴み、揺すってみる。
「哀れな、子羊」
ガンッ!
視界に火花が出現した。僕は顔面を押さえて背中を丸めた。勇者は睡眠中に攻撃された時に自動で反撃するスキルを身につけている。ミカゼの拳が僕の顔を捉えたのだ。
「お前は初期型のエアバッグか! 反応が敏感すぎるんだよッ!」
素直に万能薬を使うことにした。幸いにも、寝ているミカゼの口は半分開いたままだ。つまんだ薬をそっと唇の間に入れる。
「ペッ!」
コン、と音を立てて、万能薬が僕の額に当たり、床を転がって行った。吐き出した物を正確に僕に当てたのはわざとなんじゃないかと疑いたくなる。
起こすのが嫌になってきたが、僕が今頼れるのはミカゼしかいない。ケースから新たに取り出した薬を、人差し指と中指で挟み、ミカゼの口に入れる。指を奥まで突っ込み、奥歯まで押し込む。
「おえっ」
「行き過ぎた、スマン」
ガンッ!
焦りから喉を突っついてしまった。それがミカゼへの攻撃と見なされたのか、また反撃された。
「そのスキル、敵と味方の区別くらいできるようにしてくれよ」
そう言っても、返事は返ってこない。
再度、慎重にミカゼの口へ薬を入れ、ゆっくりと指で奥歯を探る。
奥歯をこじ開け、薬を挟み込む。これでよし、あとは無意識にでも噛んでくれるだろう。
と、そこでミカゼが、はむはむと僕の指を前歯で咥える。
「えっ、抜けない。痛たたたた」
噛む力が強くなっていく。無理に振りほどくわけにもいかず、ミカゼの口に指を挟まれたままの姿勢で立ち尽くす。飴でも舐めている夢を見ているのか、舌で指を舐め回してくる。僕の指は唾液でべとべとだ。
頼むから指じゃなくて薬の方に集中してほしい。
「あにゃおおいあー、いいおんぐんぐ(罠を閉じた。指示を頼む)」
「羊の話まだ続いてんのかよ。薬を噛んでくれ」
「おうあいいあ、いおんおもーもう(了解した。地獄に送ってやる)」
堅いものが割れる感触が顎を通して伝わってくる。万能薬の効果はすぐに出るはずだ。
ぱちり、と開かれたミカゼの目と視線が合う。
「おはよう」
「おあおう(おはよう)」
そのままミカゼは僕の手首を掴み、口から指を引き抜く。細やかな液体の雫が、重力に従って、輝きながら落ちていった。
ミカゼは手首を掴んだまま、首を傾げる。
「何で千早の手を食べていたんだろう」
「それは僕も聞きたい」
「邪悪な羊の群れを討伐する夢を見ていた」
「勇者はモンスター羊の夢を見るのか」
クラスのみんなは眠ったままだ。もしかすると、学校にいる生徒や教師みんなが寝ているのかもしれない。とても健康的なシエスタだ。
「魔界のモンスターの気配がする。すぐ近く」
「まさか、学校の中にいるのか」
「うん。急ごう。このまま放っておくわけにもいかない」
僕の手を引いて、ミカゼが教室を飛び出し、廊下を駆け出す。勇者は、魔王の手下に対して敏感だった。僕たちは風のように疾走する。
魔王軍の動きが活発化していると聞いていたが、人間に影響する魔法攻撃までしかけてくるとは。ついに、この世界に本格的な侵攻を開始したのかもしれない。
「どんなモンスターなんだろう」
「この気配は多分、魔王側についた人間だよ」
ミカゼが言う。魔王軍と契約を交わし、人間社会に紛れ込み害を成す。そんな脅威が学校に紛れ込んでいると。
「戦闘の可能性がある」
「まじかよ」
今まで森の中でしか、まともにモンスターと戦ったことがない。
日常生活で見慣れた場所は、剣を振り回すほどの戦場にならないと思っていたけれど、よく考えれば、敵がいたらどこでだって戦う可能性はあるのだ。変化のない日常は、実は簡単に壊されてしまうものだったのかと、恐ろしくなる。
ミカゼが目指す先は、校舎の端にある目立たない女子トイレだった。
「女子トイレ?」
「うん、女子トイレ」
「馬鹿な、聖域だぞあそこは」
「今はそんなこと言っている場合じゃないよ」
速度を緩めず、矢のようにミカゼが女子トイレに駆け込む。ついでに、引っ張られた僕も、いまだ踏み入れたことのない禁断の地へ突っ込んでいくことになった。
大賢者になってしまうかと思った。
男子用の小便器がないだけで、違和感がある。
そうか、女子トイレっていうのは、薄いピンク色のタイルで構成されているのか。などと冷静に観察しながら思考を整えようとするが、どうしてもそわそわと体が揺れてしまう。男子高校生にとって、女子トイレという場所は精神を集中できない場所なのだ。
僕がそう考えている間にも、ミカゼは女子トイレの中を見渡し、扉の閉じられた個室に視線を固定する。
誰かが入っている。
ミカゼが僕の方を一瞥して、一瞬頷いた。つられて、僕も頷く。テロリストのいる部屋を前にした特殊部隊のような緊張感だった。
あの中に、魔王の手先が潜んでいるというのか。
ミカゼは黙ったまま個室の前まで進み、だん! と垂直ジャンプした。
扉の上部に手をかける。
「へ、へっ?」
トイレに入っていたのであろう女子が驚く声がする。
ミカゼはそのまま、勇者ならではの身体能力を発揮し、懸垂の要領で体を持ち上げた。天井とトイレの壁の隙間から、がさごそがさごそと個室へ侵入していく。
勇者のはずなのに、むしろミカゼがモンスターに見える。あの動きはなんだか虫みたいだ。
甲高い悲鳴が中から聞こえる。もちろんミカゼの悲鳴ではない。
ミカゼの姿が完全に見えなくなり、やがて個室の鍵が開く音がした。
「どうぞ」
短いミカゼの声と共に、扉がゆっくりと開く。
トイレの中では、口をぱくぱくと動かしながら、便器の脇に女の子が腰を抜かしてへたり込んでいた。
「ど、どうして、え。ど、どうして千早さんがここにいるんデスか?」
勇者が来たことと、僕がいること、二つの意味の疑問をまとめて口にするその女子は、見覚えのあるクラスメート、黒土だった。
ここにミカゼが来たことが勘違いなどではなく、黒土が魔王の手先だというのが僕にもすぐにわかった。学校の制服の上に、ところどころ銀色のアクセサリーをつけた黒ずくめの衣装を着ていたからだ。
「おい」
とミカゼが、黒土の肩に手を置く。
「は、はいい」
「ここで何をしていた」
「い、言えないデス」
だあん! と便所の壁が音を鳴らして震える。ミカゼが空いた方の手で、木製の壁に裏拳を当てていた。敵を前にしたミカゼは、思ったよりも容赦がない。
「う、うひい」
「わかった。喋りたくなるようになるまで、私はここで待つ」
だあん! 再び打撃音。
小動物の鳴き声のような悲鳴が、黒土の口から洩れる。形勢が圧倒的過ぎてこっちが悪役に見える。ミカゼはまるで捕虜を尋問する軍の情報局員のようだった。
あのさあ、と僕が割って入る。
「は、ひゃい」
怯えたような上目遣い。彼女からは僕も凶暴な勇者の仲間に見えるのだろうと思うと気分が沈む。
「それ、弁当だよな」
「貴様は、回復アイテムも所持している。どうやら戦闘する気があるようだな」
「ち、違うんデス! これはただの昼食デス!」
「聞いたか千早」
「何を」
「昼食だと言った。これは回復アイテムよりもなお性質が悪い」
「ああ、便所飯だな。悪いのかこれは」
皆が楽しそうに輪を作ってお弁当を食べている。そんな脇でソロで昼食を食べるのは、なんとも寂しい気分になることだろう。飯が不味くなる、悲しくて食べてらんない。そうして、静かな安息の地を求め、トイレでご飯を食べる、つまり便所飯をする者がいるのだ。
「そう、便所飯。魔界へのゲートとこの世界の結びつきを強化する悪魔の儀式だよ」
知らなかった。孤独を愛する繊細な人間が、静かにトイレの個室で食事するのは、罪深き所業だったのか。
「ただの便所飯には問題がない。魔王の手先の秘術は、黒魔術の手順で便所飯を行うものなんだよ」
ミカゼが指で示す先を見ると、便器にいくつか五芒星の紋章が書かれている。確かにトイレをこんな感じでデコるというのは魔物特有の発想っぽい気がする。
便所飯、という単語が出るたびに、顔を赤くした黒土の俯く角度が深くなっていく。誰にも見られてはいけない行いであるのは、黒魔術であれ何であれ、変わらないのだ。
突然、黒土が溜めていた力を解放するかのように、顔を上げて大きな声で話し始めた。
「べ、便所飯の何がいけないんデスか! ば、馬鹿にしないで下さいデスよ、そ、そうやってみんな私を馬鹿にするから、わ、私は魔王の手先として、死神の儀式をグエーーー!」
言い返す黒土が喋り終わらないうちに、ミカゼが喉輪をかけたかと思うと、片手でぐいっと黒土を引き起こした。そのまま、黒土を宙に持ち上げる。黒土が軽いのだろうけれど、ミカゼの勇者としての力を改めて見せつけられる。
「う、うご」
「ついに正体を現したな、死神め」
さっきから黒土の語尾にデスとついているのは、死神だからなのか。確かに、少し前まではこんな語尾ではなかったはずだ。
そういえば、黒土は僕に、ゾンビではなく死神であると語ったことがある。なるほど今の衣装を着た写真で彼女のトレーディングカードを作ったならば、
【レア】悪い魔法使い 黒土 鵺
くらいにはなりそうだ。それでも見た目の弱々しさは拭いきれず、残念ながらそこまで高いステータスはつけてもらえそうにない。
吊し上げられた黒土の、死神の衣装の隙間から覗く脚は、細い。小柄な黒土は、締められている首、腕、胴それぞれが細く、華奢だった。不健康さを感じさせる痩せた脚は二本の棒のようだが、決してつまらないものではなく、丁寧に作られた美術品としての美しさを感じさせる。体全体とのバランスを考えると、いい評価を与えたい細さだ。もちろん、きちんと観察したならば、女性的な柔らかさも備えていることが分かる。
「千早、脚を見つめている場合じゃないよ。訊きたいこともあるし捕らえよう」
「あ、すまん。ひとまず黒土を縛ればいいのか」
そのまま黒土を倒しにかかるのかと思ったら、ちゃんと人道的に扱うみたいで少し安心した。ミカゼは、目についた魔界の存在を、問答無用で全て倒すわけではないらしい。
僕が紐か何か、丁度いいものはあるかなと辺りを見回した時だった。
「わ、私の邪魔をするなデスっ!」
黒土が、腕を振って抵抗する。その手には小さな鎌が握られていた。死神の衣装の中に隠し持っていたのだろう。
振り下ろされた刃が、ミカゼの胸に突き立てられた。ミカゼの力が緩み、解放された黒土は着地するとすぐさま、咳き込みながら僕を押しのけて走り去っていった。
「ミカゼ、大丈夫か」
「うん」
答えながらミカゼは、個室から一歩踏み出し、トイレの入り口を見る。黒土の姿はもう見えなくなっていた。
ミカゼの制服が赤く染まっていく。鎌は肩の下あたりに刺さったままだ。体の中心からは外れているようで安心したが、大丈夫には見えなかった。
「傷の手当てをしないと」
「滅茶苦茶痛い。でも腱や筋は切れていない。追いかけよう」
「サイボーグか、お前は」
「勇者だよ」
ミカゼは自分に刺さった鎌を抜く。赤い血液が垂れ、床にいくつもの斑点を描いた。
死神に鎌というといかにもな組み合わせに思えるが、よく見るとそれは、ホームセンターで売っている園芸用の小さな鎌だった。
ミカゼは黒土が移動した道筋を感じ取ったらしく、トイレを出てから悩むことなく校舎を進んでいく。意外なことに黒土は出口までの最短距離を逃げているわけではなく、一旦教室に戻っていたようだ。
黒土は教室の前の廊下に、僕たちを待ち構えるようにして立っていた。布に包まれたエクスカリバーを両腕で抱えている。
そして黒土の足元にはラメ入りのマーカーが転がっていて、床にはマンホールの蓋よりも少し大きいくらいのサイズの魔法陣が二つ書かれていた。走って近づけばどうということはない距離だが、警戒して少し手前で止まる。
黒土と目が合う。自信の表れなのか、口元に笑みがあった。あまり見たことのない彼女の表情だった。
「ほ、本当なら勇者を眠らせた隙に、こいつを奪う予定がだったんデスよ。で、でもどうやら上手くいきそうデス」
「なんだその魔法陣は」
「ふ、ふん、気になるデスか? お、追いかけてきた勇者をこうやって足止めするんデスよ! い、い出よ魔界のモンスター!」
黒土は後ろに下がりながらそう言い放ち、片足で床を踏み鳴らした。その途端、黒土が書いていた魔法陣が黒い光に包まれる。何度も見た、魔界の出入り口が現れる時の兆候とよく似ている。
「魔界のゲートなのか」
「千早、これは黒土さんの魔法だよ。便所飯の儀式で魔法の力を溜めていたんだ」
「僕は魔界の出入り口がトイレにならなくてよかったと思っているよ」
怪談話に出てくる女生徒の幽霊ならまだしも、恐ろしい姿のモンスターが恰好いい決めポーズで便器からせり上がって来る様子には、恐怖より先に同情を覚えることだろう。
魔法陣の光は柱となって天井近くまで立ち上った。そこから黒い帯状の影が飛び出し、空中を素早く動いてミカゼに襲い掛かった。
大人の腕ほどの太さがある触手状のモンスターだ。その皮膚は石のような質感があり、見るからに堅そうだった。
触手は蛇のようなしなやかさでミカゼの足を捕らえ、彼女の身体を這い上がって胴体をぐるぐる巻きにした。身動きの取れなくなったミカゼは、モンスターに縛られたまま床に倒れた。
僕はミカゼに駆け寄り、モンスターの隙間に手を入れてこじ開けようとしたが、縄のように固くてびくともしない。
「う、動けないようデスね。じ、じゃあ、ばいばいデス!」
死神の衣装を翻して、黒土が逃げていく。
「私はいいから早く黒土さんを追いかけて」
ミカゼはどうするんだ、と聞きかけたが、間を置かずに「早く」と促され、黒土を追いかけることにした。黒土が逃げていっているということは、向こうにも余裕がないのかもしれない。
廊下を走る黒土の背に向かって走る。足は速くないみたいだが、建物の中で見失ったら、追いつくのが難しくなってしまいそうだ。
「ち、千早さんも縛られるがいいデス!」
黒土は走りながら指をパチンと鳴らそうとして失敗し、びすっという音を廊下に響かせた。
「く、くっ、やり直しデス!」
焦った彼女が、廊下を踏みつけ、音を立てる。僕の背後で黒土の魔法陣が輝く。またモンスターを呼び出そうとするのか。
背後から音もなく触手が襲い掛かってくるのが分かった。僕は慌てて床を蹴って、横に飛んだ。モンスターは勢いよく僕を追い越し、狙いを外して黒土の足に絡みつく。
「わ、わわっ! ば、バカっ、私じゃないデスっ!」
黒土は足元でばたばたと動く触手のせいで、転倒しそうになりながらふらふらと走る。魔力のようなものが足りないからなのか、それとも人間の使う術だからか、魔界のモンスターを完全に制御できていないようだった。
「ひ、ひゃあ、そんなとこ入ってきちゃだめデスっ!」
「どんなとこだよっ!」
さらに触手が暴れるように動き、黒土が着ている死神の衣装ごと、制服のスカートを捲り上げた。
黒土の下半身の全容がよく見えるようになった。黒い服を着た死神は、下着も黒だった。
華奢であるとはいえ、黒土の腰にはきちんと豊かな丸みがついている。そこから膝下まで伸びる脚は、ガラス細工の繊細さを彷彿とさせる。爪先から腿までが全体的に細く、壊れないよう、触らずに見るだけで愛でるものだと直感が訴える。
「う、うわーん。ち、千早さんのトラップもなかなか卑劣なんデス!」
「僕は何もしていないぞっ、下着を見ただけだっ!」
「さ、さっ、最低デスっ!」
黒土は僕を罵りながら、持っていたエクスカリバーを触手にぶつけて振り払って、廊下を走っていった。
黒土が階段を登る足音が聞こえる中、僕は自分が、脚に見とれて棒立ちになっていたことに気がついた。
死神の術の威力が高すぎて、賢者では対抗できなかったらしい。僕は走り始めながら、いろいろと悔しい気分になった。
僕が追いつくよりも先に、黒土の方が力尽きた。
校舎の屋上に出てすぐのところで、黒土は地面にがっくりと膝をついていた。運動が得意ではない黒土は、慣れないダッシュにより体力を使い果たしてしまったらしい。
「ぜ、ぜえぜえ。ち、千早さんは、なかなかの強敵デスね」
「僕は黒土を追いかけただけで何もしてないぞ」
「ぜ、ぜえぜえ。し、しかもこれ、重いデス」
エクスカリバーも金属の塊である。勇者ミカゼならまだしも、非力な女子生徒には相当な重量物になるはずだ。それを抱えて階段を駆け上がるなんていうのは、ほぼ運動部のトレーニングメニューのようなもので、黒土には過酷だったようだ。
もう逃げ場はなさそうだったので、僕は立ち上がれずにいる黒土を見下ろしながら声をかけた。
「黒土はミカゼが勇者だと知っていたのか」
「げ、『月刊むむう』を見て知ってましたよ」
「あの雑誌、黒土も読んでたんだな」
「ま、毎月読んでるんデスよ。ち、千早さんも、勇者の仲間デスか」
「賢者らしい。僕はまだ魔法も使ったことがないけど」
「そ、そうデスか。ど、通りで私は写真を取られてマークされていたんデスね」
写真。そう言われて、ゾンビと書かれたトレーディングカードを見られたことを思い出した。あれは全く関係がない。
「ち、千早さんが勇者の仲間だったことは誤算デス。で、でも私はここで捕まるわけにはいかないデス」
黒土は立ち上がり、エクスカリバーに巻かれた布を取り払った。狭い歩幅で後退り、僕から離れる。
「こ、来ないでくださいデス。ち、千早さんも、ミカゼさんみたいに怪我をしてしまうんデス。け、怪我じゃすまなくなるかもしれないデスよ?」
挑発的に僕を制止する黒土。だが、黒土の肩が震えているのが、僕には見えた。人を刃物で傷つけたのは初めてだったのかもしれない。
黒土はエクスカリバーの柄を握り、僕に向けて構え、
「ふ、ふぎゃ」
と悲鳴を発して、再び膝をついた。エクスカリバーの先が地面に当たり、鈍い音がした。
「お、重ッ! な、なんデスかこれ!」
「ああ、それって重いんじゃなくて、勇者専用の装備だからだ」
勇者の使う伝説の武器には適性がある。『装備できない』武器を装備すると、なんとも言えない疲労感に襲われ、軽い頭痛までしてくるのだ。もちろん、本来の攻撃力を発揮することもできない。
黒土が慌てて、エクスカリバーの柄から手を離し、装備不可の拒否反応が出ないように、刀身を抱えた。勇者が持たない限り切れ味はほとんどないので、怪我をする心配はない。
肩で息をしながら剣を持つ黒土の様子を見る限り、すぐに取り押さえることができそうだった。
僕は黒土を捕らえようとして、彼女に向かって手を伸ばしかけた。だが同時に、黒土はエクスカリバーを頭上に掲げると、片足を持ち上げて地面をたんっ、と叩いた。
「そ、それでも私の勝ちデスっ! こ、この学校には術を張り巡らせているんデスよ!」
黒土がそう言い、僕は何かの影に入った。危険を感じて、後ろに一歩下がると、大きな鳥の翼が、僕の額を掠めていった。
巨大な伝書鳩が、黒土の真上を旋回していた。巨鳥はエクスカリバーを口に咥えて黒土から受け取ると、大きな羽音を立ててその場にホバリングを始めた。
「ゆ、勇者からエクスカリバーを奪ったんデス。こ、これで魔王軍がこちらに侵攻する時に楽になるんデスよ」
「黒土にはもう逃げる場所がないぞ」
「ち、千早さんは甘いですね。こ、こうやって逃げるんデスよ」
伝書鳩は足で黒土の肩を掴み、上昇した。黒土の身体が宙に浮かぶ。
「黒土さん、大人しく投降して!」
背後から、屋上に駆けつけたミカゼの声がした。離れつつある黒土に呼びかけるミカゼの声は、今まで聞いた中で一番大きかった。
「あ、あははっ、これから降伏するのは、お前たちの方なんデスよっ」
黒土は嘲笑しながら伝書鳩に運ばれていく。走って彼女を追うが、高さが足りない。
このままじゃ逃げられてしまう。そう思った時に黒土の方に向けて、僕の視界の脇を何かが勢いよく通り過ぎ、巨鳥の身体に突き刺さった。
ミカゼが黒土の鎌を投げていたのだ。
ダメージを受けた伝書鳩は、エクスカリバーは咥えたままだったが、足を開いて黒土を手放した。
「う、うぎゃっ」
投げ捨てられた黒土は、屋上のフェンスに斜め上から衝突した。
さらに、黒土が当たったフェンスは屋上の外側に向かって傾き、倒れていった。老朽化していたらしいフェンスの柱は根元から折れて、コンクリートの台座から離れた。
「あっ、まずい」
黒土を追っていた僕は、速度を落とすことなく走った。黒土は屋上の向こう側、空中を落ちていく。
僕は黒土の手首を掴んだ。
軽くても、一人分の重さだ。前傾姿勢の僕も下向きに引っ張られ、上半身が空中に飛び出しそうになる。
「うおおっ!」
空いた手を屋上の縁に置くことに成功した。ミカゼもまた黒土のもう一方の手を掴んでいたから、なんとか落下せずに済んだようだった。
数十メートル下に地面が見える。うっかりバランスを崩して屋上から離れようものなら、そう思うと腹のあたりの筋肉がせり上がる感覚がした。
「う、うぎゃああっ、落ちる、落ちちゃうデスっ」
「黒土、地面を見るんじゃない、上を向くんだ」
「あ、ああっ。ち、千早さんと、ミカゼさんに捕まってるデス。は、放してくださいデス」
「放したら落ちるよ」
「や、やっぱり放さないで下さいデス!」
「どうすりゃいいんだよ」
「千早、黒土さんを引っ張り上げよう」
僕は何とか顔を動かしてミカゼに頷く。だが姿勢に無理がありすぎた。どうにか黒土を持ち上げる体勢を作れないかと体を動かしてみるが、どうしても黒土と共に落ちてしまいそうになる。
ミカゼも同じようだった。
そして恐ろしいことに、次第に屋上の外側に向かって、僕とミカゼの身体がじりじりと動いていた。
「もうだめっぽいな」
「千早は生き返る能力を持ってる?」
「持ってるわけないだろう」
「私にもない」
神の祝福を受けた勇者は、戦闘で死んでしまっても復活できると聞いたことがある。それでも屋上から落っこちて体がミートソーススパゲッティのようになったら、多分無理だろう。
人体の一部には、豆腐のような部位があるらしい。ということは、ミートソースじゃなくて麻婆豆腐みたいになるのが正解かもしれない、など、極限状態で突拍子もないことを考えていると、黒土が小さな声を出した。
「は、放していいデスよ。落ちるのは私だけでいいんデス」
僕とミカゼが助かる、とても簡単な、それでいて選択肢から除外していた方法だ。
「そんなわけにはいかないだろ」
「ち、千早さんとミカゼさんが私を助けて落ちることはないデスよ。わ、私たちは敵同士なんデスよ」
だとしても、クラスメイトとして同じ教室で過ごしてきた女の子を、苺シェイクのようにはしたくなかった。ミカゼもまた、黒土を見捨てるつもりはないようだった。
「落ちる前に、何で黒土さんが魔王軍に入ったのか聞きたいよ」
「ミ、ミカゼさん。な、何でそんなこと聞くんデスか。わ、私を放せば落ちないんデスよ」
「黒土、早く言った方がいい。人生の残り時間がもうないっ」
「す、すみませんデス!」
「謝ってるとさらに時間がなくなるんだ」
「は、はい。わ、私はこの世界が嫌いだったんデスっ。とっ、友達とかうまく作れないデスしっ。上っ面だけ仲良くしてるような人とそうじゃない人の区別も上手くできないんデスよ。だ、だからずっと、この世界から仲間外れにされてるように思ってたんデス。こ、この世界が壊れてくれれば、そのヒビに自分の場所ができるんじゃないかって、思ったんデスよ」
黒土は言い残すことがないように、話し続けた。慎重に言葉を選ぶような時間もない中で彼女から溢れた言葉は、嘘のない本心なのだろう。
「こ、こんな理由なんデスよ。わ、笑いますか?」
「ありがとう。黒土さん。私は笑わない。自分の信じたように世界を変えようとする人は少なくない。革命家は、強ければ世界を裏返し、弱ければ排除される。淘汰を恐れないで何かに立ち向かう者を、私は笑わないよ。勇者の敵なら、戦うけれど」
理解者を得たかのように、黒土はミカゼを見つめた。
「黒土、よかったな。僕たちを巻き込んでこうなったせいで、最後だけは孤独じゃなくなったらしいぞ」
「ち、千早さん、ミカゼさ……」
黒土が何かを言いかけたが、もう限界だった。僕たちは屋上から落ちた。
マジかよ。心のどこかでは、ミカゼあたりが超人的なサイボーグ勇者パワーを発揮して助かるんじゃないかと思っていた。現実は厳しく、僕はエビチリ製造ラインに乗っかってしまったようだ。
バキベキホキバキバサバサーッ
落下の時間は長く感じられた。いつのまにか木が折れる音を聞きながら減速し、地面に衝突していた。
青い空を見ていた。僕は大の字になって寝ていた。騒がしい鳥の声が聞こえる。
「僕、多分生きてる」
「私も」
「わ、私もデス」
木の枝がとてもうまい具合に落下の勢いを殺したらしい。極限まで減速した上で、花壇の柔らかい土に落ちたから、打撲すらしないで済んだようだ。
僕は起き上がり、ミカゼと黒土の方を見た。同じように立ち上がり始めていた。体全体が震える。そりゃそうだ。屋上から落ちることに慣れてる人はいない。慣れる前に死ぬからだ。
「た。助かったんデス」
「こうなるならさっさと黒土を落とせばよかった」
「千早、屋上から落ちたようなダメージを受けてみる?」
「冗談だよ。勇者の行動についていくのも仲間だからな。それに助かると分かってても黒土を落としたくはないな。少しでもしくじったらすぐ脚が折れそうだし」
遠くで、鳥の鳴く声がした。一呼吸の間をおいて、ミカゼが僕に提案する。
「千早、ここは二人で、いいことを言おう」
「いいことを言う雰囲気だな、分かった」
せえの、と言うように、僕とミカゼは発声のタイミングを合わせる。
「黒土さん、私の友達になって」
「黒土、これで二重スパイだな」
「え、えっ?」
黒土が僕とミカゼを交互に見る。鳥の鳴く声が、再び風に乗って、秒速三百四十メートルで僕達の鼓膜に到達する。
「わ、分かりましたデス。わ、私はミカゼさんの友達で、二重スパイデスよ」
「ナイス黒土!」
「千早、後で校舎の裏に来て」
そういうミカゼの顔に、笑みが見えた気がした。
「黒土さん、明日から一緒にお弁当を食べよう」
「は、はい。ふ、ふつつかものデスがよろしくお願いします」
勇者と死神は、友達になったようだ。おそらく賢者の僕も。
「あれっ?」
ミカゼがふらりと倒れそうになっていたことに気がついた。慌てて彼女を支える。ミカゼが平気そうにしていたのでつい意識していなかったが、落下の衝撃で黒土に刺された時の傷が開いていたようだった。よく見ると制服の半分以上が赤く濡れていて、出血量が多いような気がする。
「わ、わ、ミカゼさん、大丈夫デスか?」
「うん。少し体に力が入らない」
と答えてミカゼは目を閉じた。術による状態異常などではない睡眠だ。気を失ったという言い方が正しいのかもしれない。それを見て、慌てた黒土が普段より大きめの声を出す。
「ご、ごめんなさいデス! み、ミカゼさんが死んじゃうデス!」
「落ち着け黒土、死んじゃうデスってのはギャグなのか」
「ぎゃ、ギャグちゃうデス!」
「ちゃんと突っ込んでるじゃないか。手当てをしっかりして薬草で回復すれば大丈夫なはずだ。でも傷の具合は見ないといけないな」
僕はミカゼを横たえる。血で染まった上着からは、独特の感触がした。見たところ傷の近くはまだ乾いていないらしく、生温かい湿り気を帯びていた。
僕はミカゼの上着を脱がそうとして気づく。服の内側にリボンを通している独特な制服の構造が分からない。リボンを解けばいいだろうか。それともどこかから留め具を外すのだろうか。ミカゼの服の襟を掴んで、どうしたものかとしばらく考える。
「ち、千早さん、こんなところでミカゼさんを剥いちゃだめデスよ。ふ、服は私が脱がせて傷の具合を教えます」
「スマン。よく考えたらいろいろ危なかった」
この後、ミカゼを空き教室に運び込んで、皆が睡眠状態で寝ている隙に手当てをした。黒土曰く、睡眠状態はしばらく時間が経てば勝手に解けていくらしい。誰も、寝ている間に学校の中を勇者や死神が駆けまわり、屋上からダイブしていたとは思うまい。
死神と勇者が友達になった次の日のことだ。
昼休み前の授業は国語で、小テストがあった。自分の国の言葉をテストされているのに、僕たちの点数は芳しくない。バベルの塔の神話で言語を引き裂いた神は、ついでに人間の頭の出来もばらばらにしてしまったのだろうか。
授業が終わり、根岸が話しかけてくる。
「今回の点数もK点だ」
「ネットゲームのやりすぎだな」
テストに関する僕と根岸の造語は多い。K点は、有名な文豪、夏目漱石の小説「こころ」に出てくる話に基づいている。大学の教授を務めるほどの教養と表現能力によって書かれた小説の一部が抜粋され、国語の教科書の題材となっていた。その中でKという人物が登場する。彼は「精神的に向上心のない者は、ばかだ」の名言を残す。最終的にKは自殺して死ぬ。
その範囲の授業を終えた後、僕たちは、「テストの点数が非常に低く、勉強する向上心が不足してばかになって死にました」の意味で「K点」という新語を作り出した。小説中のKが聞いたらもう一度自殺してしまいたくなるだろう。
根岸との会話を終えると、僕は売店にパンを買いに行く。そして、死神装束の黒土を初めて見た例の女子トイレへと向かう。
昼休みはミカゼや黒土と、どこかで一緒にお弁当を食べようと約束していた。そして僕は、教室の外で彼女と合流することにしていたのだ。昼休みに女子と連れ立って教室を出て行くのが、男子高校生としては少し恥ずかしかったからだ。
待ち合わせ場所のトイレの前には、既にミカゼと黒土がいた。
「ここだよ、千早」
「こ、ここ、こんにちはデス」
顔を赤くして嬉しそうに挨拶する黒土の弁当の包みは大きかった。線が細いのにやけに食べるんだな、と思って眺めていると、もじもじとしながら説明をしてくれた。
「と、とと友達とお弁当を食べるのは久しぶりなんデスよ。お、おかずを作りすぎてしまったので千早さんも食べてくださいデス」
「これはありがたい」
きっと満腹になった僕は、午後の授業をストレートに快眠することだろう。黒土は今日もまた睡眠の術を僕に使ってくるようだ。
そしてすたすたと、ミカゼと黒土がトイレの中へ入っていく。僕は彼女たちの背に慌てて声をかける。
「おい。何故トイレに入るんだ」
「お弁当を食べるためだよ」
「わ、私のいつもの場所で、お弁当を食べることにしたんデスよ」
「何で便所なんだ。初めからもっと爽やかな場所で食べればいいのに」
「千早は分かっていない。トイレという空間は、外界から切り離された安息の地」
「それも個室あってのものだと思うんだが」
「だ、大丈夫デス。ひ、人払いの結界を張っているんデスよ。だ、だから誰もここに来ませんし、千早さんが女子トイレにいても見つかることはないんデスよ」
怪しげな術を使っているようだ。これはいいのだろうか。ミカゼが何も言わないので、実際問題はないのだろう。どちらかというと、便所で飯を食うために手先の死神が結界を張っていることを知った魔王が深くため息をつくところが想像できる。
僕は昨日に引き続き女子トイレに入る。女子トイレという空間には、まだ違和感がある。これに慣れると、そのうちうっかり一人で入ってしまいそうで心配になる。
「どうやってここで昼飯を食べるんだ。みんなで個室に籠って飯を食うのは不気味すぎるぞ」
「シートを広げる」
ピクニックのように敷物を敷いて、床の上で食べるらしい。そんな開放的な便所飯は聞いたことがない。集団便所飯という、これまでにないスタイルになるようだ。
「シートを使うって言っても、トイレの床だぞ」
「心配ない。キレイダナー」
「えっ?」
「キレイダナー」
「黒土、大変だ。ミカゼがおかしくなった」
「こ、これは呪文デスよ」
ミカゼの発声によって、トイレの床に緑色の光が瞬いて、消えた。除菌もできるトイレ用洗剤のCMのイメージ映像のように。
「これでトイレの床はとても綺麗になった。床を触った手でご飯を食べても毒状態になることはないよ。試してみる?」
「わざわざトイレの床を触るのは、魔法の効果というより僕の人間性を試すことになるだろうが」
「で、ではシートを敷きますデスよ」
ばさっと、白地に黒い蝙蝠が書かれた柄のレジャーシートが、トイレの床に広がる。ミカゼと黒土がその上に乗り、弁当箱の中身をつつき始める。僕も、シートの上に乗った。さわやかな風が吹き、青い空が見える草原ならともかく、便器を見ながら食事をするのは、かなり気分が重くなる体験だ。
花の香りがするけれど、それは芳香剤のジャスミンの香りだ。
黒土は悲しいことに便所飯に慣れていて、ミカゼは魔法でトイレを浄化した本人だからなのだろう、楽しそうに弁当を食べている。一方僕は、やはり今いる場所が気になってしまう。
「同じものでも、心が一度変わると同じものには見えなくなるという話を思い出した」
「ど、どういう話デスか」
あるお寺に修行者が訊ねてきた。和尚さんは、小便を入れた湯呑みを修行者に見せた。次の朝、和尚はその湯呑みを丁寧に洗ってから、どうぞ飲んでくださいと、水を入れて修行者に差し出した。修行者は、それは汚くて飲めませんと言った。和尚は「物は変わらずにここにあるだけなのに、心が変わってしまうと見え方が変わり、行動も変わってしまう。綺麗なはずの湯呑みが、あなたの心を通したことで、あなたからは汚く見える」と修行者に伝えた。自分の心で見た結果、世界を正しく見ることができているかを常に考えよと、戒めている話だ。
当然、そんなふうに戒められても、僕にはここが昼食にふさわしい場所には見えない。女の子二人を前に昼飯を食べている状況が、まだ救いか。
「小便を入れたコップを綺麗に洗って、ジュースを入れて飲むことを考えてくれ」
「千早は、小便を注いだコップでジュースを飲むのか」
「え、えっ、千早さん、なんでそんなことをするんデスか!」
「僕はそんなことはしないよ! こういう話なんだ。例えば、その弁当箱に昨日、大量のゴキ」
「おい千早その話はもうやめて」
「う、うう、なんだか気持ち悪くなってきました」
「安心しろ黒土、便器ならすぐ目の前にある」
「おい千早その話はもうやめて」
彼女たちにも僕の気持ちが少しは分かっただろうか。しかし、昼食の気分を害してしまったので、申し訳ない気分になってくる。
話題を変えようと思い、パンを齧りつつ、僕は気になっていたことを黒土に訊ねる。
「ところで、黒土はどうやって死神になったんだ」
「あ、ああそれはデスね、『月刊むむう』に魔王軍の求人広告が載っていたんデスよ」
「マジかよ。勇者の特集と同時に載せるっていいのか」
「弱小雑誌は、広告料で金を作らないと死んでしまうみたいだよ。地球侵略をする宇宙人が求人を載せていたこともある」
「凄えな『月刊むむう』。毎日の地球滅亡予言が書かれている日めくりカレンダーは当たったためしがないのにな」
「そ、そこにはデスね、このアドレスに空メールを送ると、魔王軍に仮登録できます! 本登録用のURLを返信致しますので、そこにアクセスして登録を完了してください。な、なんて書いてあったんデスよ」
勇者側もスマートフォンのアプリを使っているけれど、魔王軍も大分IT化が進んでいるのだなと思った。最近のモンスターは機械語の呪文を使うのか。
「そ、それで、私には闇の儀式の素質があったみたいで、採用されたんデス。君は一生便所飯をし続けるべきだ、って言われたんデスよ」
「なんか嬉しそうに言っているけど、黒土はそれでいいのかよ……」
闇の術を使うのはまだいいとして、勇者のエクスカリバーを盗ませようとするなんて、魔王軍も無茶をするものだ。アルバイトの仕事じゃない気がする。
「ゆ、勇者と戦う時は危険手当てボーナスが出るんデスよ。ま、魔王軍は人手不足でアルバイト募集中なんデスよ。モンスターはいっぱいいても、人間が応募してこないらしいデス」
「それは求人広告が怪し過ぎて誰も応募しないだけだと思うぞ」
暗黒の力を活用したい方を歓迎します、なんて広告を出しても、労働環境の悪いブラックな仕事に見えそうだ。
「魔王軍の話をしていて思い出したんだが、近いうちに魔王軍が攻めてくるというのは本当なのか?」
「は、はい。それは本当デス。そ、その下準備で、この学校に術を張り巡らせたり、勇者のエクスカリバーを奪ったりしようとしていたんデス」
穏やかな日々が続いているように見えて、実は全面戦争が迫っているようだ。かつて数百年に渡って繁栄した数多くの国や都市が、今はなくなってしまっていることを考えると、ありえないとは言い切れない。心配事もなく暮らしている中で世界が終わることを実感するのは、なかなか難しいことだけれども。
月刊むむうの特集記事、『徹底検証! 魔王軍×勇者戦力分析!』によると、魔王軍が総攻撃を仕掛けた場合には人間側の勝ち目が薄いらしい。世界各地に魔界のゲートを作り、大量のモンスターを送り込む物量作戦だ。
むむうには、「総攻撃の日は近い!」と、自信満々に書かれていた。
僕はミカゼの方を見た。最終決戦が近いことを聞いて、僕はこれから起こることに想像を巡らせていたのだけれど、ミカゼはいつもと変わらぬ表情で春巻きを食べていた。
だが、ミカゼが次に言った言葉は、僕にとっては意外だった。
「千早、強いパーティメンバーが必要になる」
「仲間を集めるってことか。割とやる気満々なんだな」
伝説の血を引く勇者なら、当然といったところなのだろうか。僕は、全面戦争は他の、どこか遠くの町にいる勇者に任せてしまってもいいんじゃないか、と考えていたくらいなのに。
「魔王軍との決戦の話じゃなくて、モンスター退治に必要だよ」
「えっ、それは僕ですらあまりいらなさそうだけど」
「千早はチャリを漕ぐ」
「それは本来、勇者の仲間の仕事じゃないだろ」
どうやら自転車の二人乗りは、ミカゼの中でもう完全に固定してしまったらしい。
「もしかして、山に出るモンスターが強くなるのか」
「違うよ。私が弱くなったと言っていい。エクスカリバーはもうないから」
そう言われて、僕はエクスカリバーの行方を頭の中で再生した。
「黒土の鳥が持って行った」
「ゆ、勇者から聖剣を奪うという私の企みは、せ、成功しちゃってたんデス」
黒土がしゅんと肩を落とす。既にエクスカリバーは魔王軍幹部の元に届けられたらしい。
「山に出るモンスターは、伝説の武器で戦えば楽に勝てるけれど、実はとても強い。今の私と千早だけでは苦しいと思う」
ついに、勇者を見ているだけではなくなるようだった。もちろん、僕が巨象やドラゴンとまともに戦える自信はない。ミカゼの言う通り、勇者のパーティの人数を増やすしかないだろう。
「わ、私も一緒に戦わせて下さいデス。こうなったのは私のせいデス」
あっさり一人増えた。
「黒土さん、私たちのモンスター退治は夜だから、帰りが遅くなるけど大丈夫?」
「だ、大丈夫デス。うちはお父さんもお母さんも、共働きで帰ってくるのが遅いデス。私はいつも一人で月刊むむうを読んでるだけデス」
僕とミカゼは門限を確認したかっただけなのに、なぜ黒土の家庭事情というか、生活を心配して心を痛めているのだろうか。黒土の親に会ったら、おたくの娘さん、魔王軍に入隊しているみたいですよ、ちゃんと見てあげられていますか、と忠告してあげないといけないのかもしれない。
勇者ミカゼのパーティが持つ戦力は、黒土を加えてもまだ心許ない。ミカゼはともかく、黒土はモンスターの攻撃をうっかり一撃食らうだけで棺桶に入ることになりそうだ。
「午後の休み時間に仲間を探そう」
「どうやって探すんだ?」
「賢者が一番最初に覚える魔法がある。千早もそろそろ使えるようになっているはず」
「ついに僕も賢者らしい仕事ができるようになるのか」
「私には使えない呪文だよ。周りの人間が勇者の仲間になれる存在かを調べる。その魔法は『ワカルヨー』という」
それを聞いた瞬間、さっきミカゼがトイレ掃除の魔法を使ったところが、僕の思考にフラッシュバックした。
「なんだか嫌な予感がするんだけど」
「やり方を教える。リラックスして、ワカルヨー、と叫ぶ。効果時間が短いから、教室で使った方がいいよ」
「突然そんなことを喚いたらもう賢者じゃない。変な人だ」
僕は、黒土の術で皆を眠らせた後に魔法を使うことを希望した。
「こ、この前ので力を使いすぎたんデス。か、回復までには何週間もかかるんデス」
マジか。教室の中心で、変なことを叫ぶ。僕は相当に気が進まない表情をしていたらしい。ミカゼが僕を見ていた。
「千早は、仲間を探すのがそんなに嫌なの?」
咎めるような目ではなかった。いつも通りなクールな目ではあった。だけどなんとなく、信じ切っていた親友が、実は自分が持つ信頼感ほどには、自分を大事には思っていなかったことが分かったような、がっかりした感情で僕を見たような気がした。
違う。そうはっきりと言いそうになった。僕は、今までずっと、賢者として勇者に協力したいと考えてきたはずだ。
ミカゼに失望されるのはなんだかとても嫌だ。
「僕は魔法を使うのが初めてだからな。落ち着いて呪文を言いたいと考えていたんだ。失敗して、根岸から知能指数を吸い取る魔法を使ってしまったら大変だと思った」
「な、なるほどデス。根岸君の心配もするなんて、千早さんは友達想いデス!」
「そうなのか。じゃあ千早、私が魔法を使いやすい状況を作るよ」
なんとかうまく言い訳できたようで、ミカゼが珍しく、ほっとした顔を見せた。
「じゃ、じゃあこういうのはどうデス?」
配水管に水が流れる音だけが響く静かなトイレで、僕たちは仲間を探す作戦を練った。
勇者の仲間探しが始まった。
数学の授業が終わる。予定では、ミカゼが僕の席の前までやって来て話を始めることになっている。
だが、その前に根岸が口を開く。
「そういえば昨日、ネットに乗っていた記事でさあ……」
休み時間は大体、前の席の根岸がこちらに椅子を向けて、雑談を始めてくるのだ。いつものことなので、これは織り込み済みだ。
ガタンッ、と根岸の机が音を立てる。黒土が軽く体当たりしたのだ。
「ふ、ふぎゃっ」
黒土の短い悲鳴を聞いて、驚いた根岸が意識をそちらに向ける。
「ええっ、黒土さん、どうしたんだい」
「す、すみません。貧血でふらふらしてあたっちゃったんデス」
「大きい音がしたけど、怪我とかしてないかい」
「だ、大丈夫みたいデス……」
黒土が根岸をブロッキングしている間に、ミカゼが僕の机に数学のノートを載せた。
「千早」
ミカゼのパーティによるコンビネーションで、僕が魔法を使う準備が完了した。
「さっきの内容の、類似問題の解き方を教えてほしい」
「ああ、これは底面の中心を原点にするんだ。そうすると点xの切り口が直角二等辺三角形になるから半径の範囲で積分すると体積が、ワカルヨー」
僕は語尾を強調して少し大きめの声を出した。これは人間のステータスを確認する呪文だ。
魔法の発動と同時に、ぱああーと爽やかな効果音が教室に響いているが、事情を知らない生徒たちは、スマートフォンの着信音かなんかだと思ってくれるだろう。
目の前のミカゼの頭上には『勇者』という文字が浮かび上がって見える。この呪文で表示される内容は、呪文を唱えた僕にしか見ることができない。持続時間が切れる前に、クラスメイトが勇者の仲間としての適性を持っているのか、確認していく。
黒土は『魔法使い』だ。僕が市役所の登録から洩れていたように、彼女も恐らくは、素質があるのに見落とされてしまっていたのだろう。先に魔王軍に入ってしまったので、闇の魔術に特化した『死神』になってしまったようだけれども。
根岸には『村人』と表示されている。村人とは、勇者の仲間になれない者のことらしい。
これって村に住む人を馬鹿にしてはいまいか、そんな気がしてくる。
おそらく、ステータスを見る魔法の日本語バージョンを作った魔法使いが、『一般人』といった意味の単語を『村人』に誤訳したのだろう。パソコンが進歩する前は、自動翻訳ソフトの性能が悪く『Japan』という単語が全て、日本の食器を表す『漆器』と訳されたと聞いたことがある。それと似たような現象が起きているように見える。
僕は教室を見回し、ステータスの確認を続けた。
クラスメイトは皆、村人だった。
僕が賢者で、さらに魔法使いまで同じクラスにいたんだから、すぐに仲間が見つかると思っていたが、偶然が重なっていただけだったようだ。
「全然だめだ」
僕は横に首を振った。隣のクラスに当たってみるしかない。ミカゼと前もって打ち合せをしていた通り、もう一度呪文を使う。
「次の問いを」
「この問題は極座標の曲線の長さの公式に合わせて、曲線の公式の二乗と微分の二乗を使えば、ワカルヨー」
尚、数学についてはミカゼの方が成績がいい。今ミカゼに聞かれている問題の答えは、僕には全く分からない。適当なことを言っているだけだ。
ぱああー。効果音。
僕は魔法の持続時間が切れないうちに、ダッシュで隣のクラスを覗きに行く。
全員村人。
席に戻り、僕は首を振る。
「じゃあ次の問いを」
ミカゼが指で示した先は、教科書の問いの中でも、難問中の難問だった。意味不明な記号の羅列が並んでいる。
「虚数だ、無の世界だ。ワカンネエヨこんなの!」
「千早、違う、そうじゃない」
ミカゼが台本通りにやれと僕に突っ込んだ。
その後も何度か問題を出し合う。
「C組の深谷と答え合わせしてくる」
「いってらっしゃい」
僕が走り回っても不自然じゃないように一応理由づけをして、他のクラスへ走る。廊下にいる生徒もチェックする。
同級生は皆、村人だ。
その結果を伝えると、ミカゼはありがとうと僕を労って自席に戻っていった。
魔法を連続で使った疲労感から、僕は椅子に深く腰掛けて大きく息を吐いた。次は町にて片端から通行人を見ていくしかないか。
魔法の力にも上限があり、一日に何度も呪文を使えるわけではないようなので、連発はできない。ちなみにミカゼの情報では、次にモンスターが出るのは明後日の夜らしい。時間が残されていないのが悩みどころだ。
「千早、お前ってミカゼに数学を教えてるのか」
「さっきの授業、居眠りしていたらしい。内容を聞きに来たよ」
僕とミカゼの会話を見ていた根岸が興味深そうに訊いてくる。なんだかんだで、ミカゼはクラス内で一目置かれていて、皆が気にしている存在なのだ。
僕が何故ツッコミを交えつつミカゼと会話をしていたのか、根岸は理由を知りたいようだった。
「いつの間にミカゼとそんな仲になったんだよ」
「世界史のノートを貸したことがあるんだけど、僕のまとめ方がやたらと気に入ったみたいだ」
僕は適当な思いつきを話して誤魔化しておく。
「えっ、もしかしてミカゼって意外に、授業を真面目に受けてないのか」
「ミカゼの特技は、授業中、ばれないように寝ることらしい」
「意外だ。あんなに真面目そうなのに」
「実は授業中に、机の上に枕を置いて寝ているらしい」
「まっ、マジかよ、どんだけ度胸があるんだ。ミカゼは勇者か」
「伝説の勇者だな」
話の途中でミカゼを不良生徒のように言ってしまい、彼女のイメージを崩してしまったけど、何とか勇者としての彼女の威厳を回復しておく。
「俺も勉強してミカゼとお近づきになりたいぜ」
「なれるんじゃないか」
「よし、まずは数学だ。ミカゼに数学を教えられるように問題を解きまくるぞ」
根岸は気合を入れた。
残念だが、ミカゼの数学の成績は学年でもトップクラスだ。根岸がミカゼにも分からない問題を解けるようになる前に、脳味噌が溶けてしまうだろう。
次の授業では、暖房が効くようになった教室が暖かく、僕と根岸は仲良く居眠りをした。
僕たちは放課後、どうやって仲間を増やすかを話すために、トイレに集まっていた。
第二次トイレ会議である。
小用便器のない便所は、何度来ても落ち着かない。
「千早の知り合いに勇者とかはいる? 盗賊でもいいんだけど」
「いたら仲間探しで悩んでないよ。というか、そんな犯罪者でも勇者の仲間でいいのか」
「と、盗賊には義賊もいるからデスかね? せ、世界中の大金持ちから財産を没収して、富の再分配デス」
「世界を騒がすような大泥棒と友達だったら、僕は今頃ICPOに逮捕されてるよ」
「ミカゼの親とかは」
「無理。お父さんは7つの妖精大陸を救うために、私が小さい時に精霊の国に旅立った。あと何年かは帰ってこないと思う」
「なんじゃそりゃ」
「ち、千早さんの親はどうなんデス?」
「ぎっくり腰だぞ。仕事も忙しくて、勇者の仲間はできないと言っていた」
「た、多分私の親もそうデスね。今さらそんなことはできないと思うんデス」
世界の危機が迫っていると言っても、この世に生きる人々には、仕事や生活があって、なかなか世界のためには戦えないのだ。突然、大人たちを頼りにするわけにもいかない。
そもそも、ミカゼはパーティメンバーがいなくて、やっと僕が来たくらいだから、あてがないのは分かりきったことだった。黒土には、もちろんないはずだ。勇者の仲間になれるくらい頼れる人間がいたら、魔王の手先になっていないだろう。
「勇者の仲間になれるくらいの強い人か……」
僕には、強い人と言われてすぐに思い出せる人がいた。出てこなくていいですと言っても、順番待ちにぐいぐい割り込んで真っ先に出てきてしまう。
「か、考えごとをしてるみたいデスけど、誰か心当たりが、あるんデスか?」
「あると言えば、ある」
僕の知る中では、ミカゼとどちらが強いのか、想像できないほどの人物。男子生徒の作ったトレーディングカードゲームの上級生版では、その先輩はかなり高性能なカードになっている。
【ゴールドレア】マスターオブソード 鳳凰(ほうおう)ヒメナ
盗撮されていることを見抜いているのだろう、彼女の写真はこちらに向かって笑顔でピースをしていた。