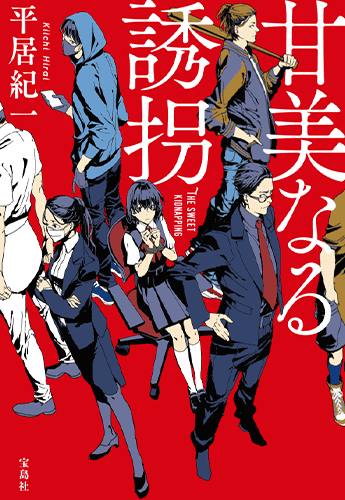試し読み
第一章ニューフェイス暴力団周辺者の日常 1 「てめえら、何なんだ、昨夜の客の入りは!?」 怒鳴り声と同時に、硬い物が飛んできた。ゴン、と音を立てて市岡真二の額に当たったが、床に転がったのを見ると、百円ショップで買った安物のマグカップだ。荒木田はけっして値の張る物は投げない。 真二と相棒の草塩悠人は、黙ってさらに頭を低くした。 「なんで、てめえらみたいな半人前に、おれのシノギを分けてやってると思ってる!?」 二言めには恩着せがましいのも、荒木田のいつもの癖だ。 「そら、パーティー屋なんちゅうシノギ、手間かかる割りに儲からんからとちゃいますか」 悠人が場違いに能天気な声で言う。とたんに、今度は悠人の顔めがけてまた何かが飛んだ。 「──あッつーッ!」 もんどりうって悠人が横転する。 「いいか、集客がわるかった理由を分析して、改善策を考えろ。あすの朝までに報告書をまとめるんだ。ビジネスマインドがないやつは、こっちの世界でも生き残れねえぞ」 言い捨てて、荒木田は席を立った。部屋を出ていく後ろ姿を頭を下げたまま見送る。 「けっ。なーに言うとんのや。ビジネスマインドやて。笑わせるわ。オレら、マジメに働くんがイヤやからヤクザやっとるんやないか。なあ?」 荒木田の椅子にどっかり腰を下ろすと、悠人は葉巻入れを勝手に開けて、高級葉巻を口にくわえた。握っていたライターをカチンと鳴らす。 「それ、さっき投げつけられたやつかよ」 「そうや。手で摑んどいてな、顔に当たったふりしたんや。どや、うまいもんやろ」 「それよりおまえ、報告書やっとけよな。この頃、おればっかり書いてるんだから」 「あ、そりゃあかんわ。頼むわ、真二。おれが打つとあのボロパソコン、誤変換ばっかりしよってなあ。また荒木田に蹴飛ばされなあかんし」 片手拝みする悠人に、真二は舌打ちするしかない。 草塩悠人は真二よりひとつ年上の二十三才だが、古いヤクザ映画の大ファンだった。『昭和残侠伝』『日本侠客伝』『網走番外地』といった高倉健のシリーズはもちろん、菅原文太の出演した『日本の首領』『仁義なき戦い』などの実録ものもほとんど見尽くしている。生まれ育ちは大阪だが、高校を中退してぶらぶらしているうち、地元にいられないような不始末をしでかした。東京に出て新宿で遊んでいるところを、歌舞伎町を根城にする麦山組にリクルートされたというのが悠人の自慢だった。 別の組のヤクザ三人と大立ち回りした度胸を買われたと本人は言っているが、真二は信じていない。背はそこそこあるものの、痩せぎすで、力はなさそうだ。口八丁なだけなのではないか、と真二はこの相棒をあまり頼りにしてはいなかった。悠人が組員になりたいと本気で思っているのかどうかも、よくわからなかった。 現代のヤクザは先細りの衰退産業なので、どこの組もどんどん人が減っている。高度経済成長の時代には十万人越えだった組員が、今では二万人を割り込むありさまだ。とくにバブル崩壊からあとの減り方はすさまじく、毎年数百人が組を離れているという。 前回の東京オリンピック頃を描いたヤクザ映画では、大親分はみな大豪邸に住まい、幹部は高級外車を乗り回している。今ではそんなヤクザは絶滅危惧種どころか、絶滅確定種である。真二たちがいる麦山組も貧乏で、組員は十四人しかいない。そのうち六人は懲役に行っているので、娑婆にいるのは八人だけだ。 親分、もとい社長は芸能プロと探偵社とイベント会社を経営している。どれもたいして儲かってはいない。それを統合している新明興業というのが、真二と悠人の所属する会社だった。新明興業の社員ではあるけれど、麦山組の盃はまだ受けていない二人は、だからヤクザのインターンなのだった。 悠人は義理と人情のために白刃をふるう東映映画の健さんが大好きだが、麦山組の親分のためにどこかへ殴り込むかといえば、そんなことはしそうもない。真二にもむろん、その気はさらさらない。麦山親分は、ちょっとおっかない、ただの職場の親方でしかなかった。 「そうや真二、ほれ、『鈴蘭』のマスターな。こないだ飲み行ったら、ねえシンちゃん連れて来てよぉ、言うて、おまえの話ばっかりしとったで」 「うるせえって。いいかげんにしろ。ちゃっちゃと仕事行くぞ」 真二は思い切り不機嫌な声を出した。幼い頃からまるで女の子みたい、と言われることが真二は大きらいだった。そのあとには、可愛らしいとか色が白いとかいったお定まりの言葉が続く。 母親がおもしろがってマッシュルームカットにさせていたので、服装によってはほんとうに女の子に間違われた。真二はそれが不愉快で、小学校高学年になるとスポーツ刈りを好むようになった。幼い頃から女子にはモテた。ところが思春期に差しかかる頃から、今度は同性愛者の男にも好かれるようになった。どちらも鬱陶しい。 2 わずか二百万円の手形を落とすようなことになったら、植草部品もいよいよおしまいと世の中に触れまわるようなものだ。いざとなれば取引のあるわかくさ信用金庫に四百万円近い定期預金が積んであるし、都銀に預けてある家計の預金もたぶん三、四百万円はあるだろう。母が亡くなってから父が通帳を抱え込んでいるのでよくわからないが、父は真面目な性格だ。家計の管理は手堅いはずだった。 しかし虎の子があるから、と安心しているわけにいかない。仕事でまわしている当座預金が底を突きかけているからだ。 植草菜々美は私立大学を卒業すると、すぐに父親の浩一が経営する自動車部品販売会社に入社した。会社といっても、従業員は六名、浩一自身と経理を見ていた母も入れてだから、ほぼ家族経営のようなものだ。家族のほかにバイトの配送ドライバーが三人。 浩一が会社を起こしたのは昭和の終わりで、今から振り返れば日本経済の最盛期だった。ジャパンマネーが世界を席巻し、ロックフェラーセンターを三菱地所が買収するというシンボリックな事件もあった。日本全国の不動産価格で、アメリカ全土を四つ分買えるなどとも言われた。円高が進み、アメリカ車が売れだし、国産車も飛ぶように売れた。それにともなって修理工場やガソリンスタンドにも好景気の波が押し寄せた。植草部品のような末端企業にまでそれが及んで、バイトも増やした。 植草部品の社屋は、旧甲州街道沿いの角地に立っている。二階建てのモルタル建築だった。一階に営業カウンターを置き、二階が事務所、残りのスペースはすべてカイコ棚式の倉庫だ。築四十年の建物は老朽化が目立ち、いかにも貧乏くさかった。 いずれは鉄筋コンクリートのビルに移り、ゆくゆくは自社ビルを建てて、扱い品もどんどん増やそう。浩一にはそんな夢があったという。修理屋やスタンドへの量販品デリバリーサービスがメインだが、いずれリフト機や注油機、洗車マシンなど大物も扱えるようにしたい。 浩一の夢はあれこれと膨らんだが、バブルの生んだ好景気はあっけなくしぼんだ。 バブルの頃には、腰が抜けるほどの立ち退き料をちらつかせて、不動産屋が地上げにやってきたが、パタリと姿を見せなくなった。いくらでも融資するから地所を買ってビルを建てろと誘っていた銀行も、まったく寄り付かなくなった。 そのあとは、植草部品も地を這うような苦しい日々の連続だった。うるさいほど鳴っていた店の電話が、一日鳴らないこともあった。 この頃、ひとつだけ明るい光が、植草家に射し込んだ。もうできないものと思い込んでいた子どもが授かったのだ。そういうわけで、菜々美が生まれたのは、両親がいちばん苦労していたその頃だった。植えた草の中に菜の花が美しく咲いている。菜々美の名前はそんな菜の花のように、明るく、地に足を根差して生きていけるように、という意味だと母から聞かされていた。 菜々美が大学を出た翌年、母が亡くなった。風邪ひとつ引かない健康自慢だったのが、検診で乳がんがあると言われた。見つかったときすでに第Ⅳ期で、手術も放射線治療も適用外という診断だった。一年経たずに命が尽きた。その後は浩一と菜々美が中心になり、ルートドライバー兼営業の社員がひとり、バイト二人でどうにかやりくりしている。菜々美自身もドライバー、書類作成、銀行やディーラーとの交渉ごとと何でもやった。 結局、事業拡大という父の夢は夢に終わるのだな、と思うこともあったが、寂しいとは思わなかった。親子二人、食べていくには不足はない。吹けば飛ぶような会社だが潰れも傾きもせず、平成不況だの失われた二十年だの言われる時代を乗り切ってきた。胸を張っていい。 ただし、菜々美自身が跡を継ぐのは、とうにあきらめている。もう小さな自営業が生き残れる時代ではなくなった。古馴染みの寿司屋、蕎麦屋、中華料理屋、自転車屋、本屋、酒屋、みんなこの二十年ばかりの間に店を畳んでしまった。自動車部品の卸も、大きなところが東京ばかりか関東エリアにチェーン展開して、修理工場、ガソリンスタンドを網羅している。植草部品みたいに、三多摩東部だけで商売しているような個人企業は、いずれ消えていくしかないのだ。 それでもいいじゃないの、とこの頃の菜々美は思っている。達観しているわけではないが、ものごとにはすべて寿命があるのだ。事業や商売にも盛りがあれば、必ず衰えがある。浩一の気が済むまで時代とそれなりにうまく付き合えたなら、以て瞑すべしだ。父の人生はわるい人生じゃない。 自分自身の人生はそれからまた探せばいい。就職するときに迷わなかったと言えばウソになる。けれど大学の頃の友だちで、一流企業に勤めた子たちだって、会えば愚痴ばかりだ。思うように人生を謳歌している子なんて、ほとんどいない。実家で働いている菜々美を羨む声さえあるほどだ。だから、もう少し父や会社の仲間たちとがんばってみよう。 そう思っていた。あのヤクザ者がやってくるまでは。 店の土地と建物を売らないかという話が最初に来たのは、半年ほど前、今年の春先だった。浩一は最初から本気にしていなかった。都心や湾岸ならともかく、何を今さら、と菜々美の前でも笑っていたくらいだ。 「お隣のアパートの大家さんも、この際だから土地はまとめて手放してもいい、とおっしゃっているんですよ。ええ、三棟すべてです。それから向こう角の連棟式店舗、じつは、あそこももう売却の条件交渉に入っている段階で」 だからあとは植草部品さんのこの建物だけなんです、と不動産会社の営業マンはうれしそうに愛想笑いを浮かべた。肩書は地元支店の営業課長になっているが、ひどく童顔の男だった。こうしてビジネスの話をしているのが楽しくてたまらないといった表情だった。 「それで複合ビルを建てるっていうの?」浩一が訊いた。 「そうなんですよ。一階は店舗を入れて、二階から上を住宅にする予定です。ぶっちゃけて言うと、もうコンビニとかミニスーパーの引き合いが来ているくらいでしてね。売却していただけるとすれば、けっしてわるい話にはならないと思いますよ」 「そう言われてもさ、あのアパートはもう老朽化してて、店子は半分もいないんじゃないの?角の長屋だって、あそこはしょっちゅう店が入れ替わるんだよ。だれも居着かないんだ。そういう物件とウチといっしょに扱われても、ちょっとねえ」 「ごもっともです」 営業マンはおとなの話を聞く賢い子どものような目で、浩一のしゃべることに耳を傾けていた。「それでしたら、私どもの方で移転先の物件を提供させていただく、というのはいかがでしょうか」 「そう簡単に言うけどね、ウチらの店はそう簡単に移転なんかできないんだよ」 浩一はちょっとむっとして、ちらりと菜々美の顔を見た。話に加われという意味だな、と思って、菜々美は浩一の隣に腰を下ろした。 「もちろん、よくわかっております。ですが、お嬢さんの将来ということもありますから。ここらで心機一転するのもよろしいのではないかと」 営業マンはキラキラした目で菜々美に語りかける。この子どもっぽい顔をした男の接客姿勢を認めるに吝かでないが、やはり不動産屋は不動産屋だ。菜々美はそう思った。こっちは母のいた時代から数えれば、ここで三十年以上も店を張ってきたのだ。ディーラーや顧客との人間的なつながりがあるから、遠方には行けない。しかし近場で探すとなると、十分な倉庫スペースのある物件はなかなか見つからない。 「それにウチはクルマの出入りが多いですから」 菜々美はわざと強い口調で言った。「幹線道路沿いじゃないとダメだと思います。住宅地に近いと、騒音とか排ガスとか通行安全とか、すぐクレームが来ますから」 「でしたら、適当なところが見つかるまで、休業補償を出すというのではどうでしょう」 声を弾ませて言う営業マンに、浩一は「ダメダメ」と首を振った。 「ウチらの商売はね、お客が毎日使うものを毎日決まった時間に届ける仕事だよ。たまに行ってみようかと思うような高級レストランじゃないんだ。休業なんかしたら、あっという間にお客は逃げてしまうよ」 なあるほど、と営業マンは丸い目を宙に据えて、考え込んでいる。 「そのへん、私どもの方で、もう少し考えさせてください」 そう言ってから、童顔の男はふいに声をひそめた。「ただし、買い手の方はかなり急いでいらっしゃる様子でしてね。私どもでうまく話がまとまらないようだと、直接お宅の方になにか言ってこられるかもしれません」 「なんだい、それ。まさかヤクザが地上げに乗り出してくるわけじゃないだろうね。もうバブルの頃じゃないんだからさ」 冗談めかして浩一が言うと、まさかそこまでのことは、とこのときばかりは童顔男の声があいまいにぼやけ、考え込むおとなの男の顔になっていた。 ところが、ウソのような話がほんとうになった。 ディベロッパー会社の名刺を持った、ひと癖ありげな中年男がいきなり訪ねてきたのだ。これが不動産会社の言っていた買い手らしいというのは、すぐにわかった。それと同時に、この男の正体がヤクザなのではないかという見当もついた。男はふつうのサラリーマンの格好をしていたが、こちらを見る目に妙に威嚇めいた光がある。 話の内容は先日の不動産屋の男とほぼ同じだったが、こちらの男は目が鋭かった。笑顔をつくっていても、目はけっして笑わない。感情の熱が少しもない、爬虫類めいた目でジッと見つめられるのは、なんとも薄気味わるかった。 その男はまた来るとだけ言って帰ったが、数日も経たないうちに、植草部品の周辺では小さなトラブルがいくつも起こった。初めはルートセールスに出ようとしたバイトが、駐車場にチンピラみたいな男たちがいて気味がわるい、と訴えてきた。植草部品では近くの駐車場に四台のバンを置いていて、店の前に横付けして積み荷をする。そのうちに駐車場にバンを取りに行くと、ガラのわるい男たちがたむろして、わざと進路をじゃましたり、車体にぶつかってきたりするようになった。 バイトのうち、気の弱いひとりが「怖いので辞めたい」と言ってきたので、そのバンを取ってくるのは菜々美の役目になった。忙しい朝に迷惑だったが、バイトに辞められるのはもっと困る。しかし菜々美が駐車場に行くと、なぜか見慣れない若い男が二、三人、所在なげにタバコをふかしているだけだった。 そうこうしているうちに、今度は修理工場やスタンドから苦情が舞い込むようになった。 「おたく、なんか暴力団とトラブルでも抱えてるのかい」 親しくしている小久保モータースの主人からそんな電話がかかってきたとき、菜々美はしまったと思った。あの連中のいやがらせは、顧客にまで及んでいたのか。 「いえ、そんなことありませんけど。どうかしました?」 つとめて平静な声で尋ねると、小久保モータースの主人は憤懣やるかたないという口調でしゃべりだした。 「めずらしくムスタングの修理が入ってさ。ほら先週おたくにフォードの部品を頼んだろ?あれなんだけど、きのう引き取りにやってきた男が、パーツをどこの部品屋から調達してるかって訊くんだよ。だからおたくの名前を出したら、植草の部品を使ったんなら、クルマは受け取れんと言うんだ。植草のところは平気でバッタものやら使い古しの中古品を売りつけるそうだからな、ってさあ」 「冗談じゃありませんよ」 菜々美は思わず声を張り上げた。「この間納めたフォードの部品は、間違いなく新品の純正部品ですよ。なんなら、ディーラーの納品書をお見せします。それにウチで中古のパーツを使うのは、お客さんから依頼があったときだけですから。それは小久保さんでも、よくわかっていただけているはずじゃないですか」 「わかってるよ。おたくのオヤジさんとは長い付き合いだし、そんな真似する人じゃないって、何度も説明したんだ。けど、クルマは引き取れん、部品を総とっかえしろとゴネられると、こっちも商売に差し支えるからねえ」 「取り替えたんですか」 「しかたないだろ。見るからにヤクザとわかる男に、店先で怒鳴られてたら、仕事にならないもの。手間はかかったけど、どうしようもない」 すみませんでした、と菜々美は電話を耳に当てたまま頭を下げた。いったいどうしたの、何があったの、と聞きたがる小久保には、「いえ、大したことじゃないんです」と言葉を濁したが、このまま放置しておいたら大変なことになりそうな気がした。二度三度と繰り返されたら、小久保だってしばらく取引を遠慮したいと言ってくるに違いない。同じ手で他の得意先を次々に潰されたら、たまったものではない。 怒った浩一は相手方と話をつけようと、毎朝駐車場に出向いたが、チンピラたちとは一度も遭遇しなかった。そうしているうちにも、小久保モータースと同じようにイチャモンをつけられたという電話が、あちこちの得意先から入ってくる。 小久保と話をしてから三日め、駐車場に出向いた菜々美は啞然とした。植草部品のロゴを入れたバンが四台とも、すべてタイヤに穴をあけられていた。エンジンをかけてみると、異音がして車体がカタカタ揺れる。排気管に粘土を包んだボロ布が押し込まれていた。 ここまで妨害されては商売に差し支える。といって、チンピラを捕らえて黒幕と対決しようにも、相手は浩一と菜々美の前にはさっぱり現れない。姿を見せるのはバイトが車を取りに行くときと、得意先にばかりだった。手の打ちようがなくなって、浩一は菅谷モータースのオヤジに相談を持ちかけてみた。菅谷のオヤジは若い頃、暴走族のアタマとしてこのあたりで鳴らした男だった。今でこそ自動車修理工場の社長に収まっているものの、気性の激しさはあいかわらずで、植草部品の配送ドライバーにも怖がられている。 あのオヤジなら裏の世界のことにも通じているはずだ、と浩一は考えた。ああいう陰湿ないやがらせにどう対処したらいいのか、菅谷なら何か知恵があるかもしれない。それに、菅谷の侠気に期待するところもあった。菅谷はガタイが大きく、声にも迫力がある。顔ときたらそのまま実録もの暴力団映画に出してもおかしくないが、気風のいい男だった。弱い者いじめのようないやがらせに悩まされていると聞けば、男気を起こしてくれるのではないか。 「なんだい、そりゃあ。ずいぶんと薄汚ねえ遣り口だな」 父娘で菅谷を訪ねてみると、案の定、腕組みしたいかつい顔を赤らめて怒り出した。 「どこの組の三下だ、そのバカ野郎どもは」 「それがわからないから、菅谷さんに相談してるんですよ。私と娘の前にはけっして現れないんです。それでいて、周りにいやがらせをしてくる」 「神経戦ってやつだな、そりゃ。あんた、あんまり気に病んでると下痢するよ。神経性の下痢ってやつ。おれも経験あるけどよ。娘が初めてお産したとき」 菅谷のような男でも神経を病むことがあるのかと菜々美はおどろき、よっぽどむずかしいお産だったんですか、と尋ねようとしたが、今はそれどころではないと思い直した。 「それで、どうやったら相手を突き止められますかね」 「突き止めるもなにも、相手はそのナンチャラいうディベロッパーに決まってるだろうが。そいつを締め上げればいいんじゃねえのか」 「しかし、ふつうに訪ねて行っても、まともに応じてはくれないでしょうし」 「ようし、わかった。そのディベロッパーとかいうやつの名刺を貸してみろ」 菅谷は太い腕を突き出した。「向こうがヤクザ者なら、あんたみたいな堅気は相手にせんわな。こっちで面倒みてやった方が早い」 「ほんとうですか。そうしてもらえると助かりますが、菅谷さんに迷惑がかかるようだと」 「何を言ってんだ。こんな相談を持ち込まれたら、もう迷惑はかかってるじゃないか」 わははは、と破顔一笑した菅谷の表情は変に可愛げがあって、浩一も菜々美も思わず頰がゆるんでくるのだった。 3 「てめえら、いつまでも事務所でタダ飯食わしてもらえると思ったら、大間違いだぞ」 荒木田に睨まれると、真二も悠人もうつむくしかなかった。任されているイベント企画事業が相変わらず振るわない。異業種交流を名目にしたものから、就活のための企業担当者と大学生の情報交換会、地方政治家の資金集めパーティまで手がけるが、出会い系パーティは隔週ごと金曜夜に開いている。 経営責任者は荒木田の友人になっているものの、もちろん名義借りに過ぎない。バンドやマジシャンを入れ、立食スタイルで、百五十人から二百人がメドだ。男は優良企業のサラリーマン、羽振りのいい自営業者などを狙い、それなりの容姿の女を集める。とはいえ、女の三分の一はサクラだった。麦山組の経営する芸能プロや、知り合いのモデル事務所から日当払いで調達する。 パーティ券は荒木田の持つルートでほとんど捌ける。男にもサクラが数人いるが、かれらの役目は、一般男性の参加者に「特別な情報」を吹き込むことだ。ほかにもおもしろいパーティを知っているとか、常連になると、モデル級の美女をお持ち帰りできるオプションがある、とか。もちろんネットでも流す。 だが、この商売のネックは、新しい客を次々に捕まえないと続かないことだ。荒木田は真二と悠人によそのパーティに潜入するよう命じた。カモになりそうな男を勧誘して、パーティ券を売りつけるのだ。ノルマは各回ごとに三十名。 最初のうちはおもしろいようにカモが引っかかってきた。ひとりに売りつけると歩合が二千円になるので、微々たるものだが小遣い稼ぎにはなる。ところが数か月もすると、パタリとチケットが売れなくなった。客は一度は来てもリピートまではなかなかしないし、売れる範囲に売り切ってしまうと、後が続かない。荒木田はチケットを二人に買い取らせた。額面一枚八千円だから合計二十四万円、歩合の分が六万円だから、差し引き十八万円だ。これを売り切れればいいが、売り残すと次の週のチケット買い取りがむずかしくなる。 「なんで、こんなセコい商売にこだわるんやろな、あのオッサン」 悠人はたびたびこぼした。 「だから、いずれイベントの仕事はそっくり任せてやるって言ってたじゃん。修業させてるつもりなんだろ」 「修業になるか、こんなもん。荒木田のオッサンは債権取り立てだの、倒産会社の債権管理だので百万単位の儲け出してるんやろ?パーティイベントなんか、せいぜい五、六十万のチンケなシノギやないか」 「だからな、そこが修業なんだってば。小さなことからコツコツと、だ」 しばらくは、真二は慰め役に回った。だが荒木田に支払うチケット代がきつくなってくると、そうも言っていられなくなった。二週間ごとに十八万円を払うのが重荷になった。 「これじゃ、オレたち、荒木田のオッサンに絞られてるだけやないか」 困り果てて、組に出入りしている島本という半グレの男に愚痴ってみると、 「おまえらもヤラれてんのか。荒木田さん、身内にまできつい追い込みかけるからな」 と苦笑して、逃げ道をひとつ教えてくれた。島本は警察の言う〈暴力団周辺層〉で、実家の土木建設会社で働いている、少年院帰りだった。 京王線の調布で、麦山組長の古馴染みだという爺さんがアパートの賃貸で食っている。稲村徳也というその爺さんはこっそり金貸しもやっていて、ケツ持ちはむろん麦山組だ。早い話が取り立てを代行してやっている。なんでも、若い頃は留学もした堅気の英語教師だったとかで、麦山親分とどういう関係なのかわからないが、仲はいいらしい。ひどく偏屈なジジイだが、このジジイに頼めば、金券やチケットの類なら引き取ってくれるはずだ。 島本にそう聞いて路地奥のアパートを訪ねると、稲村徳也は平家蟹の甲羅に似た顔をした、ミイラじみた老人で、身体はずいぶん小柄だった。 「置いていけ。捌けるだけは捌いてやろう」 ジロリと睨んで、稲村は手元の小型金庫から出した札をテーブルに放った。 「ただし、代金は売れた分だけの後日勘定だ。当座の金はすべて捌けたと仮定して払う。売れ残った分は、こっちの貸しだ。わかるな」 つまり仮に十六万円分のチケットを預けるとそれだけの現ナマを渡されるが、もし半分しか捌けなければ、残り八万円は稲村から借りている計算になるわけだ。 通りに出ると、さっそく悠人が口を尖らせた。 「なんや、けったいな話やな。よう考えたら、稲村の爺さんからカネ借りて、荒木田のオッサンに払ってるだけと違うか」 「よく考えなくても、そうなるんじゃねえのか」 やっぱ、そうやんか、悠人は肩を落とす。 「それにしてもおかしな爺さんやで。机の上にあった本、見たか?下着の金髪ねえちゃんがエロポーズ取ってた表紙のやつ。あれ、英語の本やったぞ」 「そういうところだけは目が早いな、おまえ」 悠人がいきなり腰にまわし蹴りを打ってきたので、真二はわき腹にエルボーを食らわせてやった。悠人は「おー、痛え」と大げさに痛がってみせながら、愚痴をこぼした。 「稲村の爺さんから組には、月々、ケツ持ち料が支払われてるわけやろ。結局、荒木田のオッサンも稲村のジジイもそれぞれ儲けとって、損をするのは真二とオレばっかりやん」 それでもほかに逃げ道がなければ、稲村に頼るしかないのだった。十万、十五万と隔週ごとに借金は膨れ上がった。ふた月で五十万を超えたとき、二人は頭を抱え込んだ。下働き程度の仕事しかさせてもらっていないチンピラには、重すぎる負担だ。 組の会社では、ほかにブルーリボン芸能社のスタッフもやっている。だが、任されているのは腕力仕事だった。ブルーリボンは地下アイドルグループを囲い込んでいた。少女六人組のチームで、元ミュージシャンの男が表向きの主宰者だ。この元ミュージシャンと仲間に楽曲を作らせ、ライブハウスなどでショーを開く。経費は撮影会やファン・ミーティングで稼ぐ。インスタントカメラで一枚撮らせて千円。ファン五十人が二枚ずつ撮れば、十万円だ。ファン・ミーティングはミニライブと握手会で、二十万から三十万にはなる。 真二たちの仕事は、会場警備としつこいファンの追い出しだ。ほかのファンを怖がらせないよう、ニコニコしながら慇懃に外へ出てもらう。出たら建物の裏手へ引きずり込んで、脅しつける。それで日給が五千円ぽっきり。財布はいつも限りなく軽い。 「これはもう返せへんで。カツアゲでもするしかあらへん」 窃盗、強盗などは組ではきびしく禁止されている。路上の恐喝も同じだ。小さな綻びでも見つければ、警察はすぐに手を入れてこようとするからだった。 「どこかで、マブくて尻の軽いスケでも見つけてこいよ。美人局でも仕掛ける方が手っ取り早くカネになるだろ」 「そんなもん、どこにおるねん」 今週も売り上げ目標には届かず、稲村老人を訪ねるしか手はなさそうだ。二人は暗い目を見かわして、ため息をついた。 「おい、おまえら。きょうはどこだ?」 その日も出かけようとしていると、荒木田が声をかけてきた。 「へえ。三鷹から調布まわって、あとブルーリボン社ですねん」 「ふん。ブルーリボンはなんだ」 「なんやわからへんけど、社長に呼ばれとります」 「ったく、しょうがねえな。こっちも手が足りてねえってのに。おまえらも、社長だからって気安く使われてるんじゃねえぞ」 いちばん気安く使ってるのはあんただろうが。喉もとまでそのセリフが突き上げてきたけれど、もちろんそんなことはおくびにも出さない。 「それからいつものやつ、頼むわ。数字はこれな」 メモを渡される。細かい字でいくつかの数字が書き込まれていた。 「今週はロトのほかに、ジャンボの分もある。ジャンボは締め切り近いから、忘れるんじゃねえぞ」 いっしょに渡された十万円を財布にしまう。悠人が恨めしそうに小声で言う。 「宝くじにポンと十万円かいな。いいご身分やな」 真二は横目で悠人を見やり、出口に向けてあごをしゃくった。言いたいことはよくわかる。荒木田はパー券を押しつけてきたり、組の用を言いつけたりするだけでなく、私用でも二人をこき使う。そのわりにくれる小遣いはショボい。たしかに麦山組の持ち物になっているアパートにタダで住まわせてもらっているが、築三十七年のボロアパートだ。しかも二人に宛がわれた部屋は、半年前に首つり自殺があった事故物件だった。 おまけに、組で出してくれる昼飯はいつも近所から出前するチャーハンばかり。肉も野菜もほとんど入っていない、しょっぱいだけの代物なのだ。 真二と悠人が担当させられている三鷹の案件というのは、不動産業界の支部長選挙をめぐってのトラブルだ。永倉という古手の現職に、沖田という若手リーダーが挑む格好で、もう三年ばかり対立が続いている。永倉は先々代からの老舗不動産会社を経営している。沖田はもともと建機リース業者だったのが、十年ほど前から不動産に進出してきた新興勢力。よくある新旧の対立構図だった。 あるスジから、沖田商事をちょっと脅しつけてくれないか、という話が麦山組に持ち込まれたのが、二週間ほど前。荒木田はすぐにこのスジから、依頼元が永倉建物管理株式会社で、取り持ちが麦山組上部団体の、暴力団周辺者だと聞き込んできた。そこで、まず沖田商事に送り込まれたのが、真二と悠人だった。仕事は単純で、言いがかりをつけて怒鳴り散らす。店内にある物をデスクから叩き落としたり、蹴り飛ばしたりする。女性店員が泣き顔で震え出したところで、さっさと退散する。 この手の脅しを二度ほどかけたところで、荒木田が仲裁人として登場する。もちろん仲介人として二人ばかりクッションとして入れておく。タチのわるいチンピラを押さえてくれる顔役という役まわりだった。言うまでもなく、永倉からも礼金は出ている。ここまではよくある定石だが、荒木田の遣り口はもう少し芸が細かい。真二たちが沖田商事の社員を殴ってケガさせたので、警察沙汰になりそうだ、と吹き込んで永倉を脅したのだ。 永倉は動顚した。チンピラが捕まって証言を取られでもしたら、大失態である。支部長選挙どころではない。社会的生命の危機だ。警察が動く前にチンピラを高跳びさせるからカネを出してくれと言われれば、ひとたまりもなかった。 こうして相手が反社会的団体と知りつつカネを出した証拠ができれば、今度はそれが新たな恐喝のネタとなる。 きょうの仕事は、二人で永倉建物にお詫びに行く、というものだった。お詫びと言いながら、実際は脅しなのはあきらかだった。政敵の沖田商事に差し向けた鉄砲玉に、自分の会社をうろつかれたのではたまったものではない。社員たちが胡乱な目で見つめる中で、永倉は禿げかけた頭に汗の粒を浮かべて、裏口から真二たちを押し出した。ポケットに万札が何枚かずつねじ込まれていた。 「けど、荒木田のオッサン、えげつない真似しよるわ、ほんまに」 くしゃくしゃの万札を引き伸ばしながら、悠人が言う。「あれでオッサンにはこの百倍くらいの札束が転がり込むんやで」 「だから、よく言うじゃん。ヤクザにものを頼むなってさ。いったん関わったら、とことん搾り取られる」 「けど、反社を使いこなすやつだっておるだろ。持ちつ持たれつ、ちゅうか。ほれ、何とかいうた大物がいたやないか、関西の大銀行の頭取かなんぞで」 「寄生できるくらいでかい相手ならな。けど、あれだって最後は銀行に検察の手が入ったじゃん。ましてショボい相手は、血を吸い尽くしたらポイだ」 「うへえ、任侠道、いまいずこやな」 二人は調布駅から稲村のアパートに向かう道をとぼとぼ歩いていた。 商店街のアーケードは昼下がりのせいか、空いている。2020年東京オリンピック・パラリンピックを成功させよう、という横断幕がビルの高いところに掛かっていた。年が明ければいよいよオリンピックイヤーだ。 アーケードが尽きる手前に、全面ガラス張りのパン屋がある。くそまずいチャーハンは食べ残してきたので、小腹が減っていた。パンでも買うか、と悠人に声をかけると、「シーッ、ちょっと黙っとけ」いやに熱心にガラスの向こうを見つめている。 指さす先にいるのは、すらりとした若い女だった。銀色のトレイにパンを六つか七つ載せて、レジの前に並んでいる。セミロングの髪を左肩で結んでいた。 「あれな、例の自動車部品屋の娘やぞ、たしか。ほれ調布の、甲州街道沿いの」 ああ、あれか、と真二は気のない相づちを打った。麦山組がどこかよその組から頼まれて、部品屋を立ち退かせる下工作をしている話は聞いていた。半グレのニートを何人か連れて、悠人がいやがらせを仕掛けているらしい。暴力団は人間関係が命、と言ってもいいから、いわゆる血筋の互助関係は強い。だから、ある一家に敵認定されると、そことつながる組織すべてから睨まれかねない。 「あの女な、ああ見えてめっちゃ気ィ強いねんわ。難攻不落やで、あの部品屋」 「よくそんなつまんねえ仕事、受けるな」 「よう言うわ。自分はどんだけ高尚な仕事しとるねん」 パン屋から出てきた女は、アーケードを出てとっつきのビルの前で、また立ち止まった。ビルの一角に、宝くじ売り場がある。ちょっと考えてから、女は窓口に近寄っていく。 「ほう、宝くじとか買うタイプなんか、あのねえちゃん。庶民的やな」 庶民そのものだろ、場末の部品屋なんかと言うと、そやない、オレら外れもんには堅気の娘は高嶺の花やないか、と悠人はめずらしく感傷的なことを言った。二人してなんとなく、部品屋の娘が駅の方向へ遠ざかるのを見送った。 「忘れるとこだった。オレたちも宝くじ買っとかないとな」 「そやそや。忘れよったら荒木田にデコピン食わされるで」 デコピンですむか、バカ、と鳩尾に裏拳を見舞って、真二は荒木田に渡されたメモ紙を引っ張りだした。それを見ながら、窓口に声をかける。 「えーと、ロト6のシート四枚ね。あとハロウィンジャンボを二百枚。各組から、18万台だけ十枚ずつちょうだい。連番で」 「はいはい。ロトシートはそこにあるからどうぞ」 売り場のおばさんは顔なじみに言うように気安く応じる。ロト6はオンラインくじのひとつで、1から43までの数字のうち、六つを選んでチェックする。週に二回抽選日があって、コンピュータが無作為に当選数字を選び出す。六つとも的中すれば、理論値では最高で賞金二億円をゲットできる。当選者が複数いれば、頭数で割るから取り分は減るけれど、誰も当てられなければキャリーオーバーといって賞金は積み上がる。 荒木田はヤクザのくせにサイコロにも花札にも手を出さない。その代わり、ルーレットとこのロトが大好物だった。ロトのなかでも、リターンの大きい7ではなく、6を好む。7だと賞金は六億円まで上がるが、当たる確率が下がるからだ。これまでに五十万円ほどを一度当てたことがあると言うが、損金はその何倍にもなるだろう。 「ジャンボは十枚ずつ二十組ね。組は百組まであるけど、お好みの組番は?」 「それは適当でいい」 おばさんは振り向いて、座席の後ろに山積みになった包みを手前に置き直した。 「ほんとはこんなこと、お客さんに言っちゃいけないんだけどさ。こういう買い方されるの、売り子泣かせなんですよねえ」 「へえ。なんでよ」 「宝くじって、何十ユニットあっても、売り場には一万枚ずつの束で送られてくるんですよ。10万台から19万台まで、十万枚がひと組でね。だから各組の18万台から十枚と言われると、一万枚のなかから十枚抜かなきゃならないでしょ」 そうすると、あとが面倒なんですよ、とおばさんは面倒でもなさそうにテキパキ作業を進めながら言う。番号や組にこだわりのない客ばかりなら、束の上の方から順番に売っていけばいい。だが荒木田のような客が次々に来たら、どうなるか。ひと綴りのあちこちが虫食い状に穴があく。どの束が現在どういう状況にあるかを、いちいち把握しておかないといけないから、とてつもなく手間がかかる。たとえば、ある組のある番号をくれと言われたとき、その券が売り場にあるかないかわからなければ、商売にならないのだ。 「へえ、そうなんや。わがままゆうて、すんまへんなあ」 悠人がへらへら調子を合わせる。 「ま、残り物には福があるって言うからね。どうぞ当たりますように」 「別に当たらんでもかまへんけどな」 「そんなこと言ってたら、運が逃げちゃうよ。それからね、もしも高額当選したときは、ここの売り場で買ったことを覚えておかないとダメよ」 換金は銀行本店でおこなうので、そのときにどこで買ったかを必ず訊かれるから、とおばさんは真顔で説明する。宝くじ抽選券はすべてバーコード管理されていて、どこの売り場に何組の何番の券が配送されたか、すべてデータ化されているのだ。だから当選券を盗んだり拾ったりしても、売り場を特定できなければ支払いは保留される。手続きがストップしてしまうのだ。 「へいへい、さいでっか。おばちゃんみたいな美人から買うたら、忘れまへんて」 悠人はカードと券を受け取ってバッグに入れる。十メートルほど歩いたところで、 「お、そうや。真二、小銭持っとるか」 「ちょっとしかないな」 「どうせ稲村ジジイのあと、ちょこまか動きまわらんといかんやろ。ちょい待ち。そこで万札くずしてくるわ」 悠人は宝くじ売り場に引き返すと、真二を振り返った。 「どや。ついでにオレらも一枚ずつ、ジャンボ買うとこうやないか。ひょっとしたら、当たるかもしれへんで」 「おまえといっしょに買ったら当たる気がしねえよ」 すぐにもどってきた悠人は、ハロウィンジャンボの券をひらひらさせて、 「荒木田のオッサンに乗っかろう思うてな。さっき買うた券の続きを二枚、買うてきた。あのオッサン、悪運強そうやからなあ」 渡された券を眺めて、真二は、これが当たるといくらになるんだ、と訊いた。 「一等三億円、二等一千万円や」 「それで、全部で何枚売り出されてるんだよ」 「発行枚数は九ユニット、一ユニットは一千万枚やて」 「それじゃ当たるわけねえだろうが」 ラーメン屋、焼き肉屋、不動産会社の支店、手芸品店、キョロキョロしながら駅に向かって歩いていると、いきなりにぎやかなマーチが聞こえてきた。先頭にチューバみたいな大きな管楽器がキラキラ光を弾いて、トランペットやホルン、その後ろにクラリネットとタンバリン、最後にシンバルが続く。陽気なラテン音楽バンドのあとからやってくるのは、メキシコ、ブラジル、ペルーといった中南米の国々の小旗だった。 「なんや、これ?なんかのお祭りか?」 カラフルな民族衣装を装った人々が、それぞれの小旗を打ち振っている。〈ラテンアメリカ・フェスティバル〉と花文字で描かれた横断幕が見えた。最後尾に付いたワゴンカーからマイクの声が響きわたる。 「……ラテンアメリカの音楽とダンス、代表的な家庭料理も取り揃えております。みなさま、お誘いあわせの上、どうぞ調布ミリオンホールまでお越しください」 ペネロペ・クルスの若いときみたいな美少女が、こっちを見て花束を振っている。 「見てみい、あの可愛いねえちゃん、オレのこと見つめとるで」 悠人がヘーイと叫んでジャンプすると、ペネロペねえちゃんは片手に持ったデジカメを向けて、なにか叫んだ。悠人もあわててスマホを出して、カシャカシャ撮りだす。周りで見物している中にも、スマホを構えているのが幾人もいる。エメラルドグリーンやスカイブルーやローズピンクの色彩が流れて、駅の方へと向かっていく。 「なんやろな、あれ」 「中南米から働きに来ている連中だろ。それでフェス開いて、地元住民と親交を深めるみたいな」 「おー、ええやんそれ。あのねえちゃんとしっぽり親交深めたいわ。なあ、あとでミリオンホール行かへんか」 「ほんとにおまえ、ノーテンキだな」 大通りから二つ角を折れただけで、ウソのように静かな住宅街に入る。ブラスバンドの音が遠ざかり、駅のアナウンスが風に乗って思いがけず近く聞こえた。 路地に入る。南北にまっすぐ延びる道だが、クルマが入ってくると、歩行者は塀に張りつかなければならない。もちろん一方通行だ。築年の古い一戸建てが並んでいる。ブロック塀や板塀から植木が貧弱な枝葉を伸ばしていた。 道を三十メートルほど行ったところに、稲村のアパートがあった。三棟が道路に対して横向きに建てられている。ひと棟に八室あるから、家賃の上りはかなりあるはずだ。ただし建物は古い。クリーム色だったモルタル塗りの壁が灰色になり、窓枠を囲むように黒カビが侵食している。 稲村徳也はまんなかの棟のひと部屋を事務所に使っていた。いつも開いているアルミ門扉から入り、裏側にある通り廊下にまわる。幅一メートルくらいのコンクリ廊下は、洗濯機や自転車、スチールボックス、ゴミ捨てのポリ容器などがびっしりと並んでいた。住んでいるのはほとんど独り者らしく、昼間のアパートはしんと静まり返っていた。 いちばん奥が稲村の部屋だった。夕方まではたいていここにいると聞いていたが、インターフォンを押しても、室内はしんとしたままだった。 「爺さん、おらんのかいな」 悠人がドンドンとドアを叩く。 「イナムラさーん、警察でーす。開けてくださあい」 「そういうの、やめろって」 「そやかて、爺さん、サツにいっち敏感やろ」 何度叩いても反応がないので、しゃーない、家の方に行ってみよか、と悠人は歩き出した。稲村の住まいは同じ敷地の内で、アパートのあいだを抜けたすぐ先にある古い平屋だった。めったなことでは住まいに他人を入れたがらないと聞かされていたが、かまわず玄関先に足を運ぶ。 「年寄りだから、具合わるくなって寝込んでるのかもしれないな」 「死んどったりしてな」 悠人はためらいもなく、カラカラとよく滑る引き戸を開けた。 「稲村さーん、荒木田の使いのもんですが」 声を張り上げてみたが、返事もなければ人の動く気配もしない。 「なんや、不用心やなあ。誰もおらんなら、金目のもん、もらっていきまっせえ」 ふと、真二は耳を澄ませた。奇妙な音が聞こえたような気がした。建付けのわるい戸を無理にこじ開けるような、耳障りな擦過音……?かすかに遠ざかる足音を聞いたような気もする。いやな予感がして、真二はスニーカーを蹴り脱いで、式台に駆け上がった。 「おいおい、勝手に上がってもうて、かまへんのか」 ああ、と言い捨てて、正面にある重そうな板戸に手をかける。飴色にくすんだ二枚の板戸はぴたりと閉まっていて、カタリとも動かない。玄関廊下の左手の突き当たりにも板戸がある。カラリと開いたその先はまた板廊下だった。真二は身体をひるがえし、左の方向へ突進した。 「おいおいおい。知らんぞ」 廊下は先で鉤の手に曲がっている。両側は砂壁が続き、突き当たりはガラスの格子窓だ。その手前で左にふすまの引き戸がある。真二はふすまを思い切り、引き開けた。 「──こ、こら、どういうこっちゃ!?」 悠人の声が鋼のように硬くなった。 六畳ほどの畳の部屋に、カーペットが敷かれ、座卓とざぶとん、ひとり用サイズの冷蔵庫と食器棚。壁ぎわにガラス引き戸の付いた本棚が二つ。対面の壁に八号くらいの、テーブルとフルーツバスケットを描いた静物画。居間と思われるその部屋には、けれど生活感のある雰囲気に似つかわしくないものが二つあった。 ひとつは建設会社の事業所にでもありそうな、頑丈一点張りの金庫だ。そしてもうひとつは頭から血を流して倒れている、小さな老人の身体だった。金庫の扉は大きく開かれ、老人の瞬きしない目は赤黒い血を眼窩に溜めたまま、じっと宙を見つめていた。
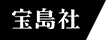

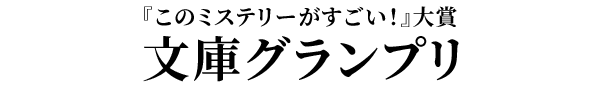
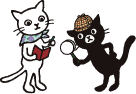 ◀ トップへ戻る
◀ トップへ戻る