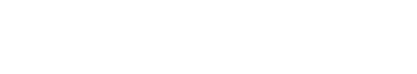試し読み
『密室の不解証明は、現場の不在証明と同等の価値がある』 ─東京地方裁判所裁判官 黒川ちよりの判決文より抜粋
Prologue 日本で初めて密室殺人が起きてから三年が経った
男が殺されたのは三年前の冬のことで、それが日本で初めて起きた密室殺人事件だとされている。幸い犯人はすぐに捕まり、断ずる証拠も十分で、ただ現場の不可能状況をどう扱うのかだけが問題だった。 そう──、不可能状況だ。現場は完璧な密室で、警察や検察の誰一人として、その謎を解き明かすことはできなかったのだから。だからそれは事件における最も重要な事柄で、当然、裁判の争点もその密室が中心となった。 「現場が密室であったことは、重要な問題であるとは言えない」それが第一審における検察側の主張だった。「客観的な証拠に基づいて、被告が犯人であることは明らかです。ならば『どう殺したのか?』などというのは、些末な問題に過ぎません。『どうにかして殺した』のでしょう。被告が秘匿しているだけでその方法は確かに存在するはずで、現場の不可能状況が、被告の無罪を裏付ける根拠には絶対にならないはずです」 対して、弁護側はこう主張した。 「我が国の裁判制度において、本来、犯行の不可能性というのは重大な意味を持つはずです。その最たる例がアリバイで、仮に被告に完璧なアリバイがあった場合、我が国では必ず無罪になる。何故なら、被告に犯行が不可能だからです。今回の密室状況もそれと同じ──、現場が密室であった以上、それは被告のみならず、この世界のどんな人間にとっても犯行が不可能だということを意味しています。つまり現場が完璧な密室であることは、被告に完璧なアリバイがあることと同等の意味を持つということです。なのに密室の場合に限って『どうにかして殺した』『やり方はわからないが、どうにかしたのだろう』と黙殺するのは、ひどく一貫性がなく、他の刑事事件の判例と矛盾するのは明らかです」 こうして前代未聞の密室裁判は密室を中心に進んでいき、東京地裁の裁判官は結局、弁護側の主張を受け入れた。すなわち、『密室の不解証明は、現場の不在証明と同等の価値がある』──、被告に犯行が不可能であることを鑑み、無罪判決を下すことになったのだ。 第二審も一審を受けて無罪──、そして最高裁は検察側の上告を棄却した。 この判決は大きな衝撃をもって、国民へと受け入れられた。どんなに疑わしい状況であっても、現場が密室である限り無罪であることが担保される。それはある意味では、司法が密室というものの価値を認めた瞬間だった。『行うことに何の意味もない』──、数多の推理小説の中でそう蔑まれていた密室殺人というジャンルが、この判例により現実の中でその立場を逆転させたのだ。 それがこの事件における些細な『功』で、 そして『罪』はわかりやすい。地裁の判決が出てひと月も経たないうちに、密室殺人が四つも起きた。さらに翌月には七つ。密室は流行り病のように、社会へと浸透していく。 * この三年で三〇二件の密室殺人事件が起きた。 それはこの国で一年に起きる殺人事件の三割が、密室殺人であることを意味している。
第1章 密室時代
女はひどく興奮しているようで、唾を飛ばしそうな勢いで『私』に捲し立てていた。かと思えば、妙にしんみりする時もある。情緒が不安定なのだ、と『私』は思った。 聞けば、女は集団自殺の生き残りであるらしい。自殺サイトで知り合ったメンバーたちと一緒に、彼女は山奥の廃屋に向かった。そこで水の入ったグラスを人数分用意する。そのグラスにアコニチンだか青酸カリだかテトロドトキシンだかを入れるのだが、実はそのグラスの中の一つには毒の代わりに睡眠薬が入っている。 「つまり、どういうことかわかりますか?」と女は言った。「一人だけ生き残るということです」 それはそうだろうな、と『私』は思った。 「そしてその睡眠薬を飲んだのが私です」 それはそうだろうな、と『私』は思った。 「まったく、面倒なことになりました。みんなで仲良く死ぬつもりが、私はこんなシケた場所で今もコーヒーを飲んでいます」 「良かったじゃないですか」と『私』は言った。「命は大切ですよ」 女は、にやりと笑った。 「あなたがそれを言いますか?」 『私』はコーヒーを一口飲んだ。まずいコーヒーだ。自分で入れたコーヒーだけど。どうやら『私』には、コーヒーを入れる才能はないらしい。 というよりも、『私』に得意なことなど一つしかないが。 密室を──、作ることだけ。 「とにかく、私は生き残った」と女は言った。「だから私は、あなたに会いに来たのです」 女は『私』の顔を指差す。 「『密室使い』さん、あなたに」 * 「香澄くん、ポッキー食べる?」 車窓の景色を眺めていると、向かいの席に座る朝比奈夜月がポッキーの箱を差し出してきた。僕は「食べる」と言って、彼女の手にした箱から一本摘む。それをくわえながら、再び窓に視線をやった。列車と同じ速度で十二月の景色が流れていく。雪は積もっていないけれど草木が枯れてうら寂しい。何となく、アンニュイな気持ちになる。 「何、アンニュイになってんだか」とポッキーを食べながら夜月が言った。「もしかして詩人を目指してるの? 毎日寝る前に自作の詩をノートに書き綴るタイプなの?」 とりあえず、こいつが詩人をバカにしてるのは伝わった。僕はあしらうように言う。 「詩なんて、中学の時以来書いてないよ」 「中学の時は書いてたんだ?」 「中学生は普通書くだろ」 「普通の基準がわかんない。香澄くんの基準と世間の基準を比べるのはやめてほしい」 何故だか怒られてしまった。ちなみに香澄というのは僕の下の名前で、名字は葛白。葛白香澄。だから小学生の時は一時期『くずかす』と呼ばれていた。『キムタク』と同じ要領なのだが、なんか全然違っていた。しまいには学級会で、先生から『葛白くんを、くずかすと呼ぶのはやめましょう』と皆がお叱りを受けたほどだ。僕はその学級会の間、とても悲しい気分だった。そのことを夜月に話すと、「『葛』に『かすみ』なわけだから、何だか俳句の季語っぽいよね」とよくわからない励まし方をしてくれた。 そんな夜月は僕の幼なじみで、二十歳の大学二年生──、高校二年生の僕より、三つ年上になる。髪の毛は肩までの長さの淡い茶色のゆるふわで、顔立ちはかなり整っている。「一日に七回スカウトされたことがある」というのが彼女の鉄板の自慢だった。そのうち四回はキャバクラで、二回は美容室のカットモデルだったが。「でも、残りの一回はちゃんとした芸能事務所だったんだよ」彼女はそう主張する。「おしかったなぁ。あっ、でも私、気まぐれな猫みたいな性格だから。やっぱり芸能界みたいな、しがらみの多い仕事には向いてないんだよね」 確かに夜月は気まぐれな猫で、そして芸能界には向いていないだろう。というより、働くことに向いていない。彼女には、どんなバイトでも一ヶ月でクビになるという特技があった。 そんな気まぐれな猫は、ポッキーを食べながらスマホを操作する。そして「あっ」と声を上げた。 彼女は、まじまじとスマホを眺めて言った。 「ねぇ、香澄くん、また密室殺人が起きたみたいだよ」 「えっ、マジで?」 「うん、青森で。県警刑事部の密室課が現在捜査中だって」 僕は自分のスマホを取り出し確認する。どうやら、マジらしい。相変わらずこの国では、密室殺人が氾濫している。 「妙な時代になったものだよねぇ」とポッキーを食べながら夜月が言った。 まったくだ、と僕は思う。一つの殺人事件を切っ掛けに、世の中は大きく変わってしまった。三年前に起きた日本で最初の密室殺人事件。それ以来、この国の犯罪は密室を中心に回っている。 * 目的の駅は無人駅だった。僕と夜月は誰もいないホームで大きく伸びをする。関節がポキポキと鳴った。家を出てから三時間──、それなりに長旅だった。 「それで、今日泊まる宿は?」 「えーとね」夜月に訊ねると、彼女は歩きスマホをしながら答える。「ここから車で山の中腹まで入って、そこで車道が途切れるから、そこからは歩きみたい」 「途中で車道が途切れるのか」 「そう。一時間くらい歩く」 「けっこう歩くのな」健康には良さそうではあるが。 二人で改札を抜けて、駅前のロータリーに出た。そこで一台のタクシーを拾う。 夜月はタクシーの運転手に目的地を告げた。 「雪白館までお願いします」 * 雪白館は現在ホテルとして使われている。冬休みを利用して僕たちがそこを訪れることになったのは、ひと月ほど前に夜月が僕の自宅を訪ねてきたのが切っ掛けだった。訪ねてきた──、と言っても、彼女は頻繁にやって来るが。でもその日の夜月には確たる目的があったようだ。僕の入れたコーヒーを飲みながら、開口一番にこう告げる。 「香澄くん、私、イエティを探しに行こうと思うんだ」 とうとう気が狂ったのかと思った。 「えっと、イエティって」 「知らないの? UMA(未確認生物)の一種よ。大きくて毛むくじゃら──、簡単に言うと雪男ね」 いや、イエティが何かは知っているが。問題なのは、彼女がどうしてイエティを探しに行こうとしているかだ。 「ほら、私、けっこうUMAとか好きだから。オカルト雑誌の『ムー』だって、物心ついた時から買ってるのよ」 そういえば、読んでいるのを見たことがある気がするが。 僕は溜息を飲み込むようにコーヒーを口に含んだ。 「まぁ、とにかく頑張ってください」しみじみと、そう告げる。「イエティを探すのは大変だと思うけど、無事に帰って来られることを祈っています」 どうか、今生の別れになりませんように。幼なじみがイエティを探しに行って行方不明とか悲しすぎる。 すると、そんなしみじみとした僕を見て、夜月が呆れたように溜息をつく。 「何言ってるの、香澄くん。香澄くんも一緒に行くのよ」 何ですと、と僕は思った。 「……、僕にヒマラヤまで一緒に行けと言うのか?」 そこまで幼なじみへの愛は深くない。すると夜月は、再び呆れ顔で僕に言った。 「何言ってるの、香澄くん。行くのはヒマラヤじゃなくて埼玉よ」 とうとう気が狂ったのかと思った。 僕はごしごしと目をこする。自信満々な彼女の顔。どうやら本気で言っているらしい。何かの間違いであって欲しかったが。 僕はまじまじと訊く。 「えっと、どうして埼玉にイエティを探しに行くんだ?」 「もちろん、そこにイエティがいるからよ」 そこに山があるから、みたいに言う。 「……、埼玉にイエティがいるわけないだろ」 「それがいるのよ。だって、埼玉イエティだもの」 「埼玉イエティ」 何だか、Jリーグのチームみたいな名前だ。 「氷河期のころはね、日本と大陸は陸続きだったの」と夜月は得意気に言う。「だから日本とヒマラヤも、歩いて行き来することができたってわけ」 「それで、氷河期にヒマラヤから埼玉にイエティが渡ってきたってことか」 「そう、ありえる話でしょ」 絶対にありえないと思うが。 「というわけで、香澄くん。一緒に埼玉にイエティを探しに行こう」夜月は身を乗り出して言う。「きっと、一生忘れられない思い出になるよ」 確かに一生忘れられないだろう。埼玉にイエティを探しに行った思い出なんて。 「……」 僕は少しの間思案し、その結論に辿り着く。 まぁ、行くわけないよな。 当然のように、僕は断ることにする。すると夜月は僕にしがみついて懇願した。 「お願い、香澄くん、一緒に来て。私に一人寂しく旅行をさせるつもり?」 「いや、友達と行けばいいだろう」 「何言ってるの。埼玉にイエティを探しに行こうなんて言ったら、友達にドン引きされるじゃない」 「むしろ、お前にそんな常識が残ってたことに驚きだよ」 縋りつく夜月を振り払う。彼女は「ああっ」と声を漏らしたが、やがて床にへたり込んだまま、こほんと息をついて言った。 「聞いてください、香澄くん」 「はい」 「今回のイエティ探しは、ちゃんと香澄くんにもメリットのある話なのですよ」 僕は訝し気に首を曲げる。「僕にメリット?」そう訊ねると、「はい、メリットです」と床に座り込んだ夜月は言った。「リンスのいらないメリットです」少し古いな。 彼女は人差し指を立てる。そして得意気に僕を見上げた。 「何と、今回宿泊予定のホテルは、あの雪白館になるのです」 「雪白館?」 僕は小さく首を捻る。何だろう? どこかで聞いたことがある名前だ。 「ほら、香澄くんが好きな雪城白夜の」 「ああっ、あの館のことかっ!」 突然、テンションが上がった僕を見て、夜月が得意気に頬を緩める。小憎らしい顔で少しムカついた。僕はこほんと咳をする。 「なるほどね、雪白館に泊まる予定なのか」 と、冷静を装ってみたものの、やはり僕は興奮していた。 雪城白夜というのは本格ものの推理作家で、特に密室を得意としていた。七年前に他界しているけれど、今でも作品の多くが本屋に並んでいる人気作家だ。 僕もかなりのファンだった。代表作は『密室村殺人事件』か『密室館の殺人』のどちらかだが、真の代表作は別にある──、というのがファンの中での定説だった。ただし、それは小説ではない。テレビドラマでも漫画でも映画でもない。 実在の、事件だ。 今から十年ほど前、雪城白夜は自身の館に作家や編集者を集め、ホームパーティーを行った。美味しい料理に美味しいお酒──、そして白夜自身の人柄の良さ。パーティーは大いに盛り上がった。でも、そのさなか、事件が起きる。 それは些細な事件で、悪戯とも言えるレベルのものだった。誰かが傷つけられたわけではない。ただ館の一室で、ナイフで胸を刺されたフランス人形が発見されたのだ。 そしてその部屋は密室だった。扉は内側から施錠され、その部屋の唯一の鍵も室内から見つかった。しかも、ただ見つかっただけではない。鍵はプラスチック製の瓶の中に入れられていて、その瓶の蓋は固く閉められていたのだから。 通称、瓶詰の密室。 その事件が起きてからずっと、白夜は常に口元に、にやにやと笑みを浮かべていた。それを見て誰もがピンとくる。この事件の犯人は彼で、これはパーティーの催しの一つ──、主催者である白夜が仕掛けた推理ゲームであるのだと。 ならば、受けて立とうではないか。 居合わせたのは同業の作家や編集者。皆、密室には一家言ある者たちばかりだ。すぐに喧々囂々の議論が始まり、やがて即席の推理大会へと発展していく。 そのパーティーの参加者は口々に「楽しかった」と語っていた。そして最後に必ずこう付け加える。「もし謎が解けたのなら、もっと楽しかったんだろうけどね」 密室トリックは未解であった。 これが雪城白夜の本当の代表作──、『雪白館密室事件』だ。もちろん、刑事事件ではないから裁判沙汰にはなっていないけれど、三年前に起きた日本初の密室殺人事件よりも、実に七年も前のことになる。 十年間も崩されていない密室。 今でもミステリーファンの間では語り草で、現場となった雪白館は、ファンならば一度は訪れてみたい人気スポットとなっている。雪白館は今は他人の手に渡ってホテルに改装されているのだけど、現場となった部屋だけは当時の状態のまま保存されているという話だった。トリックの痕跡らしきものも残されているそうだ。 「……」 そして今回夜月はそれをエサに、僕を連れ出そうという腹らしい。小憎らしいが、僕は彼女の策に乗ってやることにした。雪白館は長期滞在の客──、具体的には一週間以上逗留する客しか泊まれないという少し変わったシステムになっていて、滞在するにはどうしても費用がかさむ。今回、夜月がどこからその費用を捻出したのかは知らないが、タダで雪白館に行けるというなら、こんなに旨い話もないだろう。そのついでに彼女のイエティ探しも、少しだけ手伝ってやろうと思った。 * タクシーを降りて一時間ほど歩くと、見えてきたのは橋だった。長さ五十メートルほどの木製の吊り橋。森を両断するように左右に深い谷が走っていて、その両端を繋ぎとめるように頼りなく木の橋が架かる。谷底までの深さは六十メートル程。両岸はどちらも切り立った崖のようで、人間が上り下りするのは、まず不可能に思われた。 谷底を覗き込んだ夜月が、「うわっ」と声を上げる。 「これ、落ちたら確実に死んじゃうね」 彼女は当たり前のことを言う。でも確かに落ちたら死ぬので、僕らはおっかなびっくり橋を渡った。橋を渡り終えて、そこからさらに五分ほど歩くと、未舗装の山道の向こうに白い塀が見えてきた。随分と高い塀だ。二十メートルほどはあるだろうか。 塀の中央には門扉があった。開いているので、そこを潜る。門扉の傍には監視カメラがあって、そのレンズが来客である僕たちのことを捉えていた。 そう──、来客だ。塀の中にあったのは庭で、その中央には目的のホテルが建つ。白色の塀よりも一際白い白亜の洋館。『雪白館』はその名の通り新雪の色の建物だった。 塀に囲まれた庭は広く──、庭というよりも館の周囲の土地を壁で囲っただけという印象だった。庭木は少なく、地面も剥き出しの黒土で、花壇の類も見当たらない。 館の玄関の前まで歩くと、そこでメイド服を着た金髪の女が煙草を吸っていた。年は二十歳くらいで、髪の毛は肩までの長さ──、地毛ではなく染めているようだ。かなりの美人ではあるが化粧っ気はなく、さばさばとした印象を受ける。メイドは僕たちの姿に気付くと、ポケットから携帯灰皿を取り出し、名残惜しそうに煙草を消した。 「予約されたお客様ですか?」 メイドは素っ気ない口調で言った。「はい、予約した朝比奈です」と夜月は言う。メイドはこくりと頷いた。 「お待ちしておりました。中へどうぞ」 メイドは、本当にお待ちしていたのか怪しくなるような口調で言った。全体的に愛想が足りない。いや、足りないのは愛想ではなく、やる気なのかもしれないが。 玄関の戸を潜り、雪白館の中へ入る。玄関から延びた短い廊下を行きながら、メイドは思い出したように告げた。 「私はこのホテルでメイドをしております、迷路坂知佳と申します。何か御用がございましたら、何なりと申し付けください」 彼女は、そう定型句のように言う。完全に業務口調なので、本当に申し付けて良いのか心配になってくる。 「迷路坂さんか」と夜月が呟くのが聞こえた。「メイドのメイロ坂さんか」どうやら、語呂合わせであるらしい。夜月は人の名前を憶える際に、語呂合わせをする癖がある。 * 玄関から続く短い廊下を抜けると、そこにはロビーが広がっていた。元々は個人の邸宅だったとは思えないくらいに広く、中規模なホテルのロビーとサイズ的に遜色はない。ロビーにはテーブルとソファーがいくつか並べられていて、そこでは数人の客たちがコーヒーや紅茶を楽しんでいた。テーブルにはケーキの皿も置かれていて、どうやら喫茶店のように軽食のサービスもあるらしい。壁際には大きなテレビもあった。 僕と夜月はまずはフロントでチェックインを済ませることにした。フロントにいたのは三十歳前後の女性で、髪型はショートカット。セーターの上から黒いエプロンを付けていて、どことなく喫茶店の店主のような印象を受ける。落ち着いた大人の女性だ。日常の謎を持ち込むと解決してくれる美人の女店主のよう。 実際、彼女はこのホテルの支配人であるらしい。この館は、彼女とメイドの迷路坂さんの二人で切り盛りしているのだとか。 彼女は詩葉井玲子と名乗った。「支配人のシハイさんか」間髪入れずに夜月が呟く。 詩葉井さんは、柔らかな笑みを浮かべて言った。 「朝比奈様、葛白様、本日は雪白館にようこそいらっしゃいました。豊かな自然と美味しい料理──、そして推理作家の雪城白夜が残した密室の謎解きを。私たち雪白館のスタッフは、皆様を全力でおもてなしいたします」 詩葉井さんはどこか照れくさそうにそんな口上を述べると、フロントに置かれたパソコンのキーを叩く。どうやら、部屋番号を確認したらしい。「宿泊場所は御二方とも西棟の二階になります。朝比奈様が204号室、葛白様が205号室ですね」 そして一度フロントの奥の部屋に引っ込むと、二本の鍵を手に戻って来た。長さ十センチほどの銀色の鍵だ。すらりとしたデザインで、持ち手の部分に部屋番号が刻印されている。彼女は僕と夜月に一本ずつ、その鍵を手渡した。 受け取った鍵を確かめていると、詩葉井さんは冗談めかして言う。 「無くさないでくださいね。合鍵はございませんので」 言われて、僕はもう一度鍵を見る。鍵の先端はかなり複雑な形状をしていた。おそらく、複製は不可能だろう。 僕は鍵をポケットにしまう。そして「205号室」と自分の部屋番号を呟いて、気になっていたことを詩葉井さんに訊ねた。 「あの、西棟というのは?」 僕の部屋は西棟の205号室。でもこの館に来たのは初めてだし、外観もさっき少し眺めただけだから、正直この建物の構造がよくわかっていなかったりする。 「ちょうど、ここにパネルがございます」 詩葉井さんはそう言って、フロントの後ろの壁に飾られたパネルを指差した。建物を俯瞰した図が描かれている。雪白館の見取り図のようだ。 「この雪白館は、四つの建物から構成されています」と詩葉井さんは言った。「まず私たちが今いる──、このロビーのある建物を中央棟と申します。中央棟は一階建てです。そして中央棟の東西には、それぞれ東棟と西棟が──、中央棟の北側には食堂棟がございます。食堂棟はその名の通り、食堂がある棟ですね。朝昼晩の食事はすべてここでお出しします」 見取り図によれば、東棟と西棟と食堂棟(北棟)は、それぞれ扉や渡り廊下で中央棟のロビーと繋がっているが、逆に東西北の三つの建物はそれぞれ直接繋がってはおらず、各棟を移動する際には、必ず中央棟のロビーを通らなければならないようだった。例えば、西棟から東棟に移動する際には、必ずロビーを通る必要がある。 「その認識で合っております」と詩葉井さんは柔らかく笑う。「言わば中央棟が、他の三つの建物を繋ぐジョイントの役割を果たしているというわけですね。加えてこの雪白館には裏口の類が一切ございませんので。窓もすべて開閉が不可能な嵌め殺しか、格子が嵌まっていて人の出入りができないタイプの窓です。唯一庭に出ることができる経路は中央棟にある玄関のみですが、今申し上げました通り、この館には裏口の類はございませんから、庭を通って他の棟に移動することができない造りになっております」 「ふーん、不便ですね」と夜月が言った。「何で、そんな構造になっているんだろ」 「さぁ? 推理作家の考えることは私には」詩葉井さんは曖昧な笑みを浮かべた後で、見取り図を指差して続ける。「ちなみに、各棟を繋ぐ渡り廊下は屋根と壁に囲まれた構造です。吹き曝しではございませんので、そこから外に出ることもできません」 詩葉井さんの言葉に僕は頷く。つまり渡り廊下とは言っても、実際は室内にある廊下と変わらないということだ。 僕は見取り図を見て訊ねた。 「この建物は?」見取り図には、四つの棟の他にもう一つ建物があった。小さい建物で、西棟の北側からぴょこっと飛び出ている。渡り廊下で繋がっているようだ。 「ああ、これは離れです」と詩葉井さんは言った。「雪城白夜が執筆に使っていた部屋の一つです。通称、缶詰部屋。アイデア出しに困った際には、彼はここに籠って林檎を齧っていたそうです」 「何故、林檎を」と夜月。 「アガサ・クリスティーのエピソードにそういうのがあるんだよ」と僕は言った。お風呂に浸かりながら林檎を齧ると、いいアイデアが浮かんでくるというやつだ。そのエピソードを聞くたびに、ほんまかいなと思ってしまうが。 とにかく、雪城白夜の缶詰部屋か。それはぜひとも見てみたいが。 「残念ながら、今は客室として使っておりますので、お見せすることはできません」と詩葉井さんは申し訳なさそうに言った。「今日もご予約が入っておりますので」 なるほど、それは残念だ。ちなみに、離れも渡り廊下で繋がっているから、そこに移動するには西棟を経由する必要がある。 * 「では、ごゆるりとおくつろぎください」フロントでチェックインを済ませた後、僕たちはメイドの迷路坂さんに宿泊部屋まで案内された。西棟は三階建ての建物で、僕の205号室はその二階の一番奥に位置していた。真っ直ぐな廊下に面して、201号室から205号室の五つの部屋が並んでいる。僕を部屋の前まで案内すると、迷路坂さんはぺこりとお辞儀をした。「食事は夜の七時になっておりますので、その時間に食堂までお越しください。私と詩葉井の部屋もこの西棟にございますので、夜間に御用のある場合は、何なりとお申し付けください」 迷路坂さんは相変わらずのさばさばとした口調で言う。本当に夜間に申し付けていいのだろうか? 不安になってくる。 僕はむむっと唸りつつ、ノブに手を掛け扉を開く。すると、そこには白を基調とした清潔な部屋が広がっていた。従業員が二人しかいないとは思えないほど、掃除が行き届いている。 「いちおう、ルンバを二十台ほど飼ってますので」迷路坂さんが僕の後ろから部屋の中を覗き込んで言う。「なので、掃除はほとんどロボット掃除機まかせです。もちろん、細かいところは人の手が必要ですが、それは私が。これでも掃除は得意ですので」 「そうなんですか」何だか意外だ。 「はい、いちおう世界メイド掃除選手権のファイナリストですから」 「世界メイド掃除選手権のファイナリスト」 何だか謎の肩書が出てきた。おそらく冗談なのだろうが、もしかしたら実話かもしれない。 「それでは、ごゆるりと」 迷路坂さんはもう一度そう言って、ロビーの方へと去って行った。僕は荷物を置いた後、さっそく部屋の中を物色してみることにした。 部屋の広さは十畳ほどで、それとは別にトイレとお風呂と広い洗面所が付いている。家具はベッドとテレビと、冷凍スペースの付いた二段式の冷蔵庫くらい。床は飴色のフローリングで、窓は開閉不可の嵌め殺し。かなりいい部屋だ。迷路坂さんの話では、この部屋は元々ゲストルームとして使われていたらしい。雪城白夜は客を招くのが好きで、西棟のほとんどの部屋がこのゲストルームであるのだとか。 僕は次に扉を調べてみることにした。 チョコレート色の一枚扉。重厚な見た目に反して軽く、どうやら一般的な家屋の室内用のドアとしてよく用いられる、フラッシュドアと呼ばれる内部に空洞があるタイプの扉が使われているようだった。木製ということもあり、扉の重さはおそらく十キロ程度だろう。これなら大人が何度か体当たりをすれば、破ることができそうだ。あと、これも迷路坂さんに聞いた話なのだが、この西棟の部屋の扉はすべて同一のもので統一されているらしい。扉のデザインや大きさ、内開きか外開きかについても同じだ。なので自室の扉の構造さえ把握していれば、同時に他の部屋の扉の構造も把握できることになる。ちなみに、この部屋の扉は内開き。だから西棟の部屋の扉はすべて内開きということになる。 何だかテンションが上がってきた僕は、床に身を屈めて扉の下を覗き見た。扉とドア枠はぴったりと密着していて、そこに隙間は存在しない。いわゆる『ドアの下に隙間がない』タイプだ。これでは密室トリックのド定番──、鍵を扉の下の隙間から室内に戻すというトリックが使えない。それだけで、いちミステリーマニアとしては、何だか、にやりとするのだった。 扉を調べ終えたところで、僕はそろそろ部屋を出ることにした。夜月とロビーでお茶をする約束をしていたのだ。隣の部屋──、204号室に移動する。コンコンと扉をノックすると、「ごめんよ」と夜月が出てきた。 「まだ、荷解きが終わってないんだ。先に行ってて」 と彼女は言うものの、それは明らかに嘘だった。夜月のゆるふわの髪の毛には、ぴょこんと寝癖が付いている。どうやら寝ていたらしく、それで身だしなみを整える時間が必要なのだろう。 僕が寝癖を凝視していると、夜月は少し恥ずかしそうに、そっと髪の毛を手櫛で梳いた。 * 仕方なく僕は一人でロビーに向かうことにした。階段で西棟の一階に降りたところで、僕はその姿を見かけた。少し、びくっとしてしまう。廊下の窓辺で一人の女の子が、そっと庭を眺めていたのだ。白い肌と、肩口で切りそろえた銀色の髪。ひと目で外国人だとわかる。しかもその容姿は、人形のように整っていた。 年齢は僕と同じくらいだろうか? 高校生くらいの見た目だ。 少女は僕の姿に気付くとにこりと笑った。そして「こんにちは」と流暢な日本語で言う。僕も慌てて「こんにちは」と返した。外国人と話すのは、少し緊張してしまう。 逆に少女は、まったく緊張を見せずに言う。「ここはいい場所ですね」と笑って、「夏はきっと、いい避暑地になりますね」と世間話を始めた。 避暑地とか、難しい日本語を知っている。 「ここに来た目的は観光ですか?」と僕も世間話を繋ぐ。すると少女は「はい、観光です」と言った。「この近くにスカイフィッシュが出ると聞いたものですから」 「スカイフィッシュ?」と僕は首を傾ける。すると少女は人差し指を立てて、こんな風に説明してくれた。 「スカイフィッシュとは、空飛ぶ魚のことです。簡単に言うとUMAですね」 「簡単に言うとUMA」 その言葉に、僕は固まる。 ……、こいつ、夜月と同じ匂いがするな。 唐突に現れた夜月っぽさに、僕は警戒心をあらわにする。でも悩んだ末に結局、「素敵ですよね、スカイフィッシュ」そんな風に話を合わせた。「魚が空を飛ぶなんて夢があります」可愛い女の子に好かれたいという思いが、僕に日和見な発言をさせる。 その甲斐あって、少女は嬉しそうな笑みを浮かべた。「素敵ですよね、スカイフィッシュ」はにかむように、そう告げる。「それが見たくて、わざわざ福岡からやって来たんです」 「福岡? 海外じゃないんですか?」 「私は福岡在住のイギリス人なんです。五歳から住んでいます」 なるほど、どうりで日本語が達者なわけだ。 彼女としばらく話した後で、僕はそろそろロビーに向かうことにした。「じゃあ、また」と頭を下げると、彼女も同じ仕草を返した。そして別れ際に名前を名乗った。 「私はフェンリル・アリスハザードと申します。ここにはしばらく滞在する予定なので、ぜひとも一緒にスカイフィッシュを探しましょう」 僕はグッと親指を立てる。 「僕は葛白香澄です。ぜひ、一緒にスカイフィッシュを」 * 「大変、香澄くん、ここってネットに繋がらない」メロンソーダを飲みながら、夜月が僕の向かいの席で悲痛な声を上げた。僕はロビーのソファーに腰掛けながら、紅茶に口を付けて言った。 「タクシーを降りた時から圏外だっただろ?」 「そうなんだけど、ホテルに着いたらWi─Fiが使えると思ってたんだもん」夜月は、ううぅ、と嘆き、傍のテーブルを布巾で拭いていたメイドの迷路坂さんを呼び止める。 「すみません、ここってWi─Fi飛んでないんですか?」 「申し訳ございません」と迷路坂さんは、あまり申し訳なくなさそうに言った。「ネット回線は引いておりますが、無線LANは導入していないので。どうしても携帯電話は圏外になってしまいます」 「ううぅ、まじか。陸の孤島やんけ」夜月はそう嘆きながら、スマホをポケットの中にしまった。そしてロビーを見渡して言う。ロビーには、ぽつぽつと客がいた。 「今日は何人くらいのお客さんが泊まりに来ているんですか?」 「予約されているお客様は十二人です」 「十二人も。そんなに」夜月は目を丸くした。そして納得のいった顔をする。「やっぱり、みんなイエティに興味があるんですね」 「イエティ?」 「無視してください」僕は迷路坂さんにそう告げた。 迷路坂さんは首を傾けた後、ホテルが繁盛している理由について教えてくれた。 「手前味噌ですが、支配人の作る料理がとてもおいしいんです」 「詩葉井さんの?」と夜月は言った。「料理は彼女が作っているんですか?」 「はい、創作イタリアンで、とてもおいしいと評判です。この館が長期滞在のお客様しか受け入れていないのも、元々は色んな料理を味わっていただきたいという詩葉井の我が儘から始まったものでして。でも、その甲斐もあって、料理を目当てにやって来られるお客様も多いんですよ。例えば、あそこに座られている社様とか」 迷路坂さんは、少し離れたテーブル席で談笑する男に目を向けた。高そうなスーツを着た四十歳くらいの男と、セーターにジーンズ姿の三十歳くらいの男が談笑している。社というのは、四十歳くらいの男の方らしい。 「ちなみに社様は会社の社長らしいのですが」 「社長の社さん」と夜月。 「うちの料理を大変気に入ってくださっているようで、よくおいでになるんです。まぁ、私は支配人を口説きに来ているんじゃないかと疑っていますが」 そう言われると、そんな感じがする。社はいかにも自信にあふれたタイプで、瞳もギラついていた。何というか、女癖が悪そうだ。 「もう一人の方は、社さんのお連れの方ですか?」と夜月が訊いた。社と話すセーターの男に視線を向ける。社とは対照的に、落ち着いた雰囲気の容姿だった。 「いえ、あのお客様と社様は初対面だそうです」と迷路坂さんは言った。「お二人とも時計が趣味だそうで、互いの腕時計を見てすぐに会話が弾んだそうです。お二人とも昨日から泊まっているのですが、たった一日であのように仲良くなられました」 確かに、初対面とは思えない雰囲気だった。しかし社長である社が目に留めるほどの時計を付けているとは。あのセーターの男も、実はかなりの金持ちなのだろうか。 「はい、医者だそうです」 「医者かよ」やはり上流階級だったか。 「はい、石川さんという名前だそうで」 「医師のイシカワさんね」と夜月。 「二人とも何百万円もする時計を使っているそうです。そこまでの高級品を身に付けるのは、私は逆に下品なんじゃないかと思っているのですが」 迷路坂さんは、そんな風に毒を吐く。彼女は毒舌メイドだった。おまけに、よく考えると顧客の職業といった個人情報もペラペラと喋っているし。個人情報ゆるゆるメイドなのかもしれなかった。話し相手としては楽しいけれど、ホテルの従業員としてはどうかと思う。 そんな個人情報ゆるゆるメイドは、こちらにぺこりと一礼して、その場を立ち去ろうとする。僕はそこでふと迷路坂さんに用があったことを思い出した。呼び止めると、迷路坂さんはどこか迷惑そうに視線を向ける。 「何でしょう?」 「いや、何というか」僕は紅茶で喉を湿らせて言う。「この館には、雪城白夜の持ち物だったころから、手の入っていない部屋があると聞きまして」 僕の曖昧な言い回しに、それでも迷路坂さんはピンと来たようだった。「ああ、あなたもあの部屋が目当てなんですか」と告げる。 「あの『雪白館密室事件』の犯行現場が」 僕はこくりと頷いた。かつて雪城白夜のホームパーティーで起きた事件の現場だ。 迷路坂さんは小さく肩を竦めた。 「密室の謎解きなんて──、私には何が面白いのかわかりませんが、もちろんお見せすることは可能です。支配人の創作イタリアンと並んで、当ホテルの名物ですから」 僕は紅茶を飲み干し、腰を上げた。そしてメロンソーダを飲んでいる夜月に訊く。 「夜月はどうする?」 「私はまったく興味ないので」 間髪入れずに返ってきた。僕はとても寂しかった。 * 『雪白館密室事件』が起きたのは、僕が泊まる西棟とは反対側に位置する東棟の二階だった。東棟の二階の廊下には毛足の長い絨毯が敷かれ、歩くとフカフカとする。僕の前を行く迷路坂さんが立ち止まり、一室の扉を指し示した。 「この部屋でございます」と迷路坂さんが言った。 この部屋か、と僕は思った。 少し緊張しながら、ノブを掴み、扉を開く。その部屋は、僕が泊まっている西棟の部屋と同じくらいの広さだった。十畳ほどで、ただし二つの部屋が連なっている造りだ。部屋の入口から見て左手の壁にもう一つ扉があり、隣の部屋に行ける造り。そしてその隣の部屋こそが『雪白館密室事件』の本当の現場なのだ。 僕は室内に入り、左手の壁の扉を潜る。今は扉は開いている状態だ。十年前の──、事件の際にも開いていたらしい。 隣室に踏み入った僕の目に留まったのは人形だった。ナイフが刺さったフランス人形──、ではなく、無傷のクマのぬいぐるみ。さすがにナイフの刺さった人形ではショッキングなので、代わりに置かれているらしい。 僕は過去に書籍で読んだ事件の概要を思い出してみた。あらましはこんな感じだ。 十年前──、雪城白夜が主催するホームパーティーでのこと。中央棟のリビング(現在はロビーに改修されている)で皆が食事を楽しんでいると、東棟の方から女の叫び声が聞こえた。びっくりした皆は、悲鳴が聞こえた東棟に向かう。そこで再び叫び声。どうやら二階から聞こえる。階段を上り廊下を右往左往していたところで、みたびの叫び声。そこでようやくと皆は、どの部屋から悲鳴が聞こえているかに気が付いた。ノブを掴み、回す。鍵が掛かっていた。来客の一人が雪城白夜に言う。白夜と同年代のミステリー作家だ。 「この部屋の鍵は?」 「数日前から紛失しているんだ」と白夜は答えた。「どこに行ったのかわからない。でも、おかしいな。昨日確かめた時には、この部屋には鍵が掛かっていなかったはずだが」 「となると、誰かが鍵を掛けた?」 「そう考えるしかないだろうな」 今度は別の来客が訊ねる。大手出版社の若手編集者だ。 「マスターキーはないんですか?」 「マスターキーはないんだ」と白夜は首を振る。 「でも、持ってましたよね、マスターキー。使っているのを見たことがあります」 「ああ、あれは西棟のマスターキーだよ。西棟と東棟では鍵の体系が違っているんだ。西棟のマスターキーでは、東棟の部屋の鍵は開けられない。そして東棟にはマスターキーが存在しない」 「どうして存在しないんですか?」 「さぁ、どうしてだったかな? 忘れてしまったよ」 のらりくらりと白夜は言う。そんな彼にまた別の客が訊ねた。デビューしたばかりの十代の女性作家だ。 「じゃあ、合鍵はないんですか?」 「合鍵はない。この雪白館の鍵はすべて極めて特殊なものを使っていてね。合鍵を作ることは不可能なんだ」 「じゃあ、部屋に入るには窓を破るしかないですね」 「いや、窓には格子が嵌まっているから、人が出入りすることはできない」 「じゃあ、いったい、どうやって中に入れば……、」 そこで、再び女の悲鳴が聞こえた。皆は顔を見合わせる。「仕方がないな」と別の客が言った。辛辣で知られる三十代の男性評論家だ。 「ドアを破ろう。いいですよね、先生」 「緊急事態だ」 白夜は渋々と頷いた。 体格のいい男たちが数人、内開きの扉の前に陣取る。そして掛け声とともにドアにぶつかった。扉が軋む音。それを何度となく繰り返す。十回に迫ったところで、ようやく扉が音を上げた。 破られた扉が勢いよく開く。室内は真っ暗だった。誰かが手探りで電気を点ける。 照明に照らされた部屋の中に、異変は見つからない。 「もしかして、あっちの部屋じゃないですか」と大手出版社の若手編集者が言った。彼が指差しているのは、入口から見て左手の壁に設えられた扉だった。隣室に移動するための扉で、今はその扉は開いている。開けっぱなしの状態だ。扉は壁の中央よりも右側に──、つまり、部屋の入口から見て奥側に設置されていた。 皆でおっかなびっくりと、隣室に続く扉へと近づく。隣室の照明は、入口のある主室の照明と連動しているようだった。主室の電気を点けたことで、今は隣室の照明も灯っている。なので扉に近づくと、中の様子は良く見えた。隣室にはナイフの刺さったフランス人形が転がっていた。ちょうど、扉の真正面に当たる位置だ。床ごと貫くかのように人形に突き立てられたナイフは、刃渡りが三十センチほどもあり、その刃が扉の方を向いてキラキラと輝いていた。 悲鳴を上げる者はいなかった。ただ、皆びっくりした様子だった。 フランス人形が転がった隣室には、その人形の他にも特徴的なものが二つあった。事件の遺留品と言ってもいいのかもしれない。 一つ目がボイスレコーダーだ。これはフランス人形の傍に落ちていた。再生させると女の悲鳴が聞こえた。どうやら先ほどの悲鳴は、ここから流れていたものらしい。 そして二つ目は、『被害者』役のフランス人形から少し離れた位置に転がった瓶だ。その瓶の中には鍵が入っていた。白夜は透明なプラスチック製の瓶を手に取って、「間違いない、この部屋の鍵だ」と言った。 皆はざわついた。 「じゃあ、この部屋は──、」と白夜と同年代のミステリー作家が言った。「密室だったということか?」 「信じがたいが」と白夜は言った。「そういうことになるな」 「いや、そんなわけないでしょう。先生、ちょっとその鍵貸してくださいよ」と辛辣で知られる三十代の男性評論家が、白夜から鍵の入った瓶を受け取る。固く閉められた蓋を開けて、中から部屋の鍵を取り出した。「よくあるトリックだ。どうせこの鍵が偽物とかだろ」 彼はそう言って鍵を持って、部屋の入口の扉まで移動した。そして鍵穴に鍵を挿し、驚いたように目を丸くする。 「本物だ」と辛辣で知られる三十代の男性評論家は呟いた。 「信じられないな」と白夜は言った。「まさか、こんなことが起きるとは」 「てか、先生」 「うん?」 「先生、さっきから、何をニヤニヤしてるんですか?」 とデビューしたばかりの十代の女性作家が言った。 皆の視線が白夜に集まる。白夜は笑みを消して、しれっと言った。 「笑ってないよ」 「どう見ても笑ってるじゃないですかっ! あっ、もしかして、さては先生──、」 十代の女性作家はそこで言葉を止めた。皆まで言うまい、と彼女は思った。このジジイを吊るし上げるのは、密室の謎を解いてからでも遅くはない。 彼女は宣戦布告のように、挑戦的な笑みを白夜に向けた。その笑みを浮かべたのは彼女だけではない。白夜と同年代のミステリー作家も、大手出版社の若手編集者も、辛辣で知られる三十代の男性評論家も──、そして他の客たちも皆、同じ気分だった。 自分が一番最初に謎を解いて、このジジイに目にものを見せてやる。 こうしてホームパーティーの隠しイベント──、『雪白館密室事件』の推理大会の幕が上がった。一夜のうちに様々な推理が飛び交い、そして真相に辿り着いたものは誰一人としていなかった。 「……」 というのが僕が書籍で読んだ『雪白館密室事件』の概要だった。現場に居合わせた十代の女性作家(今は二十代で、大きな賞もいくつか取っている)の短編集の巻末に、この時のことが記載されている。僕は何度も読み込んでいるので、完璧に頭に入っていた。 僕は、ふむと一息ついて、さっそく調査を開始した。まずはこの部屋にある、唯一の窓を確かめる。窓は隣室の──、主室と隣室を繋ぐ扉のちょうど正面に位置していた。大きな窓で、床から天井までの高さがある。聞いていた通り、金属製の格子が嵌められていた。窓はスライド式の開閉窓で、事件当時は開いていたらしいが、格子が嵌まっている以上、そこから人が出入りすることはできない。 窓の確認を終えた後、僕はこの事件の最重要の遺留品である、瓶に入れられた部屋の鍵を調べてみることにした。僕は床の上に落ちていたそれを拾い上げる。 瓶は思ったよりも小さかった。サイズはカメラのフィルムケースくらいだ。蓋はジャムの瓶のように金属製で、捻ると開けられるタイプ。もちろん、事件が発覚した際には、蓋はきっちり閉められていたらしい。そしてその蓋の上部には『O』型の小さな突起が取り付けられていた。紐などを通すための突起のようだ。 僕は突起をしばし眺めた後、透明な瓶の中に入った鍵に目を移した。「この部屋の鍵です」と僕の傍で手持ち無沙汰にしていた迷路坂さんが言った。「レプリカではなく本物ですので。無くさないように気を付けてください」 鍵は僕の泊まっている西棟の鍵よりもだいぶ小さいものだった。長さは五センチほど。現場に残されたプラスチック製の小瓶にも十分に入る大きさだ。ただし、隣室の窓に嵌められた正方形の格子を通り抜けるほどのサイズではない。格子一つ一つのサイズは、瓶の中に入った鍵よりも遥かに小さいものだった。つまり、窓の格子から室内に鍵を入れることはできない。しかし、別の場所からならば──、 「なるほどね」と僕は呟く。「何が、なるほどなんですか」と迷路坂さんが言った。 僕は小瓶を手にしたまま、部屋の入口へと向かう。迷路坂さんもついてきた。彼女と一緒に廊下に出ると、僕は扉を閉めて、毛足の長い絨毯に膝をついた。そっと身をかがめて、扉の下部を覗き見る。 「……、何をしてるんですか?」怪訝そうに迷路坂さんが言った。「扉の下の隙間を調べているんですよ」と僕は返す。 扉の下には隙間があった。僕の泊まる西棟の部屋の扉にはこんな隙間はなかったが、この東棟の部屋は造りが違うらしい。もっとも、この情報を僕は事前に知っていた。事件のことを記した書籍に書いてあったのだ。 僕がそんな風に説明すると、「正確に言えば」と迷路坂さんは言った。 「扉の下に隙間があるのは、東棟の二階と三階にある部屋だけです。この東棟は三階建てですが、一階の部屋にだけは扉の下に隙間がありませんから」 「どうして一階には隙間がないんですか?」 「それは一階の部屋の床には絨毯が敷かれていないからです」 僕は首を傾けたが、少しの間を置いて、その言葉の意味に気付く。 「もしかして、絨毯が扉に引っ掛からないようにするためですか?」 迷路坂さんは、こくりと頷く。僕は、なるほどと思い、改めて扉を眺めた。 この部屋の扉は内開きで、室内には廊下と同じく毛足の長い絨毯が敷かれている。廊下の絨毯の毛足の長さは七センチほどで、室内の絨毯の毛足の長さは一センチほどといったところか。おそらく、上階である三階も同じ仕様なのだろう。なので、仮に扉の下に隙間がなかったとしたら、扉を開いた際に絨毯が引っ掛かって上手く開閉できなくなる。 そしてこの扉の下の隙間こそが、密室にとって重要なのであった。毛足の長い廊下の絨毯に隠れてほとんど見えなくなっているけど、そこには確かに隙間がある。となると、導き出される結論は──、 僕はプラスチック製の小瓶の中から部屋の鍵を取り出した。それを扉の下の隙間に通してみる。サイズ的に全然入る。鍵を使って扉を施錠した後、その鍵をこの隙間から室内に戻すことは可能なようだ。となると、次に確かめることは──、 僕は鍵を瓶に入れて蓋を閉めた。そしてその瓶を扉の下の隙間に突っ込もうとする。 プラスチックの瓶が扉に引っ掛かり、カチカチと音を立てた。この瓶のサイズでは扉の下の隙間を通すことはできないようだ。 「うーむ」 迷路坂さんがあくびをするのが見えた。僕はとても悲しかった。 ならば、別のアプローチを──、と僕は扉を観察する。扉の内側には鍵のツマミが付いておらず、その代わりに鍵穴が付いていた。つまり、この扉は部屋の中から扉を施錠する際にも鍵が必要だということだ。これでは鍵のツマミに糸などで力を加えて、扉を施錠する類のトリックを使用することはできない。 つまり、やはり密室を作るには扉の外から鍵を使って施錠するしかないのだが──、 「……、問題はその鍵を、どうやって部屋の中に戻すのかってことなんだけど」 「そうだな、その方法がわからないから問題なんだ」 突然割り込んできた知らない声に、僕は視線をそちらに向ける。 そこには男が立っていた。戦前の英国人が着ているような、古めかしいスーツを着た男。年齢は二十代半ばで、背は僕と同じくらいの高さ。そして顔はなかなかのイケメンだった。彫りが深く、短髪の髪をワックスで撫でつけ、理知的な額を出している。 「探岡様」と迷路坂さんが言った。そして彼女は呆れたように溜息をつく。「まだ、いらっしゃったんですか。てっきり、部屋に戻ったのかと思ってましたが」 「いや、トイレに行ってただけだよ」と探岡と呼ばれた男は言った。「気分転換を兼ねてな。やっぱり、ずっと考えていると、思考の泥に足を取られて動けなくなってしまうからな」 僕は二人の会話から、何となく状況を察した。 おそらく、この探岡という男は先客だろう。もちろん、ホテルの客でもあるのだろうが、先客とはそういう意味ではない。きっとこの探岡も、僕と同じく『雪白館密室事件』の謎に挑んでいる者なのだ。そして僕より一足早く調査を開始した。 「君の考えている通りだよ」と僕の思考を読むように探岡が言った。「俺も君と同じく、この密室に挑んでいる。ああ、申し遅れたな──、俺はこういう者だ」 探岡はポケットから名刺を取り出す。受け取った名刺には『密室探偵探岡エイジ』と書かれていた。密室探偵──、この人、密室探偵なのか。 密室探偵というのは、この国で密室殺人が頻発するようになってから新たに生まれた職業だ。現状、日本で起きる密室殺人の三割には、鍵のツマミに物理的な力を加えて回したり、犯人が部屋の中に隠れていたりといったひどく単純なトリックが使われているのだけど、残りの七割にはかなり複雑──、あるいは先鋭的なトリックが使われていて、こちらは並の警察官では対処できない。なので警察はその謎解きを外部の探偵に依頼する。そこで指名されるのが密室探偵だ。彼らは密室の謎を解くことで、国家から報酬を貰っている。 もっとも警察から協力を依頼されるのは一部の密室探偵だけで、大半の探偵は密室だけでは食べられないので、浮気調査や犬探しで生計を立てているという話だが。 僕の訝し気な視線に気が付いたのか、探岡は肩を竦める。 「おいおい、そんな目で見ないでくれ。これでもいちおう『この密室探偵がすごい』でベスト10に入ったこともあるんだぜ」 「えっ、本当ですか。すごい」 僕はコロッと態度を変えた。『この密室探偵がすごい』というのは半年に一度発行されている雑誌で、その名の通り事件の実績などをもとにした密室探偵のランキングを載せている。そこでベスト10に入ることは、とても名誉なことなのだ。 僕も毎回読んでいるので、この男のこともたぶん知っているはずだ。思い出そうと記憶を辿る。探岡エイジ──、確かに聞き覚えがある。どんなことが書いてあったか。 でも、探岡についてようやく思い出したのは、『この密室探偵がすごい』に書かれたのとはまったく別の記事だった。 「……、もしかして探岡さんって、この前、不倫騒動が出ていた」 「ああ、それについては忘れてくれ」 間髪入れずに返ってきた。困ったような苦笑いを浮かべている。 確か一年くらい前に、週刊誌で記事が出たのだ。『この密室探偵がすごい』に選ばれた若手探偵が人妻と不倫していると。当時「まさか、探偵の不倫が報道される時代になるなんて」と、とても驚いた記憶がある。 「まったく、苦い思い出だ」と探岡は肩を竦める。「まぁ、探偵にも得手不得手があるってことだよ。事件を解決するのは得意でも、恋の謎解きは苦手なんだ」 探岡は上手いことを言った。いや、あまり上手くないのかもしれないが。 彼は、こほんと咳をする。 「まぁ、とにかく俺は密室専門の探偵で、今回は雑誌の取材を兼ねてここを訪れているんだ。不倫記事の取材じゃないぞ? ミステリー系の雑誌で、『雪白館密室事件』の現場で俺がインタビューを受けるという企画だ。もちろん、事件の謎解きにも挑むんだが、まだ記者が来てないみたいでな。先に下調べをしてるんだ。記者が到着した時に、あっさりと謎を解いた方がカッコいいだろ?」 なかなか、地に足のついたことを言う。僕はそんな探岡に訊ねた。 「それで──、どこまで解けました?」 「正直に言うと、さっぱりだ」探岡は肩を竦める。「さっき君がやっていた通り、鍵は瓶に入った状態だと扉の下の隙間を通らない。つまり、犯人──、というより雪城白夜だな。彼は鍵を瓶に入れた後で密室に戻したのではなく、鍵を密室に戻した後で瓶に入れたということだ」 「ああ、やっぱりそうなりますか」と僕は言った。「つまり、鍵を扉の下から室内に入れ、釣り糸か何かを使って隣の部屋まで移動させる。そして何らかの方法で瓶の中に入れた」 「ほう、わかってるな、少年」探岡は感心したように口笛を吹く。「だから、ここで問題になるのは、①どうやって鍵を瓶の中に入れたのか──、②どうやって瓶の蓋を閉めたのか──、この二点ということになる」 「①は頑張ればできそうですけど、②は厳しそうですよね」 「そうなんだよ、釣り糸を蓋に巻き付けて、くるくると回転させて閉めるという方法も考えたが、そもそも瓶は床に固定されていなかったしな──、物理的に考えて厳しいだろう。でも、じゃあ、いったいどうやって蓋を閉めたんだって話になるし」 「じゃあ、こういうのはどうでしょう? 蓋を開けて横倒しの状態にした瓶を、室内の──、扉のすぐ傍に置く。そして廊下側からデコピンで鍵を弾いて、扉の下から勢いよく鍵を入れる。これで瓶の中に鍵を入れることはできます。そこから細い棒か何かを使って、扉の下の隙間から蓋を閉めれば」 「あとは瓶を隣の部屋に移動させるだけということか」探岡は、ふむと頷いた。「幸い、瓶の蓋には『O』型の突起が付いているしな。ここに糸を通して引っ張れば、確かに瓶を移動させることができる。でも残念ながら、そのトリックは実行不可能だよ。見ての通り、扉の下の隙間はかなり狭い。一センチくらいだ。この隙間から針金か何かで蓋を閉めることはできないよ。しかも、蓋はかなりきつく閉まっていたらしい。手で直接捻らないと、そこまで固く閉めることは不可能だろうな」 「うーん、じゃあ、いったいどうやって」 「ああ、そこが謎なんだ。まったく雪城白夜も、とんでもない不可能犯罪を用意してくれたものだぜ」 そんな風に議論する僕たちを、迷路坂さんが冷めた目で見つめていた。やがて溜息をついて、「ごゆるりとお楽しみください」そう言って去っていった。 * ところで、現場に居合わせた十代の女性作家──、彼女がまとめた『雪白館密室事件』のルポは、推理作家──、雪城白夜のこんなセリフで締めくくられる。夜が明け、推理大会がお開きになった後も白夜は自分が犯人であることを認めなかったが、代わりにその女性作家にだけ、こう言い放ったというのだ。 「残念だ」──、と。 「今、示されている情報だけで、この密室の謎を解き明かすことは可能なのに」 * 二時間後、密室の謎に打ちひしがれた僕と探岡は、ふらふらとロビーへと戻った。探岡は「じゃあ、また後でな」と僕に言うと、ふらふらと窓際の席に向かう。疲れたらしい。いや、僕も疲れたけど。 フロントの近くの席に夜月がいたので、僕はそこに合流する。スマホのゲームで遊んでいた夜月は、僕に気付くと顔を上げた。 「お疲れ、密室の謎はどう?」 「いや、正直、さっぱりわからん」 「だろうね、予想通りだよ」 彼女はそう言って、再びスマホに目を戻した。むかつくが、何も言い返せないのが悲しい。僕は迷路坂さんにバナナジュースを注文した後、ソファーに腰かけ目を瞑った。疲れた。体が泥のようだ。このまま眠りこけてしまいたい……。 でも、そんな僕の脛を夜月が蹴った。足がぶつかっただけかと思い無視していると、今度は思いっきり蹴られた。やっぱり、間違いじゃなかった。なんて酷いことをする女なのだろう。 目を開けると、悪びれもしない夜月の顔が映った。彼女は何故かテンションの高い小声で言う。 「香澄くん、香澄くん」 「うるさいな、何?」 「ねぇ、あれ見てよ」 夜月はカウンターの方を指差した。そこには宿泊客らしい一組の男女が立っていた。二十代後半の男と、十代半ばの少女。どう見ても、カップルではない。男は眼鏡に冴えない容姿をしていて、対して少女の方はキラキラと輝いていた。茶色の髪をツインテールに結んでいて、幼い顔立ちだが華があり、人目を惹く容姿をしている。何だか、オーラがすごい。というよりも、あの少女、どこかで見たことがあるような。 「ほら、長谷見梨々亜よ。朝ドラ女優の」 「あっ!」 僕は思わず声を上げた。梨々亜の視線がこちらに向く。僕は慌てて目を逸らした。 梨々亜──、長谷見梨々亜。彼女は秋まで放送されていた朝ドラで主演を務めた、国民的女優だった。年齢は確か十五歳。元々人気はあったが朝ドラで大ブレイクし、今はドラマやバラエティ番組などに引っ張りだこになっている。 俗人の象徴のような僕と夜月は、やはりテンションが上がっていた。 「ねぇねぇ、香澄くん、どう見ても本物だよね」 「うん、どう見ても本物だ」 「すっごく可愛い」 「確かに」 「ねぇ、後でサインもらおっか」 「嫌がられない?」 「有名税でしょ」 「確かに」 「だったら、払う義務があるよね」 僕たちはひそひそ話をしながら、梨々亜の姿を注視する。梨々亜は支配人の詩葉井さんからフロントで鍵を受け取った。そして鍵に刻印された部屋番号を見て、嬉しそうな声を上げる。 「わーっ、001号室だ。これって、アレですよね。離れの」 「はい、西棟の離れでございます。雪城白夜が執筆に使用していた」 「わーっ、やっぱりそうなんですねっ!梨々亜、雪城先生の大ファンだから、一度泊まってみたいと思ってたんです」 梨々亜は雪城白夜のファンだったのか──、僕は意外な事実を知った。そして実際に会った梨々亜はけっこう、ぶりっ子な性格だった。いや、こういうキャラなのはバラエティ番組とかで見て知ってはいたが。 「とにかく、ありがとうございますっ! 感激です」梨々亜は嬉しそうに鍵を握りしめながら、詩葉井さんにお礼を言った。そしてフッとその笑みを消し、連れの男に声を掛ける。 「じゃあ、真似井さん、部屋の前まで荷物を運んどいて」 ちょっと、びっくりするくらい冷たい声だった。真似井と呼ばれた男は「はい、梨々亜さん」と言って、床に置かれていたブランド物の旅行鞄(たぶん、梨々亜の鞄)を持って西棟の方へ消えていった。 梨々亜は再びにっこりと、詩葉井さんに笑みを浮かべた。 「ここのロビーでお茶が飲めるんですか? 梨々亜、喉渇いちゃって」 「はっ、はい、あそこにいるメイドに言ってもらえば、いろいろ頼めます」 「本当ですかっ! 嬉しいっ! すみません、メイドさん、注文いいですかーっ」 梨々亜は嬉しそうに、迷路坂さんの方に駆けていく。 何だか、裏表の激しい子だ。真似井はたぶん梨々亜のマネージャーなのだろうが、ああも冷たい対応を見せられると、芸能人って怖いって思ってしまう。 「マネイさんも大変だね。マネージャーだけに」夜月がまた語呂合わせを始めた。 先ほど注文したバナナジュースを迷路坂さんが運んできたので、僕はそれを一口飲む。ぼんやりとロビーを眺めていると、ロビーにそれなりの数の宿泊客が集まっていることに気が付いた。社長の社と医師の石川は未だに時計の話をしているようだし、朝ドラ女優の梨々亜はグレープフルーツジュースを嬉しそうに飲んでいる。探偵の探岡はソファーで、ぐでっーとダウンしていた。僕と夜月を含めると、今ロビーにいる宿泊客は六人。今夜泊まる客の数は十二人だそうだから、半数がこの場所に集っているということになる。 残りの宿泊客はどんな人たちなのだろう? そんなことを考えていた時に、僕は彼女の姿を見かけた。瞬間、全身の毛が逆立った。信じられない思いだった。どうしてだ──、どうして彼女がここにいる? 彼女はちょうど西棟からロビーに移動してきたところのようだった。腰まで届く長い黒髪と、美しく整った涼やかな顔立ち。そして切れ長の大きな瞳。美少女という言葉が、彼女ほど似合う人間を僕は知らない。 でもその姿は、僕の記憶の中のものより少しだけ大人になっていた。それはそうだろう──、彼女と最後に会ったのは、もう一年以上前になるのだから。 僕は知らず立ち上がり、彼女へと近づいていた。そんな僕の姿に気付いて、彼女は目を丸くする。そして驚いたように言った。 「葛白くん?」 頷く代わりに、僕は言った。 「久しぶりだな、蜜村」 ああ──、ここに来て良かったと思った。夜月が「イエティを探しに行こう」と言い出した時はマジかと思ったが、この報酬はその対価としては十分すぎるものだった。 「久しぶりね、葛白くん」 と彼女が笑う。 これが僕と蜜村漆璃の一年ぶりの再会だった。 * 「香澄くん、この子は?」 僕と蜜村の関係が気になったらしく、夜月がぴょこぴょこと寄ってくる。「何というか」と僕は言った。 「中学の時の同級生だよ。同じ文芸部に所属してたんだ」 と言っても文芸部の部員は、僕と蜜村の二人だけだったが。そのせいで、彼女が文芸部を辞めるまで、僕は放課後のほとんどの時間を彼女と一緒に過ごしていた。 そんなことを夜月に話すと、彼女は、ははーんという顔になった。 「なるほどねぇ」と夜月は言う。「つまり、元カノということね」 いや、違うから。何を聞いてたんだ、こいつ。 「じゃあ、友達以上、恋人未満?」 「何を聞いてたんだ、お前」 「葛白くん、その人は?」 今度は蜜村が僕に訊ねた。どうやら僕と夜月の関係を訊ねたらしい。 「うーん、何ていうか」答えづらい質問だな。「いちおう、幼なじみってことになるのかな?僕の隣の家に住んでいて、小さいころは姉代わりで」 「なるほど」と蜜村は頷く。「つまり、幼なじみ以上、姉未満というわけね」 何だか、妙なことを言い出した。 僕は彼女に訝し気な視線を向けた後で、純粋に気になっていたことを訊ねる。 「ところで蜜村、今日はどうしてここに?」 「やっぱり、イエティを探しに来たの?」と夜月。 「イエティ? いえ、ただの旅行で来たんですけど」と蜜村。「えっ、イエティが出るんですか?」 夜月は得意気に胸を張った。 「出るよ」 「いや、出ないだろ」と僕。 「いったい、どっちなの?」 蜜村は戸惑ったように言った後で、やがて小さく噴き出した。首を傾けた僕たちに、「いや、何だか懐かしくて」と彼女は笑む。「葛白くんと話すの、久しぶりだから」 「そっか、それは懐かしいよね」夜月がそう相槌を打つ。そして興味を惹かれたように、「香澄くんって中学ではどんな感じだったの?」と訊ねた。蜜村は「そうですねぇ」と記憶を辿るように答える。 「何というか、けっこうイキってましたね。いつも『俺は一匹狼だぜ』みたいな面構えで歩いていたような」 いや、どんな面構えだよ。いくら中学の時とはいえ、そんな顔で歩いてはいないような。 「あと、こんな噂も聞きました。『僕は一度見たものを、写真のように記憶できる。そういう特殊能力があるんだ。でも脳に負荷が掛かりすぎるから、普段のテストとかでは使わない。使う時は唯一──、世界に危機が訪れた時だけだ』そんなことを自慢げに、友達に言いふらしていたとか」 中学時代の僕、痛すぎだろっ! いや、確かに言ってたけどもっ!そういうのって、ある程度時間が経ったら時効になるって約束では? そんな僕の心の叫びを無視して夜月が言う。 「その話、詳しく聞かせて」 「いいですよ、じゃあ、一緒にお茶でも飲みながら」 僕の悪口で意気投合した二人は、一緒にテーブルの席に着く。僕もそこに同席した。蜜村は見た目はクールで真面目そうだけど、けっこう適当なところがあるからな。あることないこと話されないように監視しておく必要がある。 僕が二人に目を光らせていると、そのタイミングで西棟から一人の男が戻ってきた。眼鏡姿の冴えない男──、朝ドラ女優の長谷見梨々亜のマネージャーだ。名前は真似井だったか。真似井はソファーでくつろいでいる梨々亜の向かいの席に座った。そして手にしていた仕事鞄から、ぺら紙を一枚取り出す。それをテーブルの上に置いた。 グレープフルーツジュースを飲んでいた梨々亜は、その紙を眺めて言う。 「真似井さん、それは?」 「バラエティ番組のアンケート用紙です」 「げっ」 梨々亜はあからさまに嫌そうな顔をした。ジュースのストローに口を付けて言う。 「梨々亜、今そういう気分じゃないの。真似井さん、代わりに書いといて」 「ダメです、ちゃんと書かないと」 「でも、梨々亜、箸より重いもの持てないし。ペンって箸より重いでしょ?」 「材質によりますね」 それはそうだろうと思う。 梨々亜はだんだんと、不機嫌になってきたようだ。 「わかんない? 書きたくないって言ってんの」 「でも、バラエティ番組のアンケートは大事です」真似井は、意外と毅然とした態度で言った。「アンケートの書き込み次第で、チャンスの量が変わるんです。いっぱい書けば、いっぱいMCが振ってくれるんです。逆にアンケがスカスカだと、MCやスタッフさんにやる気がないやつだと思われます」 「うん、わかってる。だから、真似井さんに書いてって言ってんの」 「話がループしてますね」 「そういう魔法が掛かってるのかな?」 梨々亜はジュースを飲み干すと、真似井の手から乱暴にアンケート用紙を奪い取る。 「わかった、じゃあ、書いてくるよ。部、屋、で、ねっ!」 ガタッと勢いよく立ち上がった。そのまま梨々亜は不機嫌な足取りで西棟の方へと去っていった。真似井は深く溜息を吐く。 そんな真似井と梨々亜のやり取りの間も、夜月と蜜村は僕の中学時代の話で会話に花を咲かせていた。出るわ出るわの黒歴史。でも、二人は突然そのやり取りをやめる。梨々亜がロビーから出て行ったタイミングで、雪が降り始めたのだ。 窓の外に──、雪が。 きらきらと、勢いよく空を舞って幻想的に降り積もる。庭が白く覆われていく。そういえば、雪を見るのは今年初めてだったか。しかも、旅行先で見る雪だ。否応なくテンションが上がる。ロビーに集まった他の客たちも、窓の外に視線を向けていた。 社長の社も医師の石川も、探偵の探岡も。先ほど梨々亜と揉めた真似井も、気晴らしのように雪を眺める。コーヒーを運んでいた迷路坂さんも窓の外を見つめていた。支配人の詩葉井さんだけが、フロントのカウンターでパソコンを叩いている。 今夜、このホテルに泊まる客は、全部で十二人だと聞いている。今はそのうちの七人が、このロビーに集まっている。僕の知っている客の中で、ここにいないのは梨々亜と──、イギリス人のフェンリル・アリスハザードだけだ。 そんなフェンリルも、雪が降り始めて十分後くらいにロビーへと現れた。コートを着ていて肩に雪が積もっているので、庭を散歩していたらしい。これでロビーに集まった客は八人だ。銀髪を雪で濡らしたフェンリルは、しばしロビーをきょろきょろしていたが、僕のことを見つけると嬉しそうに近づいてくる。 「葛白さん」彼女はテーブルの上にそれを置いた。それは雪でできたウサギだった。「お土産です」 ちょっこりとした雪ウサギが、木目のテーブルの上にたたずんでいる。かわいい。 フェンリルはにっこりと笑った。 「ぜひ、お召し上がりください」 「えっ、食べるの?」 「中にあんこが入っていますから」 「……、まじで?」 恐る恐る齧ろうとしたところで、フェンリルが「冗談です」と笑った。彼女はいたずらっ子のように僕らの席を離れると、トテトテと窓際に移動してスマホで庭の撮影を始めた。窓の外の雪はいっそう激しさを増していた。 それから二十分ほどで雪はやんだ。短い雪だったが、庭はすっかり銀世界だ。高い塀に囲まれた館の箱庭を真っ白に染めている。 雪が降りやんだのを切っ掛けに、ロビーに集まった八人の客たちは、ぽつぽつと席を立ち始める。ずっとカウンターで働いていた詩葉井さんも、大きく伸びをして食堂棟の方に向かって行った。入れ替わるように、迷路坂さんがカウンターに入る。 僕も部屋に戻ることにする。フェンリルに貰った雪ウサギが、少し、ぐだーっとなっていた。融けないうちに部屋の冷凍庫に入れて延命させる必要がある。 * 夜七時、僕は夜月と一緒に食堂棟へと向かった。 夕食はもう始まっているようだった。食堂の北側の壁は全面、明かり取りの硝子窓になっていて、今は暗闇を映しているけれど、昼間はさぞ開放的だろう。広い室内にはテーブル席がいくつかあって、客たちはそれぞれそこに着いて料理に舌鼓を打っていた。席はあらかじめ決められているようで、僕たちは『朝比奈様・葛白様』と、僕と夜月の名前のプレートが置かれている席に座った。それを見た迷路坂さんが、さっそく料理を運んでくる。 「『シェフの気まぐれオードブル~南欧、西欧、北欧の風とともに~』でございます」 いきなり謎の料理を出された。どこの国の料理なのかわからない。 「多国籍だよね。このスパニッシュオムレツがスペインでしょ? それでこのカルパッチョがイタリアで、このニシンを使った何かが北欧?」夜月はそのニシンを使った何かを食べる。そして目を丸くした。「何この料理──、めちゃくちゃ美味いやんけ」 「えっ、まじで」 「食べてみ。舌が原形がなくなるくらいトロけるから」 原形がなくなるのは嫌だが。 僕は夜月と同じく、そのニシンの料理を食べる。そして思わず「はわわ」となった。 「何だこの料理──、めちゃくちゃ美味いじゃねえか」 「舌がトロけるでしょ」 「トロけるトロける。今まで食べた魚料理の中で一番美味しいかもしれん」 料理にテンションが上がった僕は思わず「シェフを呼んでくれ」モードになっていた。近くで給仕していた迷路坂さんを指パッチンで呼び寄せる。 やって来た迷路坂さんに言った。 「料理、とてもおいしいです」 「はぁ、そうですか」 素っ気ない感想を返された。僕はとても傷ついた。 そんな僕をほったらかして、夜月と迷路坂さんが会話を始める。 「この料理って、支配人さんが作ってるんでしたっけ?」 「はい、詩葉井が作っております。手前味噌ですが、彼女は都内の一流シェフにも劣らない腕前でして」 「野菜もすごく新鮮ですよね。このトマトとか」 「ああ、それは詩葉井の妹さんが送ってくださったものです。詩葉井には双子の妹がいて、山梨で農家をやっているんです」 二人の会話は弾んでいた。不思議だった。僕との会話はあんなに弾まなかったのに。 そこで僕はふと、前から気になっていることを訊ねてみた。 「迷路坂さんと詩葉井さんって、どういう関係なんですか?」 「どういう関係とは?」 「いや、このホテルを二人で切り盛りしているくらいだから、昔からの知り合いなのかなと思って」 辺鄙なところにあるホテルだし、迷路坂さんはこの館に住み込みで働いている。だから赤の他人ではなく、何かしらの繋がりがあるのではないかと思ったのだ。 そんな僕の勘は当たったようで、 「はい、確かに以前からの知り合いです」と迷路坂さんは言った。「詩葉井は私の高校時代の恩師なんです。卒業してからもちょくちょくと会っていたのですが、ある日彼女が学校を辞めてホテル経営を始めると聞いたので。何となく私も手伝うことになったんです。ちょうど、ニートだったので」 ニートだったのか、と僕は思う。 「それにしても凄いですよね」とニシンを食べながら夜月が言った。「詩葉井さん、まだ三十歳くらいでしょう? それなのにこんな大きな館を買うお金があるなんて」 そう感心していた夜月はふと、何かに気が付いたような顔をする。人差し指を立てて、おずおずと訊いた。 「もしかして、宝くじが当たったとか?」 「いえ、違います」と迷路坂さんは首を振った。「でも、それに近いものがあります」 「近いもの?」 「詩葉井は昔からかなりモテるんです。特に年上から」迷路坂さんはそう告げた後、少し声を潜めて言う。「私が高校を卒業したくらいのころに、詩葉井は四十ほど年の離れたお金持ちと結婚して、その一年後に彼と死別して数十億の遺産を手にしました。そのお金でこの館を買って、今は気ままにホテル経営をしているというわけです」 「なっ、なるほど」と夜月は言った。「詩葉井さんにそんな過去が」 「はい、詩葉井は魔性の女です」と迷路坂さんは言った。「教師時代も男子生徒と付き合ったりと、いろいろとやらかしております。でも不思議と、生徒に好かれるいい教師でした」 迷路坂さんは、最後にそうフォローして去っていった。フォローになったのかどうかは謎だったが。 * 夕食後に自室で風呂に入った後で、ロビーの自販機で何か飲み物を買おうと西棟の廊下を歩いていると、怪しげな人影を見かけた。朝ドラ女優の長谷見梨々亜だ。彼女はトランシーバーのような機器を手にして、真剣な表情でそのアンテナをいろんな方向に向けていた。 「あのぅ、何をやってるんですか?」 「ふにゃっ」 いきなり後ろから声を掛けられた梨々亜は、とてもびっくりしたようだった。深呼吸をしながら僕を見て、そして不思議そうな顔をする。 「誰ですか?」 「ただの宿泊客です」 「どうしてただの宿泊客ごときが、梨々亜に声を掛ける権利を持ってるの?」 なんか、凄いことを言われてしまった。そんな僕の表情を見て、梨々亜はさすがに反省したらしい。慌てて取り繕ったように言う。 「なーんてね、冗談よ。どんどん話しかけてきて。ほら、梨々亜、ファンサービスの塊だから。『長谷見・ファンサービス・梨々亜』に改名しようと思ってるくらいだから」 「はぁ」 「はぁ……、って。反応薄いなぁ。もしかして、緊張してる? わかるよ、梨々亜って国民的女優だもん。平均視聴率25パーセントの女だもん」 「はぁ」 「げしっ」 「ぐはっ」 何故だか思いっきり脛を蹴られてしまった。何なんだ、この女。週刊誌に訴えてやろうか? 謝る気などさらさらない梨々亜が、悶絶する僕を見下ろす。 「週刊誌にタレこんだら殺すから」 梨々亜はにこやかに笑って言った。……、何なの、この女。性格悪すぎだろ。 「……、それで」僕がようやく痛みから復帰すると、梨々亜は見下すように訊いてきた。「君、どうして梨々亜に話しかけてきたの? サインとか? それとも写真? 脛を蹴った口止め料の代わりに、そのくらいのお願いなら聞いてあげてもいいけど」 「違いますよ」と僕はふて腐れて言った。この女のサインとか、もう絶対にいらないし。「単に何をやってるのか気になっただけですよ。そんな変な機械を持って」 僕は彼女が手にしたトランシーバーのような機器を指差す。サイン目当てではないと知った梨々亜はちょっとだけムッとして、「なーんだ、そんなことか」と興味がなさそうな顔をする。 彼女はトランシーバーのような機器を翳して言った。 「これはね、盗聴器を発見する機械よ」 「盗聴器を発見する機械」 何故、そんなものを。 そんな僕の疑問が伝わったのか、梨々亜は深い溜息をつく。 「あのね、梨々亜は国民的女優なの」 「はぁ」 「また脛を蹴られたい?」 「蹴られたくないです」 「本当に? 本当は梨々亜に蹴られたくて、わざとそんな態度を取ってるんじゃないの?」 とんだ言いがかりだった。本当に──、とんだ言いがかりだった。 「まぁ、とにかく」と梨々亜は言う。「とにかくね、そんな国民的女優でデビュー曲が二億回再生の梨々亜は常にマスコミから狙われているの。ストーカーまがいのファンからもね。だから、常に警戒する必要がある。旅行や仕事でホテルに泊まる時には、いつも部屋に盗聴器や隠しカメラがないか、この機械を使って確認しているの」 彼女はトランシーバーのような機械を振った。 僕は「はぁ」と言いかけて、慌てて「なるほどっ!」と言い直した。できるだけテンション高くだ。「その機械で盗聴器や隠しカメラが発する電波を拾うってわけですねっ!」 「そうよ、わかってるじゃない下僕」 「……、下僕じゃないです」 「じゃあ、召使い? まぁ、とにかく、これさえあれば盗聴器やカメラを簡単に発見することができるってことよ。今日もがっつり調べたから──、三十分くらいかけて」 「なっ、なるほど」暇なやつだと思う。そんな時間があるなら、バラエティ番組のアンケートでも書いていればいいのに。 でも、そこでふと思う。 「そういう雑事だったら、マネージャーさんにやってもらえばいいのに。わざわざ梨々亜さんがやらなくても」 そう言うと、梨々亜は憐れな子を見るような目をした。僕は梨々亜に憐れまれていた。 彼女は溜息をつく。 「何言ってるの? 真似井さんにやらせるわけないじゃない」 ああ、なるほどと僕は思う。少し梨々亜を見直した。 「確かに真似井さんは忙しそうですもんね。梨々亜さんは、そんな真似井さんの負担を少しでも減らそうとしているんですね」 すると梨々亜はきょとんとした。そして呆れたように僕に言う。 「いや、単に真似井さんを部屋に入れるのが嫌なだけだから。だってあの人、重度のアイドルオタクなのよ? 今でも休みの日は握手会とかに行ってるし。気持ち悪いでしょ? そんな人間を自分の部屋に入れるなんてこと、梨々亜がするはずないじゃない。何されるかわかったもんじゃないし。むしろあの人が一番盗聴器仕掛けそうだし」 梨々亜の真似井に対する信頼度はゼロだった。僕は彼女を見直したことを後悔した。 梨々亜は僕との会話に飽きたようで、再びトランシーバーのような機器を片手に盗聴器を探し始めた。僕はそんな彼女に「じゃあ、また」と言った。無視されるかと思ったが、梨々亜は「おやすみ、下僕」と返してくれた。 * ロビーで自販機に硬貨を入れて、フルーツ牛乳を購入する。それを飲みながらロビーに置かれたテレビのチャンネルを回していると、この近くで大きなバス事故が起きたというニュースが流れていた。死者も二人出たらしい。その名前をアナウンサーが読み上げる。「亡くなられたのは、中西千鶴さん、黒山春樹さん──、」後ろから「えっ」という声がした。振り返ると、迷路坂さんだった。 迷路坂さんは、珍しく驚いているようだった。僕は眉をひそめて言う。 「もしかして、知り合いですか?」 「知り合いというか」彼女は少し口ごもる。そして困惑した声で言った。「二人とも、今夜ここに泊まりに来る予定だったお客様です。到着が遅いと思っていたら、まさかこんなことになっていたなんて」 その言葉に、僕は目を丸くする。宿泊する予定だった客が死んだ? 僕たちの会話を聞いて、ロビーにいた他の客たちも集まってきた。「本当ですか、それは」と探偵の探岡が言った。「信じられません」とイギリス人のフェンリル。「こんなこともあるんだね」とのんびりとした口調で誰かが言う。この人は──、確か医師の石川だったか。 「なになに、どうしたの?」そこに、今ロビーにやって来た夜月も加わった。事情を聞いた彼女は、やはり目を丸くする。 その時、玄関の方から、コツリと足音が聞こえた。 張り詰めた空気の中で、皆の視線がいっせいにそちらに向く。そして事故のニュースに戸惑っていた僕たちは、そこからさらに動揺した。唐突に現れたその男によって。 皆の視線の先──、 そこにいたのは三十歳くらいの男だった。玄関の方からやって来たところを見ると、おそらくこの館の宿泊客だろう。今夜この館に泊まる客は、全部で十二人のはずだ。既に館には九人いて、泊まる予定だった二人が事故で死んだ。となると、今現れたこの男は、十二人目の宿泊客ということになる。遅れてやって来た、最後の客。 問題なのはその出で立ちだ。 男はカトリックの司祭が着ていそうな宗教服を身に付けていた。真っ白な服で、その左胸の部分には十字架が描かれている。ただ、磔にされているのはキリストではなく、肉のない骸骨だった。 僕はその十字架のイラストを見たことがあった。ある教団のロゴマークだ。そっと、その教団の名前を呟く。 「『暁の塔』」 僕の言葉に、また皆の間に緊張が走った。「ねぇ、『暁の塔』って」と夜月が言った。「あの死体を崇めている──、」 正確にはその認識は間違っている。彼らが崇めているのは死体ではなく殺人現場だ。 『暁の塔』は最近信者を増やしている宗教団体で、でも新興宗教ではなくその歴史は意外に古い。十七世紀ごろにフランスで生まれ、嘘か本当かはわからないが、世界で十万人近い信徒がいるらしい。日本にも戦後まもなく伝わってはいるのだが、勢力を拡大し始めたのは三年前から──、日本で初めて密室殺人が起きたあの三年前からだ。 『暁の塔』は殺人現場を信仰の対象にする。その現場を写真に撮って、御神体の代わりにするのだ。殺人現場には被害者の負のエネルギーが充満する。それを信者たちの祈りによって浄化することにより、負を正へと反転させて幸福を得ようという教義だ。 そして彼らが崇める殺人現場のうち、最高峰とされるものが密室殺人現場だった。というよりも、三年前の密室殺人事件を切っ掛けに、そういう教義が付け加えられた。理由は閉ざされているからだそうだ。閉ざされ怨念が溜まりやすい分、浄化した際に得られる幸福エネルギーも大きくなる。 『暁の塔』は三年前からの密室ブームに乗って、国内での勢力を拡大させていった。その一方で悪い噂も絶えない。崇拝の対象となる密室殺人現場を増やすために、信者たちが自ら殺人を犯しているという話もあるほどだ。 僕たちは迷路坂さんと宗教服の男の世間話に耳を傾けていた。男は神崎という名前で、『暁の塔』の神父であるらしい。「神父の神崎か」と夜月が呟くのが聞こえた。 フロントでチェックインの手続きを進めながら、迷路坂さんが訊く。 「神崎様は今回はどのような目的で当ホテルに? やっぱり、あの密室現場ですか?雪城白夜が起こした『雪白館密室事件』の現場を見に?」 「いえ、違います」神崎は穏やかな口調で首を振る。「あそこでは人は亡くなられておりませんから。我々の信仰の対象にはならないんですよ」 「なるほど、ではどのような目的で?」 「タレこみがあったんです」 と神崎は言った。やはり、穏やかな声で。 「今夜この館で、密室殺人が起きると」
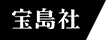

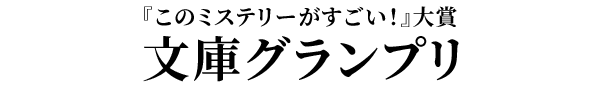
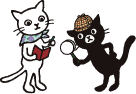 ◀ トップへ戻る
◀ トップへ戻る