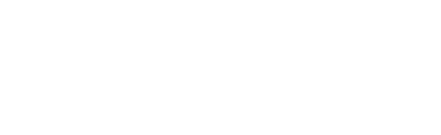試し読み
第一章
強奪する側から守る側に鞍替え
1
三重県多気町の経済は、《シャープ》の中小型液晶テレビ工場が牽引している。 《亀井製作所》─シャープに比べたら泡沫のような規模の電機メーカーだが─も、多気町に液晶テレビの工場と倉庫を構えている。 大鳳未来は、カーシェアサービスで調達した軽自動車を飛ばしていた。目的地は亀井製作所の倉庫だった。 国道四二号線を走りながら、未来はバックミラーを、ちらっと眺めた。 ゆるく波打つ、肩に掛かる髪。ホテルを急いで飛び出したせいで、ぶわっと広がっている。前髪の下では、双眸が怒りで血走っている。頬は紅潮している。 おまけに、特許公報と審査経過、あとネットの諸々の情報を徹夜で読み込んでいたせいで、肌は荒れていた。 ナビが亀井製作所・多気町工場の外観をディスプレイに表示した。未来はハンドルを切った。 「警告書を送った次の日に相手に殴り込む特許権者なんて初めて聞いた。普通の特許紛争はもっと何か月もかけてゆっくり進むもんよ。相手はよほど切羽詰まっているのね」 ぎゃぎゃぎゃ、とタイヤが悲鳴を上げた。 倉庫の近く、適当な敷地内に未来は自動車を駐めた。 道路沿いに先客の車が三台、駐まっている。一台はバックシートが作業道具で埋まった白いバン。一台は荷台の側面が大きく凹んだ軽トラック。最後に、ぴかぴかの黒塗りのベンツ。 未来はベンツを睨みつつ自動車から降りた。倉庫に向き直り、今度は自分の足で全速力で走る。 倉庫の広さはおよそ三百坪。スライド式の錆付いた搬入扉が半開きになっている。 中から怒号が聞こえた。 扉を両手で思いっきり開け放つと、薄暗かった倉庫の内部に光が差し込んだ。 平べったい段ボールの箱が天井まで積み上がっている。液晶テレビの在庫だろう。 中央には、白いスーツに赤いシャツを着た、長身で白髪の男性がいた。 未来はすぐに、男が《皆川電工》の社長、皆川竜二郎だと気づいた。 皆川の腕が、小太りの男の首を絞め上げている。亀井製作所の社長でありクライアントの亀井道弘だ。 亀井は、皆川の手下たちに囲まれていた。ざっと数えて十人。皆、目つきは悪いが服装は水色の作業着姿だった。皆川電工の従業員だ。 皆川が、わざわざ強面の従業員を選んで連れて来た可能性が高い。 一方で亀井の背後には亀井製作所の従業員が三人いる。皆、恐怖に顔を戦慄かせていた。 未来は即座に叫んだ。 「亀井さん、無事ですか。死ぬなら代理人手数料を支払ってからにして下さい!」 皆川サイドも、亀井サイドも全員が振り向いた。 亀井が半ベソで叫び返した。 「大鳳先生、助けてください。皆川さんが乗り込んで来たんです。姚愁林先生にも電話とか連絡を取ろうとしたんですが、繋がらなくって」 どさっと、音がした。亀井が地面に崩れ落ちた。 皆川は、亀井の首を掴んでいた右手をゆっくりと下げた。 こちらを睨みながら、皆川はじわり、じわりと未来に近付く。 「生意気にも、亀井が代理人を雇った話は聞いている。特許侵害が専門の特許事務所なんだってな。おい、亀井! 俺らの技術を土足で踏みつけるような真似をしておいて、人を雇って言い訳をさせるとは大したもんだ」 眼光を飛ばした気なのか知らないが、未来は、しれっと挨拶をした。 「亀井製作所側の代理人を務めます《ミスルトウ特許法律事務所》の弁理士、大鳳未来です。特許侵害を警告した、皆川社長で間違いありませんか」 未来は、ハンドバッグから名刺入れを取り出した。 名刺を、ぴらっと差し出す。名刺を一瞥した皆川は、ゆっくりと視線を未来の顔に上げた。 「弁理士? 弁護士じゃねえのか」 「弁護士は、争い事ならなんでも担当できます。スペシャリスト、というよりゼネラリストですね。でも特許権に関する話なら弁理士がスペシャリストです。話し相手として不満ですか」 皆川は、顔に「いずれにせよ不満」とマジックペンで大書きしたような表情で答えた。 「亀井んとこのメタボ社長はな、こっちが特許侵害だってわざわざ教えてやったってのに無視しやがんだ。だから仕方なく俺が出向いてだ、わからせてやろうと思ったんだよ」 未来は「ふっ」と、鼻で笑った。 「亀井さんは昨日の夕方、我々に電話で相談されました。三重県には、まともに対応できる特許事務所も法律事務所もなかった。だから、わざわざ東京の我々に連絡したんでしょう。我々も夜中に急いでセントレア空港に到着しました」 ごほごほ、と咳込みながら亀井が床から上体を起こす。 「嫌な予感がしたんです。でも、特許侵害で即日対応なんて法律事務所は大鳳先生の所以外になくって。あと、全国どこでも飛んで行くって─」 皆川の怒号が響いた。 「亀井、てめえは黙ってろ! 俺はこの嬢ちゃんと話してんだ」 亀井製作所の従業員は皆、声も出せないくらい顔面蒼白になっている。 未来は腕を組み、皆川の長身を下から見上げた。 「聞けば、警告書の回答期限は三日後だとか。普通は二週間から一か月です。三日なんて短すぎます。おまけに警告した次の日に特許権者が自ら殴り込み? 前代未聞です」 皆川は、のっぺりとした笑みを浮かべた。 「亀井にはな、再三、口頭で警告をしていたんだ。おい、やれ」 皆川が合図をすると、皆川電工の手下たちが一斉に動いた。 手下たちは積みあがった段ボールの一つを、乱暴に引っ張り出した。 亀井が目を見開き、口を大きく開けた。 「やめてくれ! 昨晩、ラインから上がったばかりの三十二型だ!」 亀井の叫びは無視された。皆川の手下たちは、鶏を絞めるような表情で段ボールを開いていく。 黒く輝く、三十二インチの薄型テレビが姿を現した。 かっと、未来の頭に血液が流れ込んだ。 「特許権者であっても勝手に触ることは許されません」 皆川は、未来の目の前に堂々と立ちはだかった。 「心配するな。ぶっ壊そうなんて思っちゃいねえ。昨日の夜中の到着じゃ、まだ侵害品もきちんと確認できていないよな。俺は優しいんだ。今、侵害の証拠を見せてやろうってんだ」 未来は、断固として怒鳴った。 「侵害品と呼ばないでください。訴訟で判決が確定するまで、誰も侵害品とは呼べません。まだ警告段階でしょう」 手下たちは、テレビをスタンドに設置した。手下の一人が、どこからか延長ケーブルと青色のインターネットケーブルを手に戻って来る。 殺風景な倉庫の中央に、亀井製作所製、三十二インチの薄型テレビが一台、鎮座する。 皆川は鷹揚に振り向くと、顎をしゃくった。 テレビに電源が入り、漆黒のディスプレイに亀井製作所のロゴが表示された。 皆川が吐き捨てた。 「ロゴなんかどうでもいい。問題は、すぐ後だ」 亀井製作所のロゴが消えるとすぐ、赤、黄、緑、青色で構成された円のマークが浮かび上がった。インターネットブラウザ、グーグルクロームだ。 皆川が、罠に掛かった鳥を見るような表情で答える。 「見たよな。テレビの電源を入れた直後に、インターネットブラウザが起動した」 部下の一人が、皆川にリモコンを渡した。 皆川は、リモコンを操作しながら、続けた。 「何が問題なのか、わかるか? テレビ番組よりも先に、ブラウザが出るところだ。もちろん、続けてネットサーフィンだってできる。見ろ」 皆川は、リモコンでクロームを器用に操作して、画面にニュースサイトを表示させた。適当なリンク先を適当に飛ぶ。一度も、テレビ番組は表示されない。 ニュースサイトの『芸能・スポーツ』欄から、皆川は動画のリンクをクリックした。 《YouTube》のリンクが起動した。 赤い、角丸の四角に白い三角形のマークのロゴが、クロームの左上に見える。 ぱっと画面から眩い光が溢れた。 テレビのスピーカーから、最近テレビで引っ切りなく流れる曲のイントロが零れた。テレビ嫌いの未来でも知っている曲だ。世間一般、いやアジア・パシフィックで広く知られている。 画面には、渋谷のセルリアン・タワーの屋上からの夜景が映っていた。夜空には月だけで、雲は一つもなかった。 イントロのギアが一段階上がったところで、カメラが夜空から屋上に下りる。 画面が一瞬だけブレた直後、誰もいなかった屋上のステージに、金髪を二つに纏めた女性が立っていた。 コンピュータグラフィックスだった。名前は、天ノ川トリィ、だったか。《VTuber》と呼ばれていた気がする。 以前に何かの本で読んだ覚えがある。コンピュータグラフィックスで人を描く場合、方向性は二極化する。限りなく人間に寄せるか、限りなくアニメ的なキャラクタ感を追求するか。 天ノ川トリィの造形は、人間に限りなく寄せられている。 真紅のドレスにヘッドセットを装着した天ノ川トリィは、目を瞑ったまま足でリズムを取っていた。やがて全身でリズムを取り始めた。髪が風になびいている。 作り立ての液晶だけあって亀井製作所の薄型テレビは、夜景もコンピュータグラフィックスも、4Kで微細に映しだした。 亀井も亀井の従業員も皆川の手下も、現実を忘れて画面に没頭していた。 イントロが最高潮に達したところで、天ノ川トリィが目を見開いた。 画面が、ぶつっと暗転した。 仏頂面の皆川は、手下たちを怒鳴り付けた。 「馬鹿野郎が。呑気にYouTubeを見に来たわけじゃねえんだ!」 皆川は、黒ずんだ手でリモコンを弄びながら未来に主張した。 「亀井の奴は、俺たちの特許技術をまんまパクったテレビを製造してやがる。間違いなく特許侵害だ」 未来は皆川電工の特許を確認する。 「電源を投入したら、テレビ番組より先にインターネット接続用の画面、つまりブラウザを表示するテレビ。合っていますか」 皆川が口笛を吹いた。 「さすがは先生だ。きちんと我が社の特許を把握されていらっしゃる」 未来は小さく舌打ちをした。今回問題となった皆川電工の特許権は、筋が良すぎる。完全にこちらの分が悪い。 縋る目をする亀井に対し、未来は淡々と説明した。 「テレビなのに最初にインターネットを表示する。アイディアとしては昔からあったと聞きますが、大手電機メーカーから販売された例は、ほぼありません。一説によると、テレビ各局より相当な圧力があったとか」 皆川は、リモコンを手の上でくるくると回した。 「俺たち皆川電工はな、圧力なんて気にしねえんだ。そもそも、技術は多数決で決まる代物じゃねえ。現に時代を先取りして、十年前に特許も取っていた」 皆川がテレビ局から苦情を受けるわけはない、と未来は確信している。皆川電工も亀井製作所も、テレビ製造業者としての規模は極めて小さく、テレビ局が気にする規模ではない。 亀井が、すかさず反論する。 「ブラウザを表示するだけのテレビが、特許になるんですか!」 未来は淡々と答えた。 「新しければ特許されます。ただし、世間一般の基準での『新しさ』と、特許庁の審査官にとっての『新しさ』は、異次元レベルで異なります。新規性といいます。世の中の特許発明は、青色発光ダイオードの作り方のような大発明ばかりではありません」 皆川は、亀井の三倍は大きな声で反論した。 「新しいに決まってんだろ。文句があるなら、電源を点けたら真っ先にブラウザを立ち上げるテレビが、十年前に出ていたって証明してみろ」 亀井は呆然とし、口を半開きにしたまま硬直した。 亀井の心中は察しがつく。皆川電工は事実として特許権を取得している。 未来は、ハンドバッグからタブレットを取り出した。 「特許庁のデータベースで確認しました。特許庁の審査官は、皆川社長と同じ意見です」 亀井が泣きそうな表情で未来を問い詰めた。 「大鳳先生も、うちの製品が特許侵害だって仰るんですか」 未来はタブレットの上辺を確認した。現在、時刻は朝の十時半を回ったところだ。 「反論材料は探しました。例えば、十年前にそんなテレビが世の中に知られていたとしたら、特許は無効です。短時間ですが調査しました。しかし、証拠は見つかりませんでした」 亀井も必死になって反論する。 「たった一晩で、きちんと調べられるわけはありませんよね。無理に決まっています。きちんと時間をかければ、きっと見つかりますよね」 未来は正直に自分の印象を伝えた。 「十年前の特許出願です。当時の技術レベルを考えると、あと一か月調査を続けても無効の証拠は見つからないでしょう」 皆川が、わざとらしく手を叩きながら答えた。 「大した専門家だ! 素晴らしい先生を雇ったな、亀井。年貢の納め時だ。侵害品は全品処分しろ。なんなら武士の情けで廃棄処分代くらい持ってやってもいい」 未来は、皆川の手下たちの表情を見やった。皆川が歓喜している背後で、ふと皆、気の抜けた表情を見せている。 確信した。予想通り、皆川電工の従業員は全員、決死の覚悟で強面を演じている。 未来は、ジャケットの胸のポケットからスマホを取り出した。着信の履歴はない。 パートナー、姚愁林を信じて時間を稼ごう。未来は皆川を問い質した。 「皆川社長、たとえ侵害でも、あなたに認められる権利はテレビの廃棄と工場設備の取り除きまで。度を越えた行為は許されません」 煩わしい、と顔に書いてあるような表情で、皆川が答える。 「だから処分してやるっつってんだろ。どこが度を越えているってんだ」 未来は、皺とくすみの目立つ皆川の顔に、自分の顔を近づけた。 「着服は、廃棄とは全く異なるとご存じですか」 視界の隅で、皆川の手下の一人が、びくっと体を震わせた。 皆川は動じなかった。しかし皆川の澱んだ目の底に見えた、覚悟の片鱗を、未来は見逃さなかった。 皆川は静かに訊ねた。 「何の話だ、嬢ちゃん」 未来は、頭に叩き込んだばかりの情報を吐き出した。 「昨晩から朝まで、実は別の調べものをしていました。皆川さんは工場で大規模なリストラをしていますよね」 皆川がリモコンを床に叩きつけ、がちゃん、とプラスチックの割れる音が響いた。コンクリートの床に黒いプラスチックの破片と電池が散乱した。 皆川は静かに答えた。 「だからなんだ。今がどんな時代か知らねぇわけじゃねえよな」 未来は証拠のニュースサイトの記事を見せようとして、やめた。釈迦に説法だ。本人たちが一番よく知っている情報だ。 未来は概要を一息に説明した。 「リストラ直後、あなたが下請けをしている《紫禁電氣》より、大規模な製品製造発注がありましたね。あなたの工場の生産力を計算しましたが、とても間に合う数じゃない。おまけにリストラ直後で人も足りない。しかしあなたは受注した。引き受けなければ次の仕事はないからです。違いますか」 皆川は澱んだ目のまま、少しだけ、早口で答えた。 「うちの台所事情に首を突っ込まれる筋合いはねえ」 未来は、皆川を問い質した。 「亀井製作所のテレビも、皆川電工のテレビも、同じ三十二型。液晶も同じ液晶パネル製造会社から購入している。制御基板も、ほぼ同じ。違うところは、ガワと電源投入時のロゴだけ。あなたは考えた。亀井製作所の三十二型テレビを納品すればいい。皆川電工には特許権がある。だったら、亀井製作所のテレビを丸ごとブン獲って、ガワとソフトだけ入れ替えてしまえ」 皆川の手下たちが、顔を見合わせた。 皆川自身の額に脂汗が浮かんだ。 亀井が悲鳴に近い声を上げた。 「嘘だろ、酷過ぎる。認められるわけがない」 未来も即座に答えた。 「当たり前です。侵害品を没収して横流しするなんて、特許で認められる救済の範囲を超えています」 皆川の手下の一人が、力なく呼びかけた。 「社長やっぱり、いくらなんでも─」 皆川は手下を遮って怒鳴った。 「こっちはな、生きるか死ぬかを懸けてんだ! 嬢ちゃんも客商売なら分かるよな。発注ってのは絶対だ。納品できなきゃ首を吊るしか途はねえんだよ」 未来は冷徹に反駁した。 「生きるか死ぬかを懸けずに作る製品なんて、ありません。亀井製作所も同じです」 皆川は、形相を激しく変えた。 「こっちは特許があるんだ。ここにあるテレビは全部俺のもんだ。亀井、触るんじゃねえぞ。もし触ったらここの在庫、全部ぶっ壊して倉庫にガソリン撒いて火を点けてやる。ついでにてめえも地獄に道連れだ」 皆川が亀井に飛びかかろうとした瞬間、搬入口の扉が物凄い音を立てて動いた。 錆のせいで、ほとんど動かなかったスライド式の搬入口が完全に開け放たれている。 かつかつ、と音を立てて向かってくる、ほっそりとしたシルエットに、未来は覚えがあった。 とりあえず、文句を付けた。 「遅いわ、姚。ずいぶん時間がかかったわね。危うくクライアントが殴られるところだったわよ」 倉庫の中央に近づくにつれ、逆光で見えなかった顔が視認できた。 年齢は未来の一つ上、二十九歳。身長は百七十センチと、未来より十センチは高い。ヒールまで履くので見た目はさらに高くなる。真っ黒な髪をポニーテールで一纏めにし、均整の取れた顔立ちが際立つ。フレームのない眼鏡のせいで、より知的に見える。 未来を含めて二人のみの、ミスルトウ特許法律事務所のもう一人のメンバー、パートナー弁護士で所長の姚愁林だ。 姚はハスキーな声で、はっきりと断じた。 「皆川電工の弁護士の居場所がわかった。深圳だ。連絡も取れた。皆川社長は面倒な弁護士がいない間に、亀井製作所からテレビをぶん盗る気でいたんだ」 未来は、姚を睨みつけた。 「調査ありがとう。でも先に連絡をしなさい」 「連絡をしたって、殴り合いになっていたら無駄だ。未来の身を案じて駆け着けたんだ」 「殴り合いを前提にしないで」 「否認は無理だろう。あれは百パーセント、侵害だ」 「弁護士は何があっても負けを認めない、ってあんたのセリフだけど」 「無理なもんは無理だ。だから、私がわざわざ弁護士の伝手を辿って、皆川電工の顧問弁護士と直接、話をする必要があった。違うか」 ともかく、裏付けは取れた。突如始まった茶番を打ち切り、未来は皆川と亀井に向かって声を張り上げた。 「ミスルトウの正式見解をお伝えします。残念ながら、侵害です」 亀井の顔から生気が抜けていく。亀井は床に座り込んだ。 「そんな。破産です。どうすれば」 未来は、姚に目配せをした。姚は「予定通りで」と、小さく答えた。 未来は亀井に近づき、しゃがんだ。 「ここからは提案です。亀井社長、本件製品の在庫、皆川電工に全品販売できますか」 亀井は一瞬だけフリーズした後、はっと未来に振り向いた。 姚が背後からフォローする。 「特許権者の指示で生産したのなら、何の問題もない。実際、皆川電工は喉から手が出るほどテレビを欲しがっている。亀井製作所が生産力を肩代わりしたとするなら、在庫は無駄にならない。皆川社長も亀井社長も、地獄に行かずに済む。ウィン・ウィンだ」 未来は、姚をぎっと睨み付けた。 「ウィン・ウィンなんて、下品な言葉は使わないで」 「いい言葉だと思うが」 「言う側の話でしょう。姚、あなた誰かに『これでウィン・ウィンですね』って言われたらどんな気分になる?」 姚は一瞬だけ視線を横に逸らした。 「ほざいた奴を殴りたくなるな」 「だったら二度と、当事者の前で使わないで」 未来の呼びかけを無視し、姚は皆川にしれっと訊ねた。 「皆川社長、おたくの弁護士は我々の提案に頷かなかった。しかし、文句があるとも答えなかった。つまり本提案については、社長の一存で決まります。納入価格は、今からお互いの代表者同士で交渉して決めればいいでしょう」 未来も、亀井に確認する。 「亀井社長、いかがですか。特許法上の解決策は、ほぼ尽きています。しかし、特許法以外なら、解決策はあります。いかがでしょうか」 亀井は、しばらく目を泳がせた。亀井の視線が、山積みの在庫に向いた。 「問題はありません」 姚が皆川に訊ねる。 「皆川社長は?」 皆川は考え込んだ。 しかし、すぐに首を横に振った。 「今から契約をしたって、過去の侵害は侵害だ。だいたい発注主にどう説明するってんだ。孫請け自体は問題ない。問題は事前報告義務だ。発注主の奴らは、縦の繋がりには煩いんだ」 姚は一呼吸した後、淡々と説明した。 「弁護士に、紫禁電氣からの下請け契約を詳細に確認して貰った。受注前から孫請け契約をしている相手なら、例外的に報告義務はない」 社長だけあって、亀井と皆川は、姚の台詞の意味を即座に理解した様子で、はっと顔を見合わせた。 皆川が、喉の奥から絞り出したような声で訊ねる。 「あんた、まさか」 未来の目から見た姚は、まるで魂の取り扱いについて巧妙に隠しながら人間と契約をする悪魔だった。自分も同類かもしれないが。 姚は皆川に強く問いかけた。 「よく思い出してください。実は亀井製作所と皆川電工は、下請けの契約を結んでいたんじゃありませんか。御社の戸棚を探したら、契約書が見つかると思いますよ」 皆川の目が怪しく輝いた。 「今から、過去の日付の業務委託契約書を捏造しろってのか」 姚は、理解できないといわんばかりの表情で、首を傾げた。 「捏造ではありません。契約を思い出して、あるはずの契約書を探すだけです」 「いくらで売るってんだ。こっちは下請けだ。紫禁電氣の発注額の中で製品を作って納品すんだ。奴らは、ほとんど原価と同額で発注してんだ」 「だとしても、タダでぶん盗るとは強欲に過ぎます。安くはないでしょうね。しかし高くもないでしょう。双方ともに同じくらいの妥協をして着地、でしょうか」 「こっちは特許があんだぞ」 「相手が売らないんだったら、意味はありませんよ。今すぐ必要なんでしょう。紫禁電氣への納品期限は?」 「一週間後だ」 「今から、ほかの侵害者を探しますか」 逡巡する皆川の姿を見て、皆川の手下たちが騒めいた。 「マジかよ」「めちゃくちゃだろ」「いやでも、社長の考えだってそもそもめちゃくちゃだし」「社長以上にめちゃくちゃだろ」 全員、皆川の手下の表情から、皆川電工の単なる従業員の表情になっていた。 皆川は、振り向きもせずにその場で怒鳴りつけた。 「何をぺちゃくちゃくっちゃべってやがる! おいてめえら、今から帰って、契約書、探すぞ」 皆川電工の従業員全員が驚いて固まった。 姚が微笑みながら未来を見た。 皆川電工の従業員の一人が、困惑した表情で訊ねる。 「社長、いくらなんでも、ですよ。もしバレたら、紫禁電氣どころか下請法とかいろいろ─」 皆川は断じた。 「探すったら探すんだよ。死ぬ気でな。ああ、死ぬ気でだ」 姚が颯爽と皆川の前に進み出た。 「私もお手伝いしましょう。弁護士でも、探し物の手伝いくらいはします。契約書の清書とかも」 皆川は、しばらく逡巡した。やがて、微笑みながら訊ねた。 「いい度胸してやがるな、嬢ちゃんら。姚さんだったか、特にあんただ。度胸がある。中国人か。中国の商取引事情には詳しいか? 亀井のとこに置いとくにはもったいねえ。うちに来ないか。今の弁護士は、《弁護士ドットコム》で雇った奴でな。専属じゃねえんだ」 姚は背筋を伸ばして、堂々と答えた。 「アフターサービスが必要な中途半端な仕事はしません。ですので、ミスルトウは顧問契約をしません。あと今回の提案の概要は、大鳳が作りました」 亀井が、一際高い驚きの声を上げた。 「姚先生じゃなくって、大鳳先生が契約書の捏ぞ─」 未来は、亀井の首根っこを絞めた。 「声が大きいですわ。皆が生き残れるんなら問題ないでしょ」 姚は何の気兼ねもなく続けた。 「私は、いつも未来の違法な作戦に従って動いているだけだ。全ての責任は、弁理士、大鳳未来にある」 未来の手に、若干の力が入った。 「私に全部、責任を擦り付けないで。クリエイティブな発想と表現しなさい」 ふと、手元を見た。亀井が泡を吹いている。未来はぱっと手を離した。 どさっと顔を真っ青に─しかし、何かほっとしたような表情で─亀井が床に崩れ落ちた。 立ったり倒れたりと忙しいクライアントだ。 亀井を介抱していると、皆川電工の従業員がベンツを倉庫に寄せた。 皆川たちは先に皆川電工に戻り、亀井が目覚め次第、姚が亀井を連れて皆川電工に向かう手筈になった。 ベンツに向かおうとした皆川が、ふと立ち止まった。 皆川は、まるで世間話でも始めるかのように訊ねた。 「事務所の名前、なんでミスルトウなんだ」 「呼びにくかったですか」 「社名にミスなんて入れたら縁起が悪いだろう。俺なら付けねえ」 なるほどと思いながら、未来は答えた。 「ミスルトウとはヤドリギの英語名です。北欧ではトロール除けのお守りの意味があります」 皆川は、納得した表情で訊ねた。 「パテント(特許)トロールか」 未来は頷いた。 「姚が思いついた、つまらないシャレです」 皆川は笑った。 「元パテント・トロールの嬢ちゃんらが付けるなら面白い」 未来は驚いた。 「どこで知りましたか」 「嬢ちゃんが来る少し前に、亀井が教えてくれた。パテント・トロールって、自分では事業をする気のない製品の特許を取得し、特許侵害だと他の企業にぶつけて金をせびる組織だよな。聞いたことがある。アメリカで日本のゲーム機を訴えたやつだ」 皆川が示唆した事件に、未来はすぐ見当がついた。 「コイル事件。一九九〇年代に米国のコイル氏という個人発明家がゲームとは直接関係のない特許を『ゲーム機の基本的な特許』と主張し、《任天堂》や《セガ》を訴えた事例です。日本企業は米国での特許紛争に慣れていませんでしたから、そこにつけ込んでの攻撃でしょう」 皆川は笑った。 「俺たちより性質が悪い」 未来は呆れて答えた。 「警告した相手に直接殴り込んだことはありませんよ。きっとコイル氏もないでしょう」 「パテント・トロールって、いくらぐらい稼げるんだ?」 未来は、しれっと答えた。 「とあるメーカーのスマートフォンに、セキュリティに関する特許を一件ぶつけたことがありました。半年で百億円を稼ぎました」 皆川は、口を開けて驚いた。 「まさか嬢ちゃんが一人でやったのか」 「一人でした。当時の仕事先では、スマホのセキュリティが理解できる人間は、私だけだったので」 皆川は顔に皺を寄せて、微笑んだ。 「パテント・トロールのエースだったわけか。今度、特許でうちにまずい問題が起きたら頼むとしよう。姚さん、俺たちは出発するが、うちの事業所の場所はわかるか」 姚は皆川に頷いた。 「少ししたら自分の車で伺います」 「頼んだ」 皆川は、ベンツに乗り込んだ。 時間にして三十分程度の水際交渉だったが、未来は、一日中マラソンをしていたような疲労感を覚えた。 亀井が寝息を立て始めた。無理もない。警告書が届く状況なんて、滅多にない。心身ともに疲労が溜まったのだろう。 亀井製作所の従業員と亀井の家族に連れられて、亀井は事務所の中に運び込まれた。 無人になった倉庫の中で、未来は大きく伸びをした。 「先々週は兵庫、先週は石川、今週は三重。全て工場内で、コピー機なりドライヤーなり、在庫の山を前にしての交渉だったわね」 姚も、首筋を掻きながら頷いた。 「電化製品だけじゃない。化学薬品も扱った。先月は台湾の新竹で、フォトレジスタの露光時間をずっと確認した」 未来は、安全光の赤い光と、酢酸の匂いを思い返した。 「しばらく、ドレッシングの香りも嫌だった。にしても、あんたとミスルトウを設立してから一年が経つけど、まともに休めた日がない。どうしてかしら。姚が仕事を選ばず、何でも引き受けるからよ」 姚は、夕暮れでも眺めるような表情で、倉庫の天井を見上げた。 「ミスルトウを設立する際、非公開の事務所指針を四番まで決めたよな。指針その一、クライアントは選ばない。文句はなしだ。防戦に休みなんてない」 未来も姚も、理解している。警告書は、ある日突然届くものだ。届いたら、ずっと緊張が続く。 姚は続けた。 「ところで以前から提案している、うちの事務所のサイトに『我々は元パテント・トロールです』と大きく書いておくかどうかについてだが」 未来は即断した。 「いらないわよ。『私たちは、元・特許ヤクザです。だからヤクザのやり口がわかります』なんて、おおっぴらに宣伝しろっての?」 「物は言いようだ。腕利きのハッカーがセキュリティ企業を立ち上げたようなものだ。クライアントの立場から考えれば、私たちの経歴は心強い」 「絶対に嫌。そもそも、広告に力を入れる必要はありません。私たちの事務所の噂は、業界ではとっくに広まっているみたいだし」 姚が、噴き出した。 「事務所じゃなくて未来の噂だな。『特許やぶり』の大鳳未来─」 話の途中で姚のスマホが鳴った。姚が電話を受けると同時に、事務所から亀井製作所の従業員が現れた。 「姚先生、大鳳先生。社長が目を覚ましました」 未来は驚き、答えた。 「もう大丈夫なのですか。まだ少しは寝ていてもいいのですが」 「早く皆川電工と話をつけたいみたいです。本人はやる気ですよ」 しばらく従業員と話していると、姚が電話を終えた。 姚はスマホを弄りながら、まるで他人事のように話しだした。 「次の仕事の依頼だ。受けておいた」 未来は、腕組みをして姚の前に立ちはだかった。 「秒で受けないで。ていうか、もう在庫の山を見ながら交渉をしたくない。ソフトウェアの仕事を受けなさい。クラウド関係とか」 姚は完全無視の表情でスマホの画面をタップした。 「次は東京だ。一か月ぶりに帰れる。私は契約書の偽造の最中に、皆川社長が亀井社長とセカンドラウンドを始めないように監視するので行けない。代わりに、先に東京に戻って話を訊きに行ってくれ。相手は直接の面談をご所望だ」 未来は露骨に嫌な顔をしてやった。 「偽造ってはっきり答えるな。にしても今から? 明日でいいわよね」 姚は首を傾げた。 「先方には、今日中に話を訊くと伝えてある。飛行機だと夜の便になる。陸路なら『快速みえ』と新幹線を乗り継げば、夕方には先方のオフィスに着ける。急げ」 文句が喉まで出かかったところで、未来のスマホが震えた。メールの着信だ。 見ると、姚からのメールだった。先程のクライアントからの依頼に関する資料が、圧縮ファイルの形で添付されていた。スマホでは開けないサイズだった。タブレットか、ホテルに置いてきたパソコンで開く必要がある。 姚が断じた。 「指針その二。クライアントからの要望は、依頼も含め十二時間以内にアクションする。指針その三。ミスルトウは、クライアントも相手方もなるべく円満に解決できる術を探す」 未来は額を押さえた。作ったよ。ええ。作ったよ。 テレビを下請け品に仕立て上げた理由も、指針その三に基づく提案だ。 未来は顔を上げた。吹けば飛ぶような超小規模特許法律事務所でも、仕事がある。喜ばしい話ではある。 未来は姚に、嫌味で微笑みかけた。 「ここのところ依頼がひっきりなし。次のクライアント様は誰かしら」 姚は、倉庫にぽつんと残された薄型テレビの背面を触って電源を入れた。 すぐにYouTubeの画面が表示された。 姚は、画面を指で差した。 「次のクライアントだ。《エーテル・ライブ・プロダクション》。VTuber事務所だ。警告書が届いたので、対処して欲しい、との連絡だ」 未来は首を傾げた。 「何が侵害だって話なの」 「この子だとさ」 姚が指差した画面を未来は凝視した。 皆川が電源を切った後も、動画はずっと裏で繰り返し再生されていた様子だった。 ディスプレイの中ではただ一人、天ノ川トリィが、渋谷の夜景をバックに歌い、踊り狂っていた。
2
確かに、ソフトウェアの仕事がしたいと言ったが。 東海道・山陽新幹線『のぞみ』の中で、未来は姚から送付された資料一式を読み込んだ。 エーテル・ライブ・プロダクションは、五年前に設立されたバーチャル・ライバー─YouTube上での活動が主のため、VTuberの呼び名が一般的だが─の事務所だ。 もともとは別の名前で、ITサービス全般を手広く取り扱っていた会社だった。VTuber事務所の事業は、数あるサービスの中の一つだった。 しかし昨今の爆発的なVTuber人気により、売り上げのほとんどをVTuber事業が占めるようになった。 経営者側は、社名をエーテル・ライブに変更。事業内容も、VTuber事業に集中させた。 VTuber事務所として、エーテル・ライブは日本一の規模を誇る。国内外を合わせて、所属VTuberは六十七名。YouTubeと、中国の《Bilibili》まであわせると、チャンネル登録者数累計は二千万人を超える。 経営状況が、全く理解ができなかった。 VTuber事業って、どうやって売上を上げるのか。どこから金が入って来るのか。広告事業か。広告だったらVTuber事業なんて書かずに広告事業って書いて欲しい。 考えれば考えるほど、違和感の原因は、一つの疑問に集約される。 VTuberとは何か。 YouTuberならわかる。ペプシコーラの風呂に入ったり、渋谷駅のハチ公前交差点のど真ん中で、青信号の間に踊ったりする職業の人だ。 未来は、添付資料の中身を何度も確認した。 エーテル・ライブの企業情報がほとんどだ。VTuberについての説明資料はない。 ついでにだが、警告書の内容に関する資料もない。 情報漏洩でもしたら大変なので、警告書の中身や警告の対象となった製品についての情報をメールで送るわけがない。しかし「VTuberが警告を受けた」だけでは情報として少なすぎる。勝手ではあるが、もう少し事前情報が欲しかった。 VTuberについて、未来もネットで調べた。しかしきちんとした説明は見つからなかった。もしかしたら、VTuberに定義なんてないのかもしれない。 スマホを閉じた。依頼人に直接訊ねたほうが早い。 姚の提案通り、快速みえと新幹線を乗り継ぎ、東急東横線武蔵小杉駅に着いたのは、午後五時を回ったところだった。 武蔵小杉駅から徒歩十五分の場所に、エーテル・ライブの事務所兼スタジオがある。 初夏の空は、まだ夕暮れと呼べるほどに赤味がかっていない。 立ち並ぶタワーマンションを眺めながら、未来はスマホで地図を確認しながら歩いた。 手荷物は、パソコンの入ったショルダーバッグのみ。着替えの詰まった小型トランクを自宅に宅配便で送って正解だった。引き摺って歩くには面倒臭い。 未来は歩きながら毒づいた。 「姚の奴、絶対に仕事の依頼をわんこそばか何かと勘違いしている。日本文化を間違って理解している」 早めに帰宅するサラリーマンのお父さんがたを速足で追い抜き、未来はエーテル・ライブの事務所に急いだ。 目的の事務所は超高層タワーマンションの下層部、オフィスフロアに居を構えていた。そこは二階から四階までオフィスフロアになっている。案内板を読むと、エーテル・ライブは、四階の全フロアを借り切っていた。 一階のショッピングフロアの喧騒を抜け、オフィスフロアに入った。 二階、三階は、疎らに人がいた。エスカレーターで四階に入った途端、一切の物音が聞こえなくなった。 「関係者以外立ち入り禁止」と書かれた札が貼ってあるだけで、受付もインターフォンも、なかった。 未来は気にせず扉の奥に進んだ。 VTuberの撮影スタジオがあるためか、防音が行き届いている。ひょっとしたら廊下の壁のすぐ裏で、演者たちが生放送の収録をしている可能性だってある。 奥に進みながら、未来は呟いた。 「最近は新しくオフィスを構える会社は、オフィス内の一室をYouTube撮影用のスタジオとして使う、って聞いたけど。エーテル・ライブは全室スタジオなのか」 廊下を曲がると扉が立ち並ぶ通路に出た。依然として、しんと静まり返っている。通路の壁には扉が並んでいる。天井には五メートル間隔で監視カメラが設置されている。扉の奥に何があるかは不明だ。 無意識のうちに、未来は廊下の壁を拳で小突いた。 「何も聴こえないし、何も見えない。稼働している会社には見えない。実は単なるペーパー・カンパニーだったりして。VTuberも実は全部人工知能で、そもそも会社に人なんて誰もいなかったり」 回答は頭上から聞こえた。 『演者に関する情報は、最重要機密です。VTuberは、決して自らの正体を表に現しません。秘密保持義務がある人間であっても、会わせるわけにはいきません』 音源は、監視カメラだった。スピーカーの機能が備わっている様子だった。 最初のコミュニケーションが館内放送経由なんてクライアントは、未来も初めてだった。こめかみが、ぴくりと動いた。 未来は一番近い監視カメラに近づいた。レンズを見上げる。 「ミスルトウ特許法律事務所の大鳳です。棚町隆司社長でしょうか。名刺は、どうやってお渡しすればよろしいですか」 監視カメラでは、相手─棚町本人の可能性が高い─の表情は全くわからない。 棚町は、はっきりとした声で答えた。 『名刺は結構です。大鳳先生の評判はこちらで調べましたので、存じております。しかし、ずいぶんと遅かったですね。ご連絡を差し上げてから、四時間三十二分です。本来なら、今頃は契約の話に入っている予定でしたが』 「申し訳ありません。なにせ四時間三十二分前まで、三重にいましたので」 未来の目の前、廊下の壁が輝き出した。 廊下の壁に画像が映し出される。廊下の足元、壁と床の角に、垂直投影型のプロジェクタが埋め込んであった。 赤毛のショートヘアの女性キャラクタが、バストアップで映っていた。フリル付きのブラウスを着ている。 目力のある、年上の先輩を想起させるキャラクタだ。 『今、第八スタジオで撮影しているVTuberはエーテル・ライブに所属するトップライバーの一人、ミレディ・スプリングフィールドです。ネット上では、ファミリーネームをもじって『春原ミレディ』とか『春原さん』とか呼ばれています』 未来はミレディを凝視した。 コンピュータ・グラフィックだが、手描きのアニメ絵にかなり近い。可愛い、と表現しても問題はない。 映像の全体を見た。 画面の右側三分の一を占めている、小さな字のコメントが、物凄いスピードで流れていく。速すぎて読めない。 画面左下には、『同接数六八五七四人』と表示されている。 音声は聞こえないが、売れ筋商品の紹介をしている様子だった。背後に大量のカップ麺の画像が映っている。 眺めていると、棚町が訊ねた。 『ひょっとして、VTuberにはあまり馴染みがありませんか』 未来は素直に答えた。 「専門ではありませんが問題はありません」 棚町は、少しだけ間を空けてから訊ねた。 『初音ミクはわかりますか。わかるとしたらどの程度ご存じですか』 未来は即答した。 「登録商標です」 スピーカーから、微かに溜息が聞こえた。 『初音ミクはボーカロイドの名称です。ボーカロイドとは、合成音声技術に関するソフトです。もっとも現在、初音ミクは独自の設定や性格を与えられ、製品名ではなくキャラクタとして一人歩きしていますが』 未来は思わず反論した。 「もうすでによくわからないので、わかる範囲でお答えします。『ボーカロイド』も登録商標です。一般名称ではありませんので、使用はご注意ください」 今度は溜息がはっきりと聞こえた。 『ではキズナアイ、はわかりますか』 記憶を全部ひっくり返したが、覚えはなかった。 「最近の登録商標を全て把握しているわけではありませんから」 『商標から離れてください』 棚町の声とともに、廊下を挟んだ反対側のスクリーンが明るくなった。 頭にハート形のリボンを結んだ少女のキャラクタが表示された。 どこかで見た覚えがあった。テレビのCMにも出ていたキャラクタだ。 『我々エーテル・ライブの所属ではありませんが、キズナアイは最初のバーチャルYouTuberと呼ばれています。バーチャルYouTuber、略してVTuberです。もっともキズナアイ自身は、自分をVTuberとは呼びませんが』 スクリーンの中では、キズナアイが怖そうなゲームをプレイしている。薄暗い洞窟で、物陰から突如現れたゾンビをピストルで撃っている。 音声は聞こえないが、キズナアイの表情はコロコロと変化している。 キズナアイのゲームプレイ動画を眺めていると、棚町の声が響いた。 『VTuberとは、YouTuberの一種です。しかし実在する人間ではありません。漫画やアニメのキャラクタのほうが近いです。アニメのキャラクタが、ストーリーの制約から解放されて自由に生きているようなものです』 「キャラクタは誰が動かすのですか。声優もいるのですか」 『裏で動かす人がいます。声優もいます。両者は同じ場合がほとんどですが、別々に用意する場合もあります。ただしこの事実は、キャラクタ性が薄くなるため公表しません』 未来は、移動中に思っていた疑問を率直にぶつけた。 「VTuberは、どうやって儲けているのですか?」 『基本はYouTubeからの収入です。一つは広告収入。一回の再生でいくらの収入です。二つ目はスーパーチャット。ライブにおける投げ銭の収入です。弊所の売上の特徴としては、投げ銭の割合が多い。あとはグッズ販売やテレビ番組の出演などで得る収入です』 投げ銭についても、未来はかろうじて知っている。YouTubeのライブ配信では、配信者にチップ替わりの電子送金ができる。 棚町が続ける。 『約三百万人のチャンネル登録者数がいるキズナアイであれば、動画再生数、チャンネル・メンバーシップの月額料金、テレビ番組の出演などで、年収は一億円を軽く超えます』 キズナアイのスクリーンから光が消えた。 『投げ銭といえば、ミレディは先月、五分間で約一〇九・八万円の投げ銭を稼ぎました。特許事務所の弁理士は、五分でいくら稼ぎますか』 未来の胸の中には、仮想的な器がある。ガラス細工の見事な器だ。特定の出来事に反応すると、器の中には、どす黒い液体がこぽこぽと溜まっていく。 今の棚町の台詞で、器は八割まで満たされた。 未来は適当に計算し、ぶっきらぼうに答えた。 「四一六六円くらいでしょうか」 二秒ほど間をおいて、棚町が冷徹に答えた。 『時給五万円ですか。米国の特許弁護士と同等ですね。ご存じですか。オックスフォード大と野村総合研究所の研究によれば、弁理士業が二十年以内にAIに代替される可能性は九二・一パーセントとか』 ガラスの器は完全に満たされたが、表面張力でなんとか溢れずに済んでいる。 「そろそろ本題に入っていただいても構いませんか。警告書が届いたんでしょう。早く拝見したいです。もし弊所がお気に召さなければ、他の事務所を当たってください」 監視カメラは、沈黙した。 何分くらい経ったか。三十秒程度だったか。静寂の後、棚町の声が再び響いた。 『申し訳ありません。我々としても、警告書は初めてです。混乱しています。勝率が高くてすぐに引き受けてくれる法律事務所を探したところ、貴所が見つかりました』 視界の端で、ミレディがカップ麺を前に笑顔を見せていた。 未来はレンズに向かって微笑んだ。 「せっかくですし、お互いにお顔を合わせてお話できれば。立ち話で済む内容とは思えません、というか立っているのは私だけな気がしますし」 棚町は、ツマミ一つ分だけボリュームを落としたような声で訊ねた。 『一つだけ確認させて下さい。ミスルトウは成功報酬以外受け取らない、とは本当ですか』 未来は呆れて答えた。 「弊所のサイトに書いてある通りです。成功報酬のみ。着手金不要。報酬は負けた場合に支払う賠償額の三十パーセント。訴訟はさせずに解決します。万が一、訴訟に持ち込まれた場合、第一審までは無料で代理します」 例えば、相手から一千万円の損害賠償請求をされた場合。相手を完全に追い払えれば、ミスルトウの報酬は三百万円となる。 棚町は即座に続けた。 『負けた場合、本当に代理人手数料はビタ一文払わなくていいんですね』 面倒だが契約に関する話なので、きちんと頷いた。 「珍しい話でしょうか。保険のセールスも御社のVTuberも同じ。売上があって初めて給料が賄えるわけですよね。我々の場合、売上ではなくどれくらい損失を食い止めたかですが」 棚町の質問は続いた。 『大鳳先生も姚先生も、元パテント・トロールとは本当ですか』 未来は静かに答えた。 「確認は、一つだけではなかったのですか」 かちゃん、と金属の擦れる音がした。 ミレディ・スプリングフィールドのスタジオの、奥の扉から人影が現れた。 二十代後半だろうか。細いシルエットの男性が現れた。白いシャツ、スキニーの黒いジーンズ、ぺたんとした真っ白のスニーカー。 しかし真っ黒のヘルメットでも被っているような、もっさりとした髪形が、いろいろとぶち壊していた。黒縁の眼鏡もファッションなのか、単に眼鏡に興味がないだけなのかわからない。 未来は、会釈もせずに即座に問い質した。 「棚町隆司さんで間違いありませんか」 棚町は、まるで小学生が近所のおばちゃんに挨拶をするような、「へこっ」としたお辞儀をした。 頭を下げるのと同時に、通路の壁が全て輝き出した。 通路に埋め込まれているプロジェクタが、全て映像を映した。画面の中では、VTuberたちの動画が流れている。 しかし雰囲気とは裏腹に、棚町はスピーカーで喋っていた際の、はきはきとした声で名乗った。 「エーテル・ライブ取締役の棚町です」 未来は、会釈をしながら棚町を眺めた。歓迎のアトラクションなのか、棚町社長が目立ちたいだけなのか。 社長なんてみんな目立ちたがり屋、と十把一絡げにしてもよくないが。 棚町は薄く笑った。 「ランチには遅いですが、寿司はどうですか。今日は寿司職人を呼んでいるんです。握らせますから」 寿司と聞いて、喉から胃にかけて、地殻変動が起こったような激震が走った。 今朝からまともに食事もしていない。移動中はずっと資料を読んでいた。プロテインバーを一つ食べただけだ。 しかし未来は、微笑みながらゆっくりと近付いた。 「お気持ちは嬉しいのですが、早くビジネスの話に入りましょう」 棚町はしれっと答えた。 「寿司は、演者たちが事務所に来る日によく振舞っています。ついでとは失礼でしょうが、食べる人間が一人増えたところで特に変わりませんし」 棚町はジーンズの後ろ側のポケットに手を入れた。 スマホを取り出して操作をすると、廊下の映像が全て消えた。 すぐに、ぱっ、と棚町のすぐ隣の壁が光った。 未来は、一歩下がって映像を見た。 今日、最初に見たVTuber、天ノ川トリィが映っていた。 棚町が説明する。 「これはデビュー初期に撮影した、トリィのプロモーションPVです」 亀井製作所製の薄型テレビで見た動画とは別の動画だった。真っ白な背景の中で黒いドレスにベールを被ったトリィが、両手を合わせ、祈るように佇んでいる。後頭部で二つに分かれた金色の髪が、風でまっすぐになびいている。 棚町はすぐに別の映像に切り替えた。 「これはYouTubeでの公開から二週間で二千万再生を超えた曲『アンライヴァルド』です」 ぱっと画面が切り替わった。くすんだ黄色の空をした、荒野の背景が現れた。 砂煙の中から、トリィのシルエットが現れた。白いワンピースに赤いヒールを履いている。音声はないが、トリィの口元の動きから見て歩きながら歌っている。 トリィの通り道を挟んだ両側から、戦車やら戦闘機やらミサイルを積んだロボットやらの大群が現われる。一斉に砲撃が始まった。トリィは気にせず、歌いながら歩く。 砲弾やミサイルやレーザーが、トリィに向かって飛ぶ。全てトリィを反れて外れる。爆風が連鎖的に発生する。トリィは無傷で、ただ歌いながら歩く。歌の内容は、わからない。 未来は訊ねた。 「弾丸や爆風は、後から合成したCGですよね」 棚町は頷き、スマホを操作した。 「もちろん合成です。リアルさを追求したいなら、こっちですね」 また画面が切り替わった。竹林の奥に、寂れた庵が映っている。 庵の周りを、ぼろぼろの着物を着た男二人が刀を持って見張っている。 カメラが庵の中を映す。薄汚れた着物を着た女性が、赤子を抱えて泣いている。 カメラがぐるっと向くと、庵の中は、ならずものだらけだった。総勢、三十人以上。ならずものたちの先頭には、頭領らしき大男が、血まみれの鉈を持って下品に笑っている。頭領は、額から右目にかけて、大きな傷がある。 棚町が説明した。 「トリィの特技の一つは格闘技です。デビュー当初は見せる機会がありませんでしたが、一部のファンよりリクエストがあったので、急遽作った映像です」 未来は訊ねた。 「これも全部CGですよね。ならず者たちも合成でしょう」 「当初の予定では。しかしトリィが『実際に相手がいないとやる気にならない』とゴネました。仕方なく、ならず者三十五人分の格闘家をモーションアクターとして集め、実際に戦わせました。CGキャラクタの動きは全て人間の動きの取り込みです」 頭領は笑いながら鉈を振り上げた。入口の襖が吹っ飛んだ。見張りの二人が、砲弾のように庵の中に飛んで来る。 革のライダースーツ姿のトリィが現れた。まず、ならずもののうちの三人が、まばらに襲いかかった。トリィは宙に回転しながら、ならずものの一人を蹴り飛ばした。蹴り飛ばされた男は、他のならずものたちの一群にぶつかった。 ならずものたちが一斉に襲いかかった。トリィは全員を足技だけで叩き伏せた。 未来は信じられなかった。 「動画の撮影現場では、生身の人間がこの通りに蹴り合っていたと」 「怪我人が三十五人出たので二度とやりません。トリィはスタント俳優ではなく格闘家を要求しました。正解でした。格闘家ですら吹っ飛ぶのに、普通の俳優なんかを連れてきたら死んでいます」 頭領の姿が見当たらない。死角から、頭領が鉈を振るう。スローモーションで、鉈がトリィの首に向かって振られた。首に近づいた瞬間、スローモーションが解かれる。トリィは澄ました表情で、姿勢を低くし刃を避けた。そのまま勢いを殺さず、トリィは頭領に向かって跳び上がった。両足を頭領の首にかけた。頭領の驚いた顔が一瞬だけカメラに映った。直後、トリィの足に巻き込まれたまま、頭領の脳天は床に叩きつけられた。 棚町が映像を切った。 棚町が嘘を吐いているとは思えなかったが、未来としてはまだ半信半疑だった。 棚町は説明を続けた。 「今、隣のスタジオに入っている演者が天ノ川トリィ。一年前にデビューしたVTuberです。彼女は先月一か月で二億円を稼ぎました。一か月での二億円台は事務所初です。動画の再生時間で割れば、五分で三五〇万円を稼ぐ計算です」 未来はざっと計算した。 「たしか世界で最も稼いだモデル、ケンダル・ジェンナーの年収が十億円。半年でスーパーモデルの稼ぎを超える計算です。本当ですか」 「前代未聞ですよ。逸材です」 ふと未来は、ミレディ・スプリングフィールドを見た際の違和感の正体に気付いた。 天ノ川トリィはVTuberの中でも表情が豊か過ぎる。 グラフィックの美麗さもあるが、天ノ川トリィの最大の特徴は、ほとんど人間と同じレベルで、表情、行動、仕草が表現されている点だ。 棚町が、トーンの落ちた声で答える。 「昨日、弊所エーテル・ライブに送付された警告書を、私は寝ないでずっと読んでいました。何度読んでも『天ノ川トリィの存在は侵害だ』としか解釈できませんでした」 直後、微かに建物が揺れた。 立て続けに小さな地響きがあった。すぐに壁が揺れていると気づいた。 未来は地震かと思った。 「地震にしては局所的な感じですが」 棚町が、くやし気に目をつむった。 今度は、壁に巨大な鉄球でもぶつけたような振動が起きた。 「誰かが、壁でも殴っている?」 棚町が呟いた。 「やはり、でき合いのトラッキング装置では話にならなかったか。少し待ってください」 棚町は、スマホで誰かに電話をかけた。 「私だ。撮影は中止です。トリィが拳を痛める前にやめさせて下さい。今以上に生傷を増やさせてはいけない」 壁の振動は続いた。 「天ノ川トリィは武芸百般、あらゆる武器に精通した、天ノ川流殺法の開祖です。しかし一番の武器は、己の肉体を武器とした、天ノ川流拳法です」 急に現れた設定に、未来はついていけなかった。 棚町は、未来の心理を知ってか知らずか、続けた。 「さっきの動画、三十五人を叩きのめしたって信じていませんよね」 答えにくかったので、話題を逸らした。 「動画の視聴者は、信じたのですか」 意外にも、棚町は頷いた。 「トリィのさっきのライダースーツ姿でのアクション、動画を投稿した五分後に、截拳道がベースだってファンにばれたんですよ。合成ではあんなに完全に再現できない、とも」 截拳道にフランケンシュタイナーって技があったか? 考える間もなく棚町の背後の扉が轟音とともに吹っ飛んだ。 扉と共に、スキンヘッドにタンクトップ姿の大男と、空手の道着を着た短髪の男が廊下に吹っ飛んだ。 既視感があった。既視感の正体を確認する前に、扉がなくなり、防音機能が役立たずになったスタジオから悲鳴が聞こえた。 「やめろ、トリィ!」「取り押さえろ!」「トリィさん落ち着いてください! ぎゃああああ」 壁に人がぶつかる音がした。 棚町は未来のほうを向いたまま俯いていた。背中で悲鳴を聞いている。 棚町が困り果てた声色で懇願した。 「エーテル・ライブで見た一部始終について、他言しないと約束してください。他の条件は付けません。代理人費用も、言い値でお支払いします。彼女が、トリィが存在する自由を守って下さい」 棚町の言葉の意味を確認するため、未来はスタジオの中に足を踏み入れた。 スタジオはめちゃくちゃだった。もとは何があったのかもわからない。壁の鏡という鏡は全て割れ、スタジオの四隅に配置されていたであろうカメラや照明スタンド、その他の機材は倒れ粉々になっている。 機材と同じように、スタッフが重なって倒れている。ジャージ姿、ボクサーパンツ姿、道着姿などなど計八名、格闘家らしき姿のスタッフばかりだった。全員、完全にのされている。 未来の視界が異質な存在を捉えるまでに時間はかからなかった。 渦の中心に、一人の女性が背を向けて立っていた。 身長は百七十センチ程度。雰囲気からして二十代前半か。体にぴったりと張り付く、長袖の青いボディスーツを着ていた。スーツの背中は開いている。隙間から見える生身の体は、ところどころに傷があった。 長い黒髪を二つに分けて後頭部で結んでいる。 未来は思わず、呟いた。 「天ノ川トリィ?」 トリィの演者はゆっくりと振り向いた。 恐ろしく整った顔をしていた。肌は真っ白で、アーモンド形の目が、興奮で大きく見開かれている。 未来は完全に混乱した。 天ノ川トリィの演者は、動画の中で、電子の存在だったグラフィックスを、そのまま現実に具現化させた姿形をしていた。 未来の質問に対して目の前のトリィは、首をゆっくりと横に振った。 奇妙な話だが、未来は天ノ川トリィの演者と話しながら、天ノ川トリィの動画を見ている気分になった。 未来の心境を察したのか、棚町社長が声をかける。 「最初だけです。すぐに慣れます。VTuberの天ノ川トリィも、演者の天ノ川トリィも」 天ノ川トリィの演者は、ひびの入ったディスプレイを指さしながら怒鳴った。 「こんなの私じゃない! 今すぐ元のツールに戻して!」 響いた声は、三重の亀井製作所で少しだけ聴いた天ノ川トリィの声と完全に同じだった。