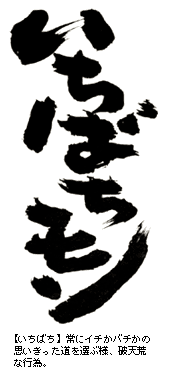
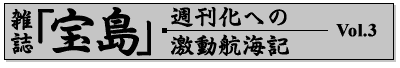
「宝島」嵐の船出(3)
故・植草甚一を責任編集者に、片岡義男、津野海太郎、平野甲賀、高平哲郎、北山耕平などのそうそうたる編集陣。当時人気絶頂だった、
矢沢永吉率いるロックバンド「キャロル」による華々しい復刊イベント。石油ショックの逆風をものともせず、1974年、新生「宝島」はまさに順調な船出を遂げたかに見えた。
しかし復刊後まもなく、蓮見清一(現・宝島社社長)は、「宝島」という雑誌に、ある重大な欠陥があることに気づく。
皮肉にも、それは「宝島」にとって最大の強みであるはずの「豪華な編集陣」そのものであった。
植草以下、編集者一人一人があまりにも個性豊かな「カリスマ」であったがゆえに、ひとつの雑誌で編集長が何人もいる状態になってしまっていたのである。
こと出版に限らず、どのような分野においても、求心力のないプロジェクトがうまくいくはずはない。
「宝島」復刊の際、出版権の買い取りを晶文社と直接交渉した石井慎二(現・洋泉社社長)は次のように述懐している。
「編集者それぞれが、宝島という仕事場に片足だけ突っ込んでいるみたいな状態でした。お互いに遠慮しあってい
たのかもしれないが、要するに“俺がこの雑誌を何とかしなきゃ”みたいな当事者意識を誰かが持てる環境じゃなかったんじゃないかな」
かくも迷走しながらも、この時期、「宝島」は後世の雑誌界に多大な影響を及ぼす編集スタイルを生み出している。
それまでのように、編集者がただ闇雲に、自身の主観で発掘した記事を寄せ集めるというカタチは排除した。
その代わり、読者が興味を持つワンテーマを取り上げ、そのテーマの中で、「あくまでも読者がその情報を参考に自分で実践できる」
ネタを総覧的に編集した。いわゆる「情報のカタログ化」である。
ポパイでもホットドッグでもない、あの「シティ・ボーイ文化」の生みの親とは?
これは当時の雑誌界においてはまさに画期的なことであった。
ちなみにその頃のテーマとしては、『お土産 植草甚一のニューヨーク大百科』『宝島マニュアル シティ・ボーイ』などがある。
「シティ・ボーイ」と聞くと、特に30代より上の読者は、かの「ポパイ」を連想するであろうが、何のことはない、その後日本の若者文化
で一世を風靡することになったこの単語の生みの親は、他でもなく「宝島」であった。
しかし悲しいかな、折角の「情報のカタログ化」という目の付け所も、他の大手出版社によってまんまと横取りされ、
我が物にされてしまう。これも当時「宝島」編集部の求心力と体力の無さがゆえであった。
蓮見率いるJICC出版局(現・宝島社)が、このマストを失った船のような編集部に大ナタを振るうのは、これよりまだ先のことである。(つづく)
文・前田知巳(コピーライター)
|
|