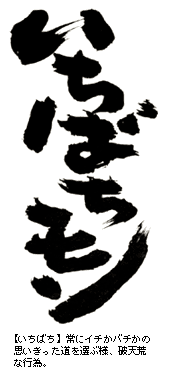
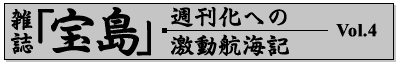
「宝島」嵐の船出(4)
1974年、「宝島」が復刊してからしばらくの間のバックナンバーは、とにかく軽い。
軽いというのは何も内容のことではなくて、雑誌自体の重量が驚くほど軽いのである。
版型(誌面の大きさ)は洋書のペーパーバックサイズ、雑誌としてはごく小さめだったというのもあるが。
しかし本当のところは、当時の石油ショックによる紙価格の高騰に対抗して、「印刷・製本できる範囲で最も粗悪な紙」を使っていたのが
実情であったというから、「宝島」が当時置かれていた状況が偲ばれるというものである。
「吹けば飛ぶような」軽量の雑誌。それは皮肉にも、その頃の編集部のモロさを象徴するかのようであった。
植草、片岡(義男)、高平といった編集長格(しかもスター級)が揃いすぎているがゆえに求心力に欠けていたという話は前項でも取り上げたが、
何にせよまず売れ行きが良ければいい。ところがこれがサッパリだったのである。
当時、「宝島」編集部は本体であるJICC出版局(現・宝島社)とは別の場所にあり、限りなく糸の切れた凧状態に近かった。
この危機的な事態を収拾しようと、蓮見清一(現・宝島社社長)は指導役と頼んだ社員を編集部に送り込むのだが、逆にあっという間に彼らに感化されてしまう。
「ミイラ取りがミイラに」とはまさにこのことである。
それもそのはず、「誰かに感化されたかったら日本一の場所」と呼べるぐらい、そこにはカリスマたちが揃っていたわけだから。
植草らカリスマたちは編集部を去った。そして謎のヒッピー集団がぞろぞろと…
さんざん手を焼いた末、1976年、ついに蓮見は一大リストラを決行する。これにより植草以下、片岡、高平など、編集の主だった面々は「宝島」を去っていった。
ちなみに日本では田中角栄、中国では四人組が逮捕されたのがこの年である。
編集体制は一新したものの、しかし「宝島」の迷走がすぐに止むわけではなかった。
雑誌の性格も「マリファナ特集」というような、いわゆるドラッグ・マガジン色がどんどん濃くなり、ヒッピーまがいの人間が、
いつも編集部のあるビル下に意味なく集まってくるという珍現象まで起きた。
「5人が熱狂し95人が無視する雑誌」。まさに当時の「宝島」は純度の高いサブカルチャー・メディアになり得ていた。
しかし「売れない」という作り手の苦悩の原因がそこにあったのも事実だ。
売上部数は、実に5000部まで落ち込んでいた。いつ廃刊になってもおかしくない瀕死の状況である。(つづく)
文・前田知巳(コピーライター)
|
|