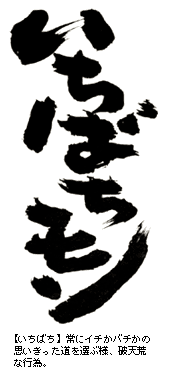
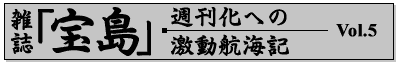
ニューウェーブの先駆的雑誌と言えば(1)
「世の中から見ればマイナーだが、一部の人々からは圧倒的な支持を集める文化」
それがサブカルチャーの定義だとすれば、70年代の「宝島」は、まさにサブカルチャーそのものの権化であった。
特にドラッグカルチャーを代表とする「過激に先を行ってるアメリカ西海岸な世界」を肌で感じたい若者には、数少ない「使える」メディアのひとつだったに違いない。
「世の95人は無視しても、5人から熱狂される雑誌」として君臨する宝島。しかしその性格は同時に、「ある一定の部数以上は絶対に売れない」という宿命を背負ったものであった。
1979年、発行部数はついに5000部台にまで落ち込む。
これは「経営」という視点からすれば、本体であるJICC出版局(現・宝島社)の足を引っ張るどころの部数低迷ではない。
サブカルチャーの殿堂「宝島」は、ここへきてついに「廃刊」かどうかの選択肢を突きつけられるまでに至ってしまった。
翌1980年は、まさに「世界が激動した80年代」の始まりを象徴するような出来事が重なった年である。
韓国では光州事件が勃発し、ポーランドでは自主管理労組「連帯」が結成された。
合衆国大統領選挙ではロナルド・レーガンが圧勝、日本では大平正芳首相の死去に伴い、鈴木善幸内閣が後を次いだ。
そしてあのジョン・レノンが暗殺されたのも、この年の暮れであった。
ドラッグ漬けで瀕死寸前の「宝島」。蓮見は大胆なショック療法に着手する
さてこの年、瀕死の状態である「宝島」を前に、蓮見清一(現・宝島社社長)は、ついに開き直りにも近い改革策を次々に打ち出し始める。
「廃刊などさせる気は毛頭なかった。逆にJICCの出版事業の柱になるのは『宝島』しかない、と信じて疑わなかった」蓮見は当時の心境をそう振り返っている。
まずはカラーグラビアの積極的な採用。当時の「宝島」は雑誌の中ではごく小型の「A5版」という大きさだったこともあり、
「カラーでビジュアル化する」という意識は作り手の中にほとんどなかった。
この着眼は後々の「宝島」に大きく影響することになる。奇しくもそれを最初に着手したのは、1月号の「植草甚一追悼号」であった。
5月号からは定価を480円から250円に。実にほぼ半額という破格の値下げである。
今では宝島社のお家芸である大胆な価格戦略は、この時から始まったといえる。
そしてここに、ある1人の人物が登場する。「廃刊するぐらいなら、俺に一度やらせてください!」と蓮見に直訴した人物。
この男によって、「宝島」の運命は大きく変わっていくことになる。(つづく)
文・前田知巳(コピーライター)
|
|