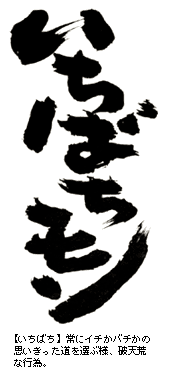
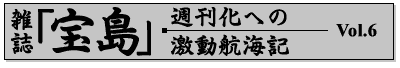
ニューウェーブの先駆的雑誌へ(2)
「廃刊になるくらいなら僕にやらせてください」。
編集長が何人替わっても一向に部数が上向かない「宝島」に痺れを切らしたのか、関川誠(現・宝島社取締役)が社長の蓮見清一にそう直訴したのが1980年。
入社してわずか3年目のことであった。申し出た関川も関川なら、それを「やってみろ」と快諾した蓮見も思い切ったものである。
当時それほど「宝島」が開き直りに近い状態だったということもあるだろうが、宝島社はつい昨年も女性ファッション誌にまだ20代の女性編集長を大抜擢しているから、
当時からそういう大胆な気風がこの企業にはあったということだろう。
関川はJICC出版局(現・宝島社)入社の前年から既にバイトで「宝島」本誌の担当を務めていたから、
一部から熱狂的に支持されながらも部数がどん底だった時代を経験している。
今も70年代の「宝島」を思い出して「あの頃が一番良かった」という人は少なくないが、
作り手である当事者としては「雑誌というものは売れなければすべてが悪循環、ということを身をもって体験した」(関川)というから、
そのギャップが興味深い。
さて、晴れて編集長になった関川は、「パンク・ニューウェーブ」という明快な路線を打ち出すことを決心する。
それまでのドラッグ・カルチャーに象徴された「過激」という志向は保ちつつ、「ロック&ファッション」という、時代の先端が顕著に表れる分野にはっきりとピントを絞りこんだわけである。
現に、関川体制になる前夜、80年3月号では当時人気に火がつき始めていた「テクノ音楽」の旗手・YMOを特集し、それが久々のスマッシュ・ヒットになっていた。
関川にはその時点で「この路線にかけるしかない」という確信めいた予感があった。
読者を増やすために、まずは読者を全員切り捨てるという過激っぷり
しかしこの思い切った路線変更は、それまでの熱烈な読者、さらには係わりのあった著者、スタッフの面々までもバッサリ切り捨てることを意味した。
「宝島」の変遷に詳しい法政大学教授の稲増龍夫氏も「70年代と80年代では『宝島』の読者層はほぼ100%変わっているでしょう」と語る。
時代とともにコロコロとスタンスを変えるこの雑誌の編集方針を指して「猫の目編集」という言葉まであるほどだが、そういう性格はこの時から始まったといっていい。
読者を増やすために、まずはそれまでの読者からスッパリとサヨナラしてしまう。そんな、全財産を投げ打っての大博打のような決断を、
「宝島」はあっさりと実行してしまった。そこには一体、いかなる勝算があったのだろうか?(つづく)
文・前田知巳(コピーライター)
|
|