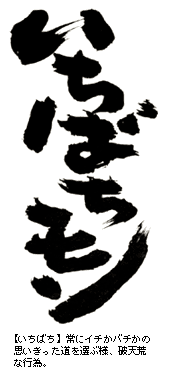
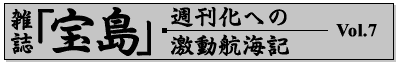
ニューウェーブの先駆的雑誌へ(3)
「とにかく売上部数を伸ばす!」。
1980年、入社後わずか3年目で「宝島」編集長になった関川誠(現・宝島社取締役)の胸には、その思いしかなかった。
それまでの、廃刊は明日か明後日かと半ば観念するようなどん底状態は二度と御免だった。
しかし関川には、そういうトラウマにも似た感情とは別に、「こうすれば事態は絶対に打開できる」という冷静な読みもあった。
「それが、読者ターゲットを思い切って大転換するという戦略だったのです」と関川は語る。
それまでの70年代における「宝島」は、「サブカルチャー誌の雄」と謳われていたように、主たる読者層はごく一部に限られたディープな人々であった。
彼らから熱烈に支持されながらも、それでは部数の伸びは永遠に期待できない。
「これから『宝島』は、もっと女性や子供たちからも広く愛される雑誌になるべきだ」関川はそう確信していた。
その方針は、永く「宝島」を愛してくれた人々との決別をも意味したのだが。
関川の確信は、時代の気配、時代の流れを絶妙に読んだ上でのことだった。RCサクセション、YMOなど、いわば「歌謡曲」とは一線を画した、
音楽的にも高い質を誇るニューウェーブのバンドやユニットが、性別にかかわらず若い世代から強い支持を集め始めていたのである。
しかも、そういう感覚的に若い世代の嗜好を受け止める雑誌が、実は当時ほとんど存在しなかった。
RCサクセションのボーカル・忌野清志郎もその頃を次のように振り返る。
「当時は音楽雑誌なんてほとんど日本になくて、せいぜい『ロッキン・オン』『ロッキン・f』『新譜ジャーナル』ぐらいだった。
中でも『宝島』は日本のニューウェーブを取り上げてた唯一の雑誌だった気がする」。
それに加え、同じ1980年、社長である蓮見清一の直感で導入された「宝島」のカラーグラビア化も功を奏した。
ご記憶の方も多いと思うが、RCサクセションもYMOも、その当時の奇抜なメイクやファッションがまた話題を呼んだものであるが、
それらはまさにカラーグラビアに打ってつけだったからである。
1980年。「日本でもニューウェーブが絶対に爆発する!」という関川の確信は…
思えば80年代前半の日本は、音楽に限らず、ファッションも文学も、海外からのニューウェーブの影響を受けて、新しい芽が次々に生まれた時代であった。
それら新芽を目ざとく嗅ぎ付け、いち早く読者に提供するメディア。
とかく物議を醸しがちな「売れるのなら、時代と寝てやる」そういう「宝島」の特異な存在は、それどころか時代そのものを変えていくことになる。(つづく)
文・前田知巳(コピーライター)
|
|