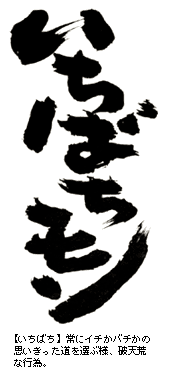
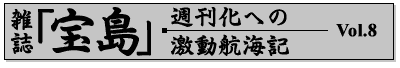
ニューウェーブの先駆的雑誌へ(4)
1980年代に入るとともに、ガラリとニューウェーブ路線に転向した「宝島」であるが、その当時、この雑誌の存在がどのように変わっていったかを象徴する話がある。
ニューウェーブ期だった80年代を通して「宝島」のひとつの顔だった忌野清志郎(RCサクセション・ボーカル)が次のように語っている。
「確かあの頃、近所のオバチャンから『宝島で見たよ!』なんて声かけられて、アレ?って思った記憶があるね」。
実際、その「近所のオバチャン」が「宝島」の愛読者だったかどうかは別にして、
仮に立ち読み程度だったとしても、そんな状況は70年代では到底想像できなかったことである。
それまでは、ごく一部のカルト・ファンが密かに信奉する雑誌だったのだから。
まさにその点では忌野自身も同じ思いだったらしい。
その頃既にRCサクセションを結成して15年以上経っていながら、オバチャンに声をかけられるなど初めてだったのではないか。
「自分らを取り巻くファン層がどんどん広がってるなんて、まだ全然ピンと来なかったんだよね」。(忌野)
しかしこれは、当時「宝島」の編集長だった関川誠(現・宝島社取締役)の狙いどおりの展開でもあった。
RCサクセションだけではない。YMOもデヴィッド・ボウイも、まさに日本でブレイクする寸前の絶妙のタイミングで採り上げたのが「宝島」であった。
そして次第にこの雑誌は、「ブレイクしたての(またはブレイク間近の)あの人に会えるのは宝島」という「先端カルチャーメディア」のポジションを獲得していく。
しかもこの「先端」は、イコール「少数派」を指した70年代とは意味が違う。多くの人から支持を集める「先端」であった。
さて、時代の寵児として「宝島」が後押ししたのは、何もロックやテクノだけではない。
80年代前半のバックナンバーの表紙を見渡すと、ひとくちに「ニューウェーブ」といっても、それは様々な分野を指していたことが良くわかる。
例えば81年11月号の表紙は糸井重里。あのコピーライターブームがまさに起ころうとするタイミングであった。
82年3月号ではビートたけしが登場。当時はまだ、彼にお笑いではなくアーティストの面からスポットを当てるメディアなど稀だったろう。
あろうことか近所のオバチャンが…!?それは、清志郎にも宝島にも初めての体験
時代の風を捉えた「宝島」の部数が伸びない訳がなかった。それは「宝島」自身が創刊以来はじめて経験する「ブレイク」であった。
とはいえこの路線は、時代という風、人気という波ほど気まぐれなものはないことを、やがて痛感する宿命にはあるのだが。(つづく)
文・前田知巳(コピーライター)
|
|