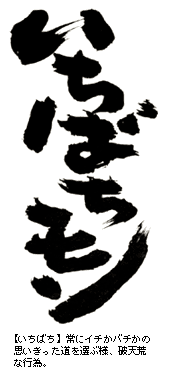
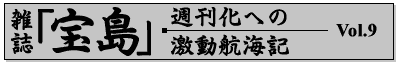
ニューウェーブの先駆的雑誌へ(5)
80年代を通して「宝島」の表紙は、まさにニューウェーブの旗手たちのオンパレードだった。ロックやパンクだけではない。
当時「花形稼業」といわれた広告業界の顔として糸井重里。「お笑い」に大地殻変動を起こした立役者としてビートたけしやタモリ。
ユニークなのはジョン・マッケンローで、試合中の粗暴な態度や大胆な言動は確かに、当時のテニス界では「ニューウェーブ」といえる存在だった。
要するに「宝島」という雑誌にとって、大事なのは「これから世の中に新風を巻き起こすおいしいネタかどうか」がすべてであり、
「そのネタをどこよりも真っ先に提供しますよ」というお約束が、この雑誌の身上になっていったわけである。
その前に、もはや扱うテリトリーや主義へのこだわりなどは、まったく意味を持たなくなっていた。
その「何でもあり」のいい加減さ、良く言えば軽やかにフレキシブルに「次の流れ」を先取りしていくスタンス。
今考えるとその編集方針そのものが「ポップ・カルチャー」だったということであろう。
「お気楽世代」「なんとなく世代」だった80年代の日本の若者が飛びついたのも当たり前であった。
「次の流れ」という意味では、かくもカルチャー誌として異例の成功を収めながら、「宝島」がそこに安住するわけがなかった。
「ビジュアルでなければ出版ではない、という時代が来る」という蓮見清一(現・宝島社社長)の判断により、85年1月号から断行したオールカラー化はまさに画期的だった。
A5版というサイズ(「文芸春秋」の大きさ)でオールカラーの雑誌など、出版史上後にも先にもこれだけであろう。
この刷新により、ファッション・雑貨・街情報は「宝島」の大きな目玉となり、女性読者をさらに増やすという結果を生んだ。
そしてこの流れは後の90年代に、宝島社がファッション誌でも次々と大ヒットを飛ばすことにつながっていく。
デヴィッド・ボウイ、糸井重里、たけし、タモリ、マッケンロー…さて、共通点とは?
「あとはやっぱり、80年代ってまだ海外と日本に『情報の時差』があったんですよね」と語るのは、当時編集長だった関川誠(現・宝島社取締役)。
「パンクなんかも、ロンドンと東京じゃ10年ぐらいのズレがあった。今と違って、まだ日本では知られていない流行のネタが海外にはいっぱいあって、
それを輸入して紹介すると『これは新しい!』って面白いようにウケる。楽といえば楽な時代だったかな」。
事実、ヒップホップ、ナイトクラヴィング、スケートボードなど、今や若者の間でも最先端の風俗を、実に10年以上も前に盛んに採り上げているから面白い。
「若者文化に疎くて」とお嘆きのお父さんは、その頃の「宝島」バックナンバーをご覧になると、巷の雑誌よりよほど勉強になるかもしれない。(つづく)
文・前田知巳(コピーライター)
|
|