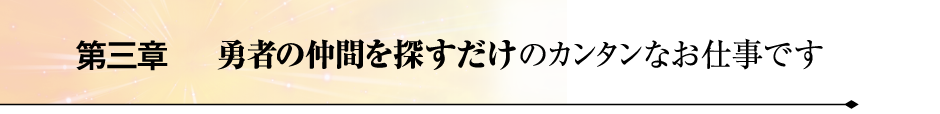噂をすればなんとやら、という言葉がある。
人間の意志は近い未来の運命を変える力があるのか、それとも予知した未来を基にして噂を始めるのだろうか。何れにせよ、ミカゼの仲間を探し始めた次の日の朝、僕は登校中に、ヒメナ先輩から話しかけられた。一つ上の学年の先輩だ。
学校へ向かうまばらな生徒の列の中、彼女が僕に追いつくようにして、背後から声をかけてきた。
「千早よ、久しぶりじゃのう」
ヒメナ先輩は糸のように細めた眼で、にこにこと僕を見る。彼女のことは、剣道部にいた時に知った。
僕が入っていた剣道部は自由気ままな、それはそれは自由気ままで、勝手に部員が来て勝手に練習し、勝手に帰っていくだけのしょうもない部だった。
適度にサボっていた僕ですら、一番参加率がよかったのではないだろうか。ヒメナ先輩に至っては、部員ですらない。
ヒメナ先輩は部外者なのに剣道部に顔を出しては、道場の隅で座って、にこにこと練習風景を見て帰っていくだけだった。誰かが竹刀を振っているのを見るのが面白いのじゃ、だそうだ。
見学しているだけかと思えば、ヒメナ先輩は竹刀を持たせると滅法強かった。世界最強の剣士を自称しているくらいだ。ヒメナ先輩が部活として剣道部に参加しなかったのは、もはや剣道の試合として成り立たないせいなのかもしれない。頼み込んで試合をした部員が何人かいるが、文字通りの秒殺だった。僕は何をされたかもわからないうちに胴を打たれて負けた。
部員に対して、どう動けばより速くなるか、隙を作らなくなるかなどを的確に言い当ててくるので、剣道場にたまに出没する腕利きのアドバイザーとして、ヒメナ先輩は半ば伝説の存在だった。部活自体が活動しているのか怪しくなるようなものだったので、ヒメナ先輩がいても、我が部が強豪になることはなかったけれど。
こういった強さを覚えていて、僕はヒメナ先輩が、勇者の仲間的な何者かではないかと考えたのだ。
僕は部活に顔を出していただけなのに、どういうわけかこの先輩に気に入られている。
「ほれ、今日のわしの太ももはどうじゃ。ほれ?」
「嬉々として脚を見せつけないでください!」
セーラー服のスカートを捲りあげながら、ほれぇ、ほれぇーと、挨拶代わりに僕をからかってくる。
この先輩には、僕が女子の脚をとても好きなことがばれている。剣術の達人である彼女には、視線が文字通り線のように空中に浮かび上がって見えるらしく、初対面で見抜かれてしまった。ちなみに胸への視線は、普通の女性ならば絶対にわかるから見るのはやめておけ、とのことだった。脚が好きな方でまだよかったのう、とも言われた。ありがたい先輩からの言葉である。
からかわれていると分かっていても、僕はちらりと綺麗な肌に目を落としてしまう。勇者がモンスターを倒さなければいけないように、僕は太ももを見なくてはいけない。大宇宙の理のようだ。
武芸をするために作られたような太ももには無駄がなく、細いと言えば細いのだが、黒土のような華奢な足ではなく、筋肉がついているため張りがある。それでいて、その上に脂肪が薄く乗っているため、ごつごつとした質感はなく、滑らかなカーブを描いている。
「いつも通り、美しいですよ。日本刀のようですね、名刀です」
「うむ、鑑定眼恐れ入るわ」
笑顔のまま、ヒメナ先輩はスカートを降ろす。
じろじろと脚を見られることを、少しは恥じらってください、と言いたかった。この人のせいで、僕の癖や趣向は悪化していたのかもしれない。
「むしろ自分から脚を見せるのは止めてくださいよ」
「そろそろ、わしの脚が恋しくなる頃じゃなかろうかと思ってのう」
「過去に何かあったような言い方も止めてくださいってば」
僕とヒメナ先輩は、学校や通学路で擦れ違うたびに話をするような仲ですらなかったはずだ。そんな相手に声をかけるのは、余程暇な時か、話したい内容がある時ぐらいだろう。ヒメナ先輩と話すのは何カ月ぶりだったっけ、と思いながら、僕は口を開いた。
「何の用事ですか? 僕を入れても、剣道部は欠員が多くて団体戦ができないはずですよ」
「ぬふふ、そうではない。そうではないよ。部の試合にはわしもあまり興味がない」
「なら何ですか」
「愛の告白じゃよ」
思わすふらついて、電信柱に頭をぶつけそうになる。この先輩特有の、突発的な、過度なからかいだ。彼女は充実した青春という餌を、僕の目の前にぶら下げて遊んでいるだけだ。本気に捉えたら僕の負けだ。
「絶対、微塵もそんなこと考えてないですよね。そこまで思っていたら、今までにもう少し話しかけて来てますよ」
「んふ、確かにそうじゃの。わしの話は、これじゃよ」
そう言ってヒメナ先輩は、腰に吊った刀をくいと持ち上げた。驚くべきことに、この人は真剣を持ち歩いている。見てくれはまさに、セーラー服と日本刀、と言ったところだ。
何故この平和な国において日本刀を腰に差していても出歩いていられるのか。僕は商店街や学校でヒメナ先輩を見るたびに首を傾げていた。本人によると「蝶に羽根がついているのを誰がおかしいというじゃろうか? 故にわしが刀を持つことは当然であるということじゃよ」である。要するに刀を遣うのが世界で一番上手いヒメナ先輩には似合いすぎていて、誰も違和感を持たないということらしい。
「突然ですね。僕に決闘の立ち合いでもしろって言うんですか?」
「そうではない。お主は勇者の仲間じゃろ」
「えっ?」
唐突にヒメナ先輩は、僕にしかわからないような単語を口にした。僕の驚きとその後の沈黙が、そのまま彼女への答えになってしまった。
「何で分かるんですか」
「千早から、何やら魔法のような力が出ているのに気づいてのう」
「そんなもんなんですか。確かに僕は呪文を使う賢者ですけど」
「じゃろ? わしの家系は、勇者の仲間の『サムライ』なんじゃよ」
僕の思っていた通り、ヒメナ先輩は勇者の仲間だったようだ。
ワカルヨーの魔法で表示される内容については、ミカゼから教えてもらっていた。『サムライ』は、剣や槍で戦う『戦士』という種類のグループに分類されている。力任せに戦うのではなく、切れ味の鋭い剣を使い、早業で戦うタイプだ。
ヒメナ先輩は武家の血筋であると聞いたことがある。勇者の仲間の家系でもあるなら、「月刊むむう」等の雑誌に『衝撃の事実! あの剣豪は勇者の仲間だった?』などという、ガセか本当かよくわからない特集記事が出来上がりそうだ。ちなみに、こういう怪しい記事は、タイトルの最後が疑問形になるのが特徴だ。たとえ間違ったことを言っていたとしても、私は嘘をついているわけではありませんよ、という便利な防御機構だ。
「それでのう、勇者から声がかかるのを待っていたんじゃが、何も連絡が来なくてのう」
「ああ、多分それって役所の怠慢で、ヒメナ先輩が仲間の候補リストから消えてますよ」
「うむ。市役所に行ったらそうなっとった。それで登録してきたんじゃが、、仲間を必要としとる勇者は今おらんらしくての」
ミカゼのパーティはむしろ仲間を探しているが、役所には募集中だと言っていない。だから彼女は知らないのだろう。
「平和でいいことじゃないですか、戦力が足りない方がまずいですよ」
「それがのう。わし、モンスターとやらを斬ってみたいのじゃ」
さらりと、とんでもないことを言い始める。
「すごく物騒ですね。血に飢えてるんですか」
「そうじゃよ。わし、このままだと人も斬ってみたくなるかもしれなくてのう」
ぬっふっふと、ヒメナ先輩は怪しげに微笑んだ。僕は彼女から二馬身くらい離れた。
「冗談じゃよ」
「貴女が言うと冗談に聞こえないんですよ」
「それはすまぬのう。わしはお主が心配でな。この前も学校で大立ち回りしたじゃろ?」
恐らくヒメナ先輩は、黒土の一件のことを言っているのだろう。この先輩には、そこまで見抜かれているのか。確かに屋上から落っこちたりなどはした。
つまり彼女は、僕を助けるつもりで、ミカゼのパーティに自分を売り込みに来たのだ。
ヒメナ先輩は、気に入った者に対しては妙に世話焼きというか、おせっかいなのだ。弱きを助ける武士道を体現していると言えば聞こえはいいが、好意を押し付けていると言うべきだろう。
正直、心配をしてくれるのは有り難い。けれど僕としては、ヒメナ先輩を仲間に加えるのはあまり気が進まない。ヒメナ先輩の行動は冗談がきつ過ぎて、ミカゼや僕達の仕事がかえって増えかねないのだ。かつて僕の腕を引っ張りながら学校を出て「他校の剣道部の礼儀がなっておらんから、道場破りに行くぞー。なーにが全国大会出場じゃ、雑魚どもめが。わしが全員倒してやるわー」などと天に向かって吼えたこともある。僕を巻き込まないでください、と必死に言って彼女から逃げたものだった。
それに、ヒメナ先輩は確かに強いが、行く先々で必ず何かをしでかす。というか、どういうわけか彼女は面倒事を吸い寄せてしまうのだ。偶然、爆弾を抱えたテロリストと地下鉄で遭遇して成敗したとか、彼女とうっかりエンカウントしたチーマーや珍走団が壊滅したなんていう噂も聞いたことがある。おそらく事実だろう。
なので、丁重にヒメナ先輩の申し出を断っておいた。ミカゼがエクスカリバーを二刀流にしていて常にオーバーキル状態ですよ、と大本営発表もしておく。
なんじゃ、つまらんのう、と残念そうに言われたが、僕としては面白いどころか笑えないことになるんじゃないかという予感の方が大きいのだ。
「わしの力が必要になったら、遠慮せず言うんじゃよ」
そう言い残して、ヒメナ先輩は先を歩いて行った。
去り際に、元々開いているのか閉じているのか分からないくらいの目で、ウインクまでされた。
やはり、ヒメナ先輩を仲間にするのは気が引ける。
開口一番、わしは千早の恋人じゃよ、などと言って、ミカゼや黒土を驚かせたりすることが容易に想像できる。あれこれと誤解されて、僕が変な目で見られるのは、避けたいところだった。
放課後、ミカゼのパーティは仲間を探すために、校舎を出て町を歩いていた。
世間話の中に「ワカルヨー」というワードを混ぜ込み、さりげなく呪文を使って、町を歩く人達を見ていく。全員が村人の表示だ。
勇者やその仲間というのはレアな存在であると、改めて認識させられる。
どうやら一つの県に二、三のパーティを作ることがやっとなレアさらしい。駅前の雑踏を見ても、村人の表示で視界が埋め尽くされる結果になった。
結局、仲間を見つけることはできず、僕たちは収穫なしで商店街を歩く。
今日の授業中に、エクスカリバーなしでモンスターを倒すのに必要な時間を見積もってみた。その結果、現在の僕たちのパーティが、山に出現する平均的な強さのモンスター一群を倒すと、軽く日を跨ぐことが判明した。
ちなみに、少しでも総合ダメージ量を増やすため、僕も金属バットという名の杖でモンスターを殴ることを想定している。数時間もそんなことをしていたら、次の日は確実に学校をサボってしまいそうだ。
このままでは受験勉強ができないどころか、留年さえも視野に入ってくる。
「ああ、モンスターも現実も手強すぎるぞ」
「ち、千早さん、何を言っているんデスか」
「僕が留年する時には、お前も道連れだ。地獄につき合ってもらう」
「み、ミカゼさん、千早さんが死神みたいになってるんデス」
「死神は黒土さんだよ」
落胆しながら歩いていると、僕の目に、村人以外の表示が入ってきた。
勇者の仲間かと喜ぶのも束の間、僕は人差し指を表示の下に向け、ミカゼに伝えた。
表示は『モンスター』。僕たちは仲間を探しに来たはずなのに、町に出現したモンスターを見つけてしまった。
薬局の前に置かれた、蛙を模した人間サイズのマスコットキャラクター。その隣に、同じくらいの大きさの、真っ黒いタコが立っていた。
町の人々は薬局の新しいマスコットくらいに思っているらしく、見向きもしないでいる。
「町中にモンスターを忍ばせるとは、魔界の脅威が拡大しているね」
「すっげえ地味な侵攻だな」
今は擬態しているだけだし、放っておいてもいいんじゃないかとも思ったが、とりあえず薬局の向かいからしばらく観察しようということになった。
杖をついている老人が歩いてくると、タコはさりげなくその杖の先を掬ってバランスを崩させている。
「千早、あのモンスターは危ない。人間に害を成しているから倒さないと」
「マジかよ魔王軍。もっと他にやることあるんじゃないのか。嫌がらせレベルだろあれは」
僕には魔王とやらが何を考えているのか、さっぱり分からなくなってきた。いっそミカゼが勇者の活動を止めてみてもいいんじゃないかとさえ思えてくる。案外、世界は何も変わらず、今まで通りの日々が続いていくのではないか。
だが黒土から聞いた話によれば、ミカゼに阻止されなければ校庭に巨大なメタルゴーレムを召喚して町を破壊しつくす予定だったらしい。やるべきところではしっかり恐ろしい計画を進めてくるのが魔王軍のようだ。
「だから魔界のモンスターは、見つけ次第倒していくんだよ」
「分かった。それはともかく、町で戦うのか」
「山に出るモンスターよりは大分弱いけれど、それでもあんな人の多い所でモンスターと戦うわけにはいかないよ」
「わ、私の術で別な場所に移動することができるんデス」
こうして黒土の提案で、学校の敷地内にモンスターを転送することにした。
僕たちはモンスターに逃げられることがないように、囲むようにして立った。
他の人からは、薬局のマスコットキャラクターに因縁をつける謎の高校生集団に見えそうだ。勇者の一団なのに。
「じゃあ黒土、なるべく早く頼む。行き先は屋上がいいんじゃないかな」
「わ、分かったんデス。こ、こうして魔法陣を描けばすぐデスよ」
黒土が座り込んで地面に魔法陣を描き始めた。彼女の指先が通った場所が、光で線を描くように紫色に輝いている。
突然黒土が、フギャッ、と素っ頓狂な声を上げた。
タコが黒土の方を向いて、彼女の顔に墨を吐きかけたのだ。
「め、目が見えないんデスっ!」
制服の袖で顔を拭っても、黒土はなかなか目を開けられないでいる。催涙スプレーのような効果のある、魔法のタコスミのようだった。
「千早、タコが動きそうだよ」
ミカゼに言われてモンスターを見ると、既に足を動かして歩き出し始めていた。
「黒土、早く術を使うんだ。あと線一本じゃないか」
「ま、魔法陣が見えないんデスよ」
僕は黒土の手を取り、彼女の人差し指が魔法陣を完成させるように動かした。
「黒土、魔法陣を書き終わったぞ」
「分かりましたデス。て、転送開始デス!」
黒土がそう言って地面をぽんと叩いた瞬間に、僕の視界は紫色の光に包まれた。
眩しさに思わず目を閉じるが、すぐに明るさはなくなった。黒土の言う通り、場所を移動したのだろうと思い目を開ける。
見慣れない部屋にいた。
部屋の片側には扉つきのロッカーが並んでいる。汗のような匂いがするが、少しいい香りのような気がしないでもない。
「黒土、ここは学校のどこなんだ」
「じ、女子更衣室デス」
マジかよ。
女子トイレに続き、禁断の領域に足を踏み入れてしまったようだ。僕は賢者王になるべき人間なのかもしれない。
「何でこの部屋なんだよ」
「ち、千早さんに手を握られて、少し緊張したんデス」
斜め下に視線を向けた黒土の声が小さくなる。魔界の術はそんなときめきに左右されてしまうのか。もう少し黒土の心拍数が速かったら、下手をすると壁の中にでも移動したんじゃないか。そう思うと恐ろしくなる。
「千早、場所のことを考えるより、まずモンスターを倒そう」
ミカゼのその言葉で、僕は気を取り直して、モンスターに向かって身構えた。と言っても、相変らず僕にできそうなことと言えば、モンスターから離れることなのだけれど。
入り口を塞ぐようにミカゼが立っていて、彼女の前にはタコのモンスター。モンスターの背後を取るようにして、僕と黒土がいる。
タコの足がミカゼに襲い掛かるが、伝説の盾が衝撃を完全に受け止める。ミカゼは全く体勢を崩すことなく、盾を使ってタコを壁際に弾き飛ばした。僕は、攻撃の呪文でミカゼを援護できるように移動した。
ミカゼが盾を構え、グラディエイターのようにタコに突っ込んだ。そしてタコを逃がすまいと、壁際のタコを盾で押さえつけ、動きを封じる。
……目が見えずに逃げ遅れた黒土を、タコと壁に挟みつつ。
「む、むぎゅっ」
潰れた黒土の肺から空気が漏れる。
「ぬ、ぬるぬるするんデス。ぐ、ぐええ」
「黒土、タコは柔らかいから大怪我はしないはずだ。少し我慢するんだ」
「(は、はいデス……)」
息を吸えないのか、黒土の声が聞き取れないくらいに弱々しくなってしまった。彼女の手が、ギブアップとばかりに壁をタップする。黒土には酷なことだが、武器を持たないミカゼはすぐにモンスターを倒せそうにない。
ミカゼが開いている手でモンスターを殴りつけた。助走も何もなし、腕の振りだけのフックだが、キレは鋭い。もし僕が受けたら肋骨を持ってかれそうな、プロボクサー顔負けの打撃だ。
何度か小気味のいい音がした後に、ミカゼが口を開いた。
「まずい」
「えっ、一方的に勝てそうに見えるんだけど」
「タコの防御力が高すぎてダメージが入らないんだよ」
素手のミカゼの攻撃力では、タコの生命力を減らすことができず、時間をかけても倒せないらしい。
「魔法攻撃とかは」
「この位置だと黒土さんを巻き込むよ」
どう見ても黒土よりタコの耐久力の方が高そうだ。こんなところでタコを倒すために黒土を失うわけにもいかない。
そしてもっと大事なことに僕は気づいてしまった。
早くモンスターとの戦いを終わらせないと、誰かが女子更衣室に入って来てしまう。そうなってしまっては賢者どころではない、ただの犯罪者だ。
そもそもタコを黒土ごと壁際に押さえつけたままのミカゼも異様だ。大騒ぎになってしまう。
「タコを消す呪文とかないのかよ、タコ消し呪文」
「あるけど千早の強さだと、まだ使えない」
あるのかよ。
アンデッドモンスターを浄化する呪文が存在することは知っていた。それのタコ版だろうか。
イカをピンポイントで消す魔法もあるのかと興味をそそられるが、いずれにせよ今は使えないので、タコを何とかする方法を考えなくてはならない。
そうしている間にも、黒土の手が、力なく垂れ下がる。
「千早、黒土さんが」
「黒土が力尽きたならもう心置きなく魔法をぶっ放せるか」
「そ、それは火葬と言うんデス。ま、まだ生きてるんデス!」
息も絶え絶えの黒土から返事があった。
「なんだ、まだ生きているじゃないか」
「千早、真面目に考えて」
「スマン。僕は難問にぶち当たると現実逃避してしまうようだ」
まずミカゼが力を緩めた隙に、黒土さんを引っ張り出そう。僕はそう提案した。
僕が彼女達に近づいて黒土の手を握り、ミカゼが頷く。
「じゃあいくよ、いっせーの……きゃっ」
ミカゼの掛け声が終わるよりも早く、隙を窺っていたタコがミカゼに足払いをかけた。ミカゼは転びはしなかったけれど、後ろに下がってしまう。
ぐにゃぐにゃと八本の足を動かして、タコが入り口に向かう。
丁寧に吸盤を使って引き戸を開け、モンスターが廊下に出て行ってしまう。
「油断した」
そう言いながら、ミカゼがそれを追って出て行く。僕もこのままここにいたのでは停学処分になってしまうので、その場に黒土を寝かせると女子更衣室を後にした。
物理的にもそれ以外にも色々危険だった。危険手当が欲しいなと思った。
廊下に出てすぐに、ミカゼとタコを見つけることができた。
中間テスト前で、ほとんどの部活が活動していなかったのが幸いした。廊下には生徒がいなかった。今のうちにモンスターと決着をつけてしまいたい。
ミカゼは走りながら、魔法を使った。
「炎の鏑矢(カチューシャロケット)!」
賢者の補助魔法と違って、攻撃魔法はかなり様になる。ミカゼは胸の前に両手を突き出し、校舎に被害を与えないように出力を最小限にした炎の矢を作り出す。
だが魔法を射出する直前に、ミカゼに向かってモンスターが魔法の墨を吹き掛けた。視界を奪われながらも、ミカゼは魔法を撃つ。
照準の外れた炎の矢はタコ焼きを作るには至らずに、モンスターを掠めて薄暗い校舎の壁を橙色に照らして飛んでいく。
そして廊下の壁にある伝言板の、英語課題未提出者のリストを焼いて、ミカゼの魔法は消滅した。確かあの紙には、根岸ただ一人の名前が書いてあったはずだ。哀れな根岸は課題を出していないことに気づかず、英語の単位を落としてしまうことだろう。モンスターの被害者がさっそく一名増えてしまった。
「こうなったら広範囲魔法を使うしかないかな」
「校舎がぶっ壊れる、止めた方がいい」
大魔法の構えを取るミカゼを制止した。本職の魔法使いじゃないとはいえ勇者の使う上位魔法は、殺傷半径三十メートルと言われるロケットランチャーと同程度の威力を持つ。そんなものを学校で使ったら、それこそ大事件になってしまう。
「墨を避けて追いかけつつ、僕が魔法でちまちまタコにダメージを与えていくしかないか」
「千早の魔力が切れる方が早いと思う」
「万事休すだな」
僕が顎に手を当てて悩んでいると、僕達の後ろから、誰かがやってくる気配がした。今まさに、この廊下に差し掛かろうとしている。
このままでは、モンスターと戦っているところが見つかってしまう。僕は咄嗟に、この場を誤魔化すための言い訳を考え始めた。演劇部の練習中という設定でいくしかない。
僕はタコに向かってファイティングポーズを取り、適当に思いついた台詞を喋った。
「おのれ竜宮城からの刺客か! 姫は渡さんぞ!」
「私は勇者だよ」
打ち合わせなしで演技を始めたため、ミカゼが合わせてくれなかった。
「合わせてくれよ。大女優なんだろ」
「勇者だよ」
「今僕が何をしようとしてるか分かるだろ」
「モンスター退治」
「もうだめだ」
はっきりモンスター退治などと言ってしまった。キングサイズのタコの姿も誤魔化しようがない。せめて、廊下に来た人を避難させよう、僕はそう思った。
「何がもうだめなんじゃ」
背後から聞き覚えのある声がした。この独特な話し声を聞いて、声の主を間違えようがない。曲がり角から出て来たのはヒメナ先輩だったのだ。
「ぬふふ、やはり千早とは切っても切れぬ縁があるようじゃ。モンスターと戦っている所に出くわすとはのう。わしが助太刀してやろう」
この展開は、どう考えても、ヒメナ先輩を仲間にする流れだ。
「もうだめだ……」
「わしの力が必要そうではないか。ははは、任せておけい、こんなタコなんぞわしにかかれば一刀のもとに両断じゃよ」
そう言いながら、ヒメナ先輩はすらっという音と共に、さも自然な動作で刀を抜いた。
「千早、この人は?」
「僕の先輩だよ。『サムライ』らしい」
僕はミカゼにそう説明する。それだけで済ませたかったけれど、ヒメナ先輩がつけ加える。
「わしは千早の愛しい愛しい恋人じゃよ」
「えっ、そうなの?」
知らなかった、とミカゼが僕に色々聞きたそうにする。
僕はため息混じりに否定した。いきなりこの言いようである。
ヒメナ先輩は冗談に聞こえない時に、冗談を言ってくるのだ。剣術では相手の死角を突くことが重要だけれど、それを日常会話にまで応用しないで欲しい。
それにヒメナ先輩はさっき縁だとか偶然だとか言っていたけれど、ずば抜けた勘で僕達がここでモンスターと戦っていることを察知したのではないか。想像が次第に確信に変わていってしまう。
もっとも、この状況で選り好みなどしてはいられない。
「それじゃあ、このモンスターを倒せばいいんじゃな」
「そうです。お願いします」
僕は半ばやけくそ気味に、ヒメナ先輩に答えた。
モンスターを見るのはおそらく初めてであるはずなのに、不敵な笑みを浮かべて、ヒメナ先輩がタコに近寄っていく。動きだけをみて彼我の戦力差を分析したのかもしれない。
先に動いたのはタコだ。墨を吐いてきたが、ヒメナ先輩はそれを避けもしなかった。しかし、墨は彼女を通り抜けでもしたかのように、放物線を描いてから床に落ちて飛び散った。
僕には見えなかっただけで、彼女はちゃんと、避けていたのだ。あまりにも速い、必要最低限の動きで。
次にタコは、ヒメナ先輩へ近づき、鞭のように足を繰り出した。彼女は正確に、刀で攻撃を受け流した。
攻撃を防がれたタコがじりじりと後ろに後退していく。
「魔界のモンスターも、大したことはないのう」
ヒメナ先輩はタコに向かって踏み込んだ。どうやったのかが分からないほど早く、たった一歩で数歩分の距離を詰める。
刀がタコに向かって垂直に振り下ろされる残像が微かに見えた。
モンスターがタコ刺しに姿を変える。そう思った。
だがモンスターの断末魔ではなく、打撃音とヒメナ先輩の声が廊下に響いた。
「ギャフン!」
「えっ?」
左手だけで刀を持ったヒメナ先輩が額を押さえながら、二歩、三歩と下がった。彼女の額には、マジックで書いたような一本の赤い筋が浮かび上がっていた。
ヒメナ先輩がタコの反撃を受けたのだろうか。瞬間移動に近い彼女の剣技を、いきなり本気を出したタコのモンスターが上回ったとは思えない。
どうしたんだろうかとヒメナ先輩を見守っていると、彼女は顔を上げ、
「なんじゃ、こやつは。固すぎじゃろう」
と言って、刀でぺいんぺいんとタコの頭を叩き始めた。不機嫌になったタコが墨を吐きかけるが、ヒメナ先輩はそれをひょいひょいと避けている。
「弾力で跳ね返されたんですね」
「そうじゃ。わしが両刃の剣を使う戦士だったら、今頃は棺桶に片足を突っ込んでいるところじゃったぞ」
タコの防御力は、ヒメナ先輩の剣技も通用しないほど高いようだった。だけどヒメナ先輩が弱いわけではない。
戦士や賢者などは『勇者の仲間』になるまでは能力を最大限に発揮できない。役所で誰の仲間になるのかを登録することで初めて、モンスターに大ダメージを与える攻撃や、呪文を使うことができるようになる。
「千早、その人を私の仲間に登録しよう。『村人』じゃないなら戦えるはずだよ」
「登録しても攻撃が通じなかったら?」
「それはその時にまた考えるよ」
「今から市役所に行って帰ってくるまで、誰かがタコを足止めしてなきゃいけないのか」
なんだかとても大変そうだ。しかしモンスターを放っておくわけにもいかない。
僕は市役所までの時間はどれくらいかと考え始めたけれど、すぐにミカゼの声に中断させられた。
「千早、その必要はないよ」
そう言いながら、ミカゼはスカートのポケットからスマートフォンを取り出した。墨で目が見えないから千早が操作して、と言って僕に渡してくる。
「仲間登録アプリがあるはずだからそれで登録して」
「スマホからできるのかよ」
ミカゼに言われるままにスマートフォンを操作してしてアプリを起動する。仲間を追加する入力画面を開いた。
どういう仕組かは分からないが、ヒメナ先輩の名前と電話番号、生年月日を入力するだけで、勇者の仲間としての力が使えるようになるらしい。でもこれは突っ込むべきところではないはずだ。神話に登場する占星術師は、星の満ち欠けと生まれた日だけで、英雄や国王の運命に神秘的な影響を与えていたという。現代においてはそれがアプリ化されているだけだ。
情報技術の進歩は恐ろしいことに、神秘的要素までも無機質なディジタルの仕組みに変えてしてしまったようだ。数百年前に偉い人が、神は死んだっぽい、と言ったらしいが、頷ける話だ。
タコの足を踏んで動きを封じているヒメナ先輩から誕生日などを聞いて、アプリに入力していく。
「入れ終った。えーと、あと最後の秘密の質問と答えを入れるところがある」
これは本人確認というやつだろう。他人が勇者の仲間を登録できないように、ミカゼしか知らない組み合わせの内容を入力するようになっている。
今はミカゼの目の前でアプリを操作しているので、聞いて入力しても問題はないだろう。内容と答えをミカゼに聞く。すると彼女は、口を開いたが少し困ったように
「あっ……」
と言い淀んでしまった。
「もしかして、あまり使わないアプリだから忘れたのか」
「そうじゃないよ」
「秘密の質問が銀行の暗証番号だったりするのか。僕は悪用しないけど」
「そうでもないよ」
やり取りをしている最中にも、タコは交互に足を振って絶え間なくヒメナ先輩を攻撃する。いつの間にか脇差を抜いて二刀流になったヒメナ先輩が、秒間10発以上の連打を捌き続ける。彼女の人間離れした守りに驚かされるが、それがいつまで保つかは分からない。
「はやくするのじゃ、登録した瞬間にモンスターをぶった斬るわ」
「ミカゼ、早くしてくれ」
ミカゼは、うーっと唸る。このように取り乱す彼女はかなり珍しい。どうしたのだろうとミカゼを見ていると、突然タコに背を向けて走って行こうとする。
「「ええーっ?」」
ヒメナ先輩と二人で、やけに長い疑問符をハモってしまった。どういうわけか勇者が逃げ出したのだ。
突然の出来事に反応が遅れてしまったが、このままではヒメナ先輩がモンスターに負けてしまう。早くアプリへの入力内容を聞き出さなくては。ミカゼを追って僕も慌てて走り始めたものの、俊足のミカゼに追いつけるかは正直、自信がない。
その時、ミカゼの目の前に突如、黒土が出現した。
「や、やっと目が開くようになったんデス!」
などと言いながら、タコと戦うべくやる気満々で女子更衣室から飛び出してきたのだ。
ミカゼは視界を失ったまま走っているために黒土に気づかず、黒土にはミカゼを避ける反射神経があるはずもなく、
「うわっ!」
「ぎ、ギャッ!」
両者は綺麗に衝突した。黒土が何メートルか吹っ飛び、どこまでも廊下を転がっていく。
「ナイスブロッキングだ、黒土っ!」
僕は黒土に呼びかけるが、返事が返ってくることはなかった。
頭を押さえて膝をついているミカゼに駆け寄る。
「ミカゼ、秘密の質問を教えてくれ」
少しためらうが、また逃げられても困るのでミカゼの手首を握る。このままだとモンスターが倒せないと言うと、ミカゼは先ほどと同じように少しだけ唸り、
「……パンツの柄っ! 猫っ!」
そう大きな声で僕に告げた。僕の手を振りほどいて、廊下を走って行ってしまった。途中で黒土を踏んでいったのは、まだ視界が戻っていないせいだろう。
パンツの柄は、猫。なるほど自分しか使わないと思って適当過ぎるものを設定していたようだ。
僕はミカゼのスマートフォンに内容を入力しながらヒメナ先輩の所へ戻る。パンツの猫とはワンポイントなのか、それとも布地の柄なのだろうか。この状況で深く考えるわけにもいかない。賢者として知識を追求するのは後回しだ。
僕はさっさとアプリの送信ボタンを押した。
スマートフォンの画面が切り替わり、登録完了と表示された。ヒメナ先輩の刀が青い光を帯びる。どうやら勇者の仲間の力は登録してすぐに使えるようになるらしい
「ヒメナ先輩、もう登録されましたよ」
と僕が言うのと、タコが上下左右から足でヒメナ先輩を攻撃するのと、ヒメナ先輩がにやりと口元を曲げて踏み込むのは同時だった。
ヒメナ先輩の一閃。それだけにしか僕には見えなかったが、タコの足は八本全てが本体から切り離された。
「ふん、通りさえすればこんなもんじゃ」
ヒメナ先輩がそう言い、さらに刀をひゅんと振る。タコは真っ二つになった。魔界のモンスターに共通の法則で、タコは炎に包まれて消滅していく。
「千早よ、やはり仲間の力を必要としておるではないか」
楽しそうに目を細めながらヒメナ先輩が僕にずい、と寄って来る。
「ヒメナ先輩、近いです」
「近づいておるんじゃよ」
この人はいつも僕に対して、妙に馴れ馴れしい。なんとなく苦手な原因はそこにある。
戦力としては文句のつけようがないはずだが、勇者ミカゼのパーティが色々と引っ掻き回されそうな気がしてならない。
「ひとまず、ミカゼを探しに行きましょう」
僕はそう言って歩き出した。うっかりミカゼのパンツについて知るところになってしまったが、なんとなく帰りにファミレスでパフェでも奢ったほうがいいような気がする。
「わしもパフェが食べたいのう」
「ヒメナ先輩、心を読まないでください」
「む、むぎゅっ」
動揺した僕は、廊下に転がったままの黒土をもろに踏んづけてしまった。
その後、強い仲間が増えたからいい、というミカゼの発言により、ヒメナ先輩を仲間に加えることが正式に決定した。
タコ退治の次の日。
昼の女子トイレで、勇者のパーティは弁当を食べる。今までよりも一人、増えていた。
ヒメナ先輩は、元々いくつか魔法を知っていたせいか、それとも彼女の適用能力が高いせいか、この異様な昼食にもすぐに溶け込んでいた。
「例えばの、茶碗に小便を注ぐとするじゃろう?」
「ヒメナ先輩、その話は僕がこの前しましたよ」
「なんじゃ、知っておったか」
「こ、孤独だった昼のトイレが、賑やかになってきたデス」
「僕はだんだん、ここが食堂に見えてきたよ」
初対面なのでよくは分からないが、彼女たちの相性は決して悪くないだろうと、僕は考えていた。学年が一つ上だというのに、違和感なく便所飯の輪に入っている。黒土が死神であることもあっさりと見抜き、なお平然と話をしているくらいだ。
「ヒメナ先輩は」
とミカゼが口を開くと、ヒメナ先輩がそれに重ねた。
「ヒメナでよいぞ」
「分かった。ヒメナは、どうして私とパーティを組むことにしたの?」
「千早の助けになるからじゃよ」
「僕ですか?」
「千早なら、何も言わずに力を貸すに値する。それで間違いは起きまい。わしはそう思っとるぞ」
「ち、千早さんはすごく信頼されているんデスね」
僕のほうは人のいい先輩だなとしか感じていなかったのだが、ヒメナ先輩の理由は、なんとも大げさだ。僕は自分をそこまでの人間だとは思っていない。
ミカゼが、一瞬だけ憚った後に、口を開く。
「ヒメナは、千早のことが好きなの?」
ドストレートすぎる質問だった。
ヒメナ先輩が言うことなら、ある程度聞き流すことができる。しかしミカゼの口から好きかどうかなんて言葉が出たものだから、僕は驚いて固まってしまった。
無意識のうちに『鯛焼きパン』を持つ右手に力が入った。哀れな鯛の口から、粒あんがぼろぼろと吐き出される。
「すごい照れくさくなる質問をするんだな」
冷静を装ってようやく口に出したが、僕は裏声になりそうだった。
黒土は、この場にいる者全員を、交互に何度も見ている。あの調子で視線を動かしたら、すぐに目を回すことだろう。
「無論、わしは千早が好きじゃよ」
「物凄い速さで直球を投げ返しますね。はっきり回答をしないでください」
「わ、わ、こ、これは」
何故かにやけながら黒土は立ち上がり、トイレの個室に入ってバタンと扉を閉めた。僕もそうしてしまいたいくらい恥ずかしかった。
「ヒメナ先輩、またからかっているんですか?」
からかってなどおらぬよ、と言うヒメナ先輩は、やはり筆で書かれた曲線のような細い目で笑っている。
からかっていないとしたら、なんで僕が好きだということになるのか。同じような疑問が再び出てきてしまった。
「雪が舞うのは美しいじゃろう。桜が散り、風に舞うのは美しいじゃろう」
「ええ、まあそうですが」
「人間はの、誰かが得をするときに、機械などで人工的に雪を降らせるじゃろ。桜が風に舞うのを見て、その景観に金を出す人がいるから木を植えるじゃろう。大雑把に言ってしまうと、得をするために美しい雪や桜をつくるのじゃ」
「花は見て楽しむ人が自分の満足のために植えるかもしれないですが、大体そうですね」
「雪や桜は、あんなにも美しいが、誰が得をするのかなんて関係がなく、広大な山に降っているのじゃよ。大きな風が吹いて、桜の花びらが散って舞うのは、誰のためでもない。ただそこにあるだけなのじゃ。わしはそれが好きでのう」
「それと千早とはどう関係があるの?」
「うむ、わしが千早と知り合った後に、こいつはわしの太ももを見ていたのじゃ。他の女子の足もみていたがの」
ええ、見ていましたとも。
「その時、千早はこう言ったんじゃよ」
僕が昔言った言葉を、ヒメナ先輩が暗唱する。一字一句が全て同じというわけではないが、同じ意味で。それは「女性の足は美しいです。足の曲線の美しさは、誰に見せるためでもなく、その形ができて、ただそこにあるだけなんです。花や星空が人の心を動かすのと同じように思いますよ」という内容の台詞だ。まさかこんなところでミカゼや黒土に聞かせるために言ったことではないので、恥ずかしい気分になる。
「こやつ、わしと同じようなことを考えておる。と、その時に気に入ってしまってのう。わしはこれから先、千早の言うことは信頼してやろう、と思ったんじゃよ」
「似たような考えの人は沢山いるじゃないですか」
「無論、それだけではない。じゃが、切っ掛けはそんなもんじゃよ。人と人との関係はのう」
ヒメナ先輩はそこで一旦言葉を切ると、口元を綻ばせながら静かに、
「千早、好きじゃよ」
と言った。黒土が個室の中でドアに頭突きをかましているらしく、バアン! バアン!バアン! という音がトイレに響く。人を信頼する理由については本当かもしれないが、やはりヒメナ先輩は僕や黒土で遊んでいる。
やがて、がちゃりと個室のドアが開いて、額から出血した黒土がふらふらと出てくる。お前はプロレスラーか。そのまま黒土はレジャーシートの上にふらふらと沈んだ。
「どうじゃ、今の答えで満足したかのう」
ミカゼは、ぽかーんとした、軽く口を開けた表情のままヒメナ先輩を見つめていた。首を傾げて、うん、と短く頷いた。
それから、昼食を再開した。ヒメナ先輩は、倒れている黒土を、箸で突いたりして遊んでいた。トイレ全体が殺菌済みなので、汚くはないだろう。
放課後、ミカゼを乗せてモンスターを倒しに行こうとして気がついた。僕の自転車は定員二名である。
「わしが黒土を担いで曲乗りをすれば全員乗れなくもないぞ」
「やめてください。勇者のパーティは雑技団じゃないんですよ」
パーティの皆で歩いて行こうか、なんて話をしているうちに、いつの間にかヒメナ先輩の自転車に黒土が乗ることになり、二台で山に向かうことが決まった。
二人乗りの自転車が並んで走っているというのも、人目を引きそうではあるけれど。
黒土は当然、ミカゼほど運動神経がよくない。むしろへっぽこな方なので、ちゃんと自転車に跨がり、ヒメナ先輩の胴に、しがみつくように腕を回している。
「ほれほれ、落ちぬように、ちゃんと掴まっておれよ」
「ん、んぎゃあああ! ひ、ヒメナさんこれ自転車の動きじゃないデスよ!」
「じゃが、実際に動いておるじゃろう」
ヒメナ先輩は、マウンテンバイクでもない普通の自転車に乗っている。それなのに全速力でヘアピンカーブをしたり、真横に近いくらいまで車体を倒したりと、驚異的な高機動で僕の周りを走っている。絶叫マシーンばりの揺れで黒土が慌てふためく姿に、とても満足しているようだ。
「千早は真似してはいかんぞ、これは秘伝の技、達人にしか扱えぬのだ」
「えっ、それ剣術なんですか。てかその乗り方、真似できる人いないですよ」
涼しい顔で、ヒメナ先輩は前輪を持ち上げると、自転車を凄まじい速度で回転させた。本当に人間が乗っている動きなのだろうか。
ヒメナ先輩が稲妻のような走りをしたところで、黒土がぐったりと力を失った。
「ブラックアウトか、恐ろしいな」
高速で飛行する戦闘機パイロットは、あまりにも急激な旋回や加速によって発生する負荷に心肺機能が耐えられず、失神することがあるという。
「千早、私は黒土さんがただ恐怖で気絶しただけに見えるよ」
僕の後ろで、ミカゼが静かに呟いた。
放っておくと黒土がどこかに吹っ飛んで行きかねないので、僕たちはいったん停車し、なるべく直線で走って下さいとヒメナ先輩に言い聞かせた。
さっきよりは体に優しい走り方になった。
「は、はっ。か、河が見えたんデス」
「それは渡ってはいけない河だな。死神でもちゃんとそこに行くのか」
「そこで泳いででも来ればよかろうに」
「むしろヒメナは黒土さんを河に突き落している」
「ヒメナ先輩、あなたミカゼにすら突っ込まれてますよ」
そしてミカゼは何故か得意げだ。上手いことを言ったつもりなのか。
「ひ、ヒメナさんの自転車に乗るのは命がいくつあっても足りんデスよ! ち、千早さん、そっちに乗せてください、そっちがいいデス!」
なんという悲痛な懇願だろう。よほど先ほどの体験がトラウマになっているようだ。ただでさえ黒土は気が小さい。あのような心臓に悪い自転車の動きには、ミカゼの方が相性がよさそうだと思った。
「後ろ、交換するか」
「は、はいデス! こっち、小学生以下のお子様が乗っちゃいけないやつデスよ」
「わしは遊園地のアトラクションではないぞ」
そもそも、黒土も小学生じゃないのに。
「ミカゼはヒメナ先輩の自転車に乗って、前衛のセットだな」
僕はミカゼと黒土を乗せ換えるために減速しようとした。
その時、急に自転車が傾いた。
ミカゼが荷台を掴んで身体を倒し、自転車の重心を限界まで横移動させていたのだ。
慌てて立ち乗りでペダルを踏み、ハンドルを曲げて自転車の傾きをなくすように走った。 ライトの光が、捕食者から逃げる小動物の様に左右に動く。
蛇行させられた自転車が、道路標識のついた白い鉄柱に接触しそうになった。
「うわっ、危ないだろ」
「千早の自転車も危ない」
「ミカゼが危なくしているんじゃないか」
強い荷重をかけられた荷台が歪む音が聞こえてくる。使い古された僕の自転車は、勇者の攻撃に耐えられるのだろうか。
「黒土、ミカゼは交換したくないみたいだ」
「違うよ。今日は風が強いだけ」
「僕には無風にしか感じられないんだけど」
そして黒土からは返事がない。どうしたのかと彼女を見ると、首の座ってない顔から、遠心力に引っ張られて涎が伸びている。また気を失ったらしい。それでもヒメナ先輩の胴をしっかりと掴んでいるようだった。死後硬直ではない、と信じたい。
「これ、交換しなくてもよいかのう」
「もうそのまま、寝ているうちに運んであげて下さい」
黒土には悪いけれど、仮死状態で山まで運んでしまうことにした。彼女がまた一歩、アンデッドモンスターに近づいたな、と思った。
またミカゼが自転車を傾け始める。
「僕の自転車でアクロバットしないでくれ」
「千早が転びそうになっても、私が立て直すから大丈夫だよ」
「そうじゃなくて、荷台が壊れて落っこちたら、ミカゼが怪我をするだろ」
勇者にとって、膝を擦りむいたくらいが、ダメージを受けたうちに入るのかは怪しいところだ。それでも彼女の美しい脚が傷んでいるところは、あまり見たいものではなかった。
僕の言葉に対して、少しの間ミカゼは無言だった。やがて、
「うん」
と答え、あっさりと姿勢を戻した。勇者はジャイロスタビライザーでも積んでいるのか。
ヒメナ先輩の刀は、勇者の持つエクスカリバー同様に、うっすらと自ら光っていた。彼女の刀もまた、伝説の武器なのだろう。
「陸奥守吉行改、幕末の勇者たちが所持していた刀じゃよ」
サムライのヒメナ先輩にそんなことを言われると、もしかして幕末を生きた志士達や新撰組は勇者の一団だったのではないか、などと考えてしまう。
色々ヒメナ先輩に訊ねたくなったが、僕は口を閉じたままにした。あっさりと「そうじゃよ」なんて返されたら、これからの日本史のテストで先生に怒られる回答を連発してしまいそうだ。黒船には魔王軍が乗っていた、なんて。本当に乗っていたんじゃないか、という気がしてくるのが悩みの種だ。
ヒメナ先輩は自信満々に刀を構えた。
「ワイバーンじゃろうが一つ目の巨人じゃろうが、わしの相手ではないぞ」
そう言ってヒメナ先輩は、見せつけるかのように素振りをした。星空の暗がりの中、刀の残像が煌めく。
道場で何度か見たことのある剣の動きだった。三段突き。幕末時代にいたトップクラスの剣豪が遣った技だとヒメナ先輩が言っていた。僕のような常人には、一度の突きにしか見えない動きで、複数回の攻撃を仕掛けているようだった。
「ふふん、どうじゃ。人型のモンスター相手ならば、秒殺してくれるわ」
「そろそろ魔界のゲートが開くよ」
ミカゼが言った直後、いつもの場所に紫色の炎が広がる。
魔界のゲートから現れたのは、粘液に包まれた薄茶色の体表を持つ巨大な蛞蝓(なめくじ)だった。サイズはマンモス象と同じくらいだろうか。
このモンスターをミカゼが何度か倒すところは見たことがある。強力ではあるらしいが動きは緩慢で、竹槍の先に括りつけたエクスカリバーで一撃であることには変わりがなかった。
ヒメナ先輩の刀の攻撃力がいかほどなのかは分からないが、彼女にとっても大して難しい戦いではないだろう。僕はそう思って、彼女の方を見た。
さっきまでヒメナ先輩がいた場所には、誰もいなかった。
「あれっ?」
「ぶっひゃーーーー!」
ヒメナ先輩は甲高い奇声を発しながら後退していた。
「ど、どうしたんデスか?」
「わし、わしは、蛞蝓だけはどうしてもだめなんじゃよ」
先ほどまで自信満々だったヒメナ先輩が、青ざめている。突き出すように持った吉行がぷるぷると震えている。冗談ではなく苦手らしい。
「えっ、こんなに可愛いのに」
「ミカゼ、僕は可愛くはないと思うけど」
蛞蝓の体表は大小の突起で覆われ、うねうねと蠢いていた。僕はヒメナ先輩が怯えるほどの嫌悪感を感じなかったが、コミカルな可愛さもないなと思っていた。
「ぬぬぬ、わしは嫌じゃ、帰る、帰るぞー」
天に向かってそう叫び、ヒメナ先輩は背を向けて帰ろうとする。その腕をミカゼが掴んで止めた。
「この蛞蝓を倒すことのできる戦力は、ヒメナしかいない」
「無理じゃ、あんな大きいのは無理じゃー」
「ヒメナ先輩、落ち着いて下さい。刀を構えて進むだけでいいですから」
伝説の武器の攻撃ダメージなのだ。多分全力で斬らなくても、すぐにモンスターを倒せるはずだ。
「刀越しに触れるのも嫌じゃよ。刀を貸すからミカゼがやっとくれ」
「その装備、サムライの専用装備だよ」
まさかあの無敵のヒメナ先輩がこんなに怯えるほど苦手なものがあったとは。僕とミカゼは、ヒメナ先輩の恐怖を和らげる方法を考えることにした。
僕が二人羽降りの要領でヒメナ先輩の手を支える。手でも握っていれば落ち着くだろう。そしてさらに僕の後ろからミカゼが手を伸ばし、ヒメナ先輩の目を手で覆い隠す。蛞蝓が見えなければいいはずだ。
「な、なんか子供の頃やった電車ごっこみたいなんデス」
「これは遊びじゃないよ。魔王軍と戦うためのフォーメーションだよ」
僕達は足並みを揃えて、かたつむりのようなスピードで蛞蝓に向かって進んでいく。
女の子二人に挟まれて動くというのは、高い精神力を必要とする。あの柔らかい感触は一体どの部分なんだ。そんな雑念が右脳と左脳を何度も往復するが、ここで呼吸を乱せば、勇者のパーティの連携攻撃は失敗してしまう。
落ち着いて深呼吸し、ヒメナ先輩の長い髪から漂ういい匂いを、なんとか無視する。
このまま前進すれば蛞蝓を倒せる。そう確信した矢先に、突如ヒメナ先輩は僕とミカゼを振り払った。敵に背を向けて逃げ出した。
「やっぱり無理じゃーっ!」
「ヒメナ先輩、そんな弱点があるなら教えておいて下さいよ!」
「千早よ、強い者はのう、身を滅ぼすようなことを簡単には言わぬのじゃよ!」
「もっともらしいことを逃げながら言わないでください」
僕はヒメナ先輩を追いかけるが、足元が暗いせいで小走りくらいの速さにしかならない。対して、ミカゼの動きはとても素早かった。暗い草地であるというのに、あっさりとヒメナ先輩の正面に回り込む。そのまま腰を低くし、クワガタ虫のように腕を伸ばして跳躍した。
ドゴッ。
「ぐはーーーーッ!」
どうしてモンスターから受けるダメージよりも同士討ちの被害の方が大きいのだろう。完璧なフォームのタックルを鳩尾に受けたヒメナ先輩が、打ち上げられた魚のように地面に跳ねる。
「千早、縄を出して。エクスカリバーに使ってたやつだよ」
そう言われて、僕は鞄から、竹槍と聖剣を組み合わせる時に使っていた縄を出した。ミカゼはそれで、倒れたヒメナ先輩を縛り上げる。
「何をするんじゃ、やめるんじゃーっ」
強力な部類のモンスターであるはずの蛞蝓は、緩慢な動きで僕達のことを見下ろして、首を傾げるように顔を斜めにしていた。モンスターが見守る中、ヒメナ先輩が誘拐された人質のようになっていく。
万歳をするような姿勢に伸ばされた手に、ミカゼが吉行を握らせ、その上から縛って固定した。刀身がうっすらと光り、装備の効果が発揮されたことが分かる。
ヒメナ先輩は何らかの呪詛まで叫び始めた。
静かにさせよう、というミカゼの指示で、黒土が蛇を呼び出してヒメナ先輩の口に突っ込んだ。もがー、もがーという声を聞くと、なんだか少し可哀想になってくる。
「千早、手伝って」
というミカゼの言葉に従い、彼女や黒土と共に、簀巻き状態のヒメナ先輩を抱える。門を破るための中世の攻城兵器のようだ。
「歩調を合わせて蛞蝓に突っ込むよ」
「ら、らじゃーデス!」
ぐるぐる巻きにされたヒメナ先輩はそれでも逃げようとして、背筋を曲げたり伸ばしたりして、蛞蝓のように動いている。
モンスターに向かって、ミカゼのパーティは破城槌……ではなくヒメナ先輩を抱えて前進し始めた。
だが途中でヒメナ先輩が暴れたため、黒土が躓いてしまった。急に重さを感じた僕が踏ん張り、そのせいでミカゼが手を滑らせた。
「「「あっ」」」
僕達は、ヒメナ先輩を落っことしてしまっていた。
ゴンッ
「ふぎゃっ」
地中に石でも埋まっていたのか、地面にぶつかったヒメナ先輩の頭から大きな音がした。
「うおっ、ヒメナ先輩が痙攣してるぞ」
「でも大人しくはなったみたいだよ。今のうちに蛞蝓を倒してしまおう」
「お前は鬼か」
「勇者だよ」
僕たちは再びヒメナ先輩を持ち上げ、蛞蝓に向かって構えた。
ついこの間までは竹槍を括りつけたエクスカリバーで、勇者が一人で倒しているのを眺めるだけだった。やっと勇者と協力してモンスターを倒すことができることになり、少し感慨深い。僕たちは吉行を括りつけたサムライを構えた。
「ま、また滑ったんデスっ!」
モンスターを攻撃しようとしたところで、黒土が枯葉に足を取られた。
「「「あっ」」」
僕が黒土の分もヒメナ先輩の体重を支えようとして変に力を掛けてしまう。そのせいでミカゼの手が緩んでしまった。
ゴキッ
またしても石か何かが埋まっている場所にヒメナ先輩の頭が落下して、とても大きな音がした。
「黒土、今のはわざとなのか」
「そ、そんなわけないデスよっ」
自転車であの世に送られそうになる恐怖を植えつけられた復讐に、黒土がヒメナ先輩を葬ろうとしているのではないか。二回目ともなると、そんな気さえしてくる。無意識にヒメナ先輩に大ダメージを与えることになっていたなら、それはそれで死神のセンスが抜群だ。
「ミカゼ、ヒメナ先輩がついに動かなくなったんだけど」
「刀がまだ光ってるから大丈夫だよ。勇者の仲間の力が使えるなら、死なないはず」
「伝説の武具はバイタルサインを確認することにも使えるのか」
これだけ目の前で隙を作っても、蛞蝓はじっとこちらを見ているだけだった。ヒメナ先輩が苦手な敵がスローなモンスターで助かった。だがインド象も簡単に溶かしてしまう強酸を吐くらしく、しっかり倒しておかなければならない。
そうして勇者ミカゼのパーティは、僕がヒメナジャベリンと名づけた大型の兵器を使って、巨大な蛞蝓を倒した。
攻撃力はエクスカリバーほど高くないらしく、三回ほど前後に動く必要があったので、ヒメナ先輩を縛る分も合わせて、戦闘終了までかなり時間がかかってしまった。
帰り道、夜風に髪を靡かせながら、ヒメナ先輩が不思議そうにしていた。
「何でじゃろ、記憶がないんじゃが。今日ってわしら、どんなモンスターと戦ったんじゃったっけ?」
モンスターを倒し終えたヒメナ先輩は、頭をぶつけた衝撃で何も覚えていないらしかった。
「キマイラですよ。山羊の胴体と毒蛇の尻尾を持つ獅子で、圧勝したじゃないですか。最後に記憶を消す毒霧がヒメナ先輩に当たったんですよ」
「そうじゃったっけ。なんか頭が痛いんじゃが」
「気のせいですよ。多分思い出さなくてもいいです」
僕は適当に話をでっち上げて、誤魔化すことにした。ヒメナ先輩にとっても、思い出さない方が幸せだろう。