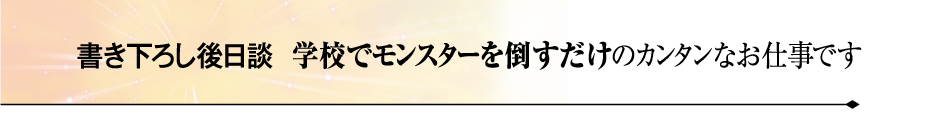冬休み明けの英語の授業中、僕は教科書に書かれた文章のうち『退屈』を意味する単語『boredom』を二重丸で囲み、ノートに落書きをしていた。
教師の言っていることがよく分からなくなってしまったので、本来ならば気を抜いている場合ではない。しかし僕は、正月気分の抜けないまま、暖房の効いた教室で授業を受け続けることに飽きてしまっていた。
この時期は、何も僕だけが不真面目なわけではなく、クラスの生徒がほとんどそんな感じだ。さぼっているクラスメートすらいることを考えると、出席しているだけまだましなのかもしれない。
三国志に登場する軍師と猫を掛け合わせたゆるキャラ『司馬にゃん』を7色のグラデーションで着色していると、どこかからスマートフォンの振動音が聞こえてきた。
僕の斜め前方、ミカゼの席からだった。いまの振動パターンには聞き覚えがある。魔界のゲートが開いてモンスターが出現するというお知らせが、市役所から送信されてきたときのものだ。
授業中に魔界のゲートが開いたことは、これまでに一度もなかった。時間帯はほとんど夜に固定されていたはずだ。僕は、年末の最終決戦の後に、魔王軍が『魔界のゲートを開く新しい術』を作り出したことを思い出した。魔王軍の行動パターンが、いままでと変わったのかもしれない。
普段と違う時間帯であっても、町にモンスターが出現したのならば倒しに行かなければいけない。だが今は授業の真っ最中だ。どうやって抜け出したものか。
勇者と関わりのないクラスメートや教師は、モンスターのことなど当然知らないのだ。
僕が悩んでいると、ミカゼの一つ前の席に座る黒土が、手で机をバンと叩いた。
すると、たちまち教師が黒板に寄りかかって、眠ってしまった。教室の皆も机に伏せ始めた。普段真面目に授業を聞いているクラスメートでさえ、ノートを取る手をとめて、寝てしまった。
この光景は、前にも見たことがある。黒土が術を使って、教室の皆を眠らせたのだ。
「黒土が仲間で助かった。連れションくらいしか出る方法が思いつかなかったぞ」
「み、皆で、しかも男女でトイレに行くなんて目立ちすぎデスよ。い、今のうちに教室を出ましょう」
ミカゼが黒土に頷いて、教室の後ろに立て掛けられていたエクスカリバーを手に取った。
エクスカリバーはモンスターに大ダメージを与えることができる勇者の装備だ。学校に持ってくるときには、賢者の特殊能力を使って目立たないようにしている。
聖剣には僕が『軽音楽部』という銘を刻んでいるので、周囲からはケースに入ったギターに見えるはずだ。かつて剣に『野球部』の刻印を入れていたこともあるが、ミカゼが常にバットを持ち歩く武闘派の女子高生だと思われそうだったので、今では偽装の内容を変えている。
廊下に出て走りながら、ミカゼに訊ねる。
「ゲートが開くまであとどれくらいなんだ?」
「アプリには5分と表示されていたよ」
いつも魔界のゲートが開く場所は、町の外れにある小高い丘だ。自転車を使っても。ここからでは30分以上かかる。
間に合わないな、と言う僕に、ミカゼが
「いや、場所は学校の中庭だよ」
と言った。
なんと、今回はゲートが開く時間だけではなく、開く場所までいつもと違うらしい。
他のクラスが授業中なので、なるべく音をたてないように走り、階段を一気に駆け下りた。
僕たちは昇降口を使わずに、校舎と学食を繋ぐ通路から中庭に飛び出した。上履きのままだったけれど、今はモンスターが現れる場所へ移動するのが優先だ。
魔界の出入り口はまだ開いていないようだった。
僕は息を整えながら辺りを見回した。授業中にモンスターと戦ったら大騒ぎになるのではないかと心配したけれど、この場所ならば教室から死角になっていて、他の生徒に見られることもなさそうだ。
僕はミカゼに、これから出現するモンスターの名前を尋ねた。
聖剣を片手持ちにして、空いた手でスマートフォンの情報を見ていたミカゼは、
「イビルアイ。戦ったことがない相手だけど、強いモンスターじゃないみたい」
と答えた。
少なくとも校舎や町に被害が出ることはなさそうだと、僕は胸を撫で下ろした。エクスカリバーを装備したミカゼの攻撃力はとても高く、炎を吐くドラゴンなどという強力なモンスターですら一撃で倒してしまう。これから戦うモンスターに手間取ることはいだろう。
ミカゼがモンスターの詳細を調べようとしたところで、中庭の気温が少しだけ下がり、冷えた空気が緩やかに移動し始めた。景観を重視するために植えられた木々の葉がそよぐ。
空中に、濃い紫色の霧が現れ、次第に広がっていく。魔界と、こちらの世界をつなげる出入り口が出現したのだ。
霧の塊が、人間一人くらいは包めそうなくらいにまで膨らむ。その中心に魔界のモンスターの姿が浮かび上がり、前進してくる。
現れたのは、健康器具のバランスボールほどの大きさの目玉だった。背中側にあたる場所から視神経のように触手が伸びているが、地面には触れていない。目玉のモンスターは、空中にふわふわと浮かんでいた。モンスターの背後にある魔界のゲートが役目を終えて、小さくなって消えていった。
ミカゼがスマートフォンを上着のポケットに納め、聖剣を両手で握る。
「イビルアイは特殊な攻撃をしてくるみたい。モンスターの動きに気をつけて」
僕はミカゼの背中とモンスターを見ながら、静かに頷いた。賢者というと、さぞかし大層な存在に聞こえるが、僕の能力値が低すぎるせいで、戦闘ではほとんど何もできない。大抵、強すぎる勇者ミカゼの後ろで戦いを見ているだけだ。
ミカゼは剣を握る両手を腰の前辺りに落とし、切っ先を斜め上に向けて構えた。彼女はモンスターに向かってじりじりと近づき、斬りかかる機会を伺う。
巨大な目玉は、見た目こそグロテスクだが、クラゲのようにゆっくりと空中を漂っているので、簡単に倒すことができそうだった。
ミカゼがいよいよモンスターに斬りかかろうと、一歩大きく踏みこもうとした。
そのとき、巨大な目玉が突然、光を放った。
ピカッ
「あっ」
「えっ」
しまった、光線による攻撃だ。特殊な攻撃を気にして慎重になっていたのが、かえってよくなかった。僕とミカゼは、巨大な目玉の光彩から薙ぎ払うように発射されたビームをもろに浴びてしまった。
「ミカゼ、大丈夫かっ」
「うん、千早は」
なんともない、と答えた。身体の痛みはない。当たった者を焼くような光ではなかったらしく、ミカゼも僕も無傷のようだった。
目眩ましだろうか、と推測したところで、何かがおかしいことに気がついた。
僕は試合中の柔道選手のように軽く腰を落とした構えのまま、姿勢を変えることができなくなっていた。
僕の数歩先で、剣をモンスターに向けたままじっとしているミカゼが、振り向かずに話しかけてきた。
「千早、身体は動く?」
「動かないな」
「さっきの光は相手を金縛りにする攻撃らしい」
「身体が動かないだけで、喋ることはできるぞ。これって魔法の呪文とかで治せないのか」
「魔力の流れも止められてしまうから、何もできないんだよ」
ミカゼが金縛りについて説明した。ただ動けなくなるだけではないらしい。
「金縛りを解くにはどうすればいんだ」
「この手の特殊な攻撃は、時間が経てば治ると思うよ」
「それって、まずいんじゃないか。それまでずっと、一方的に攻撃されてしまうぞ」
そんな会話をしていると、背後から誰かが走ってくる気配がした。
「ぜ、ぜえぜえ、や、やっと追いついたんデス。お、置いて行くなんて酷いデスよ!」
一緒にここに向かってきたはずの黒土だった。
思い出してみれば、黒土の身体能力はとても低かった。彼女には中庭まで一気に走る体力もなく、僕が気付かないうちに遅れてしまったようだ。ばらばらにここに到着することになってしまったけれど、この状況なら、むしろ都合がいい。
「あ、相手はあの大きな目玉なんデスね」
黒土が僕の脇に立ち、モンスターを指差した。そして、僕とミカゼが構えたまま動かないことに気づく。
「な、なんでモンスターを攻撃しないんデスか?」
「モンスターのせいで動けなくなってしまったんだ、いま戦えるのは黒土だけだ」
「あ、あいつが特別な攻撃をしてくるんデスね? わ、わかったんデス!」
黒土は攻撃を食らわないように、注意深くモンスターを観察した。
ピカッ
「ぎ、ぎゃっ」
目玉から放たれた光が黒土を直撃した。もし僕の身体が自由なら、落胆でがっくりと肩を落としていたことだろう。
「……目玉から出る光を浴びると金縛りになるぞ、気をつけるんだ」
「い、言うのが遅いデスよっ!」
それでも黒土は動けなくなったわけではないようで、ふらふらと歩いていた。
「あの目玉の攻撃が効いていないのか?」
「い、いえ、千早さん、私の身体が少し変なんデス」
黒土が僕の前に立って、ファイティングポーズを取った。
「黒土、もしかしてそれって」
「た、多分操られているんデス。ち、千早さんを攻撃しようとしているみたいなんデス!」
なんてこった。
ミカゼと僕は動けない、黒土は体を操られている。絶体絶命だ。ロールプレイングゲームの世界でも、この状況になった勇者のパーティは大抵全滅する。
「は、はああっ!」
掛け声と共に、黒土が僕を殴ってくる。
僕はパンチの衝撃に耐えるために息をとめた。僕よりもいくらか身長の低い黒土の拳が、胸に当たった。
ぽこ、ぽこ
まったくとして痛みを感じなかった。黒土の力が弱すぎるようだ。
「と、とりゃああ!」
ぺし、ぽす
威勢のよい声とは正反対に、黒土の攻撃が生み出したのはへっぽこな打撃音だ。何度殴られても、僕がダメージを受けることはない。
「は、はあはあ。ち、千早さん、なかなか強いんデスね」
「そんなことはないと思うぞ」
再度、黒土が僕を攻撃する。
「と、とう!」
僕を殴る黒土の手首が、関節の可動域いっぱいまで曲がり、派手な音を立てた。
こきっ
「ぎ、ぎゃああっ! い、痛いデスっ! ち、千早さん酷いデスっ!」
「僕のせいかよ」
手首の弱すぎる黒土は自爆したようだ。なお、僕はまったくダメージを受けなかった。
金縛りのせいで後ろを見ることのできないミカゼが、黒土の悲鳴を聞いて僕を咎める。
「千早、黒土さんは操られているだけだよ。いくら攻撃されたからといって、女子を叩くのはよくない」
「僕は何もしていないんだけど」
続いて、黒土は僕の制服のボタンを外し始めた。
「って、何をしているんだよっ」
「こ、これは体が勝手に動いているんデスよ! ち、千早さんは防御力が高すぎるので、下げようとしているんデス」
「まて、僕が着ているのは多分ゲームで言ったら初期装備みたいなものだぞ。制服の防御力がなくても、さっきと同じことになるんじゃないか」
黒土を説得しようとしたけれど、彼女の手はとまらない。
「ミカゼからも何か言ってくれよ」
「僅かでも防御力を下げるのは正解だよ。少しでもダメージが入るようになれば、あとは攻撃を繰り返すだけで、いつかは倒せる」
「ミカゼ、いまは黒土をとめて欲しいんだけど。僕が求めているのは勇者クイズの答えじゃない」
黒土は僕の上着を剥ぎ取ると、また攻撃してきた。
「ち、千早さんごめんなさい。と、とうっ!」
こきっ
「ぎ、ぎゃああっ!」
僕の予想通り、またしても黒土が悲痛な声を出すことになった。
「黒土さん、強い敵が現れたら、弱点を狙えばいいんだよ」
「何でミカゼが黒土にアドバイスしてるんだよっ」
ミカゼの言葉を聞いた黒土は上半身への攻撃が効かないと判断して、狙う場所を変えることにしたようだ。
「と、とう、とう」
黒土が僕の脛を蹴り始める。彼女は運動をほとんどしないせいか、力の使い方に関するセンスがないらしい。わざわざ僕に密着するように立って繰り出した蹴りは、有効打にならないどころか、まったく痛くなかった。近い方が攻撃を当てやすいとでも思っているのだろうか。
「は、はあ、はあ。ち、千早さんがまさかこんな強敵だとは」
「僕も、自分が強いと錯覚し始めてきたぞ」
「と、とう、とう……ぜ、ぜぇ、ぜぇ。め、目の前が暗くなってきたんデス」
疲労が溜まっていく黒土を見ていると、つい正しいフォームやベストな距離を教えてあげたくなってしまう。しかし、いま攻撃されているのは僕なのだ。いくら相手が黒土だとしても、急所を蹴りあげられでもしたら、確実に大ダメージを受けてしまうだろう。僕は何も言わないことにした。
しばらくすると、黒土は僕のズボンのベルトに手をかけ、外し始めた。僕の防御力をさらに下げようとしているらしい。
「黒土、それはわざとやってるんじゃないか」
「わ、わざとじゃないデスよっ」
「千早、防御力を下げないと、黒土さんがダメージを受けるんだよ」
「僕の心配もしてくれよ。よく聞いてくれ、黒土が僕のズボンを降ろそうとしているんだ。細い指が、拙いながらも黒い革製の帯を握って引っ張り、金属の留め具から解放しているんだ」
「だ、だああっ! こ、こんなことを細かく説明しないで欲しいんデス!」
黒土は恥ずかしそうに上目遣いで抗議しながら、ズボンのベルトを引き抜いた。
チャックを降ろす特徴的な響きは、ズボンを守る最後の砦が陥落した音だ。冷たい空気が僕の下半身に、直に触れる。
上半身こそワイシャツを着ているものの、その下は脛のあたりにズボンを引っ掛けた間抜けな姿になってしまった。これでは昼の中庭に出現した不審人物に見えてしまうだろう。
「は、ハートブレイクって書いてあるんデス」
「黒土、トランクスのロゴを読まないでくれ」
「ご、ごめんなさいデス」
女子がまじまじと自分の下着を見ているというのは恥ずかしく、どこかへ逃げ出してしまいたくなる。あいにく金縛りになっているせいで、僕は姿勢を変えることができない。
先ほど動けなくなる前に、モンスターに向かって、軽く開いた手を突き出すように構えていたことを後悔した。少し格好をつけたポーズでズボンを下ろしているのは、とても情けない気分になる。何とかして、せめて棒立ちくらいの姿勢に変更したい。
黒土がまた蹴ってくるが、ズボンを脱いだくらいで彼女のへっぽこな蹴りが効くようになるはずもなかった。
「ま、また体が動くんデスっ。も、もっと防御力を下げようとしているんデス」
黒土は、さらに僕の服を脱がそうと手を伸ばす。それはハートブレイクと書かれた下半身最後の一枚だ。いろんな意味で僕の心がブレイクしてしまうだろう。
「待て黒土、効いてるぞ、どても痛い、滅茶苦茶痛い、すげえ痛いからもうやめるんだ」
僕は慌てて、攻撃が通じていることにした。これ以上防御力を下げられたら、いろいろと危ない。それにもし防具、というか服を全部外された姿を学校の誰かに見られたら、死んだも同然になってしまう。即死攻撃だ。
「千早、本当にダメージが入ってるの?」
「なんで疑うんだよ。マジで大ダメージだぞ」
僕は主に精神的に傷ついている。ミカゼには、僕のデリケートな心をもう少し分かってほしい。
「って、さっきのモンスターはどうなったんだ。町に出ていったら、大騒ぎになるぞ」
「まだ中庭にいるよ」
巨大な目玉は、中庭に置かれている初代校長の胸像に向かって光を放っていた。相手を生身の人間とでも勘違いでもしているらしい。
初代校長の像が派手にライトアップされている姿は、これから後にも先にも見ることはないだろう。銅像に反射した光が校舎の白い壁に色をつける様は、幻想的な感じがする。文化祭でやったら、生徒たちにとても喜ばれそうだ。
モンスターを倒すならば、よそ見をしているいまが絶好のチャンスだ。なのに、こちらも相手を攻撃できる者がいない。
歯がゆい気持ちでいると、
「間に合ったようじゃの」
という声が背後から聞こえてきた。聞き覚えのある独特の話し方で、勇者ミカゼのパーティメンバーの一人、ヒメナ先輩だとすぐにわかった。
「どうしてここにいるんですか」
「先ほど千早たちが廊下を走っていくのが見えたんじゃよ。わしのクラスは自習じゃったから、気配を消して教室を抜けてきたんじゃよ」
授業が自習であっても教室から出るのは目立つんじゃないか。疑問が浮かんだけれど、僕はヒメナ先輩は剣術の達人で、勇者の仲間『サムライ』の力も持っていることを思い出した。気付かれずに行動する特別なスキルでも持っているのかもしれない。
ともかく、ヒメナ先輩はかなり強い。魔王軍との決戦でも、強力なモンスターを相手に善戦し続けたのだ。彼女がきてくれたからには、今回の戦いはもう大丈夫だろう。
「ヒメナ先輩、ミカゼと僕は金縛り状態で、黒土はモンスターに操られています。早くあの目玉を倒してください」
「うむ、造作もないことじゃ」
ヒメナ先輩はモンスターを一瞥すると、余裕そうに僕と、僕をぽこぽこと叩く黒土を見た。はて、と不思議そうな顔をしている。
「ところで千早よ、何故そんな涼しそうな恰好をしているんじゃ」
「モンスターのせいですよ。操られた黒土が僕の服を脱がしました」
そこまで話したところで、ヒメナ先輩の目の端が、鋭く光ったような気がした。
しまった。ヒメナ先輩が人をからかって遊ぶときの目だ。すごく嫌な予感がする。
ヒメナ先輩がいきなり、
「ぬわーっ」
と叫んだ。抑揚のない、わざとらしい声だった。
「千早よ、大変じゃ。わしは操られたぞっ」
「僕にはモンスターが何かしたようには見えなかったんですけど」
「凄まじい速さの攻撃じゃったわー。わしにすら見えんかったわー。いかんぞ、このままでは千早の服を脱がしてしまう」
「説得力、ないですよ」
僕に突っこまれても、ヒメナ先輩は操られたと言い張り続けて、にやにやとしながらこちらに歩いてくる。
「わ、わわっ、身体が勝手に動くんデス!」
ターゲットを変更した黒土が、ヒメナ先輩を攻撃する。黒土が操られていたことが、むしろ丁度よかった、彼女がヒメナ先輩をとめてくれるかもしれない。
こきっ
「ぎ、ぎゃあああっ」
黒土の攻撃はまたしてもノーダメージ。またしても手首を捻って自爆している。
僕は絶望した。
ヒメナ先輩は鼻歌交じりで僕のワイシャツのボタンを一つ、二つと外していく。おそらくふざけているつもりなのだろうけれど、度が過ぎた冗談だ。
結局、僕は薄手のシャツとトランクスのみという格好にされてしまう。一月の外気が僕から、体温を奪っていく。
モンスターと戦っていたら、いつの間にか下着姿になっていた。そういうのは賢者の役目じゃなくて、女騎士や、魔法使いの少女が定番じゃないのか。
「ヒメナ先輩、寒いんでやめてくださいよ」
「よいではないか、もし千早が凍えたら、わしが温めてやるわ」
ヒメナ先輩が手をとめることはなく、僕はついにパンツ一枚にされてしまった。
晴天の下、緑豊かな中庭で、ほぼ全裸だ。これではまるで駅前や公園に置いてある謎の銅像のようだ。よく考えてみると、どうして公共の場所に、楽しそうな微笑みを浮かべた全裸の少女の像を置こうと思うのか。僕は賢者であるが、芸術家の心理は分からない。
「もうすぐ昼休みになっちゃいますよ。こんな姿を誰かに見られたらまずいですって」
「しかし千早よ、お主は意外と、この状況ですがすがしい気分になっておるのではないか」
「僕にそんな性癖はないですよ。至って普通です」
「千早の性癖は普通とは言えないよ」
「ミカゼ、いきなり割りこんでないで助けてくれ……」
モンスターの緩慢な動きを見てか、ヒメナ先輩は余裕しゃくしゃくだが、のんびりしている時間はあまりないのだ。
モンスターが中庭から移動する様子がないとはいえ、昼休みになれば校舎から食堂へ向かう生徒が、中庭のすぐ近くを通る。モンスターと鉢合わせでもしたら大変なことになりかねない。そして、僕もまた大変なことになりかねない。
ヒメナ先輩は、僕の焦りすら楽しんでいるようだった。ついに僕のトランクスまでも下げようとする。
誰かにパンツ一丁でいるところを見られるのなら、まだ辛うじて致命傷で助かるかもしれない。日々の生活に疲れてしまった賢者が己を解放したかったのではないか、などと好意的に解釈する余地がありそうだ。
だが、これ以上防御力の下がった『装備なし』の状態で見つかったならば、どう言い訳しても危険人物扱いだ。モンスターの如く学校から退治されてしまうことだろう。
「僕の服を脱がせている場合じゃないですって。モンスターを倒す方が大事ですよ」
「そうかのう? あやつはまだ放っておいても大丈夫じゃろ」
イビルアイは僕やミカゼの方を見てすらいなかった。初代校長の銅像を強敵だと認識したらしく、太い視神経のような触手を絡みつかせて、首を絞めようといる。固い金属で作られた校長は、穏やかに微笑んだままだ。
目玉のモンスターはド近眼のようだ。乱視も入っているのかもしれない。これではヒメナ先輩が呑気に僕を弄っているのも頷ける。どうしてもっと脅威を感じるようなモンスターを送りこんでこなかったのかと、魔王軍に文句すら言いたくなってくる。
「ではでは、最後の一枚といこうかのう」
ヒメナ先輩はくくく、と悪役のように口の一端を吊り上げて笑った。そして僕のトランクスの布地を掴むと、少しずつ下に向かってずらし始める。
「これ以上は洒落にならないですって! やめて下さい本当に! もういい加減にしてくださいよ。それにモンスターがこっちに近づいてきますよ」
焦った僕は、早口で語気を強め、ヒメナ先輩をとめようとした。モンスターについては出まかせではない。初代校長を倒すことを諦めたらしいイビルアイが、ゆらゆらとこちらに移動してくるのが見えたのだ。
相当に際どい半ケツの状態にまでトランクスが下がったところで、ヒメナ先輩がようやく手をとめた。
「むふふ、本気で焦る千早はやはり面白いわ。流石にここまでにしておいて、モンスターを斬るとするかのう」
僕は、ヒメナ先輩がやっと真面目に戦ってくれるのかと安心した。
ピカッ
「ぬおっ」
モンスターの放った光が、ヒメナ先輩を直撃していた。
「ヒメナ先輩、あなたもですか」
これでパーティ全員がモンスターの光を浴びてしまい、まともに戦えなくなってしまった。黒土はまだいいとして、ヒメナ先輩が味方を攻撃し始めたら確実にオーバーキルなダメージになってしまう。
ヒメナ先輩は大丈夫だろうかと声をかけてみると、「むにゃ」という返事だけが返ってきた。首を前に傾けて、すやすやと静かに息をしている。
ヒメナ先輩は、モンスターの攻撃で眠らされてしまったようだ。
困ったことに、モンスターの特殊な攻撃や魔法で眠らされた場合は、声をかけたり揺すったりしたくらいで目を覚ますことはない。
「むにゃ」
立ったまま眠っていたヒメナ先輩が、かくっと地面に膝をついた。彼女の手に引っ掛かったままのトランクスが、一気にずり落ちる。
「うおおっ! まずいっ」
「千早っ、大丈夫っ?」
「もうだめだっ、いや、僕はなんともないぞ!」
「何を言ってるかわからないよ。落ち着いて」
ミカゼがこちらを心配してくれているようだが、起きていることを上手く伝えられず、彼女を混乱させてしまう。詳しく説明したくない状況なので、僕は言い直さないことにした。
そして、気がついたときには、モンスターが僕の目の前まで移動していた。巨大な目玉の触手が、びゅんびゅんと空気を切り裂いた。地面に当たった触手が土埃を跳ね上げる。なかなかの威力がありそうだった。
目玉の下部からは触手の他にも、鋭い爪の生えた一本の太い尾が伸びていた。もし刺されたり斬られたりしたら、大怪我は免れられないだろう。
何か策はないだろうかと考えてみるが、そんなものをすぐに思いつくのならば、とっくの昔に実行しているはずだった。
モンスターの尾が、振り被るようにして反った。腕をあげて身を守ることすらできそうにない。
そのときだった。
「え、えい!」
という掛け声と共に、黒土が僕の背中をどんと押した。
操られた黒土は、僕への攻撃をまだ続けようとしていたようだ。素手で殴っても効果がなかったから、押して地面に転ばせるつもりのようだ。
うおっと驚きつつも、身体の動かない僕は目玉に向かって突っこんでしまう。生温かく湿った感触が気色悪かった。
僕とヒメナ先輩はその場に倒れたが、体当たりされる形になったモンスターは空中をぷかぷかと漂っていった。
「あっ」
モンスターが、ミカゼが構えっぱなしにしていたエクスカリバーの先に接触した。
――エクスカリバーを装備した勇者ミカゼの攻撃力は、並大抵のモンスターを一撃で葬り去る。
目玉の断末魔は、「ピッ」か「ジュッ」のどちらだったか、よく分からなかった。
針で突かれた風船のように、目玉が破裂し、残骸が紫色の炎に変った。
モンスターの痕跡は、跡形もなく消え、後には北風が中庭の木を静かに揺らしているだけだった。
優しそうな顔の初代校長の像は、いつも通り微笑んでいる。
「モンスターを倒した」
ミカゼが言った。
「こんなんでいいのかよ。いや、いいんだろうけどさ」
苦しい戦いをしていたような気がするけれど、やけにあっけなく終わってしまった。
まだ金縛り状態は解除されないが、ひとまず魔王軍の脅威は、もうなくなったようだ。モンスターや魔界のゲートが開く気配は感じられなかった。
「もう大丈夫みたいだね」
「いやまて、まだ大問題だ」
ヒメナ先輩の上に乗っかるようにして倒れていた僕は、何も着ていないことに気がついた。突き飛ばされた勢いで、ヒメナ先輩の手に引っ掛かっていたトランクスが、ズボンごとすっぽ抜けていたようだ。
全裸の男が寝ている女性の上に覆い被さっているところは、犯罪行為にしか見えない。確実に現行犯で処刑されてしまうだろう。冤罪を主張することは、モンスターを倒すよりも遥かに難易度が高そうだ。
「ミカゼっ、この金縛りはまだ解けないのか」
「もう少しだと思う」
授業が終わったら、食堂に向かう生徒たちがやってくる。モンスターを退けたというのに、最悪の危機が訪れようとしていた。
「黒土、僕に服を着せてくれっ、かけるだけでもいい」
黒土に呼びかけるが、返事はなかった。さっき僕を押したときに転んで地面に頭をぶつけたらしく、額を押さえながら遠くへ転がっていくところだった。
大ピンチだ。それでもまだ望みはある。昼休みになる前に金縛りが解ければ、素早く服を着ることができる。
そう思った矢先、昼休みを告げる鐘が無情にも冬の空へと響いていく。
早めに授業を終えたクラスの女子生徒たちが、校舎から出てくる話し声が聞こえる。
僕は絶望しかけたが、その瞬間身体が急に軽くなった。金縛りが解けて、動くことができるようになったのだ。
「間にあえっ!」
僕はすぐさま、散らばった服をかき集めた。ヒメナ先輩の手に握られたままのトランクスだけは回収できなかったが、いまはそれどころではない。
「千早、大丈夫っ?」
「うおおっ、こっちを見るんじゃねえっ!」
ミカゼには悪いが乱暴にそう応え、中庭の隅に向かって全力ダッシュした。
僕は急いでフル○○からフル装備の学生服に着替え、毅然とした態度で茂みから出た。
僕のすぐ近くを、中庭までお弁当を食べにきた三人組の女子生徒たちが楽しそうに話しながら、立ちどまることなく歩いていった。危険度99.9%の状況から生還した!
僕は魔王軍に勝った。
達成感に包まれた気分で見る青空は、とても鮮やかに見えた。
「千早、怪我はない?」
と言いながら、ミカゼが近づいてくる。僕が戦いの終盤で大きな声を出しまくっていたので、心配していたようだ。
「あと少しでこの世界から消されるところだったけど、大丈夫だ。何ともない」
「それなら良かった。それじゃあ、ヒメナを起こして戻ろう」
ミカゼは中庭の中央で寝ているヒメナ先輩の方に向かって歩き始めた。勇者や賢者は、モンスターの特殊な攻撃で眠ってしまった仲間を目覚めさせる魔法が使えるのだ。
「ちょっと待て」
「えっ?」
僕は慌ててミカゼの制服の袖を摘んで引き留めた。不審者になる一歩手前で助かった安心感からすっかり忘れていたけれど、心地よさそうに寝ているヒメナ先輩は、僕のトランクスを握ったままだった。
ヒメナ先輩が寝返りをうって体勢を変えると、ハートブレイクというロゴがひらひらとはためいた。
少し離れた場所でお弁当を食べている女子生徒たちが、怪しむようにヒメナ先輩を見ているのがわかった。「ねえ、あれって……」とひそひそ話しながら、トランクスを指差している。
中庭のど真ん中で下着を持って寝ている謎の人物が、注目を集めつつあるのが分かった。
目を覚ましたヒメナ先輩が僕に向かって手を振るなどでもしたら、新しい面倒事が発生してしまうかもしれない。いまはもう彼女に関わらず、他人のふりをすることにしよう。
「ミカゼ、気持ちよさそうに昼寝をしているヒメナ先輩を邪魔しないように、ここから立ち去ろう」
「えっ? うん、分かった」
適当な理由をでっちあげて、教室に戻ろうとミカゼを促した。
ミカゼは戸惑いながらも僕に頷いたが、ヒメナ先輩が持っている布の塊の正体には気付いていないようで、視線をずっとトランクスの方を向けている。
「ヒメナが持っているのは何だろう」
「さあ。でかいハンカチじゃないかな」
僕はヒメナ先輩の関係者だと周囲の生徒たちにばれないように、「猫の形をした雲があるぞ」とごまかしてミカゼの顔を空に向け、中庭を後にした。
結局僕はトランクスを取り戻すことを諦め、ズボンの下に何も履かずに午後の授業を受け続けた。
放課後までずっと、ヒメナ先輩がトランクスを片手に僕の教室のドアを開けて来るのではないかと不安になり、心が落ち着かなかった。
魔界からやってきたモンスターは、勇者ミカゼによってすぐに倒された。しかし、賢者の装備を奪い、さらに心にダメージを与えることには成功していた。
魔王軍の恐ろしさを、僕は今日、この身を持って知ったのだった。