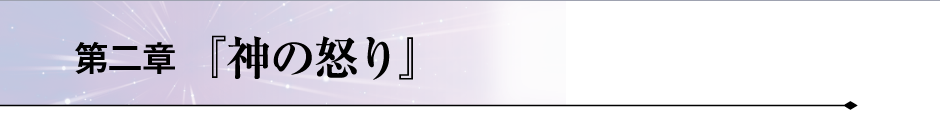一
下校中、強い風が吹き、アリスは髪を手で押さえる。
灰色の髪が風をはらんで、ふんわりと柔らかく広がった。
ずいぶん肌寒くなってきたが、最城市に比べればマシである。高良市(ここ)と比べて冬場の平均気温が五度ほど違うのだ。コートが必須になる天食学園での晩秋を懐かしく思った。
アリスは歩きながら、ショルダーバッグを担ぎ直した。
外国語の辞書が入っているので今日はいつも以上に重い。
敬護屋中学に通い始めた当初は肩に荷物が食い込み痛いくらいだったが、今はそれほどでもない。体力がついたのか、単なる慣れなのか、彼女自身分からなかった。
ただ、学校生活に慣れて緊張が解れ、肩の荷がすこし下りたのは間違いない。
現在、アリスたちが歩いている通学路もずいぶん身近に感じられるようになっていた。排水口の汚れや角が欠けている側溝のコンクリートブロック。途中、ブロック塀の上に突き出た枝に実っているのは渋柿なので手を出したら死ぬ。
下校時と登校時で同じ道の行き来のはずなのに印象はずいぶんと違う。
それは帰宅後と登校後で、傍にいる人間が異なることも大きな理由の一つだった。
わずかに先を歩くマリアが「ねぇ」と肩越しに振り返り、アリスに話しかけた。
「アリスは部活どうするの?」
アリスはすこしだけ早足になって、マリアに並んでから答えた。
「んー、アタシは音楽部かな。時間の融通が利くし」
「そっか。ボクは陸上部にしようかな。せっかくだから、体力作りしようかなって」
「良いと思うよ。マリアちゃん、足速いしね」
アリスたちは今後の学校生活について話し合う程度には適応していた。納得したつもりはないが、現実に追い立てられると受け入れるしかない部分がある。
そこで「あれ?」とアリスは違和感を覚えて立ち止まった。
「どうしたの、アリス?」
「さっきまで道の反対側に車停まってなかった?」
道路の反対側にあった車がアリスには消えたような気がした。いきなりの消失は音も何もなく、幻覚でも見たのか、と自分の目と頭を疑うほど唐突だった。
マリアは「んー」と唸って首を捻ったが「分かんない」と降参した。
「ボクは気づかなかったよ。走って行ったんじゃないの?」
「違うと思う。でも、そう言われれば、そんな気もするのだけど……まぁ、良いか」
アリスは釈然としないながらも、確かめるすべ術もないのであまり気にしないことにした。
マリアは「ハッキリしないんだね」と笑ってから「そういえば」と呟く。
「忘れていたけど、ボクも昨日、屋根の上に大きなカラスを見たんだった」
「大きなってどのくらい?」
「人くらいのサイズ。もしかしたら、もっと大きかったかも。天狗かな?」
マリアのとぼけた物言いに、アリスは笑う。
「それ、冗談のつもり?」
「うん、半分だけどね。つまんなかったから忘れて」
無茶を言うなぁ、とアリスは苦笑する。
最近、彼女たちは奇妙なことが周囲で起きているような気がしていた。
言葉を濁し、断言できない理由は奇妙なだけで害も易もないからだった。
最初は驚き警戒していたのだ。それこそテロリストが何かしているのではないか、と考えた。だが、彼女たちは何の証拠も正体も掴めず、徐々にその異常に慣れていった。
今では、奇妙なことがあれば、互いに伝え合う程度に落ち着いていた。
何も起きないから、警戒心も鈍ろうというものである。張り詰め続けるなんてストレスで死ぬ。ただでさえ、学校や家で考えることは多いのだから。
マリアは「そんなことよりも」と気炎を上げた。
「アリス、今日こそはアイツに勝つわよ!」
アイツとは幸太郎で、勝つは魔術知識比べのことだ。ここ最近、二人は義兄に一問一答や古今東西で勝負を挑んでいるが、全敗だった。アリスは首を横に振る。
「無理だと思うよ。お義兄さま、一問一答も古今東西も強すぎるもん。雲行法師の『五行和歌百八首』の裏問答まで網羅しているとか異常でしょ」
「それでも勝つの! 今日こそは……」と拳を掲げたマリアが「あれ?」首を傾げた。
そして、半瞬遅れて、アリスも異常に気づいた。声を潜めてマリアに言う。
「……おかしいね。今、一瞬だけ音が消えた」
「アリスは何だと思う?」
「魔術結界。しかも、結構大規模な魔術道具が使われている」
マリアは「同感」と口の中だけで呟き、頷いた。そして、大きな声を上げる。
「でもさ、アイツって黒髪で魔術士の才能はないけど、研究者として補佐に回れば大成するとは思わない? ボク、普通にブレインに欲しいとか思っちゃったよ」
アリスも何も気づいてないですよ、と平静を保ちながら話を合わせる。
「そうだね。アタシもあんなに知識がある人、お義兄さまの他に知らないもん」
「でしょ? 親戚たちが言っていた怠け者って話は大嘘だったね」
「悪意の流布って怖いね。いや、嫉妬かな。マリアちゃんも天食セラとか可音さんに嫉妬するなんて止めてね」
マリアは真っ赤になって反駁する。
「はぁぁぁっ!? 誰が誰に嫉妬するって? アリス適当なこと言わないでよ!」
アリスの狙い通り、マリアはムキになった。これで多少不自然ながらも、ごまかせた気がする。何と言っても、姉は演技できるタイプではないからだ。
アリスたちは魔術結界を張った人間がどこにいるのか探ろうとしていた。
外部から魔力を供給して魔術士を強化することはできないが、道具を使って行使する魔術を強化することは可能だ。その違いを簡単に言うと、計算機を使用したからと言って本人の計算能力が向上しているわけではない、にすこし似ている。結果が同じようでも、かかったコストが百円と一万円では全く別もの、でも可。
汎用性や応用性に欠けるが、上位の魔術士と戦うため魔術道具や儀式は必須になる。
彼女たちの勘だが、今、その魔術道具が使用された気がしたのだ。
魔術道具とただの道具の違いは魔術士であればひと目だ。
現在のアリスたちでは見分けがつかないだろうが、判別できないにしろ、今まで多くの魔術道具を見てきた経験で区別できるかもしれない。先ほどの結界の件だって、その経験がものを言ったからこそだ。剣道の達人は老衰しても未熟な若者を打倒する。
アリスとマリアの歩調は揃っていた。向かうべき方角が一致しているということだ。
危険かもしれないのにあえて踏み込もうとしているのは、現在の奇妙に感じる状況を打開したいと願っているからだ。魔力量を抑えられている現状では取り押さえるなんて不可能だが、その正体くらいは掴みたいと考えていた。
アリスは会話を続けながらも警戒を怠らない。
「でも、マリアちゃん、お義兄さまのこと気に入っているでしょ?」
マリアは顔を赤くしながら頷いた。もう警戒している様子は見えない。
「……だって、にーちゃん、超努力家だし……そういうアリスはどうなのさっ?」
「人間的には嫌いではないわね。優しいし、気遣いもできる人だから。ただ、魔術の才能がないから、やっぱり、眇めて見ちゃうところはあるかな」
アリスとマリアの一番の違いはそこかもしれない。アリスの才能原理主義は信仰に近い面があるので、容易には覆せない。感情が納得できないのだ。
マリアは妹のその辺りの気持ちが分かっているので、特に反論はしなかった。
ただ、自分の感情を嫉妬なんて言葉で片づけて欲しくなかったので、彼女は説明する。
「でも、ボクは別に嫉妬なんてしないよ。確かにアイツのこと結構気に入っているけど、これ、絶対に恋愛感情とかじゃないもん」
「あれ、マリアちゃんって恋したことあるの? あ、アタシはないからね」
「そういうことじゃなくて! ボクは純粋にアイツの態度に腹が立っただけだもん!」
真っ赤な顔で否定しても説得力ないなぁ、とアリスは思ったが、ここでからかっても話が進まないので「どういう意味? 捨てられるって思ったから?」と質問する。
「捨てられる? もしかして、ボクらが? 違うよ。そうじゃなくてアイツの口調だよ」
「口調?」
「人生に絶望して、自棄(やけ)って言うか……全てを諦めているみたいだったじゃん」
「? そうだったかな? アタシはそう思わなかったけど」
マリアはどうしてアリスが分からないのか、分からなかった。
「間違いないよ。にーちゃん、まるで自殺志願者みたいだったよ」
アリスは理解できなかったが、姉の直感は信頼しているので、次から気をつけてみようと思った。何か感じ取れるかもしれない。
「大体さ、アリスだって見たでしょ? にーちゃん、何かうなされていたじゃん」
それは朝、偶然目撃した光景だった。
幸太郎の自室は図書室になっているので、彼はソファーに座って休んでいる。
普段の幸太郎は声をかけるとすぐに応答するが、その日は寝たように動かなかった。
魂を着ぐるみに転写させた状態で睡眠が必要なのか不明だが――実際、生物に不可欠な食事や排泄は不要なのだ――そもそも、二人が起きた時には朝食を作ったり洗濯したりしている義兄にしては珍しいことだった。
そして、彼は苦しそうに「止めて……」とか「そんなこと……」とうなされていた。
マリアが慌てて揺り動かすと、すぐに目覚めた義兄だったが、
『え? 夢? いや、見てなかったけど……僕、何を言ってたの?』
と、とぼけているのか、それとも、ごまかしたのか分からない反応だった。
「ほら、にーちゃんってば、京二叔父さんたちに嫌われていたよね? 夢野家から追放されていたわけだし、だから、人生が嫌になったりしたんじゃないかな?」
「……あまりお義兄さまから想像できないね」
多少は悩むのだろうが、そこまで自棄になるタイプとは思えなかった。
「ボクも同感。でもさ、悩まない人間なんていないよね? だから、ボクはなるべく認めてあげたいなって思うんだよ」
アリスは姉の優しげな表情に胸を打たれた。
「……マリアちゃんって凄いね」
「ど、どうしたのさ! いきなりっ?」
「ううん。率直な感想」
そこで会話を打ち切ったのは、近いと二人とも心の何処かが警告を発していたからだ。
彼女たちは緊張していた。もしかしたら、相手はテロリストで自分たちを殺そうとしているのかもしれない。そんな想像が二人の手足を重たくしていた。
そして、細い路地の間にそれはいる、と言葉を交わさずとも彼女たちは確信していた。
一度だけ目を合わせて、二人同時に問題の路地を覗いた。
そして、そこにいたのは――猫だった。
ダンボール箱に入れられた痩せた子猫が一匹だけ捨てられていた。
アリスとマリアは目を合わせて、それから、堪え切れずほぼ同時に吹き出した。
「あははははは、猫、猫って!」
「ふくっ、アハッ、フフフハッ、お、お腹痛いですっ」
二人とも緊張の反動で笑いの衝動が堪えられない。
ひとしきり笑った後、アリスは目尻に浮かんだ涙を人差し指で拭って言う。
「あー、おかしい。アタシたち、もしかして、ノイローゼなのかしら?」
マリアは「あー、あー、ん、喉の調子狂った」と喉元を押さえながら言う。
「かもね。ここまで勘が外れると自分でもどうかと思うよ」
二人でひとしきり笑った後、アリスが「そう言えば」と言う。
「マリアちゃんって、実はお義兄さまのこと『にーちゃん』って呼んでいるのね」
「ハッ!? ア、アイツのこと何て呼ぼうがボクの勝手でしょ! さっさと帰るよ!」
踵を返そうとして、二人が足を止めたのは弱々しい猫の鳴き声が聞こえたからだった。
痩せた子猫は生後数週間というところか。放置していたら、間違いなく死ぬだろう。
アリスとマリアは探るような視線を絡ませて、どちらともなく呟く。
「「ど、どうしよう……」」
二
黒髪の少年が大人たちに取り囲まれている。
そして、周囲の大人たちが幼い少年を見下ろす表情は侮蔑と嫌悪ばかりだった。
……ああ、これは夢だ、と幸太郎が考えたのは、それが過去の再現だったからだ。
もちろん、違う点も多々ある。ここまで大人たちは多くなかったし、幸太郎自身ももうすこし成長していた。つまり、これはイメージの再現だった。自分は弱く、敵の力はより強大に……よくある夢の誇張だ。そして、胡蝶の夢ではないが、まるで他人事のようなふ俯かん瞰した視点で現在の幸太郎は過去の自分を見ている。
あの時の幸太郎は、わけの分からない悪意をぶつけられて、戸惑っていたのだ。
大人たちの一人が表情を歪めて吐き捨てる。
『――どうしてお前なんかが! お前みたいな黒髪が……っ』
罵倒する大人は鮮やかな紫色――魔力値十万を超える優秀な魔術士だ。
そんな人間からすれば、幸太郎の黒髪は取るに足りない存在のはずだった。
なのに、目の敵にしている理由は、幸太郎が夢野家の嫡子として扱われていたからだ。
『――何故天食はお前なんかに娘を差し出すんだ……っ』
天食家も夢野家に並ぶほどの名家で、幸太郎はそこの娘の一人と婚約関係にあった。
魔術の才能はほぼ遺伝によるので、優秀な魔術士の子どもは強い魔力を持って生まれることが多い。幸太郎は母と同じく黒髪だったが、黄金の髪を持つ敬太郎唯一の子どもでもあった。遺伝的な素質はある、と期待されていたからこその名家同士での婚約だ。
普通ではありえないが、これも一種の政略結婚である。
『――黒髪なんかと婚約するんだから、その天食の娘もどうせ落ちこぼれだろうがな』
嘲笑をぶつけられ、夢の中の幼い幸太郎は言い返した。
『セラちゃんは落ちこぼれなんかじゃないよ。綺麗な輝く髪を持ってるんだ』
幸太郎が反論したことで、大人たちは激高する。
夢の中の彼らは一瞬で人の形が崩れ、巨大で真っ黒な不定形の化け物へと変化した。罵倒は意味不明の雄叫びになり、威嚇か捕食しようとしているように見えた。
恐ろしくなった幼い幸太郎はその場から逃げ出そうとする。
しかし、取り囲まれている状態からでは抜け出ることなんてできない。
幼い幸太郎は恐ろしさから足が震え、しゃがみ込み泣き出す。
そこで、元々紫髪だった大人の一人が再び意味のある『言葉』をぶつけ――。
幼い幸太郎は泣き叫びながら拳を振るった……。
……と、幸太郎はようやく目を覚ました。
すこし疲労が溜まっていたのか、現実時間で十秒ほど睡眠していたようだ。最近、こんな夢を見ることが多かった。現実と似て非なる夢は心にしこりを残す。
目が覚めた理由は電話がかかってきたからだった。
*
幸太郎は電話口に聞く少年の声に違和感を覚えていた。
ただ、それと報告内容は全くの別物なので、余計な雑念を払って確認する。
「それで、昨日あの子たちを見張っていた賊の正体は掴めましたか?」
『無理だった。いや、調べても無駄なことが判明した、の方が正確かな』
幸太郎たちは、マリア・アリスの二人を拉致しようとした人間について調べていた。実際、もう今日で四度目になり、合計で十一人を捕まえていた。
現在、その情報交換と対策会議を電話で行っていたのだ。
「今までと同じパターンですか」
『ああ、仲介業者が斡旋した実行犯たちに与えられた情報は、あの二人の顔写真とダミーの素性。あとは拉致しろという指令だけで、その雇い主の仲介業者さえも何も知らなかった。多分、今日の奴らも無駄だろうな』
情報を守る一番簡単な方法は、余計な人間に情報を与えないことだ。使い捨ての駒になる人間なんて、大金を餌にすればいくらでも釣れる。
「しかし、黒幕は成功すると思ってやってるんですかね」
『成功したらラッキーくらいかもな。嫌がらせとしては趣味が悪くて嫌いじゃない』
呑気な少年の言葉に、幸太郎は苦笑する。
「もしも、成功されたらそんなこと言ってられなくなりますよ」
『お前があの子たちは生命を懸けて守るんだろ? こっちは心配してないさ』
信頼の軽口をすこしだけ嬉しく思うが、同時に照れくさい。幸太郎は咳払いして言う。
「一応、今までに分かっていることをまとめてみますか」
『ああ。捕獲した奴らにあの二人のダミーの素性はそのまま漏れていた。ただし、本当の素性については何も知らなかった』
「つまり、黒幕は本当の素性を伝える気が最初からなかった。何故ならば、伝えても意味がないから、ですね」
『いや、そうとは限らない。他にも可能性はいくらでもあるぞ。黒幕は二人の素性を知られては困る立場にあるのかもしれないし、実行犯をあえて俺たちに捕まえさせるため情報を制限したのかもしれない。あるいは、ダミーの素性以上の知識を本当に持っていなかったのかもしれない。予断は禁物だな。だから、ここで論ずるに値するのは、仲介業者以下の人間はダミーの素性程度の知識しかなかった、という事実だけになる』
幸太郎はなるほど、と納得する。無意識的に敵の正体を固定化していたようだ。
『ただし、ダミーの素性ではあの二人に拉致するほどの価値がないということを考える必要がある。大金がせしめられるわけでもないし、灰色髪では遺伝的価値もない』
「そうですね。実行犯たちは、大概、変態趣味の富豪が二人の容姿の可愛らしさに目をつけて拉致しようとした、なんて考えてるようでしたし」
『つまり、黒幕はやはり意図的に情報を隠蔽、操作していると考えた方が自然だろうな。一度であれば偶然かもしれないが、四度も続けば偶然とは思えない』
幸太郎も同感だった
『さて、ダミー情報の正確さ、複数回続く執拗さ、二人を巡る利害関係、黒幕の正体が俺の方で全く掴めないこと……これらの情報を統合すると結論はどうなる?』
「予想通りということですね」
幸太郎と少年はどちらともなくため息をついた。幸太郎も人のことは言えないが、少年も電話口で分かるほど倦怠感と徒労感を滲ませた重い吐息だった。
「今後の方針、どうしますか?」
『うむ、実は近々、大規模魔獣型魔力炉の除幕式があってな、俺も参加するんだ』
「それ、高良(たから)市から三十キロほど山手に建設されてた魔力炉ですよね?」
『ああ。俺らの予想が当たっているなら、黒幕はそこで何か仕掛けてくるだろう。それ次第で対応は変わるから、現状は待機していてくれ。詳しい情報については後からまとめて連絡する』
「分かりました。ところで、何か起きると思ってますか?」
『いや、起きないで欲しいと思っているさ。ただし、どちらかに生命を賭けろと言われたら、俺は起きる方に賭けるがね』
「……分かりました。気をつけてください」
『ああ。そろそろ、あの子たちも帰ってくるんじゃないか?』
「ええ。どうやら、捨て猫を拾ったみたいですよ。あ、一応、猫の餌とか一式準備しておいてもらえますか?」
少年はカカッと楽しそうに笑う。
『ああ、任せろ。しかし、ずいぶん楽しそうじゃないか。良かったよ』
「ええ、教えたことを素直に吸収してくれますしね。しかし、あの子たちが本当に凄いのは魔力制限状態でのあの鋭さですよ。昨日、屋根の上に隠れてた賊にも気づいたみたいですし、気が抜けません。あの子たちであれば、夢野家を立派に守れますね」
『そうかもな。そろそろ、切るぞ』
「はい、また何かあれば」
幸太郎は切れた電話を体内(着ぐるみの中)に隠す。ここは家で最も物を隠すのに適している。
そして、一分もしないうちにソロソロと音を立てないように玄関が開いた。
二人は猫を隠れて連れ込むつもりのようだが、そうはさせない。どうやったって、学校にいる間は世話できないのに、そこまで考えが及んでいないようだ。
この辺りまだまだ子どもだな、と幸太郎が思ってしまう理由だった。
幸太郎は捨て猫をペットとするか二人と話し合うため、玄関に向かった。
三
幸太郎、マリア、アリスの三人がリビングに揃っていた。
厳粛な空気が漂っているのは双子が真剣な面持ちだったからだ。
三人はやや俯きながらコの字の形で膝を突き合わせている。
幸太郎から見て右手のマリアが魂でも注ぐような口調で言った。
「……チェシャ」
シンと静粛さは保たれたままだった。
十秒ほど経っただろうか、マリアがガクリと項垂れる。
そして、幸太郎から見て左手のアリスが祈るようにして言った。
「……イヴ」
シンと静粛さは保たれたままだった。
やはり十秒ほど経って、アリスが天を仰ぎ細く吐息する。
そして、双子に挟まれる形の幸太郎が軽い感じで言った。
「丹八(たんぱち)」
ニャー、と即座に応じる鳴き声があった。
その瞬間、マリアは「うにゃああああああ!」と絶叫して、その場にひっくり返った。
「意味分かんない! どうしてなの! アンタのセンス最悪じゃん!」
アリスも不機嫌そうに口を尖らせて、姉に同意する。
「同感です。お義兄さまのセンスはマリアちゃんの絶望レシピくらい理解できません」
幸太郎は「そんなこと言われても……」と困ったように後頭部を掻き、その背後でマリアが「どさくさ紛れにボクも罵られている! どういうこと!?」喚いていた。
幸太郎の膝上には、双子姉妹の険悪な様子に怯えたのか、子猫――丹八が乗っている。拾って来た時からは考えられないほど元気になっていた。
今、幸太郎たちは拾った子猫の名前を決めようとしていた。
あーだこーだ議論を交わしたのだが、白熱しすぎたせいでなかなか決めきれず、最終的に子猫自身に決めさせることになったのだ。
その結果が命名『丹八』であり、マリアもアリスも不服で仕方がなかった。
「と言うか、どうしてアンタに一番懐いているのよ! アタシたちが拾ってきたのに!」
「単純に僕の世話する時間が長いのと、寒いからこのフサフサした毛が気持ち良いんじゃないかな? 暖房代わりだよ」
「うぅぅぅ、理由を言われても納得できません……っ」
幸太郎としては理不尽な怒りに苦笑するしかなかった。
彼がチラッと時計を確認すると、時刻は土曜の午後二時を回ろうとしていた。
休日の昼下がり、夢野邸にはのんびりとした空気が流れていた。
猫に声をかける二人は諦めたのか「丹八か……でも、ボク、なんとなく良い名前の気がしてきたかも」「マリアちゃん、それは敗北主義だよ。丹八の名前は認めても、お義兄さまのセンスを認めるのはダメだよ」愚痴のような言葉を垂れ流している。というか、何気にアリスの暴言が酷かった。
丹八は全く関係ないとばかりに、ニャーニャー鳴いている。
お腹でも空いているのか、遊んでくれというアピールなのか、もしくはそれ以外なのか幸太郎にもよく分からなかった。
このまま平和が続いて欲しいと願った瞬間、幸太郎の体内で携帯が着信を告げた。
音が出るわけではないので、マリアもアリスも気づいていない。
幸太郎は丹八を二人に押しつけてその場を離れ、中から取り出した電話に出た。
その声は「はい――」という幸太郎の応答を遮るタイミングで、
『幸太郎、後詰を頼む』
それだけを言って切れた。
幸太郎は沈黙した電話をまじまじと見てからため息をつく。
今の電話で期待は裏切られ、予想が的中したことを意味していた。
さて、どうしよう、と彼は考える。
この後の展開は既に決まっていた。すぐに敬心の使いがやって来て、幸太郎は魔力炉へ向かう。今、考えるべきなのは彼の行動指針ではなくて、マリアとアリスの双子姉妹をどうすべきか、という問題だった。何だったら、そこに丹八を混ぜても構わない。
今後の生活を考えると、二人には何も教えずに事が済んでいるのがベストなはずだ。しかし、本当にそれで良いのか、身の安全を考えれば、全てを教えた方が良いのではないか……だが、しかし、知られることは恐ろしいことで……。
幸太郎の堂々巡りは止められなかった。
迷った幸太郎はリビングに戻り、猫と戯れる義妹たちに告げる。
「マリアちゃん、アリスちゃん、ちょっと良いかな」
「どうしたの、改まってさ」
「はっ! もしかして、名前変更ですかっ? イヴ再来ですかっ!?」
「ちょっと待ってよ、アリス! 何シレッと自分のアイデア推しているのさ!」
丹八の名前で色めき立つ二人に、幸太郎は端的に事実だけを告げた。
「じいさんから電話があって、郷河原(ごうかわら)に新造された大規模魔獣型魔力炉の『双頭の悪魔(ファット・ボーイ)』が暴走したらしい」
マリアもアリスも瞳孔が半開きになるほど驚き、絶句した。
しかし、それは本当に一瞬だけだった。
二人の視線が鋭くなり、マリアが先に口を開いた。
「ねぇ、アンタ。魔力減衰薬を中和する薬くらいあるんだろ。早く出して」
続けてアリスも頷く。
「それと詳しい状況もお願いします。今からでもアタシたちにできる仕事があるはずです」
一瞬で覚悟を決め、自分の果たすべき役割を考え始めた二人に、幸太郎は正直驚く。
「本当に二人とも分かってるの? 相手は超大型魔獣だよ? 挑んで生きてられる保証はどこにもないんだよ? そもそも、君たちに戦う義務なんてないんだよ?」
アリスは静かな瞳で「そんなこと分かっていますよ」と微笑んだ。
「『種島事件』では『羊頭狗肉(ラフィング・ドッグ)』相手に上級魔術士を基軸とした精鋭百二十三名が殉職しました。『双頭の悪魔』はかの魔獣とも比べ物にならない強さだということは知っています」
「なら――」
なおも問おうとした幸太郎を遮るようにしてマリアが叫ぶ。
「うっさい! ボクたちは選ばれた人間としての義務があるんだ! 捨て石になるかもしれないけど、ボクらが頑張らないともっと多くの人が死ぬだろ! つべこべ言わずに中和薬をさっさと出せ! このアホ兄貴!」
ああ――と幸太郎は言葉にならない感動に胸を打たれていた。
この子たちなら大丈夫だ――彼はそう思った。
それはマリアとアリスなら信じられる、なんて甘いものではなかった。
この二人になら裏切られても、罵られても、嫌われても許せるという気持ちだった。
その時、ちょうど来訪を告げるドアベルが鳴った。敬心の使いだろう。
幸太郎は「試すようなこと言ってゴメン」謝った。
「移動時間はあるから、そこで全てを話すよ。でも、先に一つだけ保証するね。僕は君たちを守る。生命に代えても」
幸太郎の誓いに、マリアとアリスはキョトンと不思議そうに首を傾げた。
四
敬心の使いはマリアたちをこの街に連れて来た時と全く同じ人物・車両だった。
別に彼女たちはそれで何か感慨を覚えることもなかった。魔獣暴走の報が衝撃的過ぎてそれどころではなかったし、幸太郎の様子が着ぐるみなのに緊迫感溢れていたからだ。
三人が運ばれている大型乗用車は運転席と後部座席が仕切りで分かれている。
出入口を除いて取り囲む形の座席になっており、マリアとアリスは並び、それに向かい合うポジションで幸太郎が座っている。秘密話をするのに適した構造だった。
ちなみに、丹八も置いてくることができず、アリスの膝上で丸まって寝ている。
幸太郎は黄色い錠剤の入った瓶とミネラルウォーターを取り出した。
「とりあえず、これが中和薬だから飲んで。こっちはただの水ね」
二人は渡された薬を競うようにして即座に飲み下し、水で流し込んだ。
効果は飲んでから徐々に現れ、マリアが赤銀髪を、アリスが緑銀髪を取り戻した。
「うわぁ……」「ふぁー……」
マリアもアリスも感嘆の息を漏らす。
彼女たちが魔力減衰薬を飲み始めてそれほど長い時間経ったわけではないが、既に魔力が世界に満ちている感覚を忘れかけていた。
世界が輝いて見え、それと同じくらい彼女たちは目を輝かせている。
幸太郎は「それほど時間があるわけでもないから、本題に入ろうか」と言った。
義兄の改まった姿に「うん」「はい」と二人は居住まいを正す。
「と言っても、どこから話すべきかな……まず、君たちの魔力を取り戻させたのは、最低限自分の身を守って貰うためだから。と言っても、『双頭の悪魔』相手ではなくて、人間相手だよ。二人は最近、身の回りで奇妙なことが起きてると感じたことないかな?」
「はい、あります。ただ、全部気のせいだと思っていましたが……」
「ううん、それは気のせいじゃなかったんだ。父さんたちを殺したグループとは限らないけど、君たちは何者かに狙われてた。だから、今回の事件も実は陽動で、魔獣を暴走させた隙に君たちを拉致することが真の狙いかもしれないんだ」
マリアは理解も納得もできなかった。
超大型魔獣が本当に暴走したのであれば、国家存亡クラスの危機だ。わざわざ、自分たち二人を拉致する程度の目的で、そこまでするとはとても思えなかった。
いや、そんなこと信じたくない、の方が心情的には近い。
「そんなこと言われてもわけ分かんないし。そもそも、狙われていた? どうしてアンタはそんなこと知っているのよ?」
「うん、僕が密かに捕縛して、それをじいさんに引き渡してたからね」
「……は? どういうこと?」
「守るって誓ったのは嘘じゃなかったってことかな。ところで、二人は一番魔力量の多い髪色は何か知ってる?」
幸太郎はいきなり話を飛躍させて質問してきたが、そんなこと子どもでも知っている。
アリスはこれがひっかけ問題か何かではないか、と思うくらいだった。
「……伝説では虹色や透明だと言われています。透明色の髪と言えば、ヴォルグ・ハデスブルングが有名ですね」
幸太郎は「正解だね」と首肯した。
「人の魔力量は生まれつき定められてる。二人の銀クラスは魔術がギリギリ発動できる黄クラスの百倍の魔力量を誇るけど、虹や透明は君たちの更に十倍の魔力量がある。この差は努力なんかで覆すことは不可能。僕らの社会の差別主義は『生まれつき差があるのに等しく扱おうなんて方が間違っている』が思想の発端だよね? これは魔力量の多い人間が希少だったのと、髪色で優劣がひと目で分かるからこそ生まれた思想だろうね」
話がすこし脱線したかな、と幸太郎は苦笑する。
「別に躊躇してるつもりはないんだけど、回りくどくなってるね。で、最強の髪色は虹や透明が常識だ。でも、実は現在観測されてる最強の髪色はそれらではないんだよ」
マリアとアリスは視線だけで『知っている?』と互いに確認するが、分からなかった。
「なら、何なのよ?」
「減法混色か加法混色かで異なるけど、自然界に存在する色を多量に混ぜると無彩色に至ることがある。白とか黒だね。そして、透明と虹の二つはその色に至る過程と言われてる。つまりね、究極まで魔力量が増大すると色が失われるんだよ」
「色が失われる――それは無色ということですか? 透明と何が違うのですか?」
「よく勘違いされるけど、無色と透明は別物なんだよ。透明は透明という色。無色は言葉通り色が無いんだ。人では認識できないからこそ光は失われ、残るのは漆黒の闇だけ」
幸太郎は『漆黒の闇なんだ』と再度強調して続けた。
「一応、そうではないか、という学説を立てる研究者は過去にもいた。でも、虹や透明の時点でも半分伝説なんだから、体現できる存在はいなかった。刀自家の人間とか一部で信じている者もいたけど、与太話どころか空想上の産物でしかなかった」
幸太郎の言葉は過去形だった。
そこまで言われて、マリアとアリスは同じ結論に至ったことを理解する。双子の直感なんてものではなく、ここまで言われて理解できないとかなり鈍いだろう。
幸太郎は自身の頭部を指さして、思い出して、と言う。
「僕の肉体の髪色は『漆黒』だったんだ。闇よりも濃い黒。魔力量が極限まで増大した結果、マリアちゃんたちでも色として認識できなくなっただけ」
つまり、幸太郎のそれは自身が史上最強の魔術士だ、という告白に他ならなかった。
そこまで言われて、マリアは一つ思い至ることがあった。
――どうして、京二叔父たち親戚は幸太郎のことを悪く言うだけだったのか?
基本、悪口や陰口なんて直接文句が言えないからこそ発せられるものではないのか?
つまり、悪態をつく他に何もできなかったからではないのか?
下手に藪をつついて蛇が出ることを避けていただけではないのか?
何故なら、勝てないから。手が出せないから。
だから、彼を夢野家から追放するくらいしかできなかったのだ。
国内で五指に入る魔術士と誉れ高かった義父でさえも触れられない絶対的魔力。
ゾゾゾッと寒気がマリアの背筋を這い、鳥肌が立った。
それは戦慄にも似た感覚で幸太郎の言葉の信ぴょう性を本能的に保証するものだった。
手を出してどうこうなるレベルではないのは確実だ。
幸太郎はマリアたちよりもはるかに選ばれた人間なのだから。
今、目の前に世界最強の魔術士が座っているのだから。
伏し目がちだったアリスが、顔を上げながら訊く。
「あの、お義兄さま。以前アタシが質問した『非魔術士による魔術干渉実験について』の少年Kは、やはりお義兄さまだったのですか?」
「うん、正解。ただ、僕は別に非魔術士じゃなかったんだ。あの本が示していたのは、桁違いの魔力差さえあれば、他人の魔術を支配できるという観測結果だけ。ただの力技だね」
何のひねりもない秘密でゴメンね、と幸太郎はよく分からない謝罪をした。
アリスは問題ありませんと首を横に振って、ため息をついた。
思い返してみれば、魔力がなければ他者には干渉できないという説明が最後だった流れは不自然である。おそらく幸太郎は、魔力さえ強ければ干渉できるのではないか、という思考の飛躍を嫌ったのだろう。今更言っても負け犬の遠吠えに等しいが、正答に至らなかったことが彼女は悔しかった。
幸太郎は説明を続ける。
「著者の刀自雄大さんは、最初、可音へのコンプレックスで僕を調べようとしたんだ。僕は夢野家を出てから、魔力制御の研究を行うため刀自家に厄介になってたから、その代償みたいな形でね。でも、僕の力の一端を知っただけで雄大さんは更なる狂気に囚われてしまった。うちの親戚連中と一緒だね。自分と比べて、圧倒的だったがゆえに恐れた。不思議だよね、僕から誰かを傷つけたことは一度しかないのに」
「えっと……一度はあるのですか?」
「うん、僕の力を知らなかった親戚たちに暴言と暴力を振るわれ、初めて抵抗したんだ。ただ、ちょっと仕返しするつもりだったのに、京二叔父さんは下半身が千切れ飛んだ。僕は慌てて治そうとしたけど、一命を取り留めるに精一杯だった。未熟だったね」
淡々と事実だけを告げる幸太郎の声はどこか辛そうだった。
思い出したくない過去なのだろう、と二人にもその気持ちは分かった。
「だから、京二叔父さんはアンタのことあんなに憎んでいたんだ……」
二人が悪印象を抱いていた大きな理由が、京二叔父から聞いた話のせいだった。
京二は血の繋がらない姪である彼女たちを可愛がってくれていたので信用していた。実際、周囲も高く評価し、人望の厚い有能な人物だった。
「うん、さすがにやり過ぎだったよ。反省している。父さんたちにも迷惑がかかりそうだったから僕は放逐処分を受け入れ、夢野との関係を半ば絶たれた。君たち二人が養子として夢野家に迎え入れられたのは、その辺りの流れのせいで、つまり、僕の代わりさ。全て僕が悪かったと言えるね」
マリアはそんな自嘲的なことを言われても納得できなかった。
「でも、子どもだったアンタのこと罵ったのって、京二叔父さんたちだったんでしょ? それで、アンタだけが放逐処分っておかしくない? あ……もしかして、強すぎて力が制御し切れてなかったとか? だから、危険視されたの?」
「違うよ。僕の力は完璧に僕の制御下にある。僕より上手に魔術を操る人間なんて、可音くらいしか知らないよ」
「でも、京二叔父さんの下半身が千切れ飛んだって……」
「うん、まさかあの人があんなに弱いなんて思わなかったんだ」
魔力値十万オーバーの紫髪を弱いモノ扱いする義兄に二人は絶句した。
「力は完璧に制御されてるけど、僕の感情はそうじゃない。暴走の定義にも依るけど、もしも、僕が欲望のままに振る舞ったらどうする? それだって暴走の一種だろ? 僕の力を恐れる人間が怯えたのはね、僕が強大な魔力を自由に行使できたからだよ」
幸太郎の口調は相変わらず自嘲的で、言葉が出ない二人に対して説明を続ける。
「国内でも有名な魔術士の家系はたくさんあるよね。例えば、警察の八瀬、医療の門蔵、魔術研究の刀自、教育の天食、エネルギー産業の夢野……各名家のバランスが保たれているからこその平和だ。もしも、たった独りでその全てをぶち壊せる人間が現れたら? 結局、抑止力があるからこそ人は平静でいられるんだろうね」
アリスがゴクリと唾を飲み込んで、オズオズと訊ねる。
「それでお義兄さまの魔力量はどれくらいなのですか?」
幸太郎は淡々と答えた。
「そうだね。君たち銀の最低でも一万倍ってところかな」
つまり、魔力値百億以上。
今度こそ、二人は言葉と顔色を完全に失った。
*
幸太郎は二人の様子を見て、やっぱりこういう反応になるよね、と考えていた。
期待していたわけではないのだ。
裏切られても恐れられても構わないと思ったのは嘘ではないし、本気だった。
だが、胸の痛みはどれだけ覚悟していても――辛いものだった。
そして、マリアが叫ぶ。
「凄い! それなら、『双頭の悪魔』だって楽勝でしょ!」
「……は?」
アリスがマリアを窘める。
「ダメだよ、マリアちゃん。今、お義兄さまが言ったのは『誰かに頼り切ることは危ない』って話だったんだから。それは敵対も依存も大差ないでしょ」
「え?」
二人の様子がおかしい。キラキラと幸太郎を尊敬するような目で見ていた。
「ところでさ、今回どうして『双頭の悪魔』は暴走したのさ? 事故?」
「あ……いや、多分だけど、『平等教』の犯行じゃないかな」
「またアイツら? パパやママを殺したのもアイツらでしょ? 意味分かんない! あー、腹立つなぁ、もう!」
「一体、何の恨みがあるのでしょうね? もう潰すべきだと思いませんか、お義兄さま」
「あーっ、アリスだってにーちゃん頼みっぽいし!」
「違います! アタシは正当な手段に則って、法的に潰したいと考えているの!」
二人がギャーギャー騒ぎ始めたせいか、目を覚ました丹八が呼応したように、ニャーニャー鳴き出す。何故か深刻な空気が吹き飛んでいた。
車内のお祭り騒ぎに幸太郎は混乱しつつも、絞り出すように質問する。
「え……二人の反応、なんか違わない?」
マリアもアリスも不思議そうに小首を傾げる。
「何が?」
「? どういう意味ですか?」
そして「あ!」とマリアが叫んだ。
「もしかして、にーちゃんでもどうしようもないくらい『双頭の悪魔』って強いの!?」
「そ、そうなのですか、お義兄さまっ?」
幸太郎は縦と横の中間の角度で首を振る。
「あ、いや、確かに『双頭の悪魔』は異世界の過酷な環境下で、数千年単位生きる魔力生命体だから、生物としては僕よりも強いよ。魔力量も間違いなく多いし」
二人の絶望した顔を見て、彼は慌てて補足する。
「でも、倒すだけなら僕一人で十分だよ。例えば、虎は人間よりも強いよね? でも、銃があれば、非魔術士でも倒すことができる。それと同じで、術式で効率良く魔力を扱える僕の方が戦闘では有利だからさ」
二人のホッとした顔で、幸太郎も安心する。ではダメなのだ、と思い直す。
「そうじゃなくて! 君たちは僕が怖くないの!?」
マリアとアリスは互いに目を合わせて、同時に首を振った。
「いや……」「別に……」
「例えばさ、郷河原の魔力炉の責任者は京二叔父さんだ。僕とは遺恨がある。それで手を抜いたりするとかさ、そういうこと考えないのっ?」
「考えないよ」「考えません」
「僕が君たちに乱暴したり、好き勝手に振る舞ったりとか考えないのっ?」
「考えるわけないじゃん」
「マリアちゃんはむしろ乱暴にされたいのだと思います」
「そうそ……ってそんなわけないし! どういうことさ!」
マリアは真っ赤な顔になり、アリスはイタズラっぽい笑みを浮かべている。
二人の態度がどうしても理解できず、幸太郎は声を震わせながら訊く。
「……っ。……ど、どうして二人は僕が怖くないの……?」
「だって……?」
「ねぇ……?」
マリアとアリスは同じタイミングで言った。
「にーちゃん、良い人じゃん」
「お義兄さま、良い人ですもの」
言葉を失う幸太郎へ、マリアとアリスは口々に感想を言う。
「最初はさ、にーちゃんのこと嫌な奴だと思っていたけどさ。そうじゃないことくらいすこし一緒に暮らせば分かるもんだよね。料理美味しいし」
「はい。アタシも最初お義兄さまの強さを知って驚きましたよ。お義兄さまが力の主でなければ、アタシだって恐れたかもしれません。ですが、お義兄さまであれば、そうおかしなことに力を使ったりしないですよね」
もしかしたら、信頼に根拠など不要なのかもしれない。
今まで幸太郎の傍に寄り添う人がいなかったわけではない。両親、祖父、婚約者だった天食セラ、幼なじみの刀自可音……しかし、様々な要因が揃って一緒にいられなくなった。
そういった経験が幸太郎の心に警鐘を鳴らしている。
この子たちだって、いつまでも共にいられるわけではないのだ、と。
しかし、それでも構わないのかもしれない、と幸太郎は思った。
信頼してくれた事実さえあれば、それだけで残りの人生を生きていける。
幸太郎は肉体があればむせび泣いたかもしれない。
それくらい心が揺り動かされていた。
だから、幸太郎は深々と二人に頭を下げた。
「マリアちゃん、アリスちゃん」
「ん?」「はい?」
「ありがとう」
「どーいたしまして!」「こちらこそですよ」
二人はとても嬉しそうに頬を染めて笑った。
<続きは本編へ>