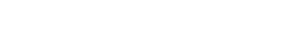試し読み
第一章 羨望と下剋上
1
「丸の内OLって聞いていたのに、女弁護士かよ」 正面に座っていた商社マンが呟いた。 自慢していた力こぶをシャツで隠し始める。賑やかなスペインバルの中で、私たち四人のテーブルにだけ沈黙が流れた。 いつものことだと思った。 ふう、と心の中で一息つくと、 「異議あーり!」 努めて明るい声を発した。右手は小さく上げている。 「玉子は立派なオフィスレディですう」 わざとらしく口を尖らせた。 爪の先には桃色のマニキュアが塗ってある。白いワンピースの上に、薄手のカーディガンを羽織ってきた。耳下で切りそろえたボブヘアは、アイロンで入念に艶を出している。 姿形だけを見て、私を弁護士だと思う者はいないだろう。 商社マンは、突然のブリッコ攻撃に面食らったようで、 「俺、生の『異議あり』、初めて聞いたわ」 と言いつつ、頰を緩ませている。 私だって異議ありなんて、合コンでしか言わない。クライアントは大企業だ。契約書を作ったり、法律相談に答えたりするのが主な業務である。法廷に立ったことなどない。 学生時代からそれなりにモテた。美人ではない私にしては上出来だと思う。 不思議な子だと思わせておけば、こっちのものだ。男は結局、本当は賢い天然ちゃんが好きなのだ。 「美法ちゃんも、弁護士ってこと?」 商社マンの問いに、私の隣で小さくなっている美法が黙って頷いた。 出会いが欲しいと美法が言うから、飲み会を企画した。それなのに、いざ本番になると消極的なのだから嫌になる。 天パは天パのままだし、いつもの眼鏡をかけて、仕事用のスーツでやってきたのにも閉口した。こういうときは、せめてメイクをしてきて欲しい。 「こいつは医者だよ」 商社マンが、もう一人の太ったほうの男を小突いた。 「へえ、すごい!お医者様なんですねえ」 すぐに反応した。条件反射みたいなものだ。 医者の男は、顎先を前に突き出すように頷いた。自信と横柄さが染み付いた動きだ。お世辞は言われ慣れているのだろう。 太い身体、太い首の上につぶれたカエルのような顔がのっている。ブサイクな男だ。 私だってメイクを落とすとブサイクだから、顔について人のことは言えない。けれども、女ってだけで損だ。男なら、稼いでいれば大きな顔ができるのに。冷めた気分になったが、すぐに気を持ち直す。 相手は医者だ。実家が裕福かもしれない。体型は後から変えられる。身だしなみだってどうにでもなる。とにかくポテンシャルを重視して、丁重に接しようと思った。 「忙しいでしょうに、今日はありがとうございます」 「ええ、仕事をしてばかりで、生活面はボロボロですから、誰か支えてくれる人が欲しいですよ」 医者は、窺うようにこちらに視線を投げた。 そうなるともう、お決まりの流れだ。 「じゃあ私が立候補しちゃおうかなあ」 軽い調子で笑いかけた。何も考えずにこのくらいの対応はできる。 この男は、結婚願望があることをチラつかせて、女を引っ掛けてきたのだろう。なめられているようでムカついた。誰しもが自分と結婚したがると思っているのだろうか。 私と同年代、二十代後半の医者なんて、現場じゃ使い走り程度のものだろう。それなのに、男女の場にくると突然大きな顔をするのが気に入らない。年収だって私の半分以下だろう。それでいて生活面を支えて欲しいなどと抜かす男に、こちらから用があるとでも思っているのか。頭の中ではいろんなことを考えてしまう。けれども、即座に自分の思考に蓋をした。考えても仕方ないことは考えない。 彼氏が欲しい。結婚もしたい。それなら、対象者は広くとっておいたほうがいい。今回の人がハズレでも、友達を紹介してもらえるかもしれない。 釈然としない気持ちを脇に置こうとしていると、美法が突然、大真面目な口調で言った。 「弁護士も忙しいです。私も誰か、支えてくれる人が欲しいですね」 医者は驚いたように、一瞬、目を見張った。しかしすぐに素っ気ない調子で応えた。 「ああ。まあね、弁護士さんも忙しいでしょう」 「仕事から解放される時間は、多く見積もっても週に四、五時間くらいです。洗濯や掃除など、最低限の身の回りのことをしていたら、終わってしまいます。でも今は、仕事を覚えるのが一番ですから、仕方ありませんね」 「まあ、仕事も大事だよね……」 仕事の話を始めた美法に、医者は戸惑っているようだった。職業や忙しさでマウントをとっても不毛だ。女同士でも不毛なのに、男女間なら尚更だ。 私はテーブルの下で美法の足を蹴った。出会いの場を欲しておきながら、どうしてその場にふさわしくない受け答えをするのか。全く見当がつかない。 医者の男は、会話に困ったのか、 「玉子ちゃんも忙しいんじゃないの?」 と訊いてきた。私はまた何も考えずに、 「玉子は天才だから、仕事も家事もできるんですう」 と、トボけた調子で続けた。 本当の自分なんてどうでもいい。その場その場で生き残るために、私はいくらでも姿を変えることができる。 男たちは一斉に吹き出して、「天才だったかあ」と笑った。 一瞬の隙をみて、私は美法を睨んだ。 美法は「分かったから」とでも言わんばかりに頷いた。その後の美法は当たり障りのない受け答えをしていた。やればできるんじゃん、と思った。 それでも私は、どうにもイライラが収まらなかった。一体何に対して怒っているのか、自分でも分からなかった。 銀座で男たちと別れて、私たちは丸の内へ歩き出した。 男たちは場所を変えて飲みなおそうと提案したが、私は、 「シンデレラタイムだから」 などと言って、断ったのだった。 しかしその実、私たちの勤務先である山田川村・津々井法律事務所に向かっている。 時刻は十一時を回っていたが、やるべき仕事は沢山あった。 「なんでさあ、雰囲気壊すこと言うわけ?」 さっきより数段低い声で尋ねた。 「ごめんって。蹴ることないじゃん」 言いながら、眼鏡の曇りを袖で拭いている。 「出会いが欲しいって言いだしたのは美法じゃん。だから今日の会を組んだのにさ」 美法とは大学、大学院、就職先と、ずっと一緒にいる。ブリッコだとか言って、私を嫌う女の子たちもいた。けれども美法は、他人にあまり興味のない「法律オタク」だったから、不思議と一緒にいて心地がよかったのだ。 「でもさ、玉子もなんであんなに頑張るの?今日の人たち、正直、微妙だったじゃん」 驚いて、私は思わず目を見開いた。 「ちょ、ちょっと、美法?今日の人たちが微妙って?」 「そうじゃん。私たちが弁護士だって聞いて、あからさまに引いていたし。商社マンだ、医者だって、チヤホヤしてくれて、家事育児一切をやってくれる女を探しているんでしょ」 ちょうど有楽町を抜けたところだった。私は立ち止まって振り返り、美法と向き合った。ヒールの音がカラン、と夜の街に響いた。 「友達として、この際言っておくけどさ。美法って、確かに仕事は頑張っているけど、女としての努力は全然してないじゃん。いつもスッピンだし、身だしなみだってテキトーだし」 街灯にうっすら照らされた美法の表情は硬かった。私の視線から逃れるように、横目であらぬ方向を見ている。 私は一瞬躊躇して口を閉じたが、もう一度開いた。 「だから、つまりさ、男の人からみたときに」 「お呼びじゃないって言いたいんでしょ!」 美法がほとんど叫ぶように言った。素早く瞬きをしている。泣きそうなときの美法の癖だ。 「そうじゃなくて」 「そういうことでしょ。見た目が悪いから、男ウケしないって言いたいんでしょ」 「そうじゃなくて、私はただ、今のままだと美法の良さが男の人に伝わりにくいと思って」 早口のまま続ける。 「恋愛の、一般的な市場の話をしているの。恋愛市場では、稼ぐ男が偉くて、若くて可愛い女が偉いってことになっている。だから、今日の人たちは、私たちよりも恋愛市場では価値が高いってことでしょ。そこは素直に認めたほうがいいって話。それで、自分より上の人を倒すには自分を磨く努力をしないと。自分の側で努力してないのに相手をくさすのは違うと思うし」 「倒すとか、努力とか、何?玉子は何と戦っているの?恋愛ってそういうものじゃないし、戦う相手が違う気がする」 美法なんて、たいして恋愛経験もないくせに、私に向かって何を言っているのだろう。腹が立った。しかし、少しでもそういうことを指摘すると、美法がひどく傷つくというのも分かっている。何も言えなくなった。 「玉子には私の気持ちは分からない」美法は睨みつけてきた。 「私、もともとブサイクなんだもん。ダイエットしたり、おしゃれしたりしても、たかが知れているの。玉子みたいに、磨けば光るタイプと一緒にしないで」 「磨けば光るタイプって……」 美法の言葉を繰り返した。思わず口元がゆがむ。 磨かないと光らないと言われているようで、不快だった。けれども反論は我慢した。見た目について指摘されたことが、美法にとってはショックだったのだろう。逆上して失礼なことを言ってきているのだ。 私は耐えたのに、美法は勢いづいたように言葉を発した。 「だいたい、玉子はブリッコばっかりして、男に媚を売って」 悪い予感がしていた。 案の定、私がこれまで一番言われていて、かつ、一番言われたくない言葉が続いた。 「玉子は結局、男好きなんでしょ?」 思わず下を向いた。ベージュのエナメルパンプスが目に入った。わざわざ低めのヒールを選んでいる。万が一、合コン相手が低身長だった場合に、こちらが相手の身長を越してしまわないよう、配慮していた。 別に男好きじゃない。ただ、私みたいな不美人は放っておくと彼氏もできず、結婚もできない自信がある。だから頑張っているだけだ。男の人は案外、そういった頑張り自体を可愛いと思ってくれることも多い。それをブリッコだとか男好きだとか言われても困る。 「私はただ、努力しているだけ。美法は分かってくれていると思っていたのに」 「玉子だって。本当は私のこと、見下しているんでしょ」 美法はその言葉を残すと、車道へ歩いて行った。ちょうど通りかかったタクシーを止めて、乗り込んだ。事務所と反対の方向へタクシーが走り出した。事務所に戻るのはやめにして、自宅に帰るのだろう。 私は有楽町の街に一人残された。ひんやりとした風にのって金木犀の香りがした。甘くてまろやかな匂いにつられて周囲を見上げた。コンクリートだらけのこの街のどこかに、金木犀の木があるのだろうか。ビルの合間には、ほんの小さな緑地しかない。隠れるように、しかし負けじと立っているなら、まるで私みたいだ。 事務所に戻って仕事をしようと思っていたのに、やる気は完全にしぼんでいた。車道に五分くらい立って、やっとタクシーをつかまえた。さっさと家に帰ることにした。 面倒なことは続くものだ。翌日の朝の食卓のことだった。 いつものように、シマばあちゃんの好きなものばかり揃えた。土鍋で炊いた白米に、甘口醬油が染みた沢庵を添える。昨日の残りの豚汁には、細かく刻んだ生姜を振りかけた。あとは、いりことクルミの佃煮が小鉢に盛ってある。これは作り置きだ。 シマばあちゃんは黙々と食事を平らげた。ちゃぶ台の隅の竹ざるを引き寄せると、中から干し柿を取り出して、三つ食べた。 そこまでは私も何も思わなかった。シマばあちゃんは華奢なわりに大食らいだ。歯が丈夫だからだろう。いつもならお茶をがぶがぶ飲む。だがその日は違った。 シマばあちゃんは湯飲みに手を出すこともなく、突然、 「あたし、結婚することにしたからな」 と宣言をした。 「えっ」手にしていた急須が止まる。 「結婚って、ばあちゃんが?」 「そうよ。ババアが結婚して、なーにが悪いね」 八十を超えているわりに皺もシミもない色白の顔に、大きな鳶色の瞳が輝いていた。量の減ってきた白髪はふんわりと整えられている。「ミス干し柿」に輝き、紀州一の美女と称された娘時代を、六十年以上経つ今でも引きずっている人だ。 「最近はな、シニアこんかつ、ってのがあってな」 こんかつ、の部分をやたらと滑舌よく、はっきり発音した。 脇の書類ケースから、薄ピンク色のパンフレットを取り出し、指し示す。「一期一会の苺会」と大きな文字で書かれていた。 「ここでイケメンをゲットしたからな」 イケメンといってもお爺ちゃんでしょ、と思った。だが指摘すると、二倍、三倍の量の言葉で言い返してくる。私は口をつぐんだ。ちゃぶ台の向こうに座る祖母を見つめる。 「指輪ももらったで」 そう言って、電話台の下からゴソゴソと紙袋を取り出す。「テトラ貴金属」と金文字が刻まれた化粧箱を開け、中央に鎮座するダイヤの指輪を見せつけた。 「ばあちゃん、指輪までもらってるの……」 ダイヤは相当大きい。詳しくないから分からないが、大豆くらいの大きさはある。 二の句が継げなかった。私があくせく働いている間に、ばあちゃんはイケメン爺さんとデートを重ねたり、プロポーズをされたり、指輪をもらったりしていたわけだ。 「あたしが玉子ちゃんより早くお嫁に行くとはなあ。再来月には入籍して、ムネちゃんの家に引っ越すから」 シマばあちゃんは、新聞屋からもらった文字の大きいカレンダーを指さした。今日は十月四日だ。十二月には「ムネちゃん」と結婚するつもりらしい。 「彼、今でも現役で会社をやっていて、シュッとした良い男なんよ。女は愛嬌、男は甲斐性やで。ビシッと女子をリードしてくれる人ってええよなあ。やっぱり野心がある男ってのは、色気があるんよね。何歳になっても……」 シマばあちゃんが独自の恋愛観を語りだすと長くなる。恋バナと言えば聞こえはいいが、私の意見を求められることはない。シマばあちゃんが一人で話し、私は同調するだけだ。 「お家は世田谷のほうにあるらしいわ。玉子ちゃんは、もうババアの面倒は見なくていいから、家を出て一人暮らしするなり、彼氏と一緒に住むなり、好きにしてちょうだい」 私はちゃぶ台に片肘をついて、頭をのせた。平静を装っているが混乱していた。私が生まれる前、三十年以上前に祖父は亡くなっている。祖母の再婚自体は問題ない。しかし、なぜ今更、急に結婚なんて言い出したんだろう。気持ちを落ちつけようと深呼吸をした。 ちゃぶ台の端には、ピルケースが山積みになっていて、朝昼晩の薬を小分けにして入れている。脱水防止用のドリンクの減り具合をチェックしたり、デイケアセンターに送り出したり、病院に連れて行ったり。本人が元気とはいえ、高齢者と一緒に住んでいるとやることは色々ある。それを、どこの誰とも分からない爺さんに任せられるものか。 「私は家を出ていかないよ。別に彼氏もいないし」 茶の間の端においてある仏壇に視線を投げた。父と母が、二十年前の姿のまま微笑んでいる。 「玉子ちゃんなあ、もう三十やろ」 「まだ二十八です」一応、口を挟む。 「何歳でもいいんやけどな。そんな歳で、ババアと一緒に暮らして、どうするん?彼氏がいても、こんなコブ付きじゃ、おちおち結婚できんし」 「だから、彼氏はいないって」 昨日も男がらみで美法と揉めたというのに、今日はシマばあちゃんとこの話をしなければならないのか。気分が打ち沈んだ。 「今彼氏がいなくても、玉子ちゃんなら、すぐできるやろ。そのときババアが邪魔になるやろ」 何度話して聞かせても、シマばあちゃんの頭の中では、玉のような赤ん坊だった「可愛い玉子ちゃん」からイメージが更新されない。いつも私に彼氏がいて、結婚しようと思えばいつでも結婚できるくらいに思っているのだ。 私も学生時代は、そのうち結婚できるような気がしていた。弁護士として働きだしてから雲行きが怪しくなった。第一、仕事が忙しくて恋愛をどうこうする余裕がない。学生時代から付き合っていた彼氏とは自然消滅してしまった。 それに、お気楽に恋愛しているぶんには良いけど、「結婚」となると急に現実感がなくなる。たまにデートするのは楽しいけど、その人が私の生活に入ってくるというのは想像がつかない。仕事をして、シマばあちゃんの世話をして、おしゃれして友達と遊んで──それだけで、一日二十四時間、お腹一杯だ。これ以上、何かを抱えられる気がしない。 それでも心のどこかで、結婚しなくちゃと思っているのが不思議だ。 「私が家を出て行ったら、干し柿、誰が作るの?」 ややムキになって訊いた。 「干し柿くらい、あたし、じぶんで作れるし」 シマばあちゃんが口をとがらせた。 私がブリッコをするときと同じ仕草である。 「お嬢様育ちのばあちゃんじゃ、絶対作れないね。スーパーのは食べられないくせに。私が出て行ったら、ばあちゃん、一生、おいしい干し柿、食べられなくなるんだからね。ふわふわの卵焼きも、いりこ出汁のだご汁も、もう食べられないからね」 本当はどうでもいいのに、食べ物の話ばかり口をついて出る。 「別にあたし、食べたいなんて、言ってないし」 シマばあちゃんの生意気な口ぶりに、腹が立って、くらくらした。 「もう、本当に知らないから」 畳に視線を落とし、放ってあるジャケットをひっつかんだ。もう片方の手で鞄を引き寄せ、立ち上がる。 「仕事、行ってくる。遅くなるからね。お昼ご飯は緑のタッパー、夜ご飯はオレンジのタッパーだよ。薬を飲むのを忘れずに。ピンポン鳴っても出なくていいから。このペットボトルのお水を一本、夜までに飲むんだからね。帰ってきてから私チェックするから」 「はいはいはいはい、任せとけい」 シマばあちゃんの陽気な声にさらに腹が立つ。 いつも勝手なひとだ。こっちの気持ちなんて考えやしない。 私が大手法律事務所で弁護士として働いているのも、半分はシマばあちゃんのためなのだ。今は元気だからいいけれど、介護が必要になって、老人ホームに入ることになるかもしれない。プライドの高いシマばあちゃんのことだ。そこらの老人ホームではケチをつけるに決まっている。こちらとしても、少しでもいい暮らしをしてほしい。 事務所から二駅の下町に、古い一軒家を賃借しているのもシマばあちゃんの要求によるものだ。畳と布団でないと眠れないと騒ぐから。 縁側には、沢山の柿がぶら下がっている。朝日を浴びて飴色のカーテンのようだ。そろそろ完成だから収穫しようと思っていた。 ばあちゃんは勝手に結婚だなんて。私の将来を気遣っているとしたら、最悪だ。 私は今の生活で満足しているというのに。 二駅ぶん歩き、勤務先である山田川村・津々井法律事務所に向かった。ダイエットのために歩いて事務所に行くようにしている。けれども、そのくらいじゃ全然痩せない。 執務室に近づくと、珍しい人が執務室の前で仁王立ちしていた。 「遅いじゃない」 腕を組んだまま、不機嫌そうな声をかけられる。 剣持麗子という弁護士だ。 体のラインにぴったり沿うパンツスーツを着て、雄のライオンのたてがみのように、ロングヘアをはためかせていた。 剣持先生は、私よりも一年先輩にあたる。 同じ部署で、よく一緒に仕事をする仲である。人使いが荒いし、勢いがあって怖いときもあるが、その点は案外平気だ。ワガママ放題のシマばあちゃんの世話で、普段から鍛えられているからかもしれない。 しかしそれでも、私は剣持先生が苦手だった。 剣持先生は確か、都内の中高一貫進学校を出て、名門私立大学に通い、するっと司法試験に合格した人だ。実家もある程度お金持ちで、顔もよくて、スタイルもよくて、私じゃ絶対穿きこなせないようなパンツスーツをサラッと着てしまう。そばにいると自分がみじめに思える。だからなんとなく嫌い。 それだけではない。剣持先生は、今年の初めにボーナス額が小さいという理由で事務所を飛び出し、数か月仕事を休んでいた。そのせいで私に割り振られる仕事量が増えて、すごく忙しかった。何食わぬ顔で戻ってきて同じ事務所で働いているというのも、厚かましくて嫌悪感があった。 腕時計を見ると時刻は午前九時である。弁護士の出所時間としては早いほうだ。やや警戒しながら口を開いた。 「おはようございます。どうかしましたか?」 「ねえ、古川君と連絡つく?あなた仲良いでしょ」 剣持先生は挨拶もなしに、本題から入った。 「仲良いというか、同期ですが」 古川君とは大学院から一緒だ。同じ部署に配属された同期だから、同じ案件に入ることは少ない。 案件規模にもよるが、通常、法律事務所では三人くらいのチームで動くことが多い。一番上にはベテラン弁護士、その次に中堅弁護士、そしてその下に若手が入る。若手弁護士が多く動員されるような大型案件でない限り、古川君と私が同じ案件に入ることはない。 もちろん同期だから助け合うことはある。分からないことを訊いたり、忙しいときにリサーチを肩代わりしてもらったりといった融通を利かせあう。というか、丁寧に頼むとだいたい引き受けてくれるから、古川君には助けてもらってばかりだ。 「昨日の夜から連絡が取れないの。昨日の夜、七時半に慌てて出ていったから、あれはきっと合コンだと思うんだけど。でも普通なら、その後事務所に戻ってくるじゃない?」 ワーカホリックな剣持先生は、確かに飲み会の後も事務所に戻るし、朝も七時頃から働いていると聞く。 「急ぎの案件があるんだけどなあ」 そういえばと思い、携帯電話を取り出して、同期たちとのメッセージを遡った。 「古川君、昨日の夜から熱が出ているみたいです。風邪っぽいって」 「風邪ですって?」 剣持先生が急に大きな声を出すから、私は思わず身を縮めた。 「風邪ってどういうことなの」 睨みつけられて、困惑した。「私に言われましても」 「だいたい、社会人がいい歳をして、風邪をひくっていうのが間違っているのよ。危機管理能力が足りない証拠だわ。手洗いうがいをきちんとして、疲れが出たら早めに休むとか、できること、いろいろあるでしょう」 執務室の入り口脇の壁に背中を預けて、腕組みをしたまま続ける。 「だいたい古川君は、あんなに体を鍛えていて、それでいて風邪をひくってのはどういうことなの。あの筋肉は飾りなの?」 執務室の前はオープンスペースになっていて、秘書やパラリーガルのデスクが広がっている。怒り心頭の剣持先生を前に、秘書たちが含み笑いをしながら、顔を見合わせている。 剣持先生は、周囲の反応には全く構わず、仏頂面のままだ。 十月に入って、朝晩は急に冷え込むようになっていた。体を鍛えている古川君があっさり風邪をひいてしまうのは確かに滑稽だが、そういうこともあるだろうと思えた。 「体が弱い人もいますから、風邪をひくのは仕方ないんじゃないですか」 剣持先生は体の向きを変えて、私の顔を覗き込んだ。自分の言葉に後輩が反論してくるのが気に入らなかったのだろうか。大きな目がじっと私を見ている。怒っているのか考えているのか、その表情は読めない。 私は身構えたが、剣持先生は顎に片手をあて、 「風邪って、普通そんなにひく?」 考え込むように首をかしげるとつぶやいた。 「私はこれまでの人生で、風邪なんてひいた覚えがないんだけど」 眉を持ち上げて、珍獣を見るように不思議そうな顔を私に向けている。剣持先生は噓を言っているわけでもなく、意地悪をしているわけでもない。ただ本当に、風邪をひくことが信じられないのだろう。 私は小さくため息をついた。 きっと、剣持先生はすごく恵まれているから、悩みなんてないのだろう。弱い人の気持ちなんて分からない。まして、私の気持ちが分かるはずない。地方から苦労して出てきて、奨学金を借りてなんとか学校を出て、祖母の世話をしながら働いている私の気持ち。 剣持先生は私の反応に構うことなく口を開いた。 「まあ、いいや。美馬先生、あなたが担当してちょうだい」 「ええ、私がですか?」 急に自分に白羽の矢が立って、顔を上げる。私よりも背が高い剣持先生の顔を見上げ、その本意を窺おうとした。 「誰でもいいってわけじゃないんだけどさ。美馬先生なら古川君の代打が務まるでしょう。私も本当は嫌なのよ。どんな案件か知らないけど、ぜんっぜん儲からないのは確かよ。落ち目の会社だもん。津々井先生の顧問先だから、仕方なく業務を引き受けたけど」 津々井先生というのは、剣持先生と私が配属されている部署のボスだ。この事務所の創設者の一人でもある。 聞くところによると、一度事務所を飛び出した剣持先生が戻ってこられたのは、津々井先生の尽力があったためらしい。義理があるから、津々井先生の案件だと断れないのだろう。 「じゃあ三時に会議室集合ね」 そう言うと、剣持先生はすたすたと歩き始めた。 「ちょ、ちょっと。私も今やっている案件で、手一杯なんですけど」 後ろから声をかけると、剣持先生はくるっと振り返り、ものすごいスピードで引き返してきた。 私の目の前でぴたっと止まり、 「できないの?」 とすごんだ。 うっすらといい香りがした。香水をつけているのかもしれない。近くで見ると、髪の毛も毛先まできれいにカールがついている。シンプルにスッと入ったアイラインは全然にじんでいない。艶のある肌からは余裕が感じられた。 私とは大違いだ。 早朝に起きて、眠い目を擦りながらシマばあちゃんの食事の作り置きをする。タッパーに詰めて粗熱をとっている間に、慌ただしく化粧をしているのだ。 アイプチで二重幅を作り、涙袋にうまく色をのせて目を大きく見せる。フェイスカラーを駆使して顔に立体感を出し、鼻筋も細く通す。こまごまと手を入れる部分が多いから、化粧は剣持先生より大変なはずだ。 その後に朝食の用意をして、シマばあちゃんを起こす。誤嚥なく朝食を平らげるのを見守ったのちに、家を出ている。 学生時代から染みついたルーティンだから慣れている。けれどもやはり、体力的に辛いときはある。 剣持先生の顔を見ていると無性に腹が立った。彫りの深い綺麗な顔。何の苦労も知らないくせに。大きな下駄をはいて、すいすいと進んできただけのくせに。 「できないならいいんだけど」 軽く顎をあげて剣持先生が言った。 「できます」私は反射的に答えていた。 「やりますから」 剣持先生は私の顔をじっと見た。 一瞬、黙っていたが、すぐに、 「オッケー、オッケー」 と笑うと、踵を返し、大股で歩いて行った。 びしっとまっすぐ伸びたその背中を見ていると、やはりどうしても腹が立った。剣持先生は悪くない。それも分かっている。 でも、どうやったって、許せないのだ。この世の不公平や不条理が許せない。 いつも思ってしまう。どうして私が、どうしてあの子が、と。 大きく深呼吸をした。自分の中に渦巻く黒い感情に飲まれそうなときは、心に蓋をするしかない。どうしたら、こんな状態から抜け出せるのか分からない。だけど私にできることは限られている。働くしかない。 「先生、大丈夫ですか?案件受けすぎですよ」 脇から、秘書が気遣わしげに声をかけてきた。 「大丈夫です」 無理やり笑顔を作って、大きく頷いた。
2
その日の午後三時、会議室に入ると、剣持先生が待ち構えていた。六人掛けの座席の上座に腰かけている。 上座下座といったビジネスルールに対して、弁護士はルーズだ。身内だけの会議なら特にそう。うるさく言う人もいない。むしろ入り口近くの下座に座っていると、後から入ってきた人の邪魔になる。詰めて座ったほうが親切かもしれない。 私も会議室の奥へと歩みを進め、剣持先生の正面に座った。 まもなく扉が再び開いて、津々井先生が入ってきた。 見事に丸い体型と、丸い顔だ。人のよさそうな微笑を常に浮かべている。小脇に抱えた書類を机の上に置くと、私の隣に座った。 「ゴーラム商会がね、倒産しそうです」 なんともないというような口調で、津々井先生が言った。 剣持先生も平然とした顔で、眉ひとつ動かさない。 「ゴーラム商会って、あのレインブーツで有名な?」 驚きを抑えながら、私は訊いた。 ゴーラム商会といえば、有名なアパレル企業だ。海外の新興ブランドを日本に持ち込んで、独占販売をする会社として創業した。 特に、二十年ほど前から取り扱っているカラフルなレインブーツのシリーズは、当時としては画期的で、若い女性から熱狂的な支持を得た。徐々にオリジナルブランドも充実させて、今ではアパレルの売上シェアで十本の指に入る。創業してから三、四十年は経っているはずだ。 「残念ながら倒産しそうです」 津々井先生は微笑を浮かべた。 笑いながらする話ではない。瞬間的に、津々井先生に対して反発を覚えた。 ひとつの会社が倒産しそうなのだ。社員には家族もいる。取引先もある。何百、何千の人間の生活がかかっている。その事態の大きさを分かっているのだろうか。 津々井先生のような百戦錬磨の弁護士になると、企業倒産なんて見慣れているのかもしれない。けれども、「よくあること」で済ましてしまう姿勢が、私には引っかかった。 津々井先生は落ち着いた調子で続けた。 「売れ筋だったレインブーツのシリーズですが、実は昨年、本国の企業から独占販売契約を打ち切られてしまいました。その後、資金繰りが悪くなって、もうどうしようもない。どの銀行も助けてくれません」 レインブーツの独占販売契約が終了したというニュースは、大々的に報じられていた。 もっとも、ゴーラム商会の経営悪化について、特集された記事は見たことはない。アパレル業界全体が不況に見舞われていたため、そう特別視されていなかったのだろう。 「売れるものはないんですか?」 剣持先生が腕組みしながら口を挟んだ。 「一部の事業を切り出して他社に売って、引き換えに得た現金で、延命することはできるでしょう」 津々井先生は頷いた。 「うちの事務所の倒産チームが、その方向で対応を模索しています」 弁護士が四百人を超える大規模事務所になると、得意とする法分野によって部署が分かれている。 津々井先生を筆頭に、剣持先生や私が属するのはコーポレートチームだ。主に会社法を専門として、会社の平常運転時のサポートをしている。病院で言うと、内科のようなイメージだろうか。 それとは別に、倒産法を専門とする部隊がいる。会社が危機的状況に置かれた場合に活躍するのは、倒産チームだ。瀕死の会社を相手にする、救急救命室のようなものだ。 景気がいいときは、コーポレートチームが儲かる。逆に景気が悪いときは倒産チームが儲かる。両方のチームを抱えておけば、景気の動向に左右されず、事務所の収益は安定する。 そのほか、金融取引を担当するファイナンスチームもある。やたら長くて複雑な契約書をまとめる超絶技巧が必要となる。法律オタクの美法はファイナンスロイヤーだ。マニアックな法律を調べて、細かい条文の細かい処理を活き活きとこなしているらしい。 働き始めて数年のうちに、どのチームに腰を据えるか決める弁護士が多い。もちろん、チームをまたいで仕事をすることもある。その中で適性を見つけて、所属チームを変更する者もいる。 「まずはなるべく倒産を避ける方向で頑張るようです。事業の一部を売れば、現金が入ってきて、しばらく社内は落ち着くはずです。そのあたりは倒産チームに任せておきましょう」 津々井先生は、持参した書類に手を伸ばしながら続けた。 「先生方に頼みたいのは、ゴーラム商会に関する別件です。ゴーラム商会には、内部通報窓口があります」 内部通報窓口というのは、社内で不正や不祥事があった場合に通報できる窓口だ。内部のコンプライアンス部門のほかに、外部弁護士宛ての窓口を設置している会社も多い。 「うちの事務所に設置されている外部窓口に、一件、奇妙な通報がありました」 剣持先生と私に一枚ずつ、書類を配る。 「一旦、読んでみてください」 私は手元の書類に目を落とした。 電子メールをプリントアウトしたものだった。匿名通報用の窓口のため、差出人の名前やメールアドレスの記載はない。 しかし、メールの件名からして、様子がおかしかった。 【件名】倒産続きの同僚 経理部の「近藤まりあ」を知っていますか。 彼女が転職するたびに、会社が潰れるんです。次はウチが潰れるのではないかと噂になっています。 彼女が過去に勤務した三社はすべて、倒産しています。こんな偶然って、あります?彼女が不正行為をして、潰して回っているんじゃないですか。 そういう人を放置されると迷惑です。真面目に働いている人がバカみたい。処罰してほしいです。 読み終わっても、剣持先生も私も口を開かなかった。正直言って戸惑っていた。念のためもう一度読み返すが、混乱は収まらない。 内部通報というと、たいていはパワハラかセクハラの通報だ。社内の人だけではなく、取引先からも通報を受け付けていることが多いから、営業担当がこっそり売上を水増ししているとか、バックマージンを受け取っているといった通報が入ることもある。 だが、会社を潰す女がいるなんて話は、聞いたことがない。 剣持先生も同様に戸惑っているようだった。書類を見つめながら、瞬きもせずに固まっている。 「あの、これは……どういうことでしょうか」私はおずおずと訊いた。 津々井先生は、面白がるように頰を緩めた。 「さしずめ、連続殺『法人』事件ということでしょうか。私にもよく分かりません。そして、分からないことを調べるのが、先生方の仕事です」 剣持先生が顔を上げて、不快そうに眉を寄せた。 「全く、馬鹿らしいことだわ」 その日の晩、剣持先生がぼやきながら、私の執務室にやってきた。 片手にブラックコーヒーを持っているが、それは彼女自身が飲むもので、もちろん私のぶんはない。 「あんなアホらしい調査をするなんて、津々井先生の気は確かなのかな」 昼の会議の際にも、剣持先生はさんざん嚙みついた。こんな具体性のない通報を相手にする必要はない。人間ひとりの力で会社が潰されるなんてありえない。たまたま落ち目の企業にばかり転職している人かもしれない。 その主張はどれももっともだったが、津々井先生は頑として聞き入れなかった。 「ですから、この通報が悪戯かどうかを調べるのが、先生方の仕事です」 と言って、一歩も引かないのだ。 通報があった以上、何もしないわけにはいかないのも確かだ。形式的にでも弁護士が調べなくてはならないだろう。 押し問答をしているうちに時間切れとなり、三人はそれぞれ次の予定へ散った。私たち弁護士は一度に数十個の案件を担当しているから、一つの案件にばかり構っていられない。 今日の予定をあらかた済まして、やっと落ち着いた夜十一時過ぎに、ふとゴーラム商会のことを思い出した。剣持先生も同じような状況だろう。 「これ、本当に調査するんですか?」 私が訊くと、剣持先生は眉間にしわを寄せた。 「するしかないじゃない。ボスがそうしろって言っているんだし」 近くの椅子に腰かけて、渋い顔で天井を見上げている。剣持先生なりに我慢をしているらしい。 「ああもう、こんなときになんで古川君は寝込んでいるわけ?信じられない」 とボヤキながら、椅子のキャスターを揺らす。 「まあ、とりあえず、ゴーラム商会のコンプライアンス担当に連絡をとってちょうだい。近藤まりあの履歴書を出してもらって、経歴を確認しましょう」 「その件なのですが」 私は控え目に口を挟んだ。 「昼間のうちにゴーラム商会に連絡をとったのです。一応、管理部門の役員の安西さんにつないでもらいました」 通常、内部通報の処理の仕方については、事前に一定の処理手順が指示されている。ゴーラム商会の場合、まずはコンプライアンス担当者に対して、通報があったということを速やかに報告することになっていた。 「法務・コンプライアンス担当のメンバーが相次いで離職したため、対応できる人がいないそうです。総務課員がなんとか契約書の対応をしている状況らしくって。内部通報なんて、とてもじゃないけど対応できないから、先生方で適当に調べて欲しいとのことです」 剣持先生の表情がみるみる硬くなるのが見て取れた。 「適当にってどういうことよ」 腕を組んで、不機嫌そうな顔をしている。 「会社としても余裕がない状況なのでしょう」 なぜか私が会社側のフォローをする。 「落ち目の会社。倒産しそうだから、社員がどんどん辞めていっているってこと?」 「そういう面もあるのですが、もともと入れ替わりの激しい会社のようです。安西さんがぼやいていました」 剣持先生はさっと立ち上がると、 「全く、そうやって、ずさんでテキトーな会社だから倒産するんじゃないのかな。とにかく、近藤まりあの履歴書をお願いね」 と言って、執務室を出て行った。 私はその場で身じろぎもせず、自分の中で、剣持先生が何気なく発した言葉を繰り返していた。 ──ずさんでテキトーな会社だから倒産する。 剣持先生は何も分かっていない。弱い人、困っている人の気持ちなんて、分からないのだ。 苛立ちとともに、不思議と嬉しさが込み上げてきた。 剣持先生の欠点を見つけるたびに嬉しくなる。剣持先生の動きや言葉の端々から、彼女の未熟さを感じ取る。その度に彼女を見下すことができる。それが嬉しい。 彼女の未熟な言動はなるべく記憶しておいて、自分の中にストックしておこうと思った。ことあるごとに取り出して、眺めて、楽しもう。自分のように恵まれない人間には、そのくらいのことをする権利があるはずだ。 その晩のうちに、担当役員の安西にメールをしておいた。内部通報の調査のため、近藤まりあの履歴書を送ってほしいと依頼したのだ。 だが返信があったのは、二日経ってからである。 「だから、ゴーラム商会はこういうところがダメなのよ。対応が遅すぎる」 と剣持先生は、送られてきた履歴書を眺めながら言った。 私たちは、事務所の会議室で向き合っていた。 「通報があったら速やかに調べる。それが鉄則じゃないの」 先日は「調べる必要なんてない」と津々井先生に食ってかかっていたというのに、いざ調べるとなると乗り気である。 本人は「こんな、お金にならない案件はさっさと片づけてしまいましょう」と言っていた。 しかしそれも、どこまで本当か分からない。もともと剣持先生は津々井先生のお気に入りなのだ。細かい案件もソツなくこなすことで、更なる点数稼ぎをしたいのではないかと邪推してしまう。
| 22歳 | 小野山メタルに入社 |
|---|---|
| 24歳 | 小野山メタルが破産申請、解雇 |
| マルサチ木材に入社 | |
| 26歳 | マルサチ木材が民事再生申立、解雇 |
| 高砂フルーツに入社 | |
| 29歳 | 高砂フルーツが破産申請、解雇 |
| ゴーラム商会に入社 | |
| 31歳 | 現在に至る |
「ま、それはそれとして。確かにこれは、変な経歴ね」 手元の履歴書には、以下のようなことが書いてあった。 近藤まりあ。三十一歳。新宿区神楽坂在住。 都内の中堅私立大学を卒業後、二十二歳で小野山メタル株式会社に入社。二十四歳のとき、小野山メタルが破産し、社員は全員解雇された。その後ほどなくして、マルサチ木材という会社に入る。だがその二年後、マルサチ木材は民事再生を申し立て、近藤は二十六歳で整理解雇されている。次に入社したのは、高砂フルーツ株式会社。高砂フルーツは、近藤の入社後三年ほどで破産している。 そして今回のクライアントであるゴーラム商会に入社した。現在、入社からちょうど二年が経とうとしている。 「確かに、これまでの三社とも、入社後二、三年で潰れていますね」 私が言うと、剣持先生が続きを引き取った。 「そして、ゴーラム商会に入社して二年。ゴーラム商会は倒産の危機に瀕しているってわけね」 だが、近藤という女が会社を潰して回っているとは、にわかには信じられなかった。 「単純に、不運な人なのでは?笑えちゃうくらい不運続きの人って、実際いるじゃないですか」 私の言葉に、剣持先生が首を傾げた。 「そうなのかしら。能力のない人だったら、経営の危ない会社しか引き取り手がいなくて、劣悪な環境を渡り歩く羽目になることってあると思う。だけど、この近藤って人は、大学卒業後、一貫して経理の仕事をしていて、専門性も高い。簿記一級も持っている」 履歴書の資格欄を指さした。 「それにこの人、転職の度に年収が少しずつ上がっている。つまり能力は十分にあって、会社が潰れる度に、彼女自身はステップアップしているのよね」 私は、履歴書とセットになった職務経歴書のほうに目を落とした。 彼女の年収は、二百八十万円から始まり、三百三十万円、三百七十万円と上がっている。現在、ゴーラム商会での年収は四百五十万円だという。三十一歳の女性としては、なかなかのものだ。 「でもやっぱり変よね。そもそも、資格もある経理のプロなら、もっと年収の高い企業に行くこともできるんじゃないかしら。たった四百五十万円ぽっちで満足するのは不自然だわ」 剣持先生が眉をひそめる。 「別に、お金だけで会社を選ぶわけじゃないと思いますけど」 と一応、私は口を挟んだ。 だが確かに、近藤の会社選びは少し不自然に思えた。 一社目の「小野山メタル」は、金物屋から始まり、台所用品などをデパートや量販店に卸していた会社だ。次の「マルサチ木材」は、材木の卸問屋である。三社目の「高砂フルーツ」は、果実の販売をしていた。現職の「ゴーラム商会」はアパレルの販売を行っている。 物品販売という共通点はあるものの、扱っている商材は全く異なる。経理という職種は一貫しているとはいえ、業種選択がバラバラなのが気になる。 履歴書に添付された顔写真に視線を落とす。 黒髪を後ろで束ねている。前髪はリクルートでよく見かける七三分けだ。目尻の先に大きなホクロが一つ、目立っている。全体としてはあっさりとした顔立ちで、印象は薄い。キツネ顔ふうの美人だ。 「どうします?」 私が問うと、剣持先生はちょっと間をおいてから口を開いた。 「仕方ないわ。もうちょっと調べるしかない。この通報がデマだとしても、デマだってことは確かめなくちゃいけないから。各社の倒産原因を洗い出しましょう。この近藤という人が、明らかに倒産と無関係だと分かった時点で、調査は終了よ」 私は、手元の履歴書を見つめてため息をついた。もう倒産している会社だ。倒産原因を調べるのにも手間がかかるはずだ。 その点を指摘すると、剣持先生は呆れたように笑った。 「何言っているの。近いところから調べればいいわ。まずはゴーラム商会がどうして倒産しそうなのか調べましょう。うちの事務所の倒産チームが対応しているんだから、倒産チームに訊きに行こう」 「訊きに行くって、もしかして川村先生ですか?」 私は顔をしかめながら言った。 川村先生は、倒産チームのボスだ。津々井先生と同様、事務所創業時のメンバーの一人でもある。だからこそ、事務所名に名前を連ねている。 直接話したことはないが、見た目が怖い。筋肉質で浅黒く、なぜか色付きの眼鏡をかけている。外見だけだとインテリヤクザのようだ。声がとてつもなく大きくて、怒鳴り声で部下の鼓膜を破ったという伝説もある。が、それはさすがに誰かの脚色だろう。 「大丈夫よ、川村先生は話せば分かる人だから。弁護士としても優秀だし」 剣持先生は肘をついた状態で、手の平だけひらひらと動かした。なぜか上から目線の評である。 「津々井先生よりもずっとやりやすいわよ」 業界で評判の倒産弁護士だし、クライアントからの信頼は厚いと聞く。 けれども高圧的な人は嫌だ。怒鳴り声も苦手である。気が重くて、もう一度ため息をついた。 その日の午後、私たちは連れ立って、倒産チームが勤務するフロアへと向かった。 担当する法分野ごとに、ざっくりと執務エリアが分かれている。私たちが所属するコーポレートチームは女性弁護士も多いし、仕事はほぼパソコン上で完結するから、フロア全体がすっきりしている。 一方、倒産チームのフロアは、様子がかなり異なっていた。 ファックス付きのプリンターがずらりと並び、電話がひっきりなしに鳴っている。裁判所とのやり取りでは、いまだにファックスを使うらしい。 全体的にタバコの臭いが漂っている。執務室は禁煙のはずだが、喫煙する弁護士が多いため、スーツや持ち物に臭いが染み付いているのだろう。 ダンボールや書類が積まれた通路を、剣持先生はずんずんと進んでいった。歩くスピードが速すぎて、ついていくだけで息切れしそうになる。 「全く、ここはいつ来ても、なんでこんなに汚いのよ」 と言いながら、通路に落ちている空のペットボトルを拾い上げ、近くのごみ箱に投げ入れた。ごみ箱まで数メートルの距離があったが、ナイスシュートだった。 「整理整頓ができていないと、非効率よね」 確かに剣持先生は大雑把に見えて案外きれい好きだ。というか、身の回りに無駄なものがない。 弁護士は自分のデスクで人生の大半を過ごす。そのためか、デスクの周辺に家族やペットの写真などを飾る人も多い。かく言う私も、自分のデスクには友達と旅行したハワイの写真を置いてあるし、パソコンにはお気に入りのレースカバーをかけている。多少でも可愛くしないと仕事のモチベーションが続かない。 剣持先生のデスクには、パソコンとキーボードがポツンと置かれているだけだ。荷物はいつも少ない。仕事以外に何の楽しみもない人なのだろう。 剣持先生は、角の執務室の前にすっと立ち止まって、 「ここね」 と言うやいなや、間髪を入れず、ドアをノックした。 相手が返事をする前に、ドアを開けて、 「失礼します」 と入っていく。 私は小走りになって、その後に滑り込んだ。 個室の奥に腰かけた川村先生が顔を上げた。 日焼けした四角い顔だ。むすっとした表情のまま、一言も発しない。噂通り厳つい風貌だ。身体自体は中肉中背だが全体にゴツゴツしている。小型のゴリラのようにも見えた。 一瞬、川村先生と目が合ったが、私は思わず目をそらした。強面の男と視線を交わすのは愉快ではない。 剣持先生は何も気にしていないようで、いつもの通りの口調で、 「お時間ありがとうございます」 と言い放った。 川村先生は、再び手元の資料に目を落とした。 「後にしてくれ。忙しい」 噂で聞いていたよりは普通の音量だった。だみ声のわりに滑舌は良い。 きっぱりした物言いから、相手を拒絶している感じがひしひしと伝わってきた。小娘二人を相手にする暇はないと言わんばかりの様子だ。 こういった雰囲気、私は苦手だ。とても居心地が悪く感じる。 思わず、 「すみません、それではまた後ほど」 と口走り、剣持先生に横目で視線を送った。 しかし剣持先生は、私に構うこともなく、 「事前に秘書を通じて、お時間を確保していただいているはずです」 と言った。堂々とした口調だ。 そして許可も取らずに、部屋中央にある応接セットに腰かけた。私も慌てて剣持先生の隣に小さく座る。 事務所の中でも偉い弁護士には、こういう広い角部屋が与えられるのだ。応接セットの脇にはゴルフのパター練習マットが敷かれている。ドラマに出てくる昭和の社長室のようだと思った。 「それで、お願いしていた件ですけど、ご説明頂けますか?」 剣持先生はにっこりと営業用の笑顔を作ったが、口調はあくまで事務的だ。 「お願いしていた件とは?」 川村先生は、手元に顔を向けた姿勢のまま、視線だけ上げた。薄い色のついた眼鏡の奥に、細い目が光っている。 剣持先生は平然とした顔で答えた。 「ゴーラム商会の経営悪化の原因についてです」 川村先生は、手に持っていたペンをゆっくり机の上に置いた。 「君たちと私とは、チームも別だし、受けている案件も別」 酒焼けした太い声だ。 「クライアントの中での担当部署も別だろう。私の案件の情報を、君たちに融通することはできないよ」 言葉を切ると、私の顔をじろりと見た。すぐに手元の書類にまた視線を落とす。不機嫌そうに舌打ちをしてから、書類を一枚めくった。 自分たちの対応のせいで川村先生の機嫌を損ねているのではないかと不安になった。相手の機嫌を損ねている状況というのは、たいそう居心地が悪い。私はこういうとき、多少自分を曲げてでも、さっさと謝って事を済ませてしまいたくなる。 脇を見ると、剣持先生は涼しい顔をしている。ランチのあとにコーヒーを飲んで、一息ついたとでもいうような、リラックスした様子だ。 川村先生は五十代後半だ。私たちより三十年もベテランである。しかも津々井先生とは若いころからライバル関係にあったという。津々井先生の子飼いの弁護士である私たちを目の敵にしていてもおかしくない。 「事前にゴーラム商会に連絡を入れておきました。川村先生に案件を依頼している担当部署のほうでも、事務所内での情報共有を承諾されています。その旨、先生にも連絡が行っているはずです」 「私は聞いていない」 川村先生はぴしゃりと言った。一瞥もよこさない。 「先生、メール見てないでしょう。さっさと見てください」 剣持先生はそう言って、机の上に置かれた携帯電話を指さした。 川村先生は事務所の中でも機械オンチで有名だ。メールを打たせると誤字が多いし、メールチェックの回数も少ない。それでも、肝心のクライアント受けは良いのだから不思議だ。優秀な秘書や若手弁護士が支えているから、業務全体としては問題なく回っているのかもしれない。 とはいえ、川村先生もその弱点を自覚しているらしい。剣持先生の指摘を受けて、あからさまに顔をしかめた。 忙しいからといって若手弁護士を追い返そうとしたり、苦手だからといってメールチェックを怠ったりする川村先生も困ったものだ。だが、剣持先生の態度も尊大でよくない。苦手なことをやれと命じられると、男の人はへそを曲げるに決まっているのに。 私は助け船を出そうと、恐る恐る口を開いた。 「川村先生、お忙しいところ申し訳ございません。我々コーポレートチームとしましても、ゴーラム商会の案件の重大性を認識しており、何とか対処しなくてはならないのです。しかし、津々井先生は顧問でありながら、ゴーラム商会の財務状況について、ほとんど把握されていないようなのです」 実際のところ、津々井先生はゴーラム商会の財務状況の悪化については前々から承知している。経営が悪化している企業にビッグディールが舞い込むことはない。そしてビッグディールがなければ、コーポレート弁護士の財布は潤わない。つまるところ、津々井先生はゴーラム商会を「金にならないクライアント」と見切り、放置しているのだ。 とはいえこの局面では、津々井先生の体裁を下げることで、そのライバルである川村先生に花を持たせるのが得策に思えた。 「ですから、川村先生のお力が是非とも必要なのです。このとおり」 丁寧に腰から頭を下げた。隣で剣持先生がつぶやいた。 「仕事なんだから、協力して当然でしょう。こうやって頭を下げないと協力してくれないってのが、そもそも間違っているのよ」 私はそれを無視した。頭を下げたままの姿勢で動かずにいる。 三秒、四秒、五秒……十秒くらい経過したところで、 「まあ、分かりましたから。頭を上げなさいよ」 と川村先生が言った。 私はすぐには動かず、 「ありがとうございます」 と言ってから、顔を上げた。そして、 「お忙しいところ恐縮ですが、何卒宜しくお願いいたします」 と、さらに頭を下げる。 こういうのは、やりすぎるくらいが丁度いいのだ。 「まあ、まあ。頭を上げて。津々井の部下にも、なかなか見込みのある子がいるもんだな。なっ。君、どうだい今度ゴルフでも」 川村先生は、さっきとは打って変わって破顔している。 剣持先生は呆れたように口を半開きにしながら、川村先生へ視線を注いでいた。 「ええでも、私、まだまだ下手ッピなんです」 と言って、小首をかしげた。 「可愛いゴルフウェアを着るためにゴルフを始めたようなもので」 こういうブリッコも、やりすぎるくらいで丁度いい。 「大丈夫だあ。変なところに飛んだボールは全部、哀田が走って拾ってきてくれるから」 哀田というのは、三十代後半の弁護士だ。 倒産チームで川村先生の右腕とも言われているが、その実、体よくこき使われているだけだ。 通常、弁護士として十年ほど働いて、三十代半ばになると、「パートナー審査」にかけられる。「パートナー」とは、自分自身でクライアントを獲得して、事務所を共同経営するメンバーのことだ。 つまり、自力で客を獲れる見込みのある弁護士は「パートナー」になる。それ以外の弁護士は事務所を去るか、他のパートナーの補助的な業務を行うか、選択しなければならない。 哀田先生は実力も十分あったというのに、未だにパートナーになれずにいる。手下としての使い勝手のよさゆえに、川村先生が手放したがらないと聞く。 「そうだ。ゴーラム商会の件も、哀田に任せているから、明日にでも哀田に会社を案内させよう」 勢いよくそう言うと、川村先生は机の上の電話機を手に取った。内線で自分の秘書に指示を出しているらしい。 執務室を出ればすぐそこに秘書は常駐しているというのに、席を立たずに内線をするのは奇妙だ。しかし何でも内線で済ませる弁護士は多い。 私たちはにこやかに二、三、言葉を交わし、執務室を出た。 最初からこうやって、柔らかく対応すればいいのに。剣持先生が変に意地を張るから、話がややこしくなるのだ。 自分たちの執務室に戻りながら、剣持先生が口を尖らせた。 「なんであんなに下手に出るの?」 こちらからすると、どうしてあんなに直截的な言い方をするのか理解できない。おじさんなんて、適当にチヤホヤして、下手に出て、転がせばいいだけなのに。 「そのほうが話が早いからですよ。実際、頭を下げたことで、スムーズに話がまとまったじゃないですか」 剣持先生は、不満そうに腕を組んでいる。 「そんなことないよ。川村先生って、あんな感じだけど、話せば分かる人よ。別にペコペコしなくたって、あと何往復か押し問答すれば、こっちの要求を聞いてくれていたわよ」 そんな話、どこまで本当か分からない。 結局、私のパフォーマンスで話がまとまったのが不満なのだろう。 「ま、別にどっちでもいいんだけどさ。話をつけてくれて、ありがとね」 剣持先生はあっけらかんとした感じで言うと、さっさと自分の執務室に戻ってしまった。 こだわりのないその様子に、逆に腹が立った。私に嫉妬して、私に対して意地悪してくるほうがずっとマシだ。私のことなんて、いかにも眼中にないといった態度だ。見下しているわけでもない。そもそも無関心なのだろう。 胸の内で、黒い感情の破片が、少しずつ寄り集まるのを感じた。なんとしてでも、剣持先生の嫌がる顔や、苦しむ顔を見たいと思った。 自分が何を憎んでいるのか分からない。でも、強いていうなら、自分より「上」にいる人は、みんな嫌いだ。みんなして不幸になればいいのに。その時になって、助けてくれって言われても、絶対助けてやらないんだから。 そんなことを考えながら、その日は残務をこなした。不思議なことに、仕事は捗った。いつもなら深夜零時を回るころに家に帰るのに、その日は午後十時に帰宅できた。 そして、帰宅した先で見つけたのは、ちゃぶ台に突っ伏して倒れているシマばあちゃんだった。 「ばあちゃん?」 小さく呟いて、駆け寄った。 片手だけ長くのばしたまま、その他の体は海老のように丸めている。明らかに、寝ているわけではないと分かった。目は固く閉じられている。苦しげに頰がゆがんでいた。 長く伸ばしたシマばあちゃんの手には、干し柿が握られている。私が作ったものだ。三分の一ほど食いちぎられた跡がある。 瞬時に最悪の事態が頭に浮かんだ。腹の底が冷えた。シマばあちゃんは八十二歳だ。いつ何があってもおかしくないのだ。私はこれまで、そのことを考えないようにしていた。いざ目の前に突き付けられて、とても驚いていた。とっさには身体が動かなかった。 鞄を床に下ろすと、急に力が抜けて膝頭が震えた。シマばあちゃんの羽織っているピンクの透かし編みカーディガンの目が鮮明に見えた。つけっぱなしになっているテレビから、スポーツニュースが漏れている。内容は何も頭に入ってこない。 呼吸をするのも忘れそうになっていた。私は意識して、すうはあ、すうはあ、と呼吸を整えた。酔っ払いのように左右に揺れながら、恐る恐るシマばあちゃんの口元に手の平をかざす。 生温かい吐息が、指先をかすめた。 息があった。 息をしている! 思わず、干し柿ごと、シマばあちゃんの手を握った。温かさが残っている。意識を失っているだけのようだ。一瞬で様々な病名が脳裏に浮かんだ。いずれにしても、速やかに治療を開始しないと手遅れになるかもしれない。 その後の私は冷静だった。すぐに携帯電話を取り出して、救急車を呼んだ。 「ばあちゃん、ばあちゃん」 救急車を待つ間、声をかけ続けた。 「ばあちゃん、大丈夫だからね。全然大丈夫だからね」 誰に向かって言っているのか分からなかった。ちゃぶ台の木目が、こちらをじっと見ているような気がした。声をかけても無駄だと笑われているように思えた。けれども、私は言葉を発し続けた。何かしら話していないと、私までおかしくなってしまいそうだ。 「ばあちゃん、イケメンと結婚するって言っていたもんね。だから大丈夫よ」 言いながら、自分の不運を呪った。 奪われるばかりの人生だ。 何かを積み上げようとしても、すぐに足元から崩れていく。どんなに頑張っても、這い上がれないのかもしれない。 背後から冷気が漂ってきた。玄関の扉を開けっぱなしにしていたようだ。 私はひとり、くしゃみをした。固く握ったシマばあちゃんの手が温かいことだけが、私の希望のように感じられた。
3
救急車に乗って十分後には、シマばあちゃんの意識が戻った。話せはしないが、ゆっくりと瞬きを繰り返している。医者によると、心筋梗塞らしい。 病院に着いてすぐ、緊急処置室に入った。私は帰ってもいいと言われた。が、帰る気にもなれず、待合席に座ったまま一夜を過ごした。仕事着のままでジャケットを着ていたが、照明を抑えた病院内は寒々しかった。ストッキングを穿いた足元が冷えて痒い。待ち時間にすることもない。ぐったり疲れていた。目を閉じて少し眠ろうとしたが、気が張っているせいで寝付けない。 じりじりと数時間が経過したところで、看護師から呼ばれた。 「発見が早かったのが、不幸中の幸いでしたよ」 と医者は言った。 血管が詰まった時点から、どれだけ早く治療を行えるかで、生死が分かれる。シマばあちゃんのような高齢者の場合、基礎疾患を持つ者も多く、生存率はそう高くない。今回は発作後すぐに私が発見したことで一命をとりとめたのだという。 複雑な気分だった。 昨日は、剣持先生の態度が気に食わなかった。イライラしていた。不思議とイライラしているほうが仕事は早く済んだ。そのおかげで、シマばあちゃんが死なずに済んだのだ。人を呪わば穴二つと言うけれど、私の場合は、人を呪う力が身を助けたわけだ。 早朝にはシマばあちゃんの容体は安定していた。 私は一旦家に帰り、タオルや寝間着など入院に必要なものを見繕って、病院に届けた。売店でもいくつかの日用品を買う。 一通りの手続きを終えても、まだ朝の十時半だ。 頭が重かった。数分に一度あくびが出るが、目は異様に冴えていた。昼過ぎには眠くなるかもしれない。くたくたになるまで起きていて、限界が来たところで泥のように眠ればいい。 これから仕事に行こうと思った。シマばあちゃんの傍についていたい気持ちもある。しかしどちらかというと、弱ったシマばあちゃんを直視したくなかった。容体は安定している。私にできることは何もない。傍にいても仕方ない。それなら働いたほうがいい。入院費用だって、かかるんだから。そう自分に言い聞かせた。 気持ちを切り替えようと、病院内のコーヒーショップに入った。ホットコーヒーを買う。片手に持って、ちょうど店から出た時だった。 「あれ?玉子ちゃん?」 後ろから男の声がした。 急に名前を呼ばれて思わず肩をびくつかせる。振り返ると、白衣姿の太った男が立っていた。つぶれたカエルのような顔を見て思い出した。 「あ、先日の飲み会の」 可愛い声を出すのも忘れて、地声で漏らした。 この前の合コンのときの、ブサイクな医者だ。美法のために開いた合コンである。商社マンと医者が参加していた。名前は覚えていなかった。その場では盛り上げるのだけど、実際のところ興味のない男の名前は全然覚えられない。いつもなら適当にごまかすのだが、今日は顔に出ていたのかもしれない。 「ええ、先日はどうも。築地です」 察したのか、男のほうから名乗ってくれた。 「この病院の放射線科で働いているんです。ええっと、玉子さんは?」 いつのまにか、「玉子ちゃん」から「玉子さん」に呼び方が変わっているのは、彼なりの遠慮なのかもしれない。 確か築地は、先日のお店からそう遠くない病院で働いていると言っていた。このあたりにある総合病院は限られている。我が家の最寄りの総合病院だったのか。へえ、とは思ったが、驚く元気は残っていなかった。 「昨晩、祖母が倒れまして。幸い、命は助かりましたので、私は一旦、仕事に戻るのですが」 築地は、小さい目を数度瞬かせた。 「それは大変でしたね」 悪くない言い方だった。 嫌味なく、同情するわけでもなく、フラットな感じだ。 「今日くらいは、玉子さんもゆっくりしたらどうですか。お仕事も忙しいでしょうけど」 築地の意外な優しさに心がほぐれそうになった。だが、ふと仕事のことに思い至って、急に気分が引き締まった。私のような者はせめて働かないと、もっと惨めな境遇になるかもしれない。弁護士になって毎日働いていても気は抜けなかった。 「お気遣い、ありがとうございます。でも大丈夫です。祖母の容体は安定しているようですし」 「そうですか。それは良かったです」 築地はそこで言葉を切って、視線をそらした。 「落ち着いたら、食事でもどうですか。玉子さん、疲れてらっしゃるみたいだから、そういう時は、美味しいものを食べるのが一番ですよ。ご馳走しますから」 「ええ、ぜひ、落ち着いたら」 築地と食事に行くことについて、具体的な考えがまとまったわけではない。社交辞令として、自動返答のように発していた。小さくお辞儀をして、その場を離れる。 何というわけでもないが、少し気分は軽くなっていた。築地が何気なく発した「大変でしたね」という言葉のおかげかもしれない。 誰かに同情されるのは嫌いだ。だけど自分の大変さについて、誰かに理解され心配されたいという気持ちはある。それが厄介なのだ。 事務所に着いたときには昼前になっていた。 もともと弁護士は夜行性で、昼過ぎから働く者もいるから目立ちはしない。 早足を緩めることなく執務室へ向かうと、案の定、剣持先生が立っていた。外出用の黒いコートを着ている。 「遅い、遅い。集合時間、ギリギリじゃない。行くわよ」 今日は外出の予定があった。 剣持先生は私の反応を窺うこともなく、さっさと歩きだす。 後ろについて歩きながら、剣持先生が手にしている鞄に目を留めた。一見して高級ブランドのものである。成金趣味で嫌になる。 私だってかなり稼いでいるけど、もっと実のあるものに使おうと貯金している。 ふとシマばあちゃんのことが頭に浮かんだ。しかしすぐに考えるのを止した。せっかく働いているんだから、働いている間は、他の心配事を持ち込みたくない。 シマばあちゃんが倒れたことは、職場の誰にも言っていなかった。 自分の百パーセントを仕事に充てられる人だけが生き残る世界だ。生活環境に陰りがあると見なされると、「配慮」という形で大きな案件から外されることもある。現に、出産した女性弁護士は、企業の法務部へどんどん転職していくのだ。 こういう過酷な環境でも、剣持先生のように難なく活躍する人もいる。でもだからこそ、剣持先生のような人に、弱みを見せたくない。 私たちは事務所の前でタクシーを止めて、汐留にあるゴーラム商会の本社に向かった。 ゴーラム商会は十二階建ての自社ビルを構えている。築年数は二十年ほどで、新しい建物ではないが、従業員数二千人足らずの会社としては、なかなか豪勢な構えだ。 だが近くで見ると、窓は磨かれておらず、雨水の垢がついているのが気になった。エントランスのマットも、端のほうが捲れたままだ。 受付に人はいないし、警備用のフラッパーゲートも電源から止まっていた。 受付前のソファ席に座っていた男が立ち上がって近づいてきた。 哀田先生だ。 「剣持先生、美馬先生。今日はどうも。ご足労頂きまして」 こちらから案内を頼んでいるというのに、あくまで腰の低い物言いだ。 痩せ型の長身で、マッチ棒のような身体をしている。顔も細長くて、垂れた眉がいかにも気弱な印象を与える。痩せこけたヤギのような印象だ。 押し出しの強い川村先生に顎で使われている様子が、容易に想像できた。 「さっ、行きましょうか」 なぜか剣持先生が先導して、歩き始めた。初めてきたオフィスのはずなのに、自分の家のように堂々としている。 受付脇を抜け、エレベーターで三階にあがる。哀田先生に案内されたのは、廊下の隅の書庫室である。ごみ置き場の隣にある、窓のない部屋だった。 二十畳ほどの空間に、書架がずらっと並んでいる。古い紙に特有の乾いた臭いが漂っていた。 その臭いに刺激されたのか、急に頭がクラッとした。めまいというほどではない。軽い頭痛だ。哀田先生や剣持先生に悟られないよう、こっそり片手でこめかみを押さえた。 「あら、大丈夫?」 脇から穏やかな声がかかった。 驚いて振り返ると、小太りの女性がこちらに駆け寄ってきた。書架脇の狭いスペースに事務机とパイプ椅子が置かれている。先ほどまでその椅子に座っていたようだ。 「頭痛いの?私の鎮痛剤でよかったら使ってくださいね」 そう言って、女性は私の顔を覗き込んだ。至近距離で目が合って、どきりとした。 ぱあんと張った丸顔に、大きく丸い目が揺れている。西洋人形をそのまま太らせたような顔立ちだ。ほとんど化粧気はないが、きめの細かい肌には艶がある。 「大丈夫です。すみません、ありがとうございます」 私は言いながら、軽く頭を下げた。一歩下がって、女性を見つめ返す。 ぽっちゃりしているが、背はそう高くない。全体のフォルムとして洋ナシ形のマトリョーシカを思わせた。肌艶からすると、二十代半ばに見えないこともない。だが、簡単に一つ結びしただけの黒髪と、落ち着いたグレーのワンピース姿からは三十代以上だろうと推測された。 「どうも、只野さん」 哀田先生がにこやかに話しかけた。そのまま剣持先生と私のほうへ向き直って、女性を紹介した。 「こちら、ゴーラム商会の総務課長の只野さんです」 只野と紹介された女性は、名刺を取り出した。私たちもとりあえず名刺を出す。 「狭いところですみません。会議室をとってもよいのですが、こちらのほうが話は早いので」 只野さんが、ゆったりした口調で言った。 「只野さんは、この件に一番詳しいですから、同席して頂くことにしました」 哀田先生の説明に対して、只野さんが微笑んだ。口の脇に小さいえくぼができて愛らしい。 「何でも聞いてください。私は転職組で、三年前に入社したばかりですので、古い話は分かりませんが」 一言二言、挨拶を交わしながら、それぞれが腰を下ろした。椅子の金属がワンピースの裾から伸びた膝の裏に触れて、ひやりとした。 「それで、本日ですけれども」 剣持先生が早速切り出すと、 「聞きたいのは、ゴーラム商会の経営不振の原因、ですよね」 と、哀田先生が引き取った。 「只野さん、あの契約書を……」 只野さんは素早く立ち上がると、三段奥の書架へまっすぐ向かった。すぐに一冊のドッチファイルを抱えて戻ってきた。 「経営不振の原因、色々とありますが、一番の原因はこれです」 哀田先生は、只野さんから受け取ったファイルを開き、一通の契約書を指さした。「独占販売契約書」というタイトルがついている。 「ああ、これは。昨年解約されたと噂の」剣持先生が口を挟んだ。 哀田先生が、苦い表情で口を開いた。 「ゴーラム商会の主力商品は、フランスのランダール社から仕入れている服飾品です。売上の四割を占めていました。ランダール社とは長い間、独占販売契約を結んでいた。他の業者に卸すことはできないし、ランダール社が直販することもない。だからこそ、ゴーラム商会の売上が安定していた。その売上を支える最重要契約が、コレというわけです」 哀田先生が契約書を数枚めくって、ある条文を指さした。 「ここを見てください」 原文は英語だが、大要以下の内容が記載されている。 第三十九条(期間) 本契約の有効期間は、××××年一月一日から同年十二月三十一日とする。 「よくある契約期間の定めです。昨年末、契約期間を満了して、独占販売契約は終了しました。契約の再締結はありません」 「再締結の交渉が上手くいかなかった、ってことですか?」 剣持先生の質問に対して、哀田先生が首を横に振った。 「いえ、そうではないんです。不思議なのですが、現場では、自動更新条項が入っていると思っていて、再締結の交渉をすることもなく、漫然と契約期間の満了を迎えたそうです」 「自動更新条項?」剣持先生が怪訝そうに聞き返した。 自動更新条項というのは、「契約の有効期間満了の〇カ月前までに、どちらかが契約終了を言い出さない限り、同じ内容で契約を続ける」と定めておくものだ。 この条項を入れておくと、何もしなくても契約が有効に続く。毎年契約を結びなおす手間が省ける。長い付き合いを行う企業間では、そのような条項が入っていることが多い。 「これまではずっと入っていたそうなのです。十年以上前に結んだ契約を、毎年、自動更新してきました。ところが、ちょうど一年前に、ランダール社から独占販売料を改定したいという申し出があったそうです」 「値上げしたいってことですか?」 哀田先生が、再び首を振った。「いえ、値下げしたいという申し出です」 「それなら、ゴーラム商会さんにとって、お得な申し出ですよね。独占販売のために払っている手数料が安くなるんだから」 剣持先生の言葉に、只野さんが神妙な顔つきで頷いた。 「ゴーラム商会にとって有利な申し出を、どうしてランダール社から言ってくるのか、不審視する声は当時からありました。ランダール社の説明は、為替レートがどうのこうのというもので、釈然としないものでしたし。コンプライアンス担当の役員である安西も、もっと詳しく調べるよう指示を出していたのですが、営業部の声が大きくてうやむやになってしまったのです。うまい話に飛びついたという感じですよね。後から振り返ると、そうなのですが……」 「現場にヒアリングした結果、どうやらこういうことらしいです」 哀田先生が説明を引き取った。 「独占販売料の改定のために、一年前に新しい契約書を取り交わした。金額を変えるだけだから、これまで入っていた自動更新条項もちゃんと入っていた。少なくとも、ドラフト段階までは」 「ドラフト段階まで?」 「はい。ランダール社が提示したドラフトには入っていました。その内容で内諾して、ゴーラム商会の社内稟議に回った契約書にも、自動更新条項は入っています。これは社内の稟議記録にも残っています」 哀田先生は、ドッチファイルを数枚めくって、稟議書を示した。そして、その稟議書に添付されている契約書のドラフトを開いて見せた。 第三十九条(期間) 本契約の有効期間は、××××年一月一日から同年十二月三十一日とする。ただし、有効期間満了日の二カ月前までに、いずれかが申し出なかった場合、本契約は同内容で一年間、更新される。 「自動更新条項、入っていますね」 私は、条文の後半を見つめながら言った。 「そうなんです」哀田先生は、困ったように眉尻を下げた。 「ドラフトにも入っている。稟議書にも入っている。しかし、いざ契約書の原本をみると、抜け落ちているんだ」 私は契約書の原本と、稟議書添付のドラフトを見比べた。自動更新条項だけが抜け落ちている。あり得るとすれば、契約書原本に細工をする手法だ。 通常、メールなどで契約書データのやりとりをして、内容を確定させる。そのあとに、紙の契約書を郵送して署名捺印を交わす。契約書は、どちらかの会社が相手方の分まで製本し、郵送することが多い。製本といっても、最終ドラフトをプリントアウトして袋綴じにするだけだ。 だがまれに、最終ドラフトとは異なる文言の契約書を綴じて送ってくる会社がある。単純ミスのこともあるだろうし、もしかすると悪意があるかもしれない。 だから、会社としてはなるべく自社で製本をする。 もし、相手方に製本を任せるなら、郵送されてきた契約書原本の内容を確認したほうがよい。最終ドラフトからずれていないか、文言を照らし合わせるのだ。もちろん、会社によってチェックの厳しさには温度差がある。けれども、会社の命運がかかっているような重要契約であれば、念のための確認は欠かせない。 「原本の製本をしたのはどちらですか?」剣持先生がすかさず訊いた。 「ランダール社です」只野さんが答えた。 「受領した契約書原本の文言確認は?」 「さあ……それがよく分からなくて。私たち総務課は、受け取った契約書に捺印する作業だけを担当しています。それまでの契約書のチェックは、法務課の担当です。しかし当時の法務担当者たちは、もうみんな辞めてしまっていて、連絡がとれないんです。案件の量に比して人員がとても少なかったので、けっこう杜撰なチェック体制だったかもしれません。契約書の最終チェックを省いていても、おかしくないです」 「なるほどねえ……」剣持先生が腕を組んで、呟いた。 「ランダール社のだまし討ちに、まんまと引っかかったってことですか?」 あまりにも直截的な言い方だと思ったが、要約すると、そういうことだ。 只野さんも反論しない。 今まで自動更新条項で、自動的に契約書が生きていた。それが一年の期限付きの契約に差し替えられる。ゴーラム商会はその事実を知らないまま、一年間が経過する。そのタイミングで、契約書は失効してしまう。 「契約書が失効してしばらくしてから、ランダール社から、契約終了の通知が来ました。そのときになって初めて社内は事態を把握して、今に至るわけです」 哀田先生は淡々と説明を続けた。 「ランダール社は日本法人を設立して直販を始める予定らしい。昨年から秘密裡にその準備は進んでいたようです。ベテランの販売員たちがどんどん引き抜かれている。ゴーラム商会としては自社ブランドを強化したり、いろいろと足搔いているものの、早々に資金繰りがショートしそうです」 私は剣持先生の表情を盗み見た。頰に手の平をあてて、考え込んでいるように見える。 そもそも今回の調査のきっかけは、「近藤まりあ」という社員に対する通報だ。彼女が会社を倒産させているのか、調べている。というか、わざと倒産させるなんて普通はできない。近藤が無関係であることを確かめに来ただけだ。 ゴーラム商会はランダール社の策略にはまって、独占販売契約を打ち切られた。その結果、倒産の危機に瀕している。近藤まりあは無関係ということになりそうだ。 だが、ランダール社が単独でそんな悪事を働けるとも思えない。ゴーラム商会側に内通者がいたと考えるのが自然だ。 「なんか変ね」剣持先生が急に呟いた。 「うん、おかしい。ちょっと、ねえ、変じゃない?」 と私のほうを向いた。 「いま十月よ。契約書が失効したのは去年の末。契約書が失効していた問題について、どうして顧問弁護士の津々井先生に相談しないのかしら」 言われてみれば確かにそうである。いくら津々井先生がゴーラム商会を放置ぎみだとしても、会社の命運を左右する問題だ。相談があれば、流石にきちんと対応するはずだ。 「えっと、その」 只野さんが居心地悪そうに口を開いた。 「弁護士先生に相談して、どうにかなるものでしたか?だって、契約書は取り交わしてしまっているのですし……」 「どうにかならないことも、ないですよ」 剣持先生がなぜか自慢げに答えた。 茨の道ではあるが再交渉を試みることはできる。最悪の場合、ランダール社を相手取って訴訟をするといった方策はあり得る。時間もかかるし、どれだけ上手くいくかも分からないけれども、何もせずに潰れていくよりはよい。 只野さんは口を小さく開けたまま、固まっている。もともとは頰の血色がよくて、いかにも健康的な印象だ。今は、頰をさらに赤らめている。 「あの時、どうにかしてれば、うちは助かったかもしれないのですか?」 興奮気味に訊いた。口元が震えている。 「今からでもベストを尽くしますよ」 と哀田先生がすかさず請け合った。力強い口調と裏腹に、哀田先生の目元は暗かった。ただでさえ忙しい人だ。疲れがにじんでいてもおかしくない。 「今からでも、どうにかなるものですか?」 只野さんの大きな目の中で、瞳が左右にせわしなく動いている。先ほどまではゆったりと朗らかな印象だったのに、急に表情を一転させたことに驚いた。 「ええ、きっと、僕たち倒産弁護士が全力を尽くして、なんとか会社を蘇生させます。だから只野さんは落ち着いて日々の業務を──」 「本当に?本当に会社は助かりますか」 只野さんはじっと哀田先生を見つめた。 「ええ、必ず助けます」 哀田先生はきっぱり言い切った。 「実は、ここだけの話ですが、御社の事業の一部を売却することで、ある程度まとまった現金を手に入れることができそうです。現金さえ入れば、延命できます」 「えっ、本当ですか?」只野さんは目を見開いている。 「本当です」哀田先生は力強く頷いた。 私はびっくりして、哀田先生を見つめた。もともと表情の乏しい人だ。どんなに忙しくても、怒ったり怒鳴ったりすることはないと聞く。だが、そういうところに、ロボットのような不気味さもある。丁寧な物腰の裏で、何を考えているのか全く分からなかった。 弁護士が「必ず助けます」と断言するのはおかしい。弁護士の仕事に百パーセントはない。「必ず勝ちます」とか「必ず成功させます」とか、そういうことを言う弁護士は逆に信用できない。哀田先生は、十年以上も弁護士として働いているのに、軽々しく成功を請け合うなんて、信じられなかった。 それに事業売却の予定があるとしても、只野さんに漏らしてはいけないはずだ。事業売却は大抵、会社の上層部で進んで、ギリギリになって現場に話が下りてくる。そうしないと現場で混乱が広がって、売却自体が潰れてしまうこともある。いくら只野さんを励ます意図があったとしても、哀田先生の言葉かけはやりすぎだ。 只野さんは依然として落ち着かない様子だ。机の上で両手の指を組んだり、外したりしている。 「もともと営業販売職ばかりの人員構成で、管理部門が弱くて。そんななか、法務の人たちがごそっと辞めてしまって。契約書を扱える人が全然いないんです。私が見様見真似でやっていたので、その……。顧問弁護士に相談するといった基本的なことが分かっていなくて。私がきちんと動いていたら、会社は助かっていたかもしれないと思うと」 「法務の方々は、どうして離職を?」 淡々とした口調で、剣持先生が訊いた。動揺する只野さんに対して、冷ややかな目を向けているように見えた。 只野さんは、曖昧な表情のまま、首を傾げた。 「さあ。不満があったのでしょうけど、今となっては分かりません」 剣持先生は表情を変えずに、質問を続けた。 「あなたは誰かに相談しようと思わなかったのですか?上司とか、役員とか」 只野さんは首を横に振った。 「うちの上司たちは、都合の悪い話は耳に入れようとしないのです。現場で対処しろ、と丸投げで。仕方なく、私も経理の方と相談したりしながら、なんとかやっていて」 急に経理の話が出てきて、私は姿勢を正した。 剣持先生も同じところに引っかかったらしい。 「その、経理の方って?」 「えっと、近藤さんって方なんですけど」 「近藤まりあさん?」剣持先生が身を乗り出して訊いた。 「近藤さんのこと、ご存じなんですか?」 只野さんは目を丸めている。 「とっても優秀で、色々と相談に乗ってもらっていました」 剣持先生と私は顔を見合わせた。 剣持先生は口を尖らせて、ひょっとこのような顔をしていた。彼女なりに驚いているのだろう。剣持先生にしては、ブサイクに見える表情だった。せっかくだから、その顔を覚えておこうと思った。
 『元彼の遺言状』待望の続編!
『元彼の遺言状』待望の続編!